▶ を押すと文が増えます
漢字からひろがる日本語の世界
ここで日本の人たちは、中国語としてやってきた漢字を中国語の読み方をいかして読むだけでなく、日本語として読むことに挑戦しました。
その読み方の違いが、実は「音読み」とか「訓読み」とか私たちが呼ぶ漢字の読み方の種類です。
中国から漢字が伝わってきて―
漢字は漢字としてだけ使われただけではありませんでした。
漢字の形からインスパイアされて、現在も私たちが使っている「ひらがな」や「カタカナ」という新たな日本語の文字の発明へとつながっていくのです。
私たちも苦労して国語を勉強しますし、英語などの外国語を勉強しています。
でも、考えてもみてください。
漢字が伝わってきた当時の日本。それまで「文字」を書く、残す、読む、という文化がなかったのです。「文字」がなかったのですから当然です。
そこから、漢字を使いこなしていった、ってものすごいことだなあ、と思います。
今となっては当たり前すぎる日本語としての文字ですが、これを使いこなすようになるまでには相当時間もかかったはずです。
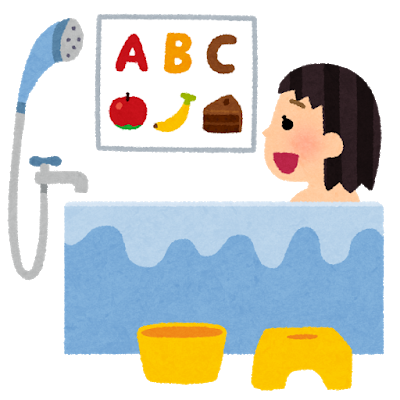

私たちが言葉を覚えたり、使うことができるようになるきっかけは何でしょう。
一番のきっかけは、相手のことを知りたい、ということだと思います。
例えば、韓流アイドルが好きで、もっと彼ら・彼女らのことを知りたいから、「韓国語を覚える」という人もいるかもしれません。憧れや、必要を心から感じたら、私たちはガムシャラになれるし、事実そうやって「できること」をひとつずつ増やしているのかもしれません。
日本は6世紀から7世紀にかけて、中国大陸や朝鮮半島から、儒教や仏教、道教といった宗教や思想、哲学を取り入れるようになります。
当時の日本にとって、中国や朝鮮半島はとても発展していて、学ぶことだらけだったのです。
さまざまな知識やものの考え方は、漢字という文字のおかげもあって、だれかに直接教えてもらわなくても、書かれたものを読むことで、理解することができるようになっていました。
書かれている言葉を何とか読みこなせば、時と場所を選ばずに内容を理解することができる!
このことにどれだけの人が勇気づけられ、はげまされたか分かりません。
中国へと渡らなくても知識が手に入るかもしれないのですから。
文字通り、この時代を生きた人たちも、「もっと知りたい」、「もっと学びたい」と心から願って、その結果として、漢字を私たちの文化に欠かせない道具へと切り拓いていったのではないでしょうか。

ちょっとダイナミックに考えすぎかなあ…。
でも、「できること」を少しずつ、じわじわ増やしてきた過程に、漢字やひらがな、カタカナの発見があって、それが今の私たちの言葉の世界やコミュニケーションを支えている、と思うと、なんだか感動してしまうのです。(うるうる)
つまり、それまでなかった「文字」を言葉として読み解く力が次第に身に付きはじめ、漢字を読むことのできる能力を備えた人たちが少しずつ、少しずつ増えていきました。
仏教という宗教も、この「漢字」をひろめていくことに一役買っていたそうです。
ありがたい仏の教えを、もっと広めよう!ということで、書かれている内容をコピーする作業がされるのです。
もちろん、コピー機なんてない時代です。
すべて手作業で書き写す―写経(お経を写す)が盛んにおこなわれました。

ちなみに、ファンタジーで正確な歴史ではないですが、
手塚治虫の火の鳥の『太陽編』は、まさに7世紀ごろの日本を舞台に仏教が日本にやってくるエピソードを基にしたストーリーを描いています。
(ものすごい展開になっていくので、あくまで遊び?気分転換?としてよかったら楽しんで見てください)
火の鳥は手塚治虫の未完の遺作とされていますが、難しくもあり、とても面白い漫画です。
長い経緯があってようやく‥‥!、ひらがなや漢字も生まれるきっかけがはぐくまれることになるのです。

ひらがなやカタカナの歴史はまた別の機会に…。
あまりに奥が深すぎて、永遠に脱線しつづけてしまいそうです‥‥
新たな漢字の読み方を生む―音読みと訓読み
先ほど、漢字が中国から伝わってきたときに、中国語をもとにした読み方を学ぶだけではなく、日本語としての読み方を生み出すことに挑戦した、とお伝えしました。
この中国語をもとにして読む読み方を音読み、日本語として読む読み方が訓読みです。
分かりやすい見分け方としてよく紹介されているのが、その読み方で意味が通じるか、どうか、の違いです。

例えば、「山」という漢字。
どんな読み方があるでしょうか? ―答えは、「やま」と「サン」があります。
もともと「山」という漢字が日本に伝わったとき、この漢字の読み方は「サン」としか読みませんでした。
もともと中国で“サン”と発音されていたからです。
…つまり、「山」の音読みは「サン」。
ですが、日本語で「山」は「やま」と呼ばれていました。
「山」という漢字が意味するものが、日本語でいうところの「やま」であったため、「山」を「やま」とも呼びましょう、ということになった。
‥つまり、「山」の訓読みは「やま」。
そもそも「音読み」の「音」という漢字は、耳で聞こえるおと、物の響きや音色の意味があります。もともとその漢字に備わった読み上げ方、なのです。
一方の「訓読み」の「訓」という言葉には「おしえる」「さとす」「おしえみちびく」といった意味があります。
漢字を前にして中国語読みで頑張って文章を読んでいた人たちに、日本語の意味に置きかえながら説明していく過程で、その漢字を日本語の意味に合わせて読み上げることにつながり、訓読みが生まれた、とも考えられています。
実は、漢字によっては、どれが日本語の意味なのか、もともと中国語の発音であったのか見分けがつかなくなっているものも少なくないようです。
音訓の使い分けは難しいこともありますが、漢字辞典などではきちんと区別して読み方が書かれています。(音読みはカタカナ、訓読みはひらがな)

漢字がどうやって日本に渡ってきたか、より漢字を理解するために生まれた訓読みという読み方、さらに「ひらがな」や「カタカナ」が新たしく生まれていった歴史を知ると、これまで以上に漢字に親しみがわいてくるような気がしませんか?




