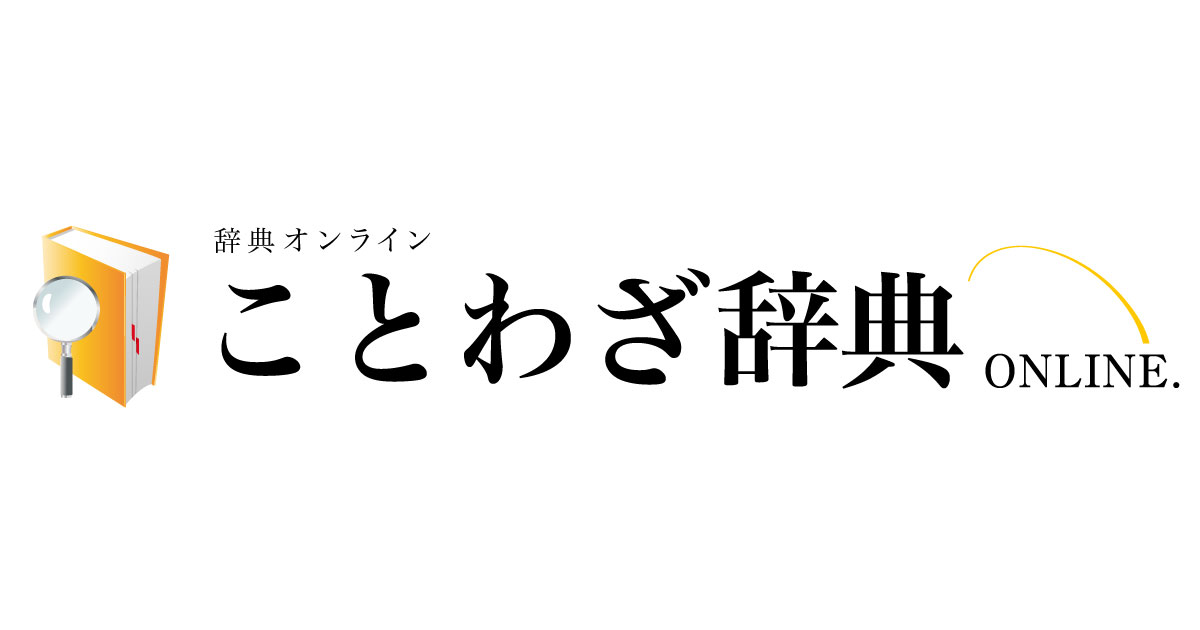▶ を押すと文が増えます
いろいろなあいさつ
目次
- あいさつの語源
- おはよう
- こんにちは
- こんばんは
- オッス
- さようなら
- あばよ
- グッドバイ
- ごきげんよう
- ありがとう
- かたじけない
- おかげさま
- 恩に着る
- すみません
- ごめんなさい
- 面目ない
- 点字と手話について
あいさつの語源
「あいさつ」。
するのは少しドキドキするけれど、されるとうれしい。
それがあいさつ。
「あいさつ」は漢字にすると「挨拶」となります。
一気に難しくなりましたね。
でも漢字から「あいさつ」の意味や秘密をたどれるのではないか…―。

…ということで、挨拶の語源を早速たどってみようではありませんか。
まずは挨拶の「挨」の字。
「おす」「ひらく」「おしのける」という意味があるそうです。
他にも「推しはかる」、「近づく」、「触れる」など。
挨拶の「拶」の字
「せまる」「おしよせる」という意味のある漢字です。
「切り込む」という意味も含まれてくるとか。

「挨」も「拶」もなかなか、勢いを感じる語です。なんだか意外。
そもそも「挨拶」という言葉の語源は禅宗の考え方があるようです。
中国の「宋」という時代に仏教の禅宗に関して『碧巌録』という本が書かれました。
その本の中に「一挨一拶。其の深浅を見んと要す」という言葉が残されています。
挨拶は、禅宗で問答を交わして、相手の悟りの深さ浅さを試みることを「一挨一拶(いちあいいつさつ)」と言った‥‥
師匠が弟子に声をかけるなどし、その弟子の返答をもって修行の度合いをはかる、ということが行なわれてきた、というのがそもそもの「挨拶」の意味であり、由来なのだそうです。
ここから一般に問答や返答のことば、手紙の往復などを挨拶と言うようになったといいます。
漢字の意味ともともとの「挨拶」の言葉の使われ方を考えてみると、
「挨拶」とは声をかけた相手の心にフッと切り込んで、相手の気持ちや元気かどうかなどの状態をおしはかり、声をかけられた方もその呼びかけにサッと答えて、自分の状態を示すような…
なんだか緊張感すら覚えるような、そういう言葉の掛け合いだったのかもしれません。

挨拶というのは魔法のような言葉で、「こんにちは」などの一言で、少し元気が出たり、緊張がゆるんだりもします。
一方で、「おはようございます」とか「こんにちは」と声を出すことは、自分自身の中で気合を入れることにもつながるような気がします。

本当に昔のことですが、通っていた中学校で「あいさつ運動」というものがありました。
なぜか、その活動がしっくりハマっていた私は(田舎だったのでできることかもしれませんね)、登下校でも「こんにちはぁ」とよく挨拶していました。
そんなある日、声をかけたおばあさんが挨拶に感激してくれたことがあります。
ただの「こんにちは」が時に、こんなにも人を喜ばせたり、感動させてしまうことがあるのか…という強い印象を残した経験です。
初めて顔を合わせる人と「こんにちは」を言いあうだけで、もう「ただの知らない人」ではなくなってしまう…そんな気持ちになれる魔法の言葉だなあ、とつくづく思います。
アイヌ語の「こんにちは(イランカラプテ)」は、
「あなたの心にそっと触れさせてください」という意味なのだそうですが、挨拶って本当に、相手の心にふっと寄り添って近づくことのできる呪文のようだな、と感じます。
おはよう
「お早う」というのが、そもそもの「おはよう」だったようです。
「お早くからご苦労さまです。」という朝早くから働く人へのねぎらいの言葉でした。
最近では、「おはよう」の魔法は時間帯を問わず使われるようにもなっています。
その背景には「こんにちは」が近い関係の相手には使いにくいニュアンスを持つ言葉として定着してきたことがあると研究されていたりもするそうです。
点字の仕組みを習ったことがある人もいるかもしれませんが、基本的には、点字は6つの点字の組み合わせで一つの音を示しています。
(濁点や拗音(きゃ、きゅ、きょなど)などはその目印の点字を組み合わせて一つの音を示していきます)
点字には漢字はありませんし、ひらがなやカタカナの区別もありません。

点字は点字で独自のルールがあったりするのですね。
そのうちの一つが基本的に耳で聞いた通りに書き表す、ということです。
そして、のばす音で「う」と書くところは、長音符を使います。
「おはよう」は「おはよー」と点を打ちます。
(のばす音でも、「あ」「い」「え」「お」の場合は長音符は使いません。)
⠊⠥⠜⠒
片手の握りこぶしをこめかみに当てて、素早く下ろします。
両手の人差し指を向かい合わせて曲げます。これは「挨拶」を表しています。
こんにちは
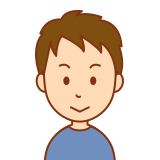
今日(こんにち)は、ご機嫌いかがですか
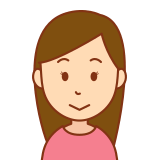
今日はよいお天気ですね
など、「今日は」を主語にした文章の略で、お昼に初めて出会った人の体調や心境を気遣う言葉の後半が省略されて定着されたものだそうです。
江戸時代の武家の挨拶が起源になったともいわれています。

「こんにちは」と書くけれど、
発音は「こんにちわ」とする背景には、もともとその後に会話が続いていた、という理由があったのかもしれないのですね。
基本的に耳で聞いた通りに書き表します。なので、「こんにちわ」と点を打つことになりますね。
⠪⠴⠇⠗⠄
人差し指と中指を額の中央に当てます。これは時計の12時を表します。
そして、両手の人差し指を向かい合わせて曲げあいさつをあらわします。
こんばんは
日が暮れてから、人に会ったり、人を訪ねたりしたときの挨拶の言葉。

今晩は良い晩ですね
など、会話文が略されて定着したものと言われています。
なので、「こんばんは」の後に文章が続くと考えると、「こんにちは」と同様、
「こんばんわ」ではなく「こんばんは」という表記します。

耳で聞いた通りに書き表すので、「こんばんわ」と点を打つのでしたよね。
⠪⠴⠐⠥⠴⠄
両方の手のひらを相手に向け、そのまま交差させながら下ろします。これは「暗い」をあらわします。
そして、両手の人差し指を向かい合わせて曲げあいさつをあらわします。
オッス
若者同士が道などで出会ったときの挨拶語で親しい間柄で用いられるといいます。
ドラゴンが持つオレンジ色のボール?を探しに行く冒険漫画の主人公も、よくこの挨拶を使っている印象がありますね。
もともとの語源は、京都にあった武道専門学校の生徒の間から生まれた言葉で「おはようございます」の略だという説もあるようです。(諸説あるようです)
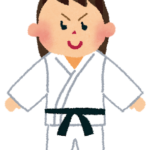
おはようございます

おはよーっす
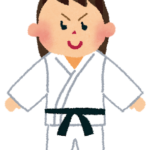
おわーす

おす!
などのように、だんだん略されて定着していった…という説もあります。
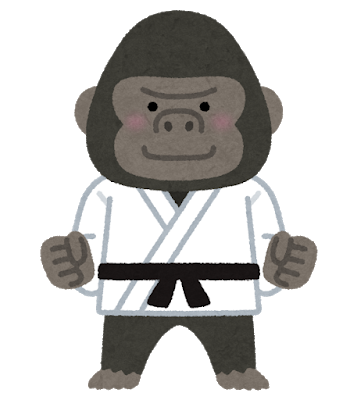
「オッス」という言葉には、武道の精神である「自我を抑え我慢する」という意味の「押して忍ぶ」があてられ、漢字では「押忍」と表記されるようになったという説もあります。
挨拶の「オッス」は恐らく「おはようございます」の略ですが、応援団などが掛け声風に用いる「オッス」は「押忍」の意味からと考えられます。

押忍っ!!

押忍っ!
さようなら
「然様なら」の略だそうで、
「然様ならば(そういうことならば)、私はこれで失礼いたします」といった意味があったそう。

のばす音で「う」と書くところは、長音符を使うのでしたよね

そうでした!
なので、下の点字のようになりますね。
長音符は視覚的にも、伸ばし棒「-」と似てますね。
⠱⠜⠒⠅⠑
私たちがいつも自然と手を振っている挨拶ととても似ていますね!
あばよ
別れの挨拶の言葉。「さようなら」よりくだけた言い方。
あばよの語源には「さらばよ」の略、「また逢はばや(またあはばや)」が転じたもの、「ああ、あれは」という感動を示す語「あは」に助詞の「よ」がついたものなど諸説あるそうです。

「按配よう(あんばいよう)」の略語という説が最も注目されているという。
「按配」とは「体調」の意味として近世から使われている言葉で、「あばよ」も近世から使われている言葉であるため、意味と語形の両面からみて、この説が妥当といわれているそうです。
グッドバイ
英語「good-bye」からの外来語。かつては「good-bye」を古くは「Godbwye」といい、「God be with ye」の短縮形だったそう。
「God be with ye」とは、「ye」が古い二人称代名詞「you」を指し、「神さまがあなたと共にありますように」「神様のご加護がありますように」という意味だったそうです。

「God」を直接口にするのを遠慮する風潮があったことや、「good morning」や「good night」など他の挨拶の言葉も登場し、17世紀から「God」が「good」に変わり、18世紀にはいり、現在の形になったのだそう。
日本では明治中期から用いられているそうです。
ごきげんよう
相手の健康状態を伺うという意味で、相手を気遣う丁寧なあいさつ表現。
「ご機嫌よくお過ごしですか」を短くして「ごきげんよう」になったと言われています。

明治時代には山の手言葉として貴族や華族が日常的に使っていたといいます。
山の手言葉とは、現在の標準語の基礎となった東京の山の手で使われていた言葉だと言われています。
明治期に武家をルーツとする華族が使っていた言葉として知られてるものでもあります。
「お嬢様言葉」として知られる言葉遣いも、山の手言葉に近いものかもしれません。
語源として知られているのは、室町時代の京都の宮中で使われる御所言葉だったそうです。女官が天皇にあったときの挨拶として使ったそう。
基本的に、朝、昼、晩を問わず、いつでも使えるあいさつ表現。
出会ったときにも、別れ際にも使える言葉です。

出会ったときの「ごきげんよう」は「お元気でしたか」という意味で用いられ、
別れ際の「ごきげんよう」には「次に会うときまで健康でいてください」という意味合いが込められているといいます。
インターネットで「ごきげんよう」という言葉を探すと「一般的ではない」ので、使うと嫌味にとらえることもある、などとも紹介されていたりします。
あいさつ表現にも流行りすたりがある、ということも、なんだか不思議です。
いろいろなありがとう
ありがとう
ありがとうの語源は、形容詞の「有り難し(ありがたし)」の連用形「有り難く(ありがたく)」がウ音便化し、「ありがとう」となったと言われています。
「有り難し(ありがたし)」は「有る(ある)こと」が「難い(かたい)」という意味で、本来は「滅多にない」や「珍しくて貴重だ」という意味を表していました。

中世になり、仏の慈悲など貴重で得難いものを自分は得ているというところから、宗教的な感謝の気持ちをいうようになり、近世以降、感謝の意味として一般にも広がったそう。
そもそも滅多にないことに対して発せられる言葉だと思うと、
うれしい!という喜びの感情も「ありがとう」の言葉の中には込められているといえそうですね。

“ありがとう”にも「う」で音がのびている!
つまり「「ありがとー」ですね!
⠁⠓⠐⠡⠞⠒
手のひらを下に向け、その手の甲に片手を当てて拝むように引き上げます。

勝った力士が手刀を切る様子に由来している、という説もあるそうですよ。
かたじけない
ありがたい。もったいない。恐れ多い、という意味。
文語「かたじけなし」の口語で、「ありがたい」が一般的なのに対し、改まった丁寧な言い方です。
本来、かたじけないは相手の身分や言動と自分を比べたときに引けを取り、「恐れ多い」といった感情を表す語で、転じて「ありがたい」「もったいない」という感謝の気持ちを表す言葉となりました。

心からありがたく思っていることを伝えたいときや、
自分にはもったいないほど親切にしてくれたときに
「かたじけない」という言葉が使われるようです。
「かたじけない」も「ありがたい」も「もったいない」も自分には不相応で恐れ多いという意味から感謝の気持ちを表すようになっており、日本人独特の感情表現といえるとも。「私なんかが」というニュアンスが含まれます。
「恐れ多い」という意味のかたじけないは、「ありがたし」の「がたし」の例から「かたしけ(難気)なし」が語源と考えられています。

かたじけない。

お気に召さるな!
礼には及ばぬ!

‥‥ちょっとかっこいい…!
真似してみたくなりますね(笑)

‥‥表現を?それとも、謎の人物のコスプレを…?
(謎の人物はいわゆる「獅子の頭」じゃな。歌舞伎に出てくる獅子の精じゃ。)
…おっといかん。脱線したな。すまんすまん。
おかげさま
感謝の気持ちを表す語。挨拶の言葉としても用います。
おかげさまは、他人からうける利益や恩恵を意味する「お蔭」に「様」をつけて、丁寧にした言葉。
古くから「蔭」は神仏などの偉大なものの陰で、その庇護を受ける意味として使われているそうです。
ただ、「蔭」という字が常用外漢字ということもあって、「陰」という漢字で代用されることが多いそう。

ちなみに「かげ」という言葉にもいろいろな漢字がありますね。
もともと「かげ」の語源は、『古典基礎語辞典』によると、陽炎、鏡などと同じだそうです。
おおもとの意味は「光」で、太陽や月、灯火などの光を意味し、「月影」といえば「月光」、「火影」といえば「灯火の火」を意味したとか。
「影」という漢字
「影」という漢字は、
・「光」を意味する字の「景」、
・彩や模様、飾りなどに関する文字を形作る「さんづくり(彡)」
から成り立ち、光でできる模様というような意味あいを持つ漢字になるようです。

光の反射などによって鏡や水面に映る姿のことも「影」の字であらわします。
そこから姿じたいを「影」という漢字であらわすようになったのだそうです。
「面影」や「撮影」などの熟語に「影」という字が含まれることも、これで納得できますね。
「陰」という漢字
「陰」という漢字は、
・小高い山や丘を意味する「こざとへん」
・インという音を表す「侌」という”つくり”
の二つを組み合わせて成り立つ漢字です。
どうやら、山などによって生じる薄暗い陰、という意味合いを持つようです。
「陰陽」という言葉があるとおり、「明るい部分」に対する「暗い部分」というニュアンスですね。

この「かげ」という言葉や漢字について、いろいろと例文を紹介しながら説明をしているのが、下記のホームページです。
「なるほど…」が詰まっていますよ。
恩に着る
受けた恩をありがたく思う、という感謝を表す表現のひとつです。
「恩」とは、他の人から与えられた「めぐみ」や「いつくしみ」という意味ももつそう。
『日本書紀』や『古語拾遺 (しゅうい)』などの日本の古典に出ている「恩」は、
「めぐみ」「みいつくしみ」「みうつくしみ」などと訓まれているようです。
「めぐみ」は、草木が芽ぐむなどというときの芽ぐむを名詞形にしたものとされているそうですが、草木が芽ぐむのは冬眠していた草木の生命力が陽春の気にはぐくまれて目覚めることによる…
‥‥つまり、ある者が他の者に生命を与えたり生命の発展を助けることが恩を施すことであり、その逆が恩を受けることであるとみられているそうです。

そもそも仏教用語でもある「恩」という漢字。
『大乗本生心地観経』という書物の中には、
・父母の恩
・国王の恩
・衆生の恩(衆生とは生きとし生ける全てを表す言葉だそうです)
・三宝の恩(お釈迦さまがお弟子さんに説かれた教え。心の拠り所となる大切なものとして、「仏」「法」「僧」の三つのことを指すそうです)
など四恩を心に深く感じ大切に思うことが、仏道修行の要素であると説いているとか…。
ちなみに「恩着せがましい(恩恵を施して、いかにも感謝しろと言わんばかりの態度)」など「着る」という表現がついてくるのはなぜなのか…
この「着る」という言葉には「身に引き受ける」という意味がこめられているそう。
「罪を着る」という言葉が同様に「着る」という語を使う例です。
「罪を着る」という場合は、自分の罪ではないのに、その罪を引き受ける、という意味になります。

「恩に着る」という表現をする場合、恩を身に引き受ける
―「このご恩は一生この身に引き受け、忘れません」というニュアンスが含まれてくるとか。
「あなたに借りができました」というようにも意味を受け止めることができる言葉です。

むかしばなしに出てくる、「浦島太郎」のカメさんや「鶴の恩返し」の鶴も、みんな「恩に着ます」と言っていたような気がしてきました…。
いろいろなごめんね
すみません
「仕事を終える」「気持ちがおさまる」「満足する」という意味を持つ「済む」に丁寧の助動詞「ます」をつけ、否定した形。
「済む」の否定ですから、
「いくら謝罪しても謝罪しきれない」という意志を伝えようとしていて、この程度の謝罪では「自分の気が済まない(気持ちがおさまらない、満足しない)」という意味が込められた言葉だったそう。

感謝を示すときにも「すみません」と伝えることがありますよね。

その場合は「大したお礼もできず、気持ちがおさまらない」という気持が込められているそうです。
ごめんなさい
「御免」とは、相手が正式な許可や認可を下すことを敬った言い方だそうで、「なさい」は「してください」という意味。
鎌倉時代からみられる言葉だそうです。
つまり、「ごめんなさい」とは、自分の罪を認めて相手に許しを乞う謝罪の言葉です。
本来は、許す人を敬う言い方として用いられたそうですが、室町前期には許しを求める言い方で、相手の寛容を望んだり、自分の無礼を詫びる表現になっていきました。
「ごめんあれ」「ごめん候へ」などの形で初めは使われていましたが、「ごめんくだされ」やその省略の「ごめん」が多く用いられるようになっています。

「ごめんください」とか挨拶で使われることもありますよね。

許しを乞う「御免させてください」の意味が挨拶として使われるようになったものなんだって。
「それは御免だ」などの拒絶・断りは、比較的新しい用法で江戸時代からみられるそうです。

「ごめんなさい」の「ご」の字は、
”こ”に濁点を意味する点字をつけて表現することになりますね。
⠐⠪⠿⠴⠅⠱⠃
人差し指と親指で眉間の辺りをつまむ動作をし、その後片手で拝みます。

「すみません」という意味としても用いることができそうです。
面目ない
「恥ずかしくて人に合わせる顔がない」という意味。
何か失敗をしたときや失態を起こしたときに「面目ない」ということがあります。
「面目」は「顔つき・世間に対する名誉・様子」を意味します。

「面」という漢字には、「人の顔」や「うわべ」など、さまざまな意味が含まれていますね。
音読みで「メン」などと読みますが、訓読みでは「おも」や「おもて」、「つら」などの読み方があります。
「面」という言葉を使ったことわざや、熟語など詳しい説明が書かれているので、下記のホームページもよかったら覗いてみてください。

いろいろな挨拶を見てきましたが、もっともっと状況に合わせていろいろな表現の仕方がありそうですね。
それにしても、私たちが日ごろしている「あいさつ」は、相手に対する願いや想い、気持ちがこもったメッセージだったのですね。
言葉には魂が宿る―「言霊」なんて言葉もありますが、ひとつひとつの表現に込められた思いを改めて考えながら、今日も「おはよう」や「ありがとう」と挨拶していきたいなあ。
みなさん、いつも見守って下さっていてありがとうございます!
点字と手話について
点字についての参考記事
点字で文章を書くときには、言葉の切れ目に1マス間を空けることが必要です。
(「分かち書き」と呼びます)
例えば、
ずっとひらがなだけでくとうてんもなくそのままかかれているととてもよみにくいわけです
上の書き方では、言葉の切れ目が分かりませんが、
ずっと ひらがなだけで くとうてんもなく そのまま かかれていると とても よみにくい わけです
のように、言葉と言葉の間をあけるだけでぐんと理解しやすくなります。

この「分かち書き」のルールは難しく、そのヒントを示してくれるのが、下記のホームページです。

ちなみに点字を打つ道具として、「携帯点字器」という装置を私は使っています!
点字を打つときは、紙に点を打っていくことになります。小さな針のついた道具で紙を押し込んで、紙を裏返した時にポツッと点が浮き出るようになっていると正解です。
裏側から点字を打ち込んで、表に返したときに意味が通じるように書かなければならないのです。
凸面(点が浮き出た面)、凹面(点がくぼんでいる面)と表現しますが、凸面と凹面は、反転しているので、これが点字をうつときに注意しなければならないポイントのひとつです。
(この反転を意識せずに点字を打つことのできる道具も開発されていたりもするようですよ!)
手話についての参考記事
そして、手話も「とっとり動画ちゃんねる」で紹介されているこちらの動画がよく使う挨拶表現が一本にまとまっていて、とても参考になりそうです!

ほかにも、下記のようなホームページから勉強することができそうです。

まだまだ点字も手話も勉強中の身…。オススメがあればぜひ教えてくださいますととてもうれしいです!!
ぜひ、よろしくお願いいたします。