▶ を押すと文が増えます
歌舞伎のたのしみかた
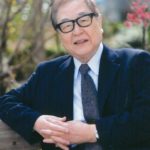
どうもどうも。山川でございます。それでは、みなさんに、歌舞伎のたのしみ方をご紹介していきたいと思います。

山川さん、よろしくお願いいたします。さっそくですが、まず、歌舞伎ってなんで歌舞伎っていうの?という、子どものみなさんからの素朴な疑問がH松の手元に届いています。
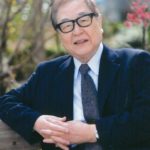
そうですか。それでは、歌舞伎のはじまりをまずご説明して「歌舞伎とは何か」をだんだんとお話いたしましょう。
歌舞伎ってなあに?
(1)歌舞伎のはじまり
歌舞伎…よくよく見ると、ちょっと難しい読み方をする言葉ですね。かぶき、という言葉は、「かぶく」という日本語からきています。傾くと書いて、「かぶく」と読む日本語です。安土桃山時代と言われている時代に、世の中を真っ直ぐに見ず、斜めから見て、見たこともないような派手な格好をして、堅苦しくなく人々を楽しませる…そうやって生きている人のことを「かぶき者」と呼んでいたんです。
そんな、「かぶき者」の精神を取り入れて、「出雲の阿国」さんという人が京都四条河原で「念仏おどり」を踊ったのが歌舞伎のはじまりとされています。念仏おどりが評判になったので、飽きられる前に新しい要素を取り入れなくては!と、出雲の阿国さんは男女の三角関係をテーマにした狂言を考えつくんですね。そうそう。今の歌舞伎は、男の人が女の人の役を演じますが、この時は逆で、女の人が男の人の役を演じていたんですよ。出雲の阿国さんの公演はどんどん評判になっていったのですが、お客さんが脚本に夢中になりすぎるあまり、刃物を使ってのケンカが起きてしまって、大問題になったわけなんですね。幕府も、さすがに見逃すわけにもいかず「女かぶき、まかりならぬ」というおふれ(命令のことです)を出して、上演禁止にしてしまったんです。
でも、そんなことではひるまなかったのが、当時の人たちです。女がダメなら男があるさ…と言ったかどうかは定かではありませんが、とりあえず!の対応として、イケメンの男の人だけを集めて「若衆歌舞伎」を作ってしまったんです。「女かぶき」がまかりならぬのであれば、「若衆」なら良いでしょうという理屈ですね。でも、このチャレンジ、いざやってみると「女以上に色っぽい」と大評判になってしまって、「若衆買い」という穏やかならぬ言葉が生まれてしまうほど、女かぶきよりも始末の悪い状況になったという次第だったんです。江戸幕府もこれは困った…ということで、「若衆歌舞伎」も慌てて禁止令を出すに至りました。
若衆歌舞伎も禁止されてしまって、困ったのは演劇を取り仕切っている業者のみなさんです。それに、街の人たちも娯楽に飢えてしまいました。そこで、業者のみなさんが江戸幕府に上演再開のお願いをして、「前髪のある少年は決して舞台に出さないこと」「色模様(恋愛)のある歌舞伎をやめて、ものまね狂言づくしという演目を上演すること」という2つの条件つきで上演を認めてもらうことになったんですね。前髪のある少年は舞台に上がれない、ということですから、歌舞伎役者は皆、前髪をそった「野郎頭」と言われる髪型にして歌舞伎を演じることになったんです。これが、「野郎歌舞伎」、つまり今の歌舞伎のように男だけで演じる歌舞伎の源になったものです。男だけで演じなければならないので、いかに女の人の動きに踊りを近づけるかという芸が磨かれ、男が女になりきる「女形」が生まれたんです。
goo辞書さんのサイトから、野郎頭のイラストを確認することができます!

(2)女形の魅力
それでは、ここでもう少しだけ、女形という歌舞伎ならではの役割の魅力についてお話ししたいと思います。歌舞伎をあまり知らない人も、歌舞伎といえば男の人だけで演じる演劇!というイメージをもってくださっていると思います。ただ、私がみなさんに知って頂きたいのは、「歌舞伎の女形は、女性そっくりに見せようとしているのではなく、男から見た理想の女性を目標にしているのだ」ということなのです。そっくりに見せようとすることを目標にする芸であれば、女優さんがやればよいという話になってしまいます。女形の役者さんは、女性そっくりに見せる芸ではなく、強くて美しく夢のような姿かたちの女性に魅せる芸を磨き、観客にみせているのです。
女形の見せ場の一つに、口説きの場面があります。歌舞伎を見ているうちに必ず出くわすのが、男女の恋愛、つまりは男女の色模様なのですが。歌舞伎の色模様には、一つの特徴があります。男の役(立役といいます)が懐に手をおいてじっとうつむいている一方で、女形が三味線の音楽に合わせて袖や袂を派手に振って「わたしはあなたのことが大好きです」と口説き続けるという特徴です。長い時間をかけて口説きの場面が展開されていくわけですが、女形にとっては踊りや唄の見せ所になるわけですから、常連さん(大向こうさんといいます)から「待ってましたあ!」と掛け声がかかる、クライマックスのようなシーンなんですね。ぜひ、歌舞伎を観るときには、女形の役者さんの芸に注目してほしいと思います。
(3)ウソをまこと、とたのしむこと
ここまで、歌舞伎の特色ともいえる女形についてのお話をしてきましたが、ここで歌舞伎をたのしむにあたって大切な心構えをお伝えしたいと思います。それは、「ウソをまこと、とたのしむこと」です。歌舞伎にはリアルなものもありますが、どちらかというと、様式美と言われている「お約束」が売りものの演劇なのです。ですから、様式美を成り立たせるために、ちょっとおおげさな演出があったり、よくよく頭で考えると話のつじつまが合わない?と思うようなことがあったりします。「絵になる舞台」を目指すために、ウソやおおげさな表現が使われることが多いのです。でも、それをいちいち理屈で考えていては面白みがありません。あまり考えすぎず、「まあいいか」として、歌舞伎を感覚で観て頂きたい。ウソをまこと、とたのしむお約束に、参加することが大切です。

様式美をたのしむことが大切なのですね。こういう演出があると、こういう話をしているのだよなという「お約束」がだんだんと分かっていくと面白みも深まってきそうだなと思います。山川さんに、引き続き「お約束」を教えて頂きたいのですが…その前に。せっかくなので、歌舞伎にまつわる言葉について、ちょっとだけ寄り道をいたしましょう。これも、まなキキの社会科の「お約束」ということで。
次のページでは、日本語になった歌舞伎の言葉をご紹介します。

