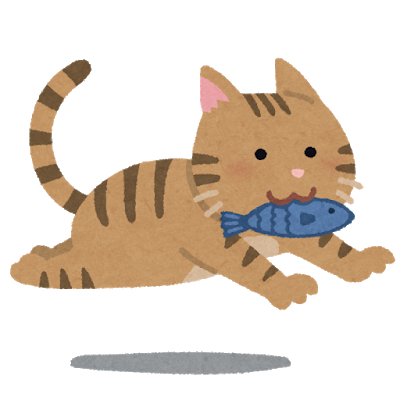▶ を押すと文が増えます
鯛 たい

「魚」に「周」で「鯛」と書くタイ。
その漢字の由来はさまざまな説があるようですが、さかなクンが説明するところによると、その鯛の形の良さに由来しているそうです。
「周」という漢字に注目してみると、
①まわり「周囲」「周辺」
②まわる。めぐる。
③あまねくゆきわたる。手抜かりがない。
(④中国古代の王朝名)
とあります。
その姿形が本当にきれいで調和のとれた魚という意味での「あまねくゆきわたる」、
お祝いに用いられることが多く、先祖を祭り、一族の繁栄を祝福するための魚であった、とう「一族に幸せを行き渡らせる魚」という意味を込めて「魚」に「周」という字をあてた、とも考えられているとか。
おさかなクンの動画の説明の中では、マダイの説明をとても細かく紹介していますよ。
なぜ鯛といえば赤い色をしているのか?や
鯛のトゲや歯の形にも触れています。
※ ちなみに、おさかなクンは「ご」を「ぎょ」と発音するので注意してくださいね。
マダイと似ているお魚のハナダイ(別名をチダイ:その由来も動画の中で説明。)のことも紹介していて、お魚をもっと観察してみたくなること間違いなしです。

お魚にもトゲや歯や毒があるのですね。
釣りをする皆さんは、ぜひ気を付けて釣りを楽しんでくださいね!
駄洒落のように「めでたい」から「鯛」などとよく言われていますが、なぜおめでたいと鯛なのでしょうか。
その背景には、日本では赤色をめでたい色として使ってきた、ということが一つに挙げられるそうです。
そして、文字通り駄洒落的な意味もあったそう‥。「掛詞」のような語呂合わせ・言葉遊びに由来して、「めでたい」と「鯛」にあやかったともいわれています。
そして、鯛はとても長生きな魚だそうで、20~40年生きる長寿の魚でもあるそうですよ。
鰊・鯡 にしん

ニシンの語源は、身を二つに裂いて食用にすることから身が二つで「二身」とする説が有力とされています。
ニシンは鰊や鯡と書きますが、
「鰊」には中国で「小魚の名」という意味を持ち、
「鯡」は「フナに似た魚の名」または「魚卵」という意味を持つ漢字だとか。

ちなみに体長は約35センチ。
築地市場などで取引される魚の中には2メートルを超えるマグロなどもあることを考えると、そのサイズは確かに小さい方、ともいえるかもしれません。
また別の由来もあるようです。
ニシンはもともと寒流性回遊魚で、北海道やサハリン西海岸で獲れることが多いお魚でした。
北海道地域に住んでいたアイヌ民族の人たちにとってニシンはよく食べるお魚の一つだったそうです。
それに由来して、江戸時代、松前の人は、「ニシンは魚に非ず、松前の米なり」と言って、「魚」に「非ず」とニシンを「鯡」と書いたという説です。
それから、お正月にいただくおせち料理によくある「数の子」はニシンの卵です。
おせち料理は、一年の始まりに祈りや願いをこめていただく食事として、願掛けされたメニューがいっぱい込められますが、数の子にはどんな思い入れがあるのでしょうか。

「数の子」という漢字のとおり、非常に多くの卵を持つことから、
「たくさんの子に恵まれますように」「わが家が代々栄えますように」という願いが込められているのですね。
ニシンはアメリカやカナダ、ロシア、ノルウェーなどでも獲れ、親しまれている魚です。
ヨーロッパではニシンは酢漬けや燻製、缶詰内で発酵させて食べる(スウェーデンのシュールストレミングとして知られています。ものすごく強烈なにおいを発する、ということでも有名)ことが多いとか。

ジブリ映画の『魔女の宅急便』でもニシンが登場することは知っていますか?
キキが土砂降りの中ニシンのパイを届けるエピソードが出てくるのですが、実在するイギリス料理だそうです。別名をスターゲイジーパイ「星を見上げるパイ」というニシンのパイです。
イギリスや北欧の人たちにとってニシンはとても馴染みが深い魚であったようであることは、「ヘリンボーン」からもうかがえます。

「ヘリンボーン」とは模様の一種のことで、マフラーやセーターなどで「ヘリンボーン柄」など言われたりします。
「herring ニシン」の「bone 骨」ということで、ニシンを開きにしたときに見える骨を想起させる模様、のことです。
日本では同様の柄のことを「杉綾」と呼び、山形と逆山形からできた織り柄として知られます。

日本では樹の名前に由来するのですね。
なんだか織り方のデザイン一つでも、その地域に暮らしていた人たちの風景が連想できるような気がします。
アイヌの人たちの歴史とニシン漁も欠かせません。
乱獲があまりに進んだことが原因で現在はほとんど獲ることができない魚です。
現在食べているニシンも輸入したニシンであることが多いようです。
ニシンは3~5月にかけて、産卵のために大挙して北海道の西岸に集まってきたそうで、それに由来して「春の訪れを告げる魚」として「ハルツゲウオ」とも呼ばれていたそうです。
鮴 めばる

メバルは、「眼張」とも書かれることがあるそうです。
その由来は目の大きさや形(目が張っている)からということで、とても大きな目が印象的なお魚です。
魚編でもメバルは表すことができます。
「魚」に「休む」で「鮴」です。
海藻付近に生息しあまり移動しないことが理由になって、鮴というそうです。
岩礁域にいるそうなので、釣りに行ったら釣ることができるお魚なのかもしれません。
サイズは全長30センチメートルほどとのこと。

‥‥が、目が大きくてのんびりしたお魚、ということになるのでしょうか?
目は大きいだけあって視力もよいそうで、
幼魚時には小型の甲殻類を、成魚になると甲殻類や小魚を捕食するとか。
(肉食のお魚です…!)
夜行性のお魚で夜になると活発に動き出すとのことなので、実はのんびりしているわけではないのかもしれません。
実は、メバルもニシンと同様、ハルツゲウオとして知られているお魚のようです。
おさかなクンも言っていましたが、
図鑑で調べる時は「メバル」ではなく、「アカメバル」「クロメバル」「シロメバル」で参照できるそうなので注意してみてくださいね。
そんなメバル、煮つけや唐揚げでいただくのがオススメだそうです!

このまま夏のお魚特集か!?と思ったのですが、
既に結構ページを割いてしまっているので、次回のお楽しみにしたいと思います!
夏のお魚もなかなか盛沢山で、M先生が謎に悶々している回でもあります。
よかったら皆さんのお知恵を拝借願います!