▶ を押すと文が増えます
クラスの中で流行る言葉とかってありますか?例えば、私がみなさんくらいの頃、「わけわかめ」とか、そんな言葉がはやりました。


なんとも”わけわかめ”ですよね。
こういう”はやり言葉“は地域によっても違うみたいですね。
方言のようなものなのかもしれません。
同じ対象を指していて、同じ日本語を話しているのに、全く違う表現の仕方をすることもあるようです。
不思議ですね。
地域によっても言葉は変わりますが、どのような集団の中にいるか、によっても変わりますね。
友達同士で話している話題や口調は、
家族のそれとも違うでしょうし、初めて会う人とする会話とも全く異なるものになるでしょう。
昔、オードリーヘップバーンというとてもきれいな映画スターが、
「マイ・フェア・レディ」というとても有名な映画に出演していましたが、その映画では、“ザ・ご令嬢”になるために必死に話し方の訓練を受ける、というお話でした。
社会階層(いわゆるお金持ちと貧しい人など)で話す言葉―イントネーションから発音まで違う、ということが、イギリスではよく話題になるのですが、それをモチーフにした映画だったのですね。
私たちが話す言葉、コミュニケーションの道具としての言葉もとても多様です。それは社会のしくみや人間関係からも影響を受けるものです。まるで国語の話をしていないようですが、国語的な知識がやっぱりベースにはあるのです。
誰がどのような表現をするかで、その言葉の意味は変わってしまう。
その言葉の受け止められ方も変わってしまうことがある。
同じ言葉のはずなのに、その話者がどのような立場、どのような属性(先生とかお父さんとか妹とか)であるか、によってその言葉の持つパワーは変わってくる。
そういった不思議な現象を具体的な例を通じて、“言語学”という学問の分野から書かれたコラムです。
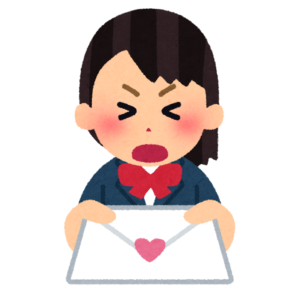
同じ「ありがとう」も日本全国、少しずつ表現が違う。
同じ告白でも「好きだっちゃ」、「好きやねん」、「好きなんさ」、「好きじゃけ」、「好きばい」・・・など様々なドキドキするシチュエーションがあり得るわけです。
方言を標準語に直そう、という矯正の傾向もないわけではないですが、方言には方言の魅力もある。
このコラムでは、さまざまな地域の方言を、それぞれの地域でしか手に入らないお土産の中に発見し、レポートしています。
コラムの第一回目を担当した田中宣廣さんは、
「『方言みやげ・グッズ』や『方言パフォーマンス』など,言語そのものを商品にして利益を得る利用と,『方言ネーミング』や『方言メッセージ』など,言語の工夫した使い方を通して利益にみちびく利用は,『言語の商業的利用』と言えましょう。言語の商業的利用や,それと似た拡張された活用を研究するのは,言語研究の新しい分野」
としています。
簡単に言い換えてみると、
方言が使われていることが、「いいな」、「買ってみたいな」「使ってみようかな」という気持ちにつながっているのかもしれない。そのあたりを、ちょっと探ってみようではないか!と思ったそうです。
方言は、言い方の違い、ということ以上に、私たちの「欲しい」という気持をくすぐるお財布のひもをゆるめさせるヒントとしても重視されているのかもしれません。

