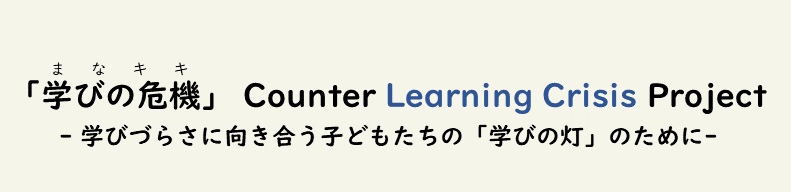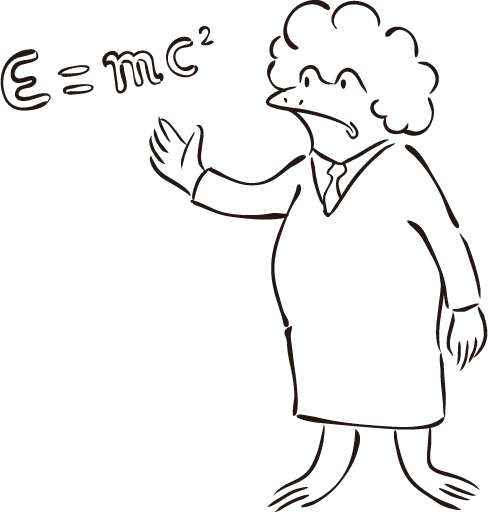▶ を押すと文が増えます
上記目次で該当項目をクリックしていただけますと、希望される講読内容ページに簡単に移動できますのでご活用ください。
第一部の内容はこちら
新型コロナウィルスの危機からの再起が遅れ、“愁い”と“畏れ”に覆われつつある時代。
今こそ必要なのは、周りに左右されず「自分で考える力」を養う学問・科学なのではないか。
私たちにとっての学問の、科学の重要性と必要性を、もう一度考え、それを身につけるための好書を購読します!
「学びの危機」に抗うきっかけづくりのために、一緒に読んでみませんか?
(どなたでもご参加いただけます!)
講読会フライヤーPDFはこちら
オンライン講読会スペシャルのお知らせ
スペシャル回フライヤーはこちら
第十二講 2020年12月22日 討議:”危機”下の学問―2020年を振り返る 補章「3・11以後の科学技術と人間」から
17:30-18:30 テキスト補章講読
18:30-19:30 パネルディスカッション
パネリスト:松本 早野香さん(大妻女子大学)、柴田 邦臣さん(津田塾大学)
まなキキ講読会、2020年の最終回は、「クリスマス・スペシャル版」として「科学哲学への招待」補講:「3.11以後の科学技術と人間」を購読します。科学技術と現代社会を論じる本章の購読を入り口に、後半では、“危機の時代”の情報技術と、学問・科学のあり方をディスカッションしたいと思います。パネリストとして、東日本大震災における災害情報支援を専門とする松本先生をお迎えし、Learning Crisis研代表の柴田をあわせ、皆さんと議論していきます。
講読書籍
『科学哲学への招待』, 野家啓一著, ちくま学芸文庫(2015年)
講読期間
2020年9月29日(火)~2021年1月26日(火) 全15回
開催時間
18:00-19:30ごろ(入退室自由)
参加方法
Google Formを通じてご参加いただけます。
(1回のみのご参加でも、お申込みいただけます。)
ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りさせていただきます。
第六講| 第七章 科学の方法 2020年11月10日
担当:H松さん
当日資料はこちら
当日リポート
先週の文化の日でお休みを挟んで、再開したのが第二部です。
科学が制度化されていったところまでが第一部ですが、それを具体的にどのように実践していったのか、その最もオーソドックスなスタイルについて報告がありました。帰納法と演繹法。これらにどのような限界があったのか、という議論もされました。
まず、帰納法について。帰納法とは、”個別的な命題から普遍的命題を導き出す論証のこと”を指しますが、つまり、たくさんのデータを集めてきてそこから何が言えるのかを問うわけです。そのとき、「前提と結論との関係は必然的ではなく、蓋然的(確率的)なものにとどまる」と本文中に書かれている点について「どれくらいで該当したら、それは法則として認められ得るのか」という疑問が出て来ました。とても難しい問題ですが、おそらく法則となりうるのは100%そうであると認められる必要がある。一方で演繹法は?演繹法は、”普遍的命題から個別的命題を論理的に導き出す方法”ですが、それはつまり新しい知見を生み出さない、ということだとも言えます。
これまで第一部でみてきたようなセントラル・ドグマが否定されてきたプロセスとは一体なんだったのでしょうか。命題から議論を進めながらも観察された事象から結論を導き出し、結果としてセントラル・ドグマを覆してきた‥‥その方法こそが、帰納法と演繹法を組み合わせた仮説演繹法であったのだ、ということをこの日の議論の中で確認することができたともいえます。コペルニクスやガリレイの時代から方法論としてはっきり自覚して実施されてきたわけではない、つまりとてもオーソドックスで自然な思考法でもありながら、それを科学として実践されてきた、ということが科学の方法の確立を確固たるものにしたといえるのかもしれません。それでも先にあげたような帰納法の弱点が解決されたことにはなりません。この問題にどう対処したのか。それが「自然の斉一性」:ひとたび生じたことは、十分に類似した状況のもとでは再び生じ、再びどころか同じ状況が繰り返されるたびごとに生じるであろう、というアプリオリを取り入れることでした。仮説演繹法を用いた議論が絶対的な事実になりえるわけではありません。でもだからこそ、科学理論や科学法則は永遠に「仮説」の身分に身をとどめ、常に経験的テストによる修正や廃棄の可能性に身をさらすもの、ということを認め、そのうえで蓄積されてきた知見にリスペクトを持つことができるのかもしれません。
その後の議論は、7章末尾の「科学者の自由な想像力と創造力」のあたりについてフォーカスしていきます。新しい仮説を発見していく―アブダクション(後件肯定)は、もともと論理的とは認められなかったような思考の方法でしたが、それが逆に仮説を生成していくための手続きとして意味のある考え方として捉えられ採用されていった、という過程についても確認することができました。果たして科学者における想像力/創造力とは一体何のことなのか。「どのような現象を観察しようとするか」なのではないか、という意見も出ました。もしそれがAIにはない側面であるとするならば、どう説明できるのだろう?という疑問にもつながっていきます。とにかく論点が多く出た回でもあったように思います。
さて、次回以降、どんなふうに議論が深まっていくのか楽しみですね。
参加者のみなさんの感想(一部)
今日のまなききでは今までにあまり習ったことがなく馴染みのないことであったのでとても難しい話でした。しかし今までも現在も科学者の方が仮説を立て立証を繰り返してきた、大変素晴らしいことを成し遂げていたということが分かりました。来週のまなききにも出席する予定なので理解を深めたいです。
少し内容が難しく理解し難いところもあったが、教科書を鵜呑みにすることは今後やめていこうと思った。今日の講読会で、もしかしたら101回目は今までと違うことが起きるかもしれないということを聞いて、本当に正しい情報はどこにあるのか模索していきたいと感じた。”
今日一番驚いたことは、H松さんが大学院生であるということでした。また内容に関して、我々学ぶ人間において、何かを知る過程や設定する仮定をどう意識し位置付けていくのかは、重要視していかなくてはならない点だと思いました。AIが発達していく中でも、可能性やデータとの関係性を見つめなおす必要もあると思いました。

AIの論点は今後もぜひ考えていくことができるとおもしろいかもしれませんね。
AIを利用することはいろいろと私たちにもたらすものもあるかもしれませんが、一方で何かを奪うこともあるのかもしれない。そのあたりについて考えていくことができたらなあと思います。
第七講| 第八章 科学の危機 2020年11月17日
担当:K原さん
当日資料はこちら
当日リポート
なかなか難しい議論が続いたこの回。この章では、「数学の危機」と「物理学の危機」を例に、今まで「そうかも」と思っていたものが覆されてきたということ、そして、その危機を受けて考えが収れんされていく契機が議論されていった、ということであったのかもしれません。これまでー第7章までで見てきたような、観察される事象からひとつずつ議論を蓄積されていく試みとして―ニュートンをはじめとする科学者たちは、古典物理学的世界像ともいえるものを確立することに至りました。すなわち、”あらゆる出来事には原因と結果があり、原因が定まればまたおのずから定まる”という「決定論的自然観」です。いわばスーパーコンピューター的に「知性(デーモン)」とは宇宙で生ずるあらゆる出来事は自然法則に基づいて予測可能とみなすような発想です。この議論はその後も「決定論と自由意志」という問題として近代哲学の中でも続いているわけですが…、この章で指摘されたのは、この決定論的自然観が突き当たった壁の存在でした。
どんな”壁”であったのか―が、「数学の危機」、「物理学の危機」として説明されていたわけですが、これまで公理としてみなし、それを前提に議論することで世界の真実を明かすことができると信じられていたものは、あくまでその前提を基に形式的に考えればそのように議論できる、といった論理ゲームのようなもので、決して世界の真実を語りうるものではなかった。そうした気づきがあったからこそ、現代数学への脱皮と発展がもたらされたともあります。物理学においても、量子力学の理論が整備されるにつれて、決定論的な古典物理学的世界像が成り立たないことが明確になっていったことも本の中で指摘されていました。
この本の中で説明されている「決定論的自然観」の議論はやや強調が過ぎたものかもしれないという指摘もありました。「数学の危機や、物理学の危機というのは、決定論が敗れたということとは少し違う話なのではないでしょうか。法則も、因果も、科学は手放してはいないように思います。」ともコメントを頂いた通り、私たちが求めている・目指しているのは、やはり変わらず科学法則や因果関係への推論に基づきながら、科学的にものを説明しようとすることで、世界を明らかにしていこうとするプロセスであるともいえます。今回の8章で説明されていたのは、その過程における限界とその「科学の危機」の克服がどのように歩まれていったのか、説明の”触り”の部分でした。ものの見方、科学的アプローチの取り方、態度の変化が求められたときに問われたのが論理実証主義であった、というところで次章への期待を高めたところで今日は議論を終えます。今がまた新たな「危機」であると考えたとき、突き詰めて今できる「科学」を実践していくことで、限界が初めて明らかになり、乗り越える契機を持つことができるのかもしれません‥‥。
参加者の皆さんの感想(一部)
決定論的自然観に関して、特に人間に当てはまるとしたら人間の行動は操られていて、常に選択しながら生きているというのはつまり実際は選択しているのではなくただ敷かれたレールを辿っているようだなと感じました。この自然観から様々な危機が起こり、時代を重ねるごとにより現実に即していると思われる理論が成立しているということから元々のその危機を起こした理論も重要な役割を果たしているのではないかと思いました。
今回の章を聞いて前提を疑うことの難しさを感じました。普通に読み進めていましたが、私たちが当たり前としていたことはそうやって疑って生まれてきたもので、まずはそこに疑問を持たなくては、議論はなにも生まれていないのだということを改めて感じました。自分は細かい知識がなかったので読むのが大変でしたが、今回のK原さんのレジュメを聞いて少し理解できたかなー?と思えました。
決定論的自然観のような考え方は私たちは普段からしていると思っていて、前例主義とか今までのことに頼ってしまうような人は多いと思います。その考え方が覆されたのはすごいことだと思います。
これまで根本的にこう見る、真実であると思っていたものがそうでないと言われる衝撃はどれほどのものだろうと思いました。しかしそれが洗練されて世の中に正しい知識として発達したとき世の中が変わるような瞬間を見るものだと思います。その衝撃もあるのだろうと思いました。
K原さんも発表の最後でおっしゃっていた様に、科学が発展してきた過程を見てみると、物事に絶対というものはないこと、そして、物事の前提を疑ってみることの重要さを改めて感じました。これまで、様々な自然感が出てきましたが、それだけの過程を踏まえて科学が発展してきたと考えると、それを見る目が少し変わった気がしました。また、様々な人が批判的な目をもって科学を見つめ、現在の様な科学が生まれたということを考えると、現代のあらゆるもの(科学も含めて)について、それは本当か?と考えたくなってきました。そして、それは大切な視点であり、科学だけでなく、あらゆる分野が発展していくためには、とても大切なことなんだと思いました。
今回、初めて参加しました。今回のお話は、文系の私にはとても難しく感じました。これまで当たり前だと思われていたものによって説明できない現象に直面することが危機なのだと解釈できました。人は、世界の全てを説明可能だと思っているので、そのような危機に直面した時には、追求された研究が行われるのだと思います。危機を乗り越えるために研究することで新たな発見があるのなら、危機に直面することでさらに世界の物事に対して理解を深めていけるとも言えるのではないかと思いました。

これまでの理論では説明できない課題が出てきたことが「危機」として捉えられ、新しいアプローチや理解、解釈が包括的に議論をしてきた経緯を見てくることができたといえますよね。
決定論的自然観は実は「前例主義」とは=ではないことは少し注意が必要です。前例主義では何も生み出さないし、決まらないということになるわけですが、実際には前例主義で動いている場面も多くあることは確かでそれはそれで興味深い議論ですよね。
また、「物事には絶対ということはない」というのは本当にそうなのですよね。説明しつづける、ということは、「”絶対”はない」ということを示すことでもあるわけですし、”絶対”があると思えば思うほど、真理から遠ざかっていくものなのですよね。
第八講| 第九章 論理実証主義と統一科学 2020年11月24日
担当:M先生
当日資料はこちら
当日リポート
今回は、狭義の科学哲学を発展させた一潮流として、論理実証主義の展開を見ていくことになりました。前回の『科学の危機』で議論されたものを乗り越えようとするものだったのか、というと、必ずしも、そのように捉えられるものではないかもしれない、ということも指摘されていましたが、それでもドラスティックに科学の在り方、ものの考え方のありようを変える革命的な発想の在り方をもたらしたものの一つが論理実証主義であった、ということができそうです。
何が革命的だったのか、というと、一つが「伝統的論理学」から「記号論理学」への転換だったわけですが、この「伝統的論理学」(名辞を基礎単位とする)がよくわからない、というところからこの日の議論は始まりました。名辞とは英語でいうとtermを指す用語になるわけですが、伝統的論理学ではいわばtermの定義を行うような議論を続けてきました。それは、トートロジー(命題論理で、要素となる命題の真偽がいかなるものであっても、常に真となるような論理式)ともいえるようなもので、その命題の真偽を問うようなものではなかった。それが記号論理学(現代論理学)において真か偽を決めるようなものへと変わっていくことになったわけです。それがまず、大きな変化だった。
そして、この記号論理学では人間の思考は5つの論理結合記号と2つの量記号のみで説明できてしまう、と考えられたものです。世界はその5+2の記号だけで説明がついてしまう。世界は論理で把握することができる―「感覚的経験による実証」―(感覚的経験によって実証できないものは議論の(科学哲学の?)対象とすべきではないとする)と捉え、その議論を発展させていったのがウィーン学団による論理実証主義でした。これまで軽んじられてきたかもしれない「経験」が「論理」と合わせられ、感覚―感情など心理的なものとは別に、五感を通じて得られる経験―から論理を組み立てていったのです。
なんとなく、思考や感情が記号で簡単に表せてしまう、ということに抵抗感を覚えてしまう、ということも議論の中で出て来ました。おそらく、このウィーン学団の論者たちも当時、多くの抵抗も受けながら、この議論を展開していたことがうかがえます。世界の在り方を論理ですべて議論することができるはず、という発想はやがて還元主義的な議論にもつながっていきますが、そこにはやはり限界も生じてきます。論理実証主義は「検証可能性」を以て有意味な科学的命題と形而上学的な命題を区別していましたが、実際に本当の意味で検証可能な議論はどうしても限界があるわけです。次章はこの章を受けての新たな展開があったことが示されていくようです。この本では、まさに科学を議論していくアプローチのダイナミックな展開をフォローしていくことができるのが魅力です。このダイナミズムをますますみなさんと共有していけたら、と思います。
最後に、今日の議論の中では、論理実証主義が展開していった背景には、『科学哲学への招待』の最初のほうの章で出てきた実学的な研究や議論が時代を経て重用されるようになっていった、という歴史の流れとも連動している、という話が確認される一幕もありました。これはもしかすると研究に携わる人たちの「専門化」をもたらすきっかけになっていたのかもしれません。「学問」や「学び」の主体がどこにあるのか、ということを考えていくうえでも、科学へのアプローチのダイナミックな変遷をたどることで、考えていくことができたらなあと思います。
参加者の皆さんの感想(一部)
今回の内容はとても難しく感じました。しかし、数学の命題と物理学の原理の説明になるほどなと思いました。数学の命題に関しては、1+1=2という考えに疑問を持つこともないし、どの時代どの場所に行ってもその命題に違いが生まれることもなく、わざわざ現実世界で実証して経験する必要性がありません。でも、物理学の原理は周りの環境に依存すると思うので実証して経験する過程が必要があると感じました。
本日初めて参加させていただきました。とても内容が難しかったです。全てのことが、実証、検証可能でデータにより説明することができることを学びました。しかし、本当にそうなのかがどうなのか、自分の突発的な行動まで全てが説明できるということに納得ができませんでした。哲学というのは奥が深くて理解をするのが難しかったです。
柴田先生のお話が特にわかりやすく、理解しやすかったです。”リアじゅうはしね”というお言葉で笑うことができました。
「我々の思考は記号で表すことができる」という話について、最初は抵抗がありました。しかし、よく考えるとドラマや現実の人間関係は記号によって表すことが可能です。むしろ、自分の頭の中では記号化して理解していたなあと気づきました。また、恋愛ものの物語ほど、「お約束」があることが多いですが、これは思考が検証可能なものであるからなのかと考えました。
E・マッハの科学観とデカルトの「物心二元論」について、どちらも正しいような、当てはまらないこともあるような、複雑な気持ちになりました。感覚的経験が全てと言われても、物体と精神は別のものだ(物体に精神は宿っていない)と言われても、どちらも完全には納得できないような感じがします。ただし、そのような「受け入れられない」という感じは「感覚」であり「精神」です。それは、確かなものである、とはとても言えないものであり、論理的でない、証明できないものにすぎません。真理であること、実証できること、それを受け入れられるかは、それぞれ別のことではないかと、個人的な感情論になってしまいますが、そう思いました。
今日の論理実証主義ですが、論理と感覚的経験を、そんなに簡単にくっつけていいのかなあというのが疑問というか、よくわからないところでした。
論理は普遍的に共有できると思いますが、暑いとか寒いとか、感覚は一人一人異なることも多く、真理の根拠となるのでしょうか。
論理と実証のつながり方が、たとえば演繹法と帰納法の関係とは、どう違うのか、同じなのか。実証というのは、柴田先生のおっしゃるような、科学実験ということなのでしょうか。ならば、近代科学の仮説演繹法と、今回の論理実証主義は、どう違うのか、同じなのか。
なかなか難しかったです。

論理実証主義がどこまでウェイトの大きな議論であったのか、というと実はそこまで大きいものとはいえないかもしれません。ただ、論理実証主義というものの考え方がユニークなのは、「論理」と「経験」を個別にみるのではなく、相互に作用させながら見た、ということにあるのかもしれないなあと思いますね。それでも、社会は理屈や感覚だけで成り立っているわけではないですから、限界もあった。そしてそれを見るのが第九講(第十章)ということになりますが‥‥。
数学の命題が環境に作用されない、というコメントもいただきましたが、実はこんな例もあります。「リンゴが1個、みかんが一個、あわせていくつ?」という問題があるとき、素直に「2」とは答え難いということがあり得ると思うんですよね。いろいろ状況によっては「2」とは必ずしも答えない可能性もあるわけで。そう思うとまた面白いですよね。
恋愛だけでなくてお笑いなども記号論で説明できてしまうなんてこともあるかもしれないですね。
私たちはまだまだ「感覚」や「精神」といったようなことを議論していく余地が残されているともいえるかもしれません。論理実証主義のいう「経験」は、どちらかというと「人類共通の経験」として前提して議論を進めているところがあるので、危うさがあるかもしれませんね。仮説演繹法と論理実証主義の違いですが、厳密にいうと、仮説演繹法という方法論があって、その上で論理実証主義という主義が登場してきた、と考えていただくと少し分かりやすくなるかもしれません。
第九講| 第十章 批判合理主義と反証可能性 2020年12月1日
担当:O田さん
当日資料はこちら
当日リポート
論理実証主義は検証可能性という観点から科学的な議論を説明しようとしてきたわけですが、今回の主役はカール・ポパーということで、ポパーが主張した「反証」がどのようなものか、その革新性についてを中心に議論していくことになりました。
ポパーが指摘した「反証可能性」とは何だったのでしょうか。反証とは、「ある仮説から導かれたテスト命題が偽であることを実験的検証を通じて示すことにより、もとの仮説の正しさを否定する論理構造」とありました。何らかの仮説や仮定(推測)があって経験/観察される事象があるわけですが、そこでその仮説をあらゆる科学的手段に訴えて反駁しようと試みる過程が持たれます。もしも立てた仮説が厳密な実験や観察によって反証されたらその仮説は廃棄されまた新たな仮説を提起し、また反駁を繰り返していく。そうした試行錯誤のプロセスのことが「反証」であり、「科学の本質」とポパーは考えたのです。
ポパーは、「検証と反証の非対称性」を唱えてもいます。検証と反証のアプローチとはそれぞれどのようなものか。柴田先生が分かりやすく例を挙げてくださっていました。
《検証》
すべての人類がリア充ならば某氏はリア充である。
某氏はリア充である。すなわちすべての人類はリア充だ。‥‥とはおかしいはずなのです。
ですが、「自然の斉一性」(第六講で取り扱った第七章で登場)の観点では上述のような論理も成立してしまう。ポパーはこの検証が後件肯定に陥ってしまっていることを指摘し、これではいつでも真実に到達しない、と指摘するのです。
《反証》
すべての人類がリア充ならばS田はリア充である。
某氏はリア充である。しかし、S田はリア充ではない。すなわちすべての人類がリア充とはいえない。
命題に対して反証することで、より厳密性と普遍性を持って議論することが可能になる、ということを指摘したのです。このことがとても劇的なことでした。
これまで科学であるかどうかを形而上学的に考えたり、経験という観点から説明しようとしてきましたが、いずれも曖昧なままでした。ポパーはこの反証に絞り込んで科学の本質を問うていくことで、より共有可能な真実に近づくことができると主張したのです。
当日は、O田さんが論点も挙げてくださり、それに従って議論が進みました。
「科学」とは「真理」を意味するのではなく、どうやら「プロセス」や「探求」、「試行錯誤」そのものを指すようだという確認もされました。また、ポパーが「科学理論」をダーウィンの進化論と重ね合わせて理解しようとした点についても議論が及びました。ポパーは、科学的仮説は常に反証される可能性を持っており、現在受け入れられている科学的仮説も「暫定的仮説」に留まるものだ、と指摘しています。将来的に覆される可能性ももちろんあるが、数々の反証をかいくぐって現在まで生き延びてきた、そのdefending championとしての特性が進化論でいう生存競争を生き抜いてきた生物種という発想と類似する側面をもつのではないか、としてこのアナロジーを用いて説明を試みたのです。
ポパーは反証される可能性が高ければ高いほどその仮説は「科学的」であるとします。これは大胆な仮説をもって反証をしようとするような、いわば”異質”な見方を歓迎するような考え方ともいえます。つまり、誰もが自由な観点から「反証」をしていくことができるように「開かれた」ものであることも非常に大事にされたのです。こうしたポパーの発想は相対主義的な考え方が拡がっていくきっかけにもなったようなものでしたが、ポパー自身は普遍的な議論としてのdefending championの持つ重要性にも重きを置いていました。ポパーは相対主義的な発想と普遍主義的な発想を両立した議論を展開してきた本当に画期的な思想家であった、とも話されました。
長くなってしまいましたが最後に…。この反証を可能にするためには批判主義的な精神が欠かすことができないが、批判主義的精神は健全な民主主義からしか生まれない、ともポパーは指摘しています。「学び」というものを考えるとき、この批判主義的精神を守っていくことが非常に重要になってくると思われます。まなキキについてのアプローチもO田さんにご指摘いただきましたが、異なる学び方を考えて提案していく試みや、異なる観点から「学び」を考え直してみることで新たな議論を生んだり問題を明らかにしていくような試みを実践してきたといえるかもしれません。
参加者の皆さんの感想(一部)
ポパーの科学観になるほどなと感じました。推測が繰り返し反駁されることによって、より洗練された仮説が生まれて真実に近づくことができるのではないかと思いました。そのように考えると、反駁できないと思われるものは真実であるようで、実際は真実から遠いものだという可能性もあるのではないかと思いました。
「進歩」や「異文化の視点」、進化論等の論点について、少しズレるかもですが、考えたことを書きます。 そもそも、障害や子供、異文化における弱者について語る際、あるいはそうでなくても、あらゆる文脈において、進化論が前提にあるように思えます。実際、私もそうです。「障害のある人たち」の存在にフォーカスすることは時に重要な視点を与えてくれることは確かなのだと思います。しかし、そこに潜む進化論的な視点がある可能性も自覚として排除できないようにも思えます。遅れている・進んでいるという序列付けは、他者との差異のなかに我々が存在している以上、なされるものなのではないでしょうか。障害種・程度も、障害で区切るならば知的障害の有無によってもだいぶ異なると思いますし、そうでなくても何かに対する優劣も異なり、その異なり様は健常者の中にも存在するはずが、あらゆる議論で「障害のある人たち」という主語でまとめられることに納得がいっていません。区別は大事、でも、「障害のある人たちの存在」って、何だか、進化論のようです。こんなに敏感に反応する必要もないかもしれませんが。
今回の講読会を経て、「科学」とは結局何であるのか、わかってきたような、わからなくなってきたような、それこそ自分の中の考えが揺らいでいるように思います。科学は真理を探究するものである、けれど、その真理は何度も変わり、証明・反証などのプロセスを経て新しい「真理」が生まれてきた、それならば、私たちはいつ「真理」にたどり着くのか、たどり着く日はくるのでしょうか。また、的外れであり意味のない意見ではありますが、「科学」が成り立つのには、「人間の思考・意思」が一つの要素ではないかと思いました。これまで触れられてきたように、科学は「観察・実験・反証」などにより成り立っている。けれど、それらを行う際には、「観察しよう、実験しよう、反証しよう」という意思が存在するのではないか、すなわち、科学を成り立たせる要素の前段階は人間の意思・思考なのではないでしょうか。ただし、感情的な意見になってしまいますが、そんなことを言ったら何にもならないし、そんなことは追求の価値に値しない。仮にそれを結論としてしまったら、それは多様性を消すことである。やはり、意味がない意見になってしまうと思いました。
久しぶりの参加でしたので、以下の感想を送らせていただきます。
1)レジュメについて(従来のものと非常に印象が違った)
①ページ数が多く、内容が重厚
②本章内容に関する「例題」の取り上げ方が分り易い
③表の作成・提示
④本書だけでなく、他の文献も読み込み(例 レヴィ=ストロース)、ここでも当を得た分り易い部分が「例」として取り上げられていた
⑤O田さんの「問」が事前にご自身の視点も加えて詳しく提示され、参加者に、より深く考える「時」が与えれている
以上①~⑤の理由で、本日の担当者は、「骨太の男性的な大学院生」と想像し、「津田塾大学にも凄い院生がいるものだ」…と楽しみに参加しました。Zoom画面を見て納得。「では、なぜZoom の背景が『ピンクの織物』なのか?」の疑問も、H松さんの担当者紹介で、更に納得したというユニークな講読会でした。
2)レジュメ p.4 の「問⑤」に、視覚障害、重複障害のある小学生に9年間英語を 教えた経験から私見を述べ、皆さんのコメントを頂ければ幸甚です。
①自閉症のある全盲1年生男児の例:自由入部の「英語クラブ」に参加しても「オラ日本人。英語はしゃべらねえ~」。児童が良く知っている “Happy Birthday” の替え歌で “Good afternoon” と挨拶を教えようとしても、「そりゃお誕生日会の歌だ!」と一人、英語で元歌を歌う。しかし、アメリカ人のゲストティーチャーには、しっかりと英語で “Nice to meet you.” と挨拶ができる。
②「視覚障害児」と言っても、生来の全盲から、中途失明児まで在籍し、「弱視児」の障害の度合いもいろいろで、まず、「アルファベット文字指導」や、「色の指導」に工夫を要する。一方、「耳」の良い児童が多いので、口頭の練習は、大変楽しく活発に行える。「知的好奇心」も大変旺盛で、「耳学問」による教科書外の知識を与えることにも腐心した。
他にもたくさん事例はありますが、①、②で彼らから学んだことは、心理的にも、身体機能的にも「彼らはそれぞれ彼らの世界に住んでおり、各人が『自分のものさし』を持っている」と言うことでした。いわゆる「健常者」が、その「物差し」で対処しても効果はありません。まさに「仮説」を立て、試行錯誤の日々でした。一方、「社会生活」を共生していく為には、「晴眼者」とも話が通ずることが求められ、「色」も教えるなど、「自立活動」との連携も重要でした。
3)「なぜまなキキでこの本を取り上げ、講読するのか?」のO田氏の質問に関して:
ディレクターの柴田先生が「正解」をお持ちでしょうが、私も最初は同じ疑問を持ちました。しかし読み進むうち、2)-①、②の児童に英語を教えるという目的を持つ『ものさし』で測れば、可算名詞と不可算名詞の「科学」の英訳、University や school の語源など、まさに「高級耳学問の宝庫」。「英語の文章は、語順を教えればよい」に加えて、本書、pp.146~147 にある「論理的な接続詞」5個を教えれば、更に論理的思考を伴う文章が書けるのではないか…など、本購読会の目的には合わない可能性のある「違った視点」 から読んでいます。
一方、かつては、自閉症のある児童に対しては、「親の育て方が悪いから、わがままなのだ」などと言われていたものが、脳科学・医学的見地から真相が解明された事例を見聞すると、「旧仮説・知識」が、「検証・反証」によって「正しい科学的真理」へと移行する本書の「科学の歴史」に通じる物があると感じました。
最後まで頑張って参加し、学ばせていただきたく存じおります
お一人、障がいの問題と進歩の問題と絡めて感想をくださっていますね。この方がおっしゃるように、遅れている、進んでいるという序列付けは、我々も無意識のうちに持ってしまう恐れが常にあると思います。障害のある人たち、という形で括ってしまうことへの違和感も、健常者だっていろいろな異なりようがあるはず、という指摘もその通りだと思います。それを認めたうえで、どんなことを考えていけるのでしょうか。
この方のコメントから、少し広げて考えてみると、「科学」が優位な文明社会では、科学の知識やスキルを持った人や文化が、優れた人、あるいは勝者として認められたり、権力や富をもったりすることがあります。ある程度は認められてもよいのでしょうが、「科学」から遠い存在が、差別されたり、貧しかったりしてよいことにはなりません。ですが、歴史的には、科学文明の力を背景に、それが経済力や軍事力と結びついて、異文化を支配する、そんな時代はかつてあったし、今もそう変わっていないかもしれません。
「障害」については、どうでしょうか。「障害」のありようも多様ですから、障害のある人の科学へのアプローチも多種多様だとは思います。障害のある人がプログラマーとして活躍する、なんて話も珍しくなくなりました。とはいっても、それこそ進化論的、優生学的な発想から、障がい者虐殺のようなことが行われたのも、やはりそんなに昔のことではありません。科学の看板も借りて行われた、悲惨な事件です。
さて今回、ラーニングクライシス実態調査の中間報告を改めて読んでみました。障害のある子どもたちの学習に、いろいろな困難が降りかかっているのがわかります。手から手に教えるような科目の困難さ。IC環境の不十分さ、あるいは家庭における格差。協同体験や直接体験の困難さ。時間調整、保護者・児童との調整、訪問などの教師の負担、等々。私たち障害者作業所の抱える困難にも通じるところがたくさんあると思いました。
そして、先日の「大学の危機を考える」スペシャル回では、大学生や先生方の抱える困難について、あらためて認識しました。これほど大変な状況にあるとは、大学外の者にとっては、想像がつきませんでした。特別支援学校の問題とも、かなり共通する困難があるように思いました。
そして、障害のある子供たちは、さらに厳しい環境に置かれているのだろうと思います。さて、こうした問題と、今回の読書会や、ポパーの議論は、どうつながってくるのでしょうか?問いを発した僕自身は、あまりはっきりした答えを用意していたわけではなく、よくわからないからこそ、聞いてみたかったというのが、正直なところでした。改めて、少し考えてみました。まず、ポパーの問題意識の一つは、科学の絶対的根拠はない、絶対正しいなんて言えず反論に開かれてなくてはいけない、ということです。僕なりの言葉でとらえると、科学文明の優位性を、唯一絶対の正しいものとして、異なる価値観を持つ人たちや文化に対して、押し付けたり自分たちこそが優れているという態度に出るべきではない、ということです。あるいは、障害のある人たちの問題に引き付けると、知識の優位性が、人間の優劣につながるものではないし、そのことで差別されてはならないということです。ですが、一方で、これは柴田先生が、相対性と同時に普遍性について考えているという言い方をされていたことに非常に共感するのですが、異なる価値観の人たちが、出会い、共存したり協同したりするときに、何を共通の土台とするのかが問題になります。「科学」というものはその共通の基盤の一つになりうるものだと思います。
最初にあげた、絶対ではないということと一見すると矛盾しますよね。ポパーは、科学の論証の手続きを明確にして、どんな実験をすれば確かめうるか(あるいは反証しうるか)、方法を提示することを重視しました。これなら、信仰が異なろうが、民族が異なろうが、こうやって確かめてみてくださいと、提示すればよい。それが、オープンで、平等であるということだと思います。方法と、真理(命題や主張)は、密接不可分なのだと思います。もちろん、文化によっては、ビーカー、フラスコなどの器具を用いた実験などになじみのない人たちも多数いるでしょう。ですが、たとえばレヴィ=ストロ-スの言うような、農耕、牧畜、機織り、陶芸などなどのレベルでの、観察、実験などであれば、どんな文化であっても、何かしら身近な問題として取り組んだものが必ずあるのではないでしょうか。そういう意味での、知識や科学の蓄積や進歩というものは、信じてもよい気がします。学校の中であろうが、外であろうが、広く根源的な意味での知識とか学びの重要性は失われず、人類にとっては普遍性や共通性があると信じたいと思います。
もう一度、「学びの危機」の問題に戻ると、手を動かしながら、手から手に伝える学びや教育ができない、というのはかなり深刻な危機と言えるでしょう。あるいは、協同作業や議論の場が失われてしまうことも、恐ろしいことです。ポパーの議論から感じるのは、絶対的根拠や真実はない、だからといって、科学や知識が無意味なのではない。仮説を提起し、実験し、反論を受け止めて議論しうる方法として、だれもが平等に参加しうる作法あるいは文化として、科学の役割がある。多様な価値観や文化が共存するためにも、科学は可能性を持つのだと、私は思います。そのためにも、前提として、この科学や学ぶことの平等性というのは、大切な問題です。学ぶことかとからマイノリティの人たちが排除されない配慮が必要だと思います。今この危機において、学ぶこと自体、そしてその平等性が、大きく揺らいでいるのだと思います。そこに、「まなキキ」プロジェクトの一つの大切な社会的意義があるのだと思います。と、勝手に考えてみました。改めて、今後議論を深めていけたらよいなと思います。(O田さん)

反証によって科学性が高まっていくのですね。だから、反証できない、ということは真実から遠ざかっている、といえそうです。
あと、「進化論」についてですが、実は「優生学」とは区別して考える必要があります。実はダーウィンは、絶滅したものが劣っているとは全く言っていないんですね。恐竜などもむしろ過剰に適応しすぎたことが原因となって絶滅したという議論もあったりしていて、ラッキーでたまたま生き残ってしまってきたものも多くある、ということがあるのです。
また、「障害のある人達」「障害者」とくくって議論してしまうことの問題を指摘してくださいましたが、非常に大事な論点ですよね。ですが、Disability Studiesの中で、”Disabled”と障害のある当事者のことを呼んで議論することがあります。障害者に共通する問題を捉えて同盟を組んで闘っていこうというような巧みな戦略を以て議論してきているとも言えなくもないわけです。そういうふうに改めて捉えてみるとカール・ポパーが進化論と重ね合わせて議論した、ということについてまた違った角度から理解を深めることができるかもしれません。
3番目にコメントしてくださった内容はサクラなのではないか、と思ってしまうほど、まさに今日(12/8)論じていこうとしている内容と重なってくるものですね。まさに科学知識をどう持とうとするのか、という哲学の話へと展開していくのです。
また、まなキキでこうした講読会を実施することの意味ですが、別に科学哲学や科学社会学に詳しくなるために読んでいるわけではないのですよね。ただこうした本を通じて学ぶことは、自分が現在持っているテーマや関心、学問の在り方を非常にクリアーにしていくことにつながると思うのです。分析軸を持っていくことにつながります。私たちは「科学的に考えよう」と日々生きていると思うのです。そのときにどのような考え方に基づいて「科学的に考える」ことができるのか、というとき、こうした試みを通じて武器を身に付けることにもつながるのではないかな、と思います。
第十講| 第十一章 知識の全体論と決定実験
担当:Kさん
当日資料はこちら
当日リポート
議論は、クワインの論理実証主義の批判が具体的にどういう批判であったのか、確認するところから始まっていきます。論理実証主義には二つのドグマがあるという批判をクワインは実施していました。①総合的真理と分析的真理の差を論理実証主義は指摘してきていました。実験や観察などの経験を通じていくことのできる「総合的真理」こそが検証可能なものであって、経験から議論できないものは科学ではない、といったことを指摘してきたわけですが、クワインはそれを否定する。「総合的真理も分析的真理も実はただの一つの知識に過ぎない」というわけです。知識活動の集大成として蓄積されてきた結果を「真実」とみなしているだけで、それらは知識のネットワークを築くものでしかない―知識全体論の発想―と指摘します。
論理実証主義のドグマの二つ目は、「還元主義」でした。「有意味な命題はすべて直接的な経験を表す命題に還元することができる」とするものです。ですが、クワインは、知識活動の集大成として生産してきた知的生産物の結果として知識体系があるだけで、そもそも客観的に存在が認められるような「知識」が個別に存在しているわけではないのだと、指摘するのです。
この発想はやがて、「本質」や「真理」というものはない、という相対主義的な発想に至っていくものです。これまで「世界の真理」に近づくために検証や反証などの試みが続けられてきたわけですが、そもそも絶対的な確実な「真理」というものはない、というのです。つまり、この議論にすら反証することが意味をなさない、ということにもなり得ます。「パラレルワールド」や「世界線」のようなものを連想する、といった感想も聞かれました。
クワインの議論を引いて出てきたのがプラグマティズム。このプラグマティズムってなんだろう?というところで次の議論も盛り上がっていきました。プラグマティズムは、研究を実施している研究者、「行為者」の視点で行為された結果からしか真理について考えていくことはできない、と捉える考え方と言えます。ひとつひとつの行為―生産物の集まったものによって世界が築かれていく、生産物の集大成が世界の全体像を築くといった発想が、クワインのいう「自然主義」に近いものだろうという指摘もされました。もはや、真理を想定して繰り返して実践していくこと、行為を通じて、真実(本質)というものが築かれていくのです。こうして自分たちが行為していくことによって真実や本質を定義していく在り方を「内在的実在論」とも呼ぶようになったのです。
長くなってきましたが、最後にプラグマティズムの代表的な論者として、R・ローティのプラグマティズムの特質の整理について当日も確認されていたので振り返っておきたいと思います。まず、「事実と価値の連続性」。これは、私たちが「ファクト」と認められるものには「価値」がある、ということを同時に示してもいる、と捉えると分かりやすくなるかもしれません。つまり科学というものは「何を真理としようかね」というゲームの様相をも示すようになってきたということでもあります。これは極端な言い方かもしれませんが、このような発想に立ったからこそ、二つ目の特質「反本質主義」が成立することになります。客観的な事実というものはない、本質というものは存在しない、という意味での反本質主義ですね。相対主義の発想はここから出てきているとも言えます。(厳密に言うと、プラグマティズム=相対主義ではないとも指摘されました)。三つ目の特質は「会話の継続」。行為した結果が真実になるのだから、常に私たちは「行為」しつづけなくてはならない、ということでもあるのです。私たちは、真理と思えるものを想定してそれを周りの人たちにも合意してもらえるように科学的方法を使って説得していこうと記述という「行為」を続けていくことをしているとも言えます。かつては、絶対的な「真理」なるものを探求するために科学的方法を用いてきたのかもしれませんが、今日は、世界の真理を証明するのではなく説明しようと努力することになるのです。一見、ファクトを記述してどれだけの合意が得られるかで、それが「真実」としての様相を示していく、と聞くと非常に政治的な意味合いも含まれてきてしまうようにも感じられる、という意見も出されました。政治ではなく、科学としての議論、コミュニケーションをとって開かれていくことが、だからこそ大事になるのだ、ということも話されました。
これから「知識」についての議論ではなく社会的生産物の展開、科学者の社会的行為を考えるといった科学社会学の議論へと軸足を移していくことになります。今日がその議論の展開の幕開けともいえる章でもあったわけです。次回もぜひ楽しみに講読していけたらと思います。(長くなってすみません)
参加者の皆さんの感想(一部)
第一のドグマ(分析的真理/総合的真理という二分法)について。発表した後に、「あれ、数学的言明は、一概に分析的真理と言えるのか?」と突っかかりました。 例えば、足し算や引き算は、ブロックや指折りなどを用いた経験を通して正しさを実証していたりもしました。つまり、経験で判断していたといえると思います。まなキキで記事を書く時にも、経験から学べるよう促しているつもりです。 よって、数学的言明は総合的真理なのでは?と思いました。が、その後、「算数」と「数学」の違いがあったことも思い出しました。どうなのでしょう。 でも、総合的真理であるとしたら、検証が不可能な領域は…? ちょっと難しかったです。
前回のコメントの、科学を成り立たせる前段階はしよう、という意思・思考なのではないかという意見に本当にはっとさせられました。結局、私たちが科学などの確実だと信じるものは考えだすと揺らぐ脆いものなのではないかと感じました。 クワインの考え方で、科学は我々の知識活動の一つの見方である、知識の生産物であるといくことがわかりました。反証はなく、これを真実とする、としたものであり、そこからが始まりとすると真理とはなんだろうと思いました。クワインの考え方は、少し考え方がずれたり、違う考え方をしたりするとものすごく変わってくるものなのではと思いました。しかし、その考え方を打ち出せたのは本当にすごいと思いました。私はこの考え方により科学はより進んだのではないかと思いました。どんな時でも多様な見方をすることの重要性を感じました。 柴田先生が「行為者が死んだらなくなる」と言っていましたが、そういう知識とはなんだろうと思いました。やっている人がいなくなったら消える知識は知識と言えるのか。知識はそんなき脆いものだったのかと少し衝撃でした。
知識全体論を我々が生産している知識の総体と考えることができると解説がされていた。このことは、知識も有形の「もの」と同様に古くなる(劣化する)ということを意味するのだろうか?と疑問に思った。私たちが生産しているものは、最終的には古くなり劣化するだろう。そうであるならば、生産される知識も同様の結果を迎えるといえるのか。それとも、目に見えるような「もの」と、目に見えないような「知識」の「生産」は、異なる概念の「生産」なのか。「知識」という言葉の概念に興味をもった。
講読会の最後に、S田先生が「大切なのは対話の継続」というようなことをおっしゃっていたと思うのですが、コロナ渦の現在、私たちはより一層、「わかりやすさ」や「はっきりとしたもの」を求めているように思います。ですが、今日の購読会を通して、そうした単純でわかりやすいものの先に真理はなく、私たちは複雑さや、不適切な言葉かもしれませんが、「面倒くささ」を受け入れて生きていかなければならないのだと改めて思いました。
第10章担当者のO田氏の質問:「本書をIESで取り上げる理由は?」 ディレクター柴田先生の解説で答えが見つかった「第11章講読会」であった。
①「取り上げた理由」:各人の研究内容に合わせて本著を読み、何か納得いく指針を見つけてほしい。見つかればよい。(…の趣旨と解釈しました)
②「第11章は、『クライマックス』ともいうべき章である」:IESの目的は、まさにパースの考えである( p.185)<研究者の共同体が真理を探求していく試行錯誤と自己修正のプロセスを重視し、研究者の共同体が研究の末に到達する収束地点で獲得される確信こそが「真理」である>(…と納得しました)

算数・数学の発想は総合的真理といえるのではないか、ということについては、そのとおりですね。まさにクワインはそのことを指摘したのだともいえますが、純粋に数学をやっている研究者にとっては、分析的真理としての意味合いをもっているかもしれません。
二つ目のコメントもとても論理的にかかれていますし、三つ目のコメントもとても発展的な指摘をしてくださっていますね。本当に「知識って何なんだろう」ということについて考えさせられますよね。「劣化する」というのもまさにそのとおりだと思うのですが、誰の目から見たときに「劣化するのか」ということも併せて考えてみたいですね。
そして、四番目のコメントも本当にそのとおりですね。例えば今の時代における”分かりやすさ”にはもしかしたらAIも該当してくるのかもしれません。でも、私たちがこれまでこの『科学哲学への招待』を読みながら学んで知ってきたのは、「失敗しながら、葛藤しながら獲得されてきた知の営み」そのものであったと思います。やっぱり、葛藤したり獲得した結果を安易に誰かから教えてもらおうとするのはやめたほうがいいと思います。悩むこと、考えていくことが大事なんだと思います。ただ、悩むのも漠然と悩んじゃうと堂々巡りしてしまったりするので、悩み方が大事。その「悩み方」こそ、積み上げてきた「科学」の蓄積から学ぶことができると思うんですよね。最後の感想に関してもまさにそのとおりです。しっかり悩みましょう。そしてしっかり考えていきましょう。
第十一講| 第十二章 パラダイム論と通約不可能性
担当:K原先輩
当日資料はこちら
当日リポート
当日は冬らしい寒い一日となりました。パラダイム転換とは、単なる「変化」を意味するのか、「進歩」と捉えるべきなのか?というあたりから議論は進んでいきます。「知識」が築かれていくプロセスというものは単に社会の変化や歴史的条件に影響を受けていく、と捉えてしまってもいいのだろうか?という疑問も浮かんできました。今まさに直面しているCOVID-19もひとつのパラダイムの転換のきっかけになったりしうるのかしら???と「なんかなんか…うーん…」とハテナがあふれてきた頃合いで、そもそもクワインが指摘してきた「知識」とクーンが指摘する「知識」にどのような差があるのか、立ち戻って考えてみることになりました。
クワインが指摘した「知識」はネットワークで体系化されていくような種のもので、知の全体性を論じるようなものでした。一方でクーンのそれは「知識」というものはひとつひとつのパラダイムの中にあるようなものとして捉えられます。
クワインおよび論理実証主義も含めた論者たちは、いわば”経験至上主義”であったといえます。知を築いていく土台には「経験」がある、として、形而上学的な発想を否定してきたわけです。しかし、クーンは、そもそも土台になりうるとしてきた「経験」そのものも本当に客観性の確保されたものなのか、バイアスのかかったものなのではないか?と疑い、”知の全体性”なるものは構築し得ないのではないかと指摘するのです。
クーンの指摘は、ひとつひとつの「知識」はひとつひとつのパラダイムの中にあり、それぞれの中で蓄積される「通常科学」のルーティンの中で達せられていくとします。そして、パラダイム間の知識のやりとりや対話は成立しない、とするのです。それが章のタイトルでもあった「通約不可能性」という言葉の意味を示すものになるのです。クーンの指摘はサイエンス、科学の本質を否定するようなものであった、といえるかもしれません。
ただし、クーンのパラダイム論は社会科学や文系のものの考え方・捉え方に大きなインパクトをもたらします。第三部へと続くサイエンス・ウォーズはこのあたりに端を発しています。例えば、alternativeな見方が成立するといった議論はクーンのパラダイム論によって支えられてもいるのです。サピア・ウォーフの仮説など哲学的な基礎を支えてきているといってもよいでしょう。
また、クーンの功績は、クライシスの現出を説明しているという点にも挙げられます。(柴田先生がLearning Crisisという表現を使い、「コロナ禍」という表現を避ける背景には、クーンの用いるクライシスという用語があるといいます)クーンは、通常科学のルーティンでは説明することのできない変則事例が現れることを「クライシス」と呼び、それがパラダイムの転換になる―新しい見方が生まれるきっかけになるとしています。つまり、クライシスは乗り越えられる対象として説明されるわけです。
クーンの指摘は今日私たちが親しんでいる議論とも大きく関っていますし、魅力的な議論であるとはいえそうです。ただし、真実というものはパラダイムによって異なりうる、というアルト・ファクト(alt-fact)を指摘したことは、パラダイム論の弱点にもつながっていくともいえます。それが先ほども少し触れた、パラダイム間のコミュニケーションは成立しない、という通約不可能性の問題です。第12章では、ポパーとクーンの議論についても説明されていました。ポパーはクーンのパラダイム論を批判していくわけですが、それは「反証可能性」の発想が、論理的に以前の議論ーいわば旧パラダイムを革新させていくような共有可能な土台としての役割を果たす、とポパーが確信していたからこそでした。通約不可能性を克服する術はあって、それが「反証可能性」という発想そのものだ、としたのです。
科学的な議論をしていく際に、反証事例を見出すことで以前の仮説を否定し、新たな命題を掲げていくとする反証可能性の発想は、科学的思考を支える共通の土台になりうる、というものです。この議論は実は、『科学哲学への招待』の第一部第一章の<可算名詞の科学>と<不可算名詞の科学>の議論を思い起こすと理解しやすくなるかもしれません。ポパーの主張は<不可算名詞の科学>を意味するようなものであり、今私たちが改めて考えていかなくてはならないのも、この<不可算名詞の科学>なのではないか、というあたりで、興奮冷めやらぬまま当日の議論を終えたのでした。
参加者の皆さんの感想(一部)
今回も内容が難しかったですが、お姉様方の議論が聞いていてとても楽しかったです。ありがとうございました。?
クーンのパラダイム論ですが、個人的にはとても納得できたと思います。「古い理論は新しい理論に変わる」「理論は絶対ではない」という点は、歴史的に見ても、現実的に考えても、だいたいあてはまるのではないでしょうか。そうであるならば、現時点で一番確かな考え方であると思います。
また、パラダイムの通約不可能性についてですが、その不可能性がどの程度であるかが気になりました。新しい理論からすれば、前の理論は間違っており、それこそ時代遅れで役に立たないものに見えるでしょう。そうであれば、パラダイム転換の前と後では、通約が不可能なのかもしれません。ですが、新しいパラダイムが成立するためにはまず、古いパラダイムが存在することが前提であると思います。また、程度の差はあれ、新しいパラダイムは古いパラダイムを参考にして生まれるものではないでしょうか。かなり主観的な意見になってしまうのですが、それまで常識だったものを参考にしない、影響を受けずにいられる、というのは想像しづらいです。そうであれば、たとえわずかであっても古いパラダイムは新しいパラダイムと共通している点があり、また古いパラダイムもそれなりに意味があるものだったのではないかと思います。
クーンによると、既存の理論から新しい理論への変化を「パラダイム転換」といい、それは山あり谷ありの断続的転換であるという。変化はあくまで「転換」であって、「進歩」や「進化」ではないとしていることが個人的には面白いと思った。またクーンによると、観察に既存の理論が内在されているため、そこから新しい理論は生み出し得ないという。そこで、既存の理論を打ち倒すのは新しい理論であるとしているが、その新しい理論でさえ既存の理論の息がかかるところに生み出されるものなのではないかと私は考えた。
今日の内容も難しかったですが、今日の講読会を通して、進歩とはなんだろうか、と考えました。これまで、進歩というと、良い方向に進むこと、発展としていくこと、と漠然と思っていましたが、今日の講読会を通して進歩はパラダイムを抜きにしては考えられないのではないかと思いました。実際、私たちが良いことだ、進歩だと考えていたことは、コロナによって一瞬で変わりました。今まで近代医療の発展の賜物のように思っていた、体調不良時には病院にすぐに行くことも、医療資源や感染予防の観点からよくないこととされました。近代国家は子どもが皆学校に行くことを目指しましたが、コロナによって行ってはいけない、とされました。これらから、あれ、進歩ってなんだろう?と思ってしまいました。もしかしたら進歩(だと思っているもの)は、そのパラダイムにとって都合の良いものでしかないのかな、とも思いました。

パラダイムというのは、考え方のまとまりのグループという風に考えると少し分かりやすくなるかもしれませんね。そこには優劣や新旧はないわけです。いろいろな考え方がある中で、中心的な考えになるものもあれば、そうはならないものもある。あるパラダイムが中心的に取り扱われるようになったとしても、他のパラダイムが消し去られてしまうわけでもないのです。ただ、古いものから新しいものへと発想がリバイスされていくそのプロセスの中には、つながっているものがあるのではないか、ということを反証可能性の議論を通じてポパーはしたかったのではないかなあと思います。
今回のCOVID-19をクライシスと捉えることは、この機会を新しいパラダイムを志向する機会としても捉えることができるのかもしれません。トマスクーンは、決まりきった考え方や進歩というものがない、ということ、直線的に何かが進んでいくと考えるのではなく、さまざまに考え方が移り変わってき得たということを説明しようとしたのかもしれません。その意味では、かつて考えられてきたことが、今改めて見直されるようなこともありえるわけです。コロナ禍という言葉では、「禍」を乗り切るうえでは神頼みしか手はないのかもしれませんが、「クライシス」として捉え、新しい考え方を見出していこうとする機会にすることができたら、とも思います。
第十二講| スペシャル回 討議:”危機”下の学問―2020年を振り返る
補章「3・11以後の科学技術と人間」から
担当:M先生
当日資料はこちら
討議:松本 早野香さん(大妻女子大学)、柴田 邦臣さん(津田塾大学)
当日リポート
当日読んだのは、2011年3月11日の東日本大震災と福島原子力発電所の過酷事故を受けて、科学技術が今、どのように役割を果たしていけるのか、科学技術のみならず私たちがどのようにかかわっていきうるのか、ということについて論じられた文章であったと思います。今、COVID-19感染拡大という事態と直面している私たちも、まさに「信頼神話」の崩壊(政治や科学技術への信頼の崩壊)と直面しています。また、トマス・クーンが指摘したような「通約不可能性」といった状況を目の当たりにしているともいえるかもしれません。dangerではなくriskとしてCOVID-19を捉えていくうえで、3.11の経験からも学ぶことがあるはずです。そんなわけで、当日は大妻女子大学から松本早野香先生をお招きし、議論を展開していきました。
松本先生はコミュニティとITというテーマでご研究されていらっしゃいます。ITを使ってコミュニティの問題解決をどう図ることができるか―といった観点から3.11の被災地支援にもながく携わられてきました。3.11で被災した地域は広範囲にわたり、どちらかといえば過疎化が進む地域が多かったという特徴があったそうです。その場合、メディアを通じて伝えられる情報はどうしても首都圏寄りにならざるを得ません。首都圏寄りの情報は被災地の人を本来的な意味でなかなか支えることが難しい―といった側面から自前のメディアとして、臨時ラジオ放送局を立ち上げられたのだそうです。そうしたご経験から、いくつかの論点を挙げてくださいました。
まず、市民との協働という観点から考えたとき、市民が科学に参加するということをどう捉えられるのか、ということについて。全員が科学に参加したいと求めているわけではない場合、どうしても政治的な側面が生じ、かつ「共感」を求めるようなことになるのではないか。二点目に、リスクに対する反応がどうしても呪術的なもの―柴田先生の言葉でいうと「魔法」に相当するような―に頼るようになってしまい、それが新たなコンフリクトを招いてしまうことがあるのではないか、ということでした。
3.11とCOVID-19は、文献中で出てきた表現でいうところの受益圏と受苦圏が明確に分けられるのか、という観点に違いがありそうだ、ということも指摘されます。3.11では本文にも書かれていたとおり、受益圏と受苦圏がある程度はっきり分かれていたといえるかもしれません。それはドラマが生まれやすい状況であった、とも松本先生から説明がされます。受苦圏における経験がドラマティックに語られるということはそのドラマを消費する対象があった、ということも意味します。ですが、今回のCOVID-19は受益圏と受苦圏は分けて考えられるようなものではありません。あまりにも広範囲にわたって暮らす人々がそれぞれの事情を抱えながら、何が具体的な問題なのか、その問題の同定すら困難な状況(リスクとは、存在していることはわかっていてもその認知が難しいという特徴を持つ、不可視なものとベックは議論しています)であるともいえます。つい、自然災害のような、デンジャーとして、この事態をやり過ごすために必死に耐える、といった発想になってしまうような状況にあるともいえるかもしれません。リスクとしての同定が難しいからこそ、コントロールの対象としてなかなか捉えられないという状況が、現在私たちが「コロナ禍」とつい呼んでしまう理由として説明できるのかもしれません。
3.11は紛れもなくデンジャーではありましたが、リスク化した実例として挙げられるものもあるといいます。例えば合意形成の在り方です。沿岸部の被災地の中には、鉄道駅の移転についてずいぶん長く議論されたりしていました。鉄道駅が移るとは町の中心地が移るということを意味しますので、当然利害関係なども絡み、合意形成がとても難しい問題でもあったわけです。ある地域では7年の時間をかけて移設に至ったということもあったそうですが、この合意形成のプロセスが、端折られてしまう、ということも少なくなかったそうです。東京のコンサルタント会社からのそれらしい提案を受けて、受動的に復興の在り方が決まっていったとき、そこには日常を暮らしていくうえでの問題性や課題を多く残す側面もあったといいます。そもそも被災した人たちがそれぞれの事情を抱えており、さまざまな利害関係があるのですから、そもそもそう簡単に結論がでるような話ではありません。「通約不可能性」も多く存在していたに違いありません。それでも合意形成していく困難さに目を向ける、ということの意味や意義は否定し難く、過度な単純化がはらむ問題性が指摘されるような出来事であった、とも議論が進みました。
今、COVID-19を前に、私たちも多くの課題を抱えています。例えばワクチン接種などがその一例です。ワクチンの有効性を保つためにはある程度の人数の人が一気に接種をしないとその効力を発揮できない可能性があります。ですが、ワクチン接種が逆の問題を引き起こす可能性を否定することもできないわけで、ワクチン接種一つをみても、「通約不可能性」、合意形成の困難さが存在しているのです。ただ、3.11の事例から学ぶことがあるならば、この「通約不可能性」をすっ飛ばしてはならない、ということであったのではないか、と。エビデンスに基づきながらしっかり議論していくこと、このことがパラダイムとパラダイムを”つなぐ”ことになり、それこそが科学にも、私たちひとりひとりにも求められてるものなのではないか。長期戦になることが予想されるCOVID-19だからこそ、私たちは敢えて焦らず、しっかりとリスクを同定しながら問題に向き合い、克服していくための努力―議論を重ねていかなくてはならないのではないか。そのように議論されました。
簡単には結論を持つことができないようなテーマでしたし、まだまだ議論が続いていきそうな気配を持ちながら、当日のパネルディスカッションはお開きとなりました。皆さんはどのように考えられたでしょうか。松本先生、柴田先生、本当にありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします!(2021年は『科学哲学への招待』第3部からスタートです!)
参加者の皆さんの感想(一部)
講読会の補章部分で、神話の話が特に興味深かった。この本で述べられているのは3.11での事例であったが、コロナが流行ってワクチンを導入しないかするか、打つか打たないかが議論されている今の現状にも当てはまることだなと思ったからだ。ワクチンの副作用が多発していることから、科学技術への信頼が落ちていると感じる。実際に私もそのようなニュースを見て医療、科学に対して信頼感をあまり抱けていない。地震などの自然災害においても、コロナなどの疫病災害においても、この本で述べられていた3つの神話が当てはまると思った。また、松本さんのお話の中で、「3.11はドラマ化されていたけどコロナはドラマ化されていない」というのが印象的だった。たしかに3.11の時は震災から○○日と情報が節目ごとに流れていたが、コロナはそういうイベントがないなと気付いた。
自分は福島出身なので、原発事故に関することはとても身近なものに感じています。震災の頃、メディアの中でもラジオの情報が何よりも速く頼りでした。地元ラジオのアナウンサーが「頑張りましょう!」と毎日のようにエールを送っていていたことが印象的で私は勇気付けられていましたが、先日見たドキュメンタリーでは、この「頑張りましょう」「がんばろう」という言葉が被災地の現状を見ていないから言えるとても無責任な言葉だと思っていた被災者の方もいたことを知りました。有事の際には、誰しもが情報を得られるものにすがると思います。情報を伝える側はその時、いかに聞き手に寄り添って、いかに情報を伝えるべきかという問題を意識しなくてはいけないと思いました。
災害の程度は地域によって様々で、私が住んでいる地域は高い建物が密集しているため津波は来なかったものの、福島第一原発から100キロ離れているにも関わらず線量が高かったのです。給食で出される地元の酪農家の牛乳を飲むことも念のためやめました。そういった10年ほど前の記憶を思い出した今回の講読会でした。
途中までしか参加できなかったのですが、興味深いお話を聞くことができとても勉強になりました。私は昨年度の1年セミナーにて大島堅著の『原発のコスト』を購読したことがあり、そこで話し合った内容とリンクするところもあり改めて原発の安全神話の非合理性について考えさせられる機会となりました。震災から月日が経って、現在はあまり原発事故について取り上げられることは無くなりましたが、あれから原子力発電が縮小されることはあっても、当時の原発関係者、また原発を推し進めた政府が原発の脅威について理解していなかったことは、ほとんど追及されないままです。コロナ禍の現在の状況でも、同じようなことが起きかねないような気がします。ウイルスにおいては予測できない点が原発の時と異なるかもしれませんが、国や自治体のの責任者が下した判断についてわたしたちが反応を示すことができ、世界中すべての人に関与する出来事であるため、説明責任から逃れられない状況でもあると言えるのではないでしょうか。そのため世界中の生命がかかっている中で、利害を気にしたり責任逃避する人はあまりいないのではないかと思います。
3年セミナーの一貫で参加しました。コロナ禍と、東日本大震災の性質の違いについてのお話が印象的でした。東日本大震災は地域や期間が限定されていたけど、コロナは全世界であり、期間も長期なうえ不確実。そこから考えたのは、では収束後の動きは同じだろうか、異なるだろうかという問いです。松本先生もおっしゃっていましたが、東日本大震災で言うと、被災地は過疎地域で産業もそこまで大きい規模ではなかった。しかしコロナ禍は全国民、全自治体、つまり国全体に影響を及ぼしたので、収束後のリカバリーの動きは震災と比較して圧倒的にスピードが早いのではないかと考えました。
はじめて参加したのですが、とても面白い会でした。うまく文章にまとめられなかったので、以下に箇条書きで今回の感想を示します。
・最悪のシナリオには、「最悪」のグラデーション(程度)がある。福島第一に例えると、最悪のシナリオとは、「福島第一原発の停止」、「原発のメルトダウン」、「原発からの放射能漏れ」というように、最悪にも程度がある。どれほどの最悪まで想定しなくてはならないのか、想定できるのか。科学技術がリスクを伴う時、市民合意をはかりながら、意思形成をするのであれば、どの「最悪のシナリオ」を市民に提示するべきなのか。
・責任所在が特定不可能であり、被害が補償不可能であった原発問題。そのしわ寄せが、被災地にいってしまっているのではないだろうか。
・科学的根拠がないのにもかかわらず、行為を行うことが呪術的である(例えば、3m離れているのにマスクをつけるなど。アマビエもそうですよね?)との話を聞いた時、RARA課題で読んだ『宮廷と呪術』の話を思い出した。呪術・おまじない等には、行為に対して、「真実性」や、今回のパネルディスカッションで言うのであれば、「効力」のような、ある種の力を付けさせる機能があるのかもしれないと思った。ただそれに付随して、「本当に私たちは、科学的に証明された安全性を求めているのか?」という疑問が浮かんだ。
・合意形成の段階で、「東京のコンサルの人がはいってきて・・・」とのお話を聞いた時、私は福島出身の東北県民なのですが、東京の人とは全く違う文法・コミュニケーションを使って、わたしたちは人と意思疎通をはかっている気がしています。ただの感想なのですが、話を進めるには、相性が悪そうだなと感じました。
初めて参加させていただきましたが、前半部分でのM先生の説明がとてもわかりやすく、ありがたかったです。
「危険」と「リスク」という定義を読み、コロナ禍で「どうしようもない」「誰のせいでもない」と考えてきたことを見直していく必要があると感じました。また、現在の人々を「受益者」と「受苦者」として明確に分けることができないという点には思い当たることがありました。3.11の時とは異なり、自分自身がこの状況に苦しんでいたり、アクティブになれなかったりと、支援者として動くことができない状況(ドラマとして見る余裕がない状況)にあると感じています。未来世代への責任という点においては、現状が改善されるとさらに直面する課題に向き合う必要があるために、根本的な改善ができず、その場しのぎの対策になってしまっているという印象を抱いています。
どのようにしてこの問題を解決していくかということについては現段階の知識で述べることはできませんが、この講読会を通して知識を得て、自分なりにこの問題に向き合っていきたいと感じました。ありがとうございました。
テキスト講読とパネルディスカッションどちらも大変面白かったです。問題から目をそむけず、市民も意思決定に積極的に参加し、つきつめて議論することの重要性が分かりました。「はやくコロナが収束してほしい」と思っていた自分の根底には、コロナをどうすることもできない災害と捉えることでコントロールしたり、リスクにしっかり向き合って解決することから逃げようとする気持ちがあると気づきました。
日本の議論体制は整っていないのだなという風に感じました。だからこそ復興しないし、検証していくこともできないのだろうと思いました。こういう時に教育の中での議論体制がでてくると思っていて、何事も言える、まずは議論という体制を作っていく必要があると考えました。いったん落ち着いても、また経験したことないことが起きると日本は再び復興までに時間がかかり、ばらばらになるのだろうと思い、この社会はリスクだらけで何も進んでいないのではないかと思い怖いと感じました。
東日本大震災と違うところとして団結しにくく、リスクがみにくいというところが意識していないところでした。
私たちの世代は今後怖い、希望見えないと言っているだけではなく、長く続く状況を経験できた私たちが考えて、逃げずに向き合っていくしかないなと感じました。
今回この講義に参加して印象に思ったことは合意形成にはやはり時間も労力もかかるということだ。被災地では合意形成に時間がかかっているから復興も遅れているというのはなるほど確かにその通りだと思った。
次にエッセンシャルワーカーについての話だ。これはCOVIDー19が世界的に流行してから聞くようになった言葉だ。これは医療従事者だけを表す言葉ではなくて運送業者やコンビニやスーパーで働く方々のこともさす言葉だ。本来なら私たちはこう言った自分たちも危険な状況になっているのに働いてくれている人達に感謝しなければならないのに何故か差別されていたりして生きづらい状況になっていることは私はおかしいと思う。こう言った人たちにもっと感謝を持つべきだと考えている。
今回こう言った機会で色々な研究をしている方々の話を聞けてよかった。また参加したいと思う
「課題や問題の当事者が議論・意思決定の場に参加する」ということは言葉で聞いていると当たり前のことに聞こえますが、実際はあまり実践されていないのかもしれないと今回改めて感じました。国際協力などの場面でもトップダウンの支援の仕方から、当事者参加型の持続可能な開発が注目され潮流となっていることからも考えられるように、当事者(特に受苦者)の参画が持続可能性や、未来に向けて重要なことなのだと感じられる回でした。
自分は、心的外傷経験とどのように向き合っていくか、向き合う過程でそれを他者とどのように共有できるかということに興味があります。
わたしが住んでいた地域はあの日、震度6弱で、田んぼがあった場所にできたようで、とても揺れたことを覚えています。小学校の渡り廊下はヒビが入りました。担任の先生は阪神淡路大震災の被災者で、落ち着かせてくれてとても安心したことを覚えています。
あの日を、どのように、そして何を思い出すかは、様々だと感じます。とても辛い経験で、封印されている方もいると思います。
受益圏と受苦圏に分けることができるこの震災からの復興は、ドラマとして語られていきます。それは、全体の復興しか見えないと感じます。直接的に経験をし、苦しみを味わっている当事者以外の人々(うまく表現ができません)は、ドラマ化されたものを受け継いでいくことでしか、向き合うことができていないように感じています。
反省を共有することも、悲しみを共有することも、また、打ち勝ったとしたらその喜びを共有することも、そう簡単なことではないと思います。その難しさが、合意形成の難しさにつながっているのかなと思いました。
「寄り添う」って、震災当時の報道でも、また、COVID-19に関連する心身不調に対しても、多用されています。共有できない苦しみに、どう「寄り添う」のでしょう。共感できるものではないだろうと思います。ただし、気持ちをわかろうとする努力は怠ってはならないと思います。
COVID-19は、全員が今、何らかの形で直面しています。でも、程度や経験の差異があるにも関わらず、共通の経験として語られがちです。COVID-19の流行は、確かに災害ではない。COVID-19はとても大きなリスクだと思います。誘発的に、教育や職をはじめ、家庭環境に対する非常に大きなリスクです。死を招きかねません。実際に、COVID-19を誘因としてどれほどの人が死に至っているか、考えるまでもない。この状況下で、どうすることもできないことがたくさんあります。その場合、「耐える」ほかないのではないでしょうか。散々に向き合ってきたうえで、その都度向き合い対処することに限界を感じざるを得ない年の瀬です。この2020年の出来事が、のちの教科書には、どのように載るでしょうか。1行に短縮されてはたまらないと思います。教科書に載ったときに、それを自分で説明することは可能なのか、怪しいです。
まとまりに欠けた文章で大変恐縮です。
頭がついていかない部分もあったため今回のトピックに対して纏まってはいないが、covid19がdangerではなくriskであるという点や、受益権や受苦圏の地域間、世代間格差は本来covid19にはないにもかかわらず存在しているように見えるということには非常に納得できた。covid19がriskであるのは、covid19を引き起こした事象とcovid19によって引き起こされた現象は既存の社会的要因や問題と連動している部分は多いように思えるし、その際どう対応するのか、支援するのかということによって大きく変わっていたと思うためである。また、covid19はと3.11の東日本大震災ではその復興とされるゴールが異なるのだということが分かった。科学技術の導入について思ったことは、(理想論だとは思うが)導入の条件として、最悪なシナリオを想定する場合はそれへの対応策を緻密に練ったり、その最悪なシナリオとその対応策をセットで国の安全保障を脅かさない程度にできる限り公にする必要があるということ、その最悪のシナリオと対応策は都度アップデートされていかなければいけないということ、科学者や専門家以外の人も(教育にその知識を導入するなどして)ある程度の科学技術へのリテラシーを持っていること、そのリテラシーの程度や科学者や専門家以外の人が科学技術に対する知識を持つことによって、科学技術に振り回されたり危険にさらされることがないこと、科学技術と社会的合理性が協働していること、責任追及型の傾向が強くない社会であること、科学者や専門家が政治利用されないことなどがそろわなければ難しそうだということである。これらの条件をどう達成するかという方法の点や条件をそろえるためにあまりに多くのことを変えていけなければいけないという点が不可能に近くても、せめて過去の未曽有の事態から学べることやその失敗を生かして対応策を考えること、未曽有の事態のシチュエーションをいくつも想定しておき国民に知らせておくこと、未曽有の事態が起こった事態の支援の方法や必要なものなどを考え備えておくことは出来ないことではないと思う。
五限の授業があり途中参加になってしまったのが自分でも残念ですが、非常にタイムリーなコロナについての回だったのもあり、今まさにこの問題の当事者である自分であるからこそ考えさせられるものがありました。また3.11も経験しているので、どちらも「経験した側」からの視点で考えることが出来面白かったです。また初参加でどの様なものかと不安でしたが、温かい空気の中進むディスカッションでリラックスして皆さんのお話を聞くことが出来ました。1月の講読会も参加してみたいのですが、丁度テスト期間と被っているので自分の頭と要相談ですね。

今回のCOVID-19の問題を考えると、年末から年始にかけてもまたいろいろと状況が変わった、ということもありえそうですね。特に、当事者性という問題を考えた時、日本中の人がまさしく当事者になってしまうわけですから、そこからどのような分断が起きてしまうのか、ということはそれこそリスクとして向き合っていかなくてはならないのかもしれません。3.11は、もしかしたら美しい支援される被災地・支援する東京の物語を描けたかもしれない。でも、3.11のときも被災地では、本当にほんの少しのことで運命が大きく分かれてしまう―道路一本隔てたかどうか、本社勤めであったか支社であったか、家族構成がどうだったか―状況だったのです。「格差」というものは、本来コントロール可能なリスクとして捉えられなくてはならないものかもしれませんが、今まさに直面しているCOVID-19でも分断を生むきっかけになってしまっているかもしれません。そのことに向き合いながら、それでも当事者が参画して、合意点を探っていくことを続けられたらと思います。
痛みは「共有」することも「共感」することもできないし、されるものでもないのでしょう。言葉だけならだれにでもできるような”ごまかし”といっていいようなものとすらいえる。でも「理解」できないで終わらせるのではなく、そこからともに一歩進めること―共感ではなく、合意をする努力をしていけたらと思います。「わからなさ」にはリスペクトを持ちながらも「耐える」ばかりではなく、次の一歩として「合意」を探っていくこと。そしてそれを支えるのが科学だとも思います。
本当に皆さんがそれぞれ濃密なコメントを残してくださって本当に嬉しいです。時間の関係でひとつひとつのコメントに対してのお返事をすることができずにいましたが、今回、皆さんのコメントを見ていて思うのは、COVID-19という事態を受けて改めて、3.11や原発事故のことを振り替える機会を持つことで、これまでとは異なる3.11の捉え方をしていただけたのではないか、ということです。3.11とCOVID-19を並べて考えてみることで共通項として見える物があるかもしれないと気付くことができたこと、これから一歩進めていくために自分たちができることが何か、改めて考える機会を持つことができたかもしれない。科学は、よく自然をコントロールするもの、といった言い方がされたりしていて、どちらかというと”傲慢なもの”として説明されがちかもしれません。でも本来、科学がコントロールしようとしているのはリスクの方なんですよね。2021年も皆さんと一緒に議論していけたら、と思います。