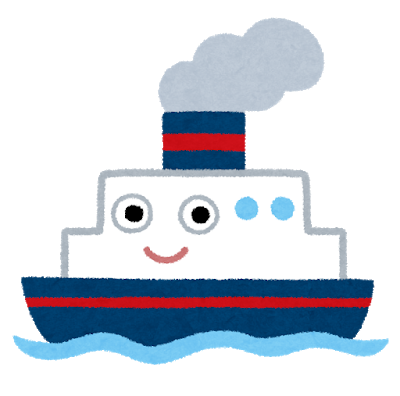▶ を押すと文が増えます
「学びの灯」は灯台、学びの「羅針盤」に航海士を意味する「ナビゲーター」…、そして学ぼうとするあなたが船長!と想いを込めていたりするのです。
今回はそんな船のはなしにかこつけて、船の名前を楽しんで注目していきたいと思います。
いろいろな「フネ」
「ふね」と聞いて、みなさんはどんな漢字を頭に想いうかべたでしょうか?
もしかしたら、「舟」と「船」の二つが思い浮かんだよ、という方が多いのではないでしょうか。
両方とも「フネ」と発音するはずですが、何が違うんでしょう…?
しかも実は「フネ」を意味する漢字は、舟や船以外にもたくさんあるみたい。いったいどういうことなんでしょう!?

ちなみにサザエさん一家のおばあちゃん、サザエの母の名前がフネさんですね。夫である波平は波。
波にゆられるフネ。なんか…ちょっとお二人の仲の良さがうかがえますね…(ほのぼの)
フネをあらわす漢字には、 舟 、 艇 、 船 、 舶 、 艦 などがあるようです。
それぞれどんな違いがあるのか?というと、そのフネのサイズや、どんな特徴を持ったフネなのか、ということによって使い分けているようなのです。
舟
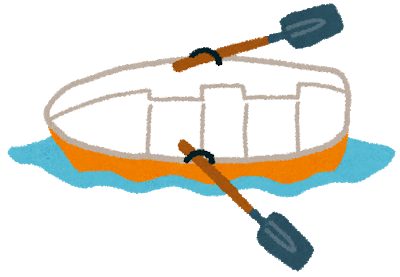
音読みで「シュウ」、訓読みで「ふな」「ふね」と読みます。
人力で動かすようなフネですね。川岸と川岸をつなぐ“渡し舟”の形に由来した象形文字なのだそうです。
一番オーソドックスなフネの原型を示すようなこの漢字は漢字を構成する「偏」として、フネにまつわる漢字を作っています。

艇

小型のフネのことを指し、“短艇”、“艦艇”などと使われているようです。フネの仲間だから、舟偏が付いていますね。
特に漢字の右側を構成しているパーツ「廷」は「階段の前に突き出た庭」を示すものらしく、そこからフネはフネでも、「先端が突き出て風の抵抗を小さくした軽快な小船」を意味するのだそうです。
船
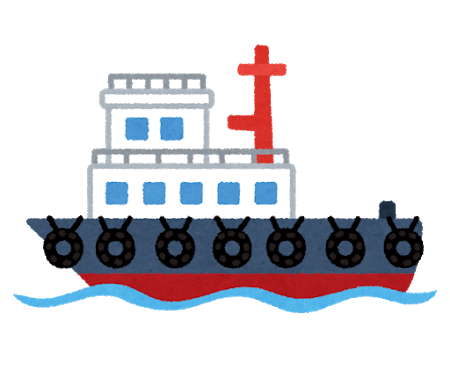
こちらは結構広い概念を指すようです。小型から大型のものまでもっとも広く使われている、私たちがよく見聞きする漢字ですね。
舟との違いは、機械の力で進むフネである、ということ。
ただの舟ではなく、どんなフネなのか、を示すのが、右側のパーツ。
右側のパーツは、「二つに分かれている物の象形と谷の口の象形」を意味し、「川が低いところに流れる」という意味から川に沿って下る、という船という漢字が生まれたそうです。

舶

これはフネはフネでも、大型のフネを意味するのですね。
右側は“白”というパーツが組み合わされていますが、「泊」に通じる意味を持つパーツであるらしい。一泊旅行、などと言ったりしますが、その意味するところは旅先で一晩明かす、ということですよね?
寝泊りして長期にわたって海を行くことができるような「大きな船」を意味する漢字、それが舶です。

「うみ」という童謡の作曲家は実は私が通った小学校の大先輩、井上武士さんです。
海なし県の群馬県から「うみ」という曲は誕生したんですねぇ…
校庭に「うみ」の歌詞が書かれた石碑がありました…
艦

この漢字からどんなイメージを持つでしょうか?
パーツがたくさんあって書くのが大変そう。パーツがたくさん寄り集まってできている漢字のひとつです。
一つ一つ見てみると、右側のパーツ「監」という字には、左上のパーツ「臣」が意味する「しっかり見開いた目」の象形、右上の「たらいをのぞきこむ人」の象形、下のパーツ「皿」の「水の入ったたらい」を示す象形で「監」というパーツを成り立たせています。それがめぐりめぐって転じ、「檻(かん)」に通じる意味を持つことになったそう。
「檻(かん)」とは「おり」を意味する言葉です。板で囲われた“いたがこい”や罪人や獣をいれる“かこい”を意味する言葉です。
檻ですから四方は壁に囲まれているような作りをしているわけです。別の見かたをすれば、自分の周りに囲いがあるから、外からの攻撃を防ぐこともできる…!
おりのように四面を板で囲んだ「いくさぶね」、戦闘用の船を意味する漢字として艦は使われるようになっています。

ちなみに教会の天井はすべて船底型になっているそうです。
それは、ノアの方舟の物語からきているとか…

へぇ!知らなかったよ、つっきー。教えてくれてありがとう!
漢字のひとつひとつにもエピソードがあったけれど、こうして”フネ”にまつわる物語や伝説は、まだまだたくさんありそうですね!
意味を教えてくれる文字―漢字
フネにまつわる漢字をいろいろ見てきましたが、「舟」という漢字をベースに、他の意味を持つ形(漢字)がいろいろ組み合わされていることが分かりました。その組み合わせ方次第で、どんなフネなのか、私たちは想像することができます。
これは、漢字を使う文化圏独特の特徴かもしれません。
漢字ひとつひとつに意味が込められている。意味が含まれる文字のことを表語文字などと呼びますね。
一方で、「ふね」とか「フネ」と“ひらがな”や“カタカナ”で示された場合は、「舟」なのか「船」なのかは分かりません。
ただ、「艦」や「舶」ではないことは分かる。なぜなら読み方が「ふね」であるということが分かるから。
音をあらわす文字、ひらがなやカタカナのことは表音文字と呼びます。
漢字を組み立てるパーツ
漢字が意味を教えてくれる文字であること、そのためにいくつかのパーツを組み合わせている、ということが分かりました。まるでブロックのように意味を持ったパーツとパーツが組み合わされるから、私たちは漢字一つ一つから意味を読み解くことができる。
このパーツのことを「部首」と呼びます。 今日は、「舟偏」という部首に注目しました。
「舟」という漢字をパーツとして取り扱うときに「舟偏」と呼ぶのです。
「偏」とありますが、これは部首の種類を示す名前であり、そのパーツをどこにはめ込めばいいか教えてくれる目印でもあります。
例えば…
◆ 「偏」は漢字の左側にくる部首です。
◆ 一方で、漢字の右側にくる部首は「つくり」。
◆ 上半分に来るのは「かんむり」
◆ まわりを囲む部首は「かまえ」
などなど。
さきほど見てきた通り意味を込めれば込めるほど、パーツをたくさん組み合わせて一つの漢字を作ります。
その分、「部首」にもいろいろな種類が増えました。
皆さんの名前は、どんな漢字で書くことができるのでしょうか。
その漢字にはどんな意味があるのかな。どんな「部首」でできているのかな。

たくさんある部首をノリノリで紹介してくれる動画を発見しちゃいました!

♪♪♪
下のホームページからも漢字の意味や部首のことなど、調べることができますよ