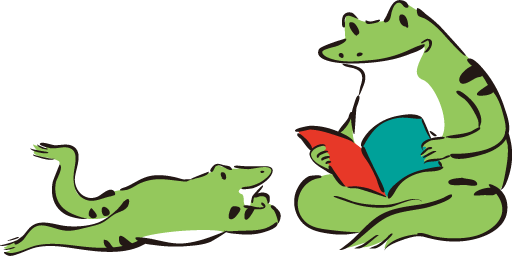▶ を押すと文が増えます
最近、M先生は『声の文化と文字の文化』(著者:W-J・オング、翻訳者:桜井直文・林正寛・糟谷啓介)という本を読みました。
そこから、
実際に会って言葉を交わすことと、
文字を通じてコミュニケーションをとろうとすること
の違いのようなことを考えていました。
著者のオングさんは、
文字を持たない文化の人びと、文字の持たない時代を生きた人びとの考え方や生き方は、文字を扱う私たちの考え方や生き方と一味違ったものになっていたのではないか、としています。
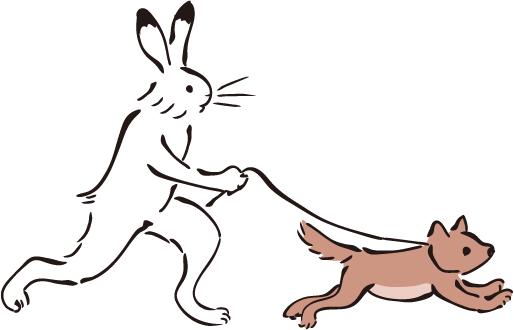
例えば、私が「ポチ」という名前の犬を飼っていたとします。
声の文化では、
「ポチ」という一匹の犬の話をすることが大事で、
「犬」について話したいわけではないし、「犬」について話すのが大事なのではなかったりするのです。
「ポチ」が今日どんなふうに過ごしたか、「ポチ」と散歩したときにあった出来事などを語ることのほうが大切であったりします。
声の文化に根ざした精神は、定義に無関心である。
語の意味は、そうした意味がつねにそこに固着している現実の状況からしか生まれない。
W-J・オング著『声の文化と文字の文化』p.103
※ 太字はM先生による

「作文を書く」ことが苦手、という人はいますよね。
この声の文化と文字の文化を意識すると、少し「作文」への取り組み方が変わってくるのではないかな、と思っているのです。
口頭伝承について

皆さんは「口頭伝承」と聞いて、どのようなものかイメージできますか?
「口承」などとも言いますね。
歌いついだり、語り継いだりして、口から口へと伝えること。あるいは伝えられたもののことです。
口から伝え・伝わることなので、「口伝」、「口伝えの伝承」などとも呼ばれます。
つまり、文字による記録に頼らずに、その人が語ることをつうじて物語や内容を見知っていくというものです。
日本で代表的な口承文学として指摘されることがあるものに、『平家物語』があります。
これまでも「フネで旅する漢字の海原シリーズ⑤ 夏のおさかな天国」など、いくつかの記事の中で紹介してきたことがありますが、『平家物語』とはどのような作品なのでしょうか。

国語の教科書にも出てくる有名な作品ですね。「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす」という言葉から始まる作品で、最初のフレーズを知っている人はとても多いです。
平家物語とは
中世初期に成立した軍記物語。12巻。
平清盛を中心とする平家一門の興亡を描いた歴史物語で、「平家の物語」として「平家物語」とよばれたが、古くは「治承物語」の名で知られ、3巻ないし6巻ほどの規模であったと推測されている。それがしだいに増補されて、13世紀中ごろに現存の12巻の形に整えられたものと思われる。
平家物語は、本来は琵琶という楽器の弾奏とともに語られた「語物」で、耳から聞く文芸として文字の読めない多くの人々、庶民たちにも喜び迎えられた。庶民の台頭期である中世において、『平家物語』が幅広い支持を得ることができたのもこのためで、国民文学といわれるほどに広く流布した原因もそこに求めることができる。『平家物語』をこの「語物」という形式と結び付け、中世の新しい文芸として大きく発展させたのは、琵琶法師とよばれる盲目の芸能者たちであったが、古い伝えによると『平家物語』ばかりでなく、当初は『保元物語』や『平治物語』も琵琶法師によって語られていたらしく、また承久の乱を扱った『承久記』という作品もそのレパートリーに加えられていたといい、これらを総称して「四部の合戦状」とよんだ。
(日本大百科全書より)
平家物語といえば、琵琶法師が語った作品として知られているのです。

「びわ」と聞くと果物の「びわ」を連想する人もいるかもしれませんが、果物の「びわ」という名前は楽器の「琵琶」に形が似ている、ということに由来しているそうです。
正倉院にある「螺鈿紫檀五絃琵琶」は、その美しさから有名です。
琵琶法師とは、琵琶を伴奏にして叙事詩を語った盲目の法師形の芸能者です。
山鹿良之さんは、明治34年生まれ、昭和48年に亡くなった最後の琵琶法師と呼ばれる方です。動画では『羅生門』をうたっていらっしゃいます。

みなさんは、どんなふうに感じられたでしょうか?
私は「ぞぞぞ」とするような凄みを感じます。
カッコいい…!と聞きほれてしまいます。
アイヌの物語
ほかに、アイヌ民族の方たちの口承文学が例として挙げられるかもしれません。
阿寒湖温泉アイヌ文化推進実行委員会が制作した「神々とともに生る アイヌ文化遺産」の中で、
アイヌ民族は、長い年月を経て独自にはぐくんできた文学があり、近代にはいる前までは文字に頼ることなく、人から人へ口伝えで厖大な物語を語り継いできた
と説明しています。
アイヌの物語は大きく分けて3つに分けられるのだそうで、
・ 超人の少年英雄が大活躍する物語(ユーカラまたはサコロベ)
・ クマやキツネなどの自然界の神様たちが主人公の物語
・ 主に人間達が自らの体験を語ることによってアイヌ社会のできごとを伝え倫理を教える物語
があります。
少年英雄の物語や神様の物語は、独特のメロディーに乗せて語られます。

このような物語には、神々と人間との関係性を基本とする世界観、自然の中で生きていく知恵、アイヌ社会でのルールなどが豊富に盛り込まれています。
アイヌの人びとは、物語を聞くことによって文化や伝統などを学び、継承してきたのだそうです。
アイヌの神々の物語を日本語に置き換えた『アイヌ神謡集』という作品は、知里幸恵さんが残しています。
アイヌの物語が持つ世界観を、日本語に忠実に「翻訳」していることがとても評価されています。
知里幸恵さんのことをもっと知りたいという方は、「NHK 北海道スペシャル・知里幸恵 19歳のメッセージ~「アイヌ神謡集」の世界から」の動画を観ていただくとよいかもしれません。

ギリシアの叙事詩―ホメロスの作品から
オングさんが紹介していた「声の文化」の代表作はホメロスの作品です。
(オングさんは、「口頭文学」という用語を、口頭伝承や口頭で演じ語られるものにまで「文学」という術語を使ったら、これらを文字を前提とする「書かれたものの一変種」に還元してしまうかもしれない、という理由で否定的に用いています)
ホメロスとは紀元前8世紀ごろのギリシアの詩人。
ヨーロッパ最古の詩人と言われ、英雄叙事詩『イーリアス』と『オデュッセイア』の作者といわれていますが、なぞに包まれた人物です。
(青空文庫で『イーリアス』を読むことができます。)
まだ、文字も成立しない時代。
もともと口承詩として、語られ聞かれることによって作られ伝えられたといわれています。
トロイア戦争伝説に取材し、『イーリアス』は戦争と英雄の悲劇を克明に冷酷に描き、『オデュッセイア』は戦争後帰還する英雄の冒険と、故郷で彼を待つ妻の難儀と、二人の再会をロマン的につづったものと説明されています。
(百科事典マイペディアより)
ホメロスの物語がどのように生まれたのかをTED Edで説明もしています。
(英語音声ですが、日本語訳が表示できます)