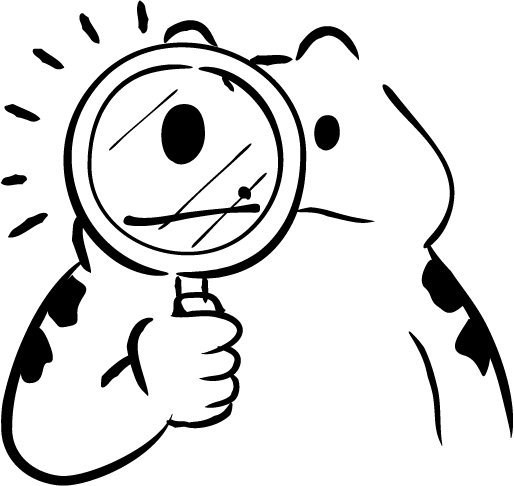▶ を押すと文が増えます
- 講読会について
- 第一講| 第2章 質的研究-なぜ、いかに行うか/第3章 質的研究と量的研究 2023年5月16日
- 第二講| 第6章 理論的立場/第7章 認識論的背景:テクストの構築と理解 2023年5月23日
- 第三講| 第8章 質的研究のプロセス/第9章 研究設問 2023年5月30日
- 第四講| 第10章 フィールドへのアクセス/第11章 サンプリング戦略 2023年6月6日
- 第五講| 第13章 半構造化インタビュー/第14章 データとしてのナラティブ 2023年6月13日
- 第六講| 第15章 フォーカス・グループ/第17章 観察とエスノグラフィー 2023年6月20日
- 第七講| 第22章 データの記録と文書化/第23章 コード化とカテゴリー化 2023年6月27日
- 第八講| 第24章 会話、ディスコース、ジャンル分析/第25章 ナラティブ分析・解釈学的分析 2023年7月4日
- 第九講|第28章 質的研究の評価基準/第29章 質的研究の質-基準を超えて 2023年7月11日
- 第十講| 第30章 質的研究を書く/第4章 質的研究の倫理

ようやく“終わり”を告げつつある、COVID-19 Crisis。急速にその「かたち」を取り戻そうとするようで、確実に、しかし“見えにくく”変わっていく現代社会…。Chat GPTに「聞く前」に、むしろ「問うため」にこそ、私たちに必要な〈技法〉がある。
アフター・コロナを急ぐがゆえに、静かに深く広がる「学びの危機」に対峙するための、〈社会そのものを読み解く技法〉について考えます。
※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
(どなたでもご参加いただけます!)
講読会フライヤーPDFはこちら
講読会について
講読書籍
『新版 質的研究入門 <人間の科学>のための方法論』
ウヴェ・フリック著 小田 博志 監訳 春秋社(2011年)
講読期間
2023年5月16日(火)~2023年7月18日(火) 全10回
開催時間
18:00-19:30ごろ(入退室自由)
参加方法
ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。
- ①一般参加会員
その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。
当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員
継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。
講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
※ 参加登録は一度のみで完了いたします。
※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。
お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加
特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。
一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。
ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。
お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!
第一講| 第2章 質的研究-なぜ、いかに行うか/第3章 質的研究と量的研究 2023年5月16日
当日資料はこちら
当日リポート
ようやく?!始まったまなキキ・オンライン講読会。現在は2023年5月。
今月8日には、新型コロナウイルス感染症も5類感染症に移行しました。
それ自体の是非はともかく、新型コロナウイルス感染症が、私たちの社会のカタチを確かに変えたことは確かです。そのひとつひとつを、ただ受け身的に流して「共感」していくのではなく、正面から向き合い、一歩踏みとどまって、考えていく――社会を読み解くための技法として、今回の文献に挑戦していきましょう、ということになりました。さて、その第一回目。
今回の内容は、特に「なぜ、質的研究なのか」という、意義と可能性に関する議論で構成されていたように思います。実は質的調査は、「これって科学なの?」と、「全然客観的ではない」と批判されてきたような方法論であったかもしれないものでした。
ですが、実は「科学的」で「万能」であるかのように思われてきた量的アプローチもまた、厳密に実施されないことには、まったく意味や価値のないものです。
今日、義務教育下でも、データ・サイエンス的な観点から統計的な内容を取り扱うことがありますが、そもそもそのデータがどのように集められたのか――サンプリングされたのか、といった前提が省略されてしまうことが多々あるそうです。でも、やっぱり、「適切なサンプリングができていない調査の価値はゼロ」なのです。盲目的に「万能」ととらえ、絵空事になっている可能性に気づけていないとしたら、それはとても危うい事態です。
量的調査・量的研究が有効に機能する領域は確かにある。でも、この調査法を有効に活用するためには、厳密なサンプリングやそれに伴うコストを無視することはできない――質的調査・質的研究の意義の問い直しは、いわば、量的調査の不可能性や限界を見直すことをきっかけに始まったといえるかもしれません。
では、質的調査・質的研究は、社会の現実に対して、どうしたら科学として有効で、妥当なアプローチをとることができるのか――、こうした問題意識の下で、実践や検討が蓄積され、質的調査・研究は進展してきました。そこに見出される質的研究・調査の「論理」を学び、議論していくことは、この講読会の目標の一つとも位置付けられそうです。
今日話題のデータ・サイエンスやAIの議論は、量的研究・調査と質的研究・調査の間にある緊張関係やそれぞれの限界を無視してパワーを持って突破してしまおうとするアプローチともいえるのかもしれません。恐らく、このアプローチが有効な局面もあるのでしょう。
ですが、フリックの議論に従えば、量的研究・調査では解明できないものが、質的研究・調査にはある――つまり、データ・サイエンスやAIでは説明できない社会の理屈や現実がある、と言えるはず。
質的研究・調査もまた、万能では決してない、ということ。でもその限界やゆがみを自覚的に捉え、なんとか妥当に克服しようとする/してきた方法論であるからこそ、学ぶことが多くあるはずです。
例えば、質的研究・調査のサンプリングが、サイエンスとして有効なcherry pickingとなるよう、どのようなコントロールが実践されているのか、質的研究・調査における「論理」とはどのようなものなのか、などなど、次回以降も楽しく読み進め、議論していきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
今回の講演では、量的調査と質的調査において、一つの対象を研究する時に個々の研究方法をもつ弱点や盲点を補い合うために異なった方法論的なアプローチを組み合わせて用いるという、質的研究と量的研究を補完的なものとして捉えることを学んだ。質的研究と量的研究は、「データ」「方法」「結果」のそれぞれのプロセス・段階において、双方を組み合わせ、双方の補完的な関係を達成でき、それは扱いたい研究設問の性質に基づいて、特定の方法を使用するといった、適切性を吟味した上でどちらの方法をどのように組み合わせるのか決めるべきであると学んだ。
質的研究と量的研究の関係性において、「組み合わせる」という方法が出ていたが、データ・方法・結果のそれぞれの組み合わせにおいて、どうして質的研究または量的研究を、採用したのかという根拠の示し方が、また難しい点だと考えました。質的研究と量的研究のどちらを取り入れるのか、という論点において、どれくらいの情報量であれば、一般的に質的研究を採用すべき、量的研究を採用すべきという基準点が存在しないのか疑問を持ちました。
今回の講演において、第3章で紹介されたように、「質的データと量的データとを組み合わせる」「質的方法と量的方法を組み合わせる」「質的研究と量的研究の結果を結合する」という、質的方法と量的方法を補完的なものとして捉える方法が紹介されていた。これにおいても、論文を書く際には、なぜ結果において質的研究と量的研究を組み合わせたのか、なぜ方法において質的研究と量的研究を組み合わせたのかという、自分が正しいと思う根拠の提示の仕方が難しい点だと思いました。
質的研究と量的研究が相補的なものであると考えると(そうでなくても研究というものはそういうものなのかもしれないが)、先に方法を質的研究に絞るというのは望ましくない、質的研究のそもそもの目的に沿わないことなのだと感じた。 「一つの事例でしかないけど、それで結論づけていいのか」という質問にあるような、そこに事実があるにも関わらず、量的な実証データがないと研究として示せる感じがしないのは、これまで多くのことが量的研究によって示されてきたことによる偏見でしかないのだろうと思いつつ、量的研究の成果が膨大にある(と思われている)なかで当面の間は仕方ないのだろうとも思った。 質的研究の恣意性(?)・調査者の偏見が入ることに対する批判(H松さんのお話された例など)に対して、例え量的研究であっても、いわゆる科学的と言われる研究であっても、量的、数値的にまとめるために用いる枠組みや基準、対象が恣意的に選択されたり偏見に基づいて選択されたりする可能性は十分にあり、同じ批判はできるようにも思われた。
大変楽しく拝聴いたしました。こちらはあまりにも不勉強で、的外れな質問をしていまうのではないか、と思いつつ・・。 質的研究を支持していて、今後適切なやり方で実施していきたい、こと前提で、以下の質問です。 10日間の活動に参加した1人の対象者の様子を観察し、またその方の手記(日記や感想文のようなもの)を分析した研究で、「この人はこういう変化・成長を遂げたようだ」「その要因として、活動のこの特徴が挙げられる。」という報告がありました。変化を遂げた要因として挙げられたものの中で、「険しい道のりを長く歩き切る」などはわりと納得できたりするのですが、「そこにある木が自分(対象者)を見ている、自分は意識していない(感想文などに出てきたわけではない)が、無意識的に感じている、ということが対象者の成長を促した」という内容に、「うーん・・」となりました。 不勉強で、この研究が質的研究に分類されるのか自体、分かりませんが、こういうものも認められるのでしょうか?
購読会の雰囲気ってこんなかんじなんだなと新鮮な気持ちで参加させていただきました。私も小中高の総合的な探求の時間で、クラスメイトを対象にアンケートをとり調査をした経験があります。この時、質問する項目が自分の望む結論を導くためのものではないか不安になったり、集計したデータをみてそのデータをどのように調査に反映すれば有効なのか疑問に思ったりしました。今もデータを扱うことに少し苦手意識のようなものがあります。今回、質的研究の存在を知って、アプローチの仕方は量的データだけではないことがわかりました。購読会を通して、どこでどんなアプローチができるのか、質的研究と量的研究の使いわけについて考え、自分で研究をデザインできるようになりたいです。
「質的研究」、「量的研究」という言葉をこれまでに聞いたことがなく、この講義で初めて耳にし、考えるきっかけになった。よりそのままの形の結果を重要視する質的研究と、客観性を大切にした量的研究を組み合わせた実証を図っていくことが大切なのだということを知った。AIなどが普及する世の中で、これからは自分の手で集めた結果と、技術がもたらしたデータをうまく対応させる力が必要だと思った。

質的と量的のどちらのアプローチを採用すればよいのか、その判断が難しいという議論がありましたが、実はスモールサンプルだから質的、マスサンプルだから量的とは言い難いのですよね。サンプルの量だけで決まるものなのではない。スモールサンプルだからこそ、積極的に質で語られるべきことがあるのです。
例えば、広島の原爆で亡くなった人の数を示すことは量的なアプローチですが、そのアプローチからは、伝えられないことがあるのです。石段に残された人影が示すさまじさは、質的でしか表すことができないもので、かつ非常な説得力を持つものです。フリックは、積極的に質をとる必要がある局面がある可能性を指摘していたともいえるかもしれません。
実際、量的のほうがエビデンスとして強いと思ってしまいがちですが、有効性が限られているところもあります。マイノリティー研究や歴史研究にも量的手法は使えられないところがあるわけです。
結局、量が多ければ多いほどいえるということばかりではなく、数が多くても言うことができないものがあるのです。結局、調査者が何を語ろうとしているのか、リサーチクエスチョンや研究目的によって変わりますし、質的な方法だからこそ、できるサイエンスがある、といえるのではないでしょうか。
そして、質的研究にも、技法があります。それに則っているか、否かで、それが研究といえるものなのか、語りにすぎないものなのか、が分かれてきます。
AIやデータサイエンスについても、この講読会の裏テーマ的なところがありますので、ぜひ論じていきたいと思います。客観的にみせようとして、主観的に陥ってしまっている例は、一部の量的調査やプーチンの主張などとも通じるところがあるかもしれませんね…。
第二講| 第6章 理論的立場/第7章 認識論的背景:テクストの構築と理解 2023年5月23日
当日資料はこちら
当日リポート
今回の講読会冒頭、G7のサミット会場で行われたゼレンスキーの講演動画を視聴しました。広島記念資料館の展示品ーー石段に残された影のエピソードが盛り込まれた、戦争を影にしよう、戦争を過去のものにしよう、という強い思いが訴えられた講演でした。
ある種、ゼレンスキーの「主観」が語られているわけですが、説得力がある……そんな時事的な話題とともに、第二回目の講読会が開催されました。
非常のボリューミーで、いろいろな専門用語が出てきていて、質的調査でのさまざまなアプローチとして、(1)象徴的相互行為論、(2)エスノメソドロジー、(3)構造主義がまずは紹介されていました。それぞれ、異なった理論的前提や対象の理解の仕方に基づいて展開されてきたアプローチではありますが、共通していた特徴もありました。
特に、認識論的原則--研究される現象や出来事をその内側から理解することを目指すという共通点は、「主観」をどう取り扱うべきか、という議論につながっていったように思います。
議論そのものは、「象徴的相互行為論とは?」という問いから始まりました。象徴的相互行為論の「象徴的」という言葉につい、惑わされてしまいますが、英語では「symbolic interactionism」と呼称され、「意味論」くらいに捉えるとわかりやすくなるかもしれないとも言及されてもいました。
人間における社会的相互行為を考える際に、行為者はひとつひとつの物事に意味を持ち、それに応じて行動するということ、そしてその物事の意味は行為者と他者との間の社会的相互行為から生まれていく…そのような立場から、社会を捉えようとしたもの、と説明されていました。(要確認)
その本人がどのように思ったり、考えたりするのか……というのはつまり「主観」ですが、この「主観」と正面から向き合い、どのように取り扱うかが、ポスト構造主義の過程でも議論されていったといえるのかもしれません。
量的調査において、まるで「客観」が成立しているかのように見えますが、実は、結果の解釈は、調査者の「主観」でもあるわけです。また、調査票の選択肢をどう選択するか、も回答者の「主観」にゆだねられています。
あらゆるものが主観的で、テクストとして示されるものは、すべて社会的に構築されたものである。むしろ、「客観的現実」があると信じていることのほうがクレイジーで、常に「主観」が入り込んでいる可能性を考慮して、社会的現実を捉える努力をしていかなくてはならないのではないか――テクストは、現実を表象したものとは捉えることができない「表象の危機」――…。そうした問題意識に立つことで、すべてが「主観的」であることを織り込んで社会的現実を理解しようとするプロセスが「ミメーシス(いわば世界を意味づけて捉えようとする)」を通じたプロセスとしても理解されようとしてきたのかもしれません。
結局、主観的であることを避けようがない中で、この「主観」をどのようにコントロールして、みんなにとっても妥当な「主観」を社会的現実として提示することができるのか、その技法を質的研究が生み出してきたといえるのかもしれません。
主観をコントロールした先に相互理解や相互解釈の余地を残すのではないか――そうした方法論について、今後も学んでいきたいと思います。
90分という限られた時間の中で非常に盛りだくさんで密な議論で、あっという間の時間となりました。(私のまとめもおぼつかず…涙)
また来週も頑張っていきたいですね!
参加者の皆さんからのコメント
今回の講読会は、わからない単語が多すぎて、内容の理解が困難でした。しかし、そこで唯一授業中に自分で質問してみて、少し理解できた、「象徴的相互行為論」についてまとめたいと思います。質的研究には、三つの視覚がある。一つ目は、個々人の主観的な意味づけを探る象徴的相互行為論の立場。二つ目は、日常のありふれた行為をその産物に関心を向けるというエスノメソドロジー的立場。三つ目は、心理的社会的な無意識の過程に目を向ける構造主義ないし精神分析的立場。の以上三点であった。一点目の、「象徴的相互行為論」とは、社会的相互行為から生じる自分にとっての意味をあらわるものである。この「主観的な意味」が、象徴的相互行為論の立場に立って実証研究を行うときに焦点が当てられる。キーポイントとなるのは、「主観的」「意味」であると理解した。
実証研究を行う際にカギとなるのは「主観」であり、出来事や経験に対する意味付けの方向で研究が行われる。また、科学的⾔明と規範的⾔明を区別する実証主義と、認識、知覚、知識は構築物であるとし、科学的事実は社会的構築物であるとする構築主義がある。事実は既に解釈を経たものであり、純粋な事実というものは存在しない。
自分は質的研究を実践したことがないので、わかりませんが、今回の講読会で質的研究には三つの基本的前提(視点)があると学んだ。三つの視点とは、一つ目に、象徴的相互行為論の立場に立って実証実験を行うとき、二つ目に、日常的な行為やその遂行、さらにそうした行為が遂行されるローカルな文脈の構想に関心を向けるエスのメソドロジー立場、三つ目に、心理社会的な無意識の過程に焦点を当てる構造主義の立場、の以上の三つであった。そこで、質的研究において、これら三つの視覚を組み合わせて研究を実施できるのか疑問に思ったのと、これら三つの視覚から同じ調査を実践した場合に、結果に影響は出るのか疑問に感じました。
社会は人々の主観によって構築されたもので、実証研究を行う際に、客観的な調査や調査結果であるということは不可能なのだということが分かった。客観的な調査結果を求めるのではなく、調査が主観的なものだと理解したうえで、多くの人が認めうる主観の相互理解を目指すことが必要だと感じた。
すべてのものは主観で見ていて、「客観的に見る」ということが基本なく、客観に限りなく近い主観として物事えお見るものだという視点を初めて知り興味深いと思いました。 難しい単語が多くあまり理解できていない部分もあったと思うので、個人的にも調べようと思います。
質的研究は量的研究では妥当なアプローチにはならない可能性がある。それを踏まえて、マイノリティーの話など一つの事象でも十分語れるテーマの場合、質的研究の方が量的研究よりもサイエンスである。加えて、質的研究の方が主観的でもあるが、客観性を見出すことも可能である。そのための質的研究には、主観的な状況を再構築する象徴的相互行為論や、メンバーが現実に作り出す方法を分析する社会的・主観的現実モデルなど三つの支える意見があり、その三つの意見は、共通点を持つ。つまり質的研究の方が根拠を提示するのに適する場合がある。
本題ではありませんが、最初のゼレンスキー大統領のスピーチのお話が印象的でした。授業内で同じ動画を見た際に、同時通訳の方が全くスピードに追いついていなくてほとんど何を言っているのか分かりませんでした。しかし今日のお話の中で、それはゼレンスキー大統領が直前で話す内容を変更しているということが原因として考えられると聞き、彼がその問題をよりリアルに聞き手に訴えたいのだと感じました。
量的研究では表せず、質的研究でしか表せないものがあるということを学んだ。例えば、核兵器が挙げられて、量的研究でどれだけの人間が死亡したか調べるよりも、ゼレンスキー大統領の演説内の影の話、すなわち、質的研究をする方が核兵器の残虐さがよく伝わる、という話があった。今回の講義を受ける前までは、数値やデータで表すことが最も大事なことだと思っていた。しかし、実際今日の話を聞くと、残虐な行為は、人の感情を聞き、共感をするという意味では質的研究のような他人の話が一番効果的なのかもしれない。
抽象的な部分は難しくて理解しきれていないが、今まで思っていたことが覆され、面白かった。
レジュメや説明がとても分かりやすく、勉強になりました。質的研究の歴史や質的研究に関する最近の議論の所は個人的に混乱しがちなポイントだったので、今回の講読会を通して頭の中の整理が出来て良かったです。 質問なのですが、感想フォームはいつが提出期限ですか。今回は感想フォームに入力をするのが遅くなって大変申し訳ございません。ありがとうございました。
初回に参加できませんでしたが、Mせんせいの復習とコメント・質問紹介で議論に参加したような気持ちになり、2回目に入りやすいです。ありがとうございます!
以前は質的研究の個別性が気になり、アプローチ自体に懐疑的だったのですが、多少勉強しているうちに、そもそも研究の「客観性」とは何か(そもそもあるのか)、と考えるようになりました。第1講と重なる部分がありました。 象徴的相互行為論が興味深かったです。
研究している人(=対象)の視点に立つ、というところです。もちろんルールや手順があって、研究すると思いますが、それが本当にその人の視点に立てているのか、ということは分からないと思います。本人が何を考えてある行動につながったか、ということを必ずしも外側から理解できるのか?と疑問に思うのです。重要なのは「本人が本当はどう思っているか」ではなく、「行為からどういう意味をもって行動したかと考え得るか」ということでしょうか。
7章の最後とも関わるかもしれませんが、だんだんわからなくなってきました。
・・・・・・・・

ゼレンスキー大統領の講演で使われていた「人影の石」の話は、「主観」であり、質的なものではありますが、”みんなが同意できるような主観”で、だからこそ、客観にきわめて近いものともいえるようなことであったのかもしれません。
実際に、絶対的な事実として科学は論じてこなかった、ということもこれまでの講読会でも議論してきましたね。例えば、天動説は数千年にわたって、ある種「事実」であり「客観」だった。でも、ガリレオガリレイやコペルニクスなどの「主観」を通じた問題提起を経て、発表されたり、報告されるといったコミュニケーションを経て、みんなが「確かにそうだ」と説得されて、「みんなが同意する主観」≒客観が確立してきたといえるのかもしれません。科学では反証可能性と呼びますが、反論がありうることを織り込んで、その反論に答え続けることを通じて、主観と客観を築いていくことが大事になるのですね。
だから、最初から客観的事実があると思い込んでしまわないようにすること。自分が独りよがりになってしまっていないか、思い込みになっていないか、ということを、特に社会科学はより注意して(変数も多いし、実験もできないからこそ)主観をコントロールしていく必要があるのでしょうね。
また、フリックが紹介していた質的調査の3つの異なるアプローチで、同じ対象に調査をしたとき差は出る可能性はあるのか、という点については、もしかしたら差は出るかもしれないです。どこにフォーカスをおくのか、ということももちろんあるかもしれませんが、力点による差なのか、そもそも差があるのはおかしいとして議論になるのか、それとも、調査者によってみえる社会的事実は異なっているという議論になるのかもわかりません。
いずれにしても、「事実」とか「客観」とか「正当性」、「正解」として社会的現実を語ろうとするのではなく、「妥当性を探っていく」--確かにそうといえるかもしれないと、みんなも納得できるようなそうした試みとそのためのコントールの技法が大事になってくるのだろうと思います。
また、「主観」についての話をたくさんしてきましたが、主観にもいろいろな意味があるのですよね。例えば”対象者の「主観」”もあるし、”調査者の「主観」”もある。調査者が知りたいのは、”対象者の「主観」”です。それをしりたいと思う調査者にも「主観」があるので、それをどうコントロールするのか、ということが大事になります。また、対象者の「主観」を探るためのさまざまな考え方や立場のようなものも説明されてきた、とも理解できるかもしれません。このあたりが、まさに「ミメーシス」の例を通じて説明されてきたところ、ともいえるのかもしれませんね。
第三講| 第8章 質的研究のプロセス/第9章 研究設問 2023年5月30日
当日資料はこちら
当日リポート
今回も、本当にたくさんいただいたご質問を振り返っていくことで、論点を整理していきながら(柴田先生にまとめていただいているからこそですが)、今日の内容に入っていくことができました。たくさんのご質問をありがとうございます!(🥰)
今日の内容は、量的研究に対して、質的研究がもつ強みや特性を改めて確認することができるような内容になっていたかもしれません。8章は、「プロセス」とタイトルにあるとおり、まさに議論する内容や分析するための枠組みの「切り出し方」に関連する点が論じられていました。
もちろん、テーマを設定していったりする過程は、量的研究も質的研究もさまざまな試行錯誤があるわけですが、量的研究は、どうしても理論がそもそも前提としてあって、その検証という流れで進むことのほうが多い。でも、質的研究では、インタビューなどを経て研究を進めたりしていく中で、新たな観点に注目してみる必要性に気づかされたり、修正するなどして、紆余曲折しながら研究していくことが、そもそもの大前提になっている方法論といえるのかもしれません。ある種、研究に誠実な態度、といえる、ともコメントがありました。
質的研究として挙げられていた、Grounted Theory Aproach(GTA)の”Grounted”とは、そもそもどういう意味なのか――という確認も今回の講読会の中でされていました。
「根差した」というニュアンス…つまり「地に足をつけて」理論化していくようなアプローチとして理解できるのかもしれない、と議論されていました。
調査で得られたデータはその後分析されていくわけですが、この分析する際に使う「枠組み」、いわばtheoryの採用の仕方は、だいたい2パターンある、とも紹介されていました。
一つ目は、外来の概念を使う、ということ。例えば、フーコーの生権力の概念を使って現場を分析する、とかそういうやり方がありえるわけです。ただ、理論や概念の正しさを説明することができるような現場を選んでしまったり、理論ありきになってしまうことも起こしてしまいかねないことも言及されていました。
二つ目のやり方が、GTAのようなやり方です。現場に入ってみることで、「こういう理屈や概念で説明できそう」というふうに考える。現場に入って考えて、また現場に入って改めて考えて修正して…というプロセスを通じて、分析枠組みを築いていく、というようなやり方、といえるでしょうか。
この現場に入って立ち上げては、修正し、また現場に入って立ち上げていくようなtheory…のことを、「バージョン」としても説明されていました。それぞれのバージョンを理解したり解釈していく中では、もちろん外来の理論(フーコーとかオリバーの議論などなど)を使うことはもちろんある、とも確認されていました。
さらに9章では研究設問、リサーチクエスチョンともいえるようなものについても概説されていました。リサーチクエスチョンは、なぜか常に「問い」の形をしているべきと捉えられがちですが、むしろこの《問いの形》から離れ、「あいまいなもの」「漠然としたテーマ」(これが「感受概念」とされていたもの)として掲げ、いろいろな条件と照らし合わせながら(研究対象との近接性や方法論の選択などなど)大事な関心や問題意識を失う(=摩擦損失)ことがないよう、意識してコントロールしながら、「刈り込んで」いく必要があるものとも確認されました。いわば、刈り込み(shaping)をしていくその過程も、調査のプロセスに含まれている、といえるのかもしれません。
ここで、リサーチクエスチョンや研究設問とはいわずに、「battle fieldの設定」と捉えたほうがいいのかも、というアドバイスもありました。
量的研究では、どうしても数値をとろうと試みるので、無前提に刈り込みが行われてしまうものです。例えば選択肢をリッカート方式で5つ設けたとき、「2.3」や「4.9」などの隙間のデータはとりようがなく、零れ落ちていくわけですが、これをmanageすることは量的研究ではほとんどできないわけです。
逃げ道としてopen answerなど自由記述欄を設けたり、「その他」の選択肢を持つなどの方法もあるのかもしれませんが、それはどちらかというと質的なアプローチです。つまり、質的研究は、摩擦損失をmanageする強みも持つ方法論ともいえるのかもしれません。
こうして量的研究に対しての質的研究を議論して、どこがポイントになるのかをみてきましたが、次回はサンプリングに関するところです。こちらも量的研究と質的研究とで全く捉え方が異なっている、という指摘もありました。ぜひ、楽しみに勉強していきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
とてもわかりやすかったです。レジュメにも、自分なりの解釈や理解できなかった点なども記載されていたため、噛み砕いて表現してくださったところがとても良かったです。ありがとうございました。
今回はエスノメソドロジーや構造主義的モデルなど、自分の理解があやふやだった所の説明を聞けて勉強になりました。レジュメの構成も分かりやすかったです。ありがとうございました。
質的研究と量的研究の違いについて理解することが出来た。質的研究が典型的と思われる、代表者を研究対象にするのに対して、量的研究は研究テーマとの関係に基づいた人を対象とするという対象者の違いも分かった。すべての研究がリサーチ、アナルシス、コンクルージョンと段階を踏んでいるように見えるが、実際はそんなことがないということを知った。
私はこの購読会に初めて参加したため完全に理解できたということではありませんが、質的研究と量的研究がどのように違うのか理解することができました。量的研究は直線的なプロセスを辿って研究するが、質的研究はそうではないということ、グラウンデッドセオリーアプローチは循環的で全体を常に配慮しながら団愛的に取り組むということがわかりました。今回の購読会を通してますます次回の内容に興味を持ちました。来週も参加したいと思います。
質的研究では代表性よりも、研究テーマとの関連性を重視して調査対象が選ばれるというのが印象的でした。研究設問の設定と、研究設問のためのインタビュー方法や具体的な内容を決めることは質的研究では特に重要だと感じました。世界のバージョンとしての研究プロセスにおける理論についての話が難しかったです。
量的研究が直線的なプロセスを辿って行われ、質的研究は全体的な研究プロセスが依存しあっており、はっきり分けることができないGTAアプローチを採用していること。また、量的研究の直線的プロセスにおいて重視されるのが、データと調査結果の代表性であり、質的研究のGTAアプローチでは、代表性よりも研究テーマとの関連性を重視して調査結果が選ばれると勉強した。しかし、これらは著者が「量的研究は直線的プロセスを辿って行われるべきで、質的研究はそうではない。量的研究では代表性を重視すべきで、質的研究は関連性を重視すべき」と提言しているのか、それとも「これまでに行われてきた量的研究や質的研究を見てみると、こういった特徴が見られるよね」とまとめて言っているのかが疑問に思いました。
個人的には研究設問の理解が難しかったです。研究のやり方について考えることはあっても、設問自体を問題に取り上げて考えたことがなかったからだと思います。
用語、内容ともに難しく十分に理解できたとは言えませんが、研究の中でどうやってファクトを見つけ出すのか、主観をコントロールすることが大切になってくるということを学びました。また、量的研究は直線的だと言われているが本当なのかについて、確かに一概に規定して良いものなのか疑問に感じたので、今後考えていきたいです。
私の学科は卒業論文でフォールドワークが必須となっています。そのため、グラウンデッド・セオリーの部分で紹介されていた「どうしても選択を行う際に、自分が主観的に期待するものや、持っている傾向を追ってしまうが、これは行ってはならない。」という部分が特に印象に残りました。自分が求める綺麗な結果を導きたくなってしまうけれど、主観的な傾向を追うと認識が歪むとのことだったので、実際にフィールドに行って研究する際にはその都度視点が偏っていないか振り返る必要があると実感しました。
1,2回目の講読会には予定があり参加できなかったのですが復習をしっかりして下さったので、幾分か理解できました。質的研究と量的研究についてはセミナーで読み進めている「ヘンな論文」という著書に出てきてちょうど議論したところだったので内容が理解しやすかったです。K原さんは難しい内容の著書を要約する中ですべてを理解している訳ではないと思いますが、その中でも自分の意見をしっかりもたれていてすごいなと思いました。
グラウンデッド・セオリー・アプローチではデータや調査現場から理論的仮定を発見することや、調査対象を選ぶときは代表性より研究テーマとの関連性を重視することが分かりました。様々な側面が存在する調査現場では、どのように・誰に尋ねると自分がほしいデータを得られるのか考え、研究対象を限定することが重要であることも学べて良かったです。 個人的には、現場を観察して「ここの部分に注目しよう」と考えることが「感受概念」なのかなと考えていたのですが、いまいち自信がない(多分間違っている)ので、もう一度説明していただけると嬉しいです。
第四講| 第10章 フィールドへのアクセス/第11章 サンプリング戦略 2023年6月6日
当日資料はこちら
当日リポート
今回は、Mせんせいが不在だった講読会でした。代わりに食パンぱん子が「先週のまとめ」に挑戦します!
大学院生Mさんの発表を受けて、さっそく「テキストp.130にある、調査者が調査者という本当の役割を明かさずにフィールドに入ることは問題ではないか?」という質問がありました。また、これはテキストのp.135で触れられているような研究の倫理的な問題とも関係するのではないかと議論がありました。
例えばボランティア団体やNPO団体の調査を行うとき、私たちは純粋に「調査者」として現場に参入し、現場でノートと鉛筆と録音機を持って佇むことは可能なのでしょうか。
明らかに「よそ者」が現場に入ってきたと判断され、本音が聞き出せないかもしれません。一方で、何かボランティアの手伝いをしたり、NPO団体の活動に参加したりして現場に参入することもできます。むしろ、その方が対象者と「自然」なやり取りができるかもしれません。
しかし、このように調査者が現場に参加してしまうと、調査者によってその団体の実態が多かれ少なかれ影響を受けてしまいます。さらに、調査者の立場が外部的な「調査者」ではなくその団体の構成員に近くなればなるほど、批判的な視点や問題点など、その団体の不利益になるような指摘を研究として発表できなくなってしまう可能性もあります(going nativeの問題)。
ここで考えるポイントがあります。
1つは、その質的研究において純粋に「調査者」というアクターが現場で受け入れられるのかどうか、そして2つ目は「調査者」というアクターが現場に影響を与えずにいられるかどうかです。
どちらもその影響を0にすることはほぼ不可能かもしれませんが、大事なことは、これらをきちんと調査者の意識下に置き、コントロールすることです。得られるべきデータが得られるか、その調査が意味を持っているかどうかを考えることが重要なのです。手法の善悪の問題ではありません。
その点で、これは調査倫理の問題とは別物であると考えられます。
研究倫理は、例えばその調査対象や団体が何を許可しているのかについて、問題となるのです。言い換えれば、研究対象との合意形成の問題です。
サンプリングについては、「理論的飽和点」が話題になりました。
サンプリングは、計画的に事前にすべて決めてしまった方が分析的に見えるかもしれません。しかし、調査者が内部と関わり、その対象に対する理解や親密の程度が変化するにつれて、そのサンプリングの代表性も変化してしまいます。そこで重要になってくるのが「理論的飽和点」です。
例えば、この調査はどの団体の誰に聞けば調査できるのかが分かり、さらに対象から、調査を行なっている自分が「これは本当だ」と思えるような情報や状況を十分に調査できた状態のことです。
対象の団体にいる全員から話を聞く必要は全くなく、重要で必要な人物に辿り着き、「うそ」や「建前」で構成された調査ではなく、有益な調査を行うことが大切なのです。
その程度や見極め、つまり「理論的飽和」が分かるようになって初めて、質的調査が始まると言っても過言ではないのかもしれません。
この「理論的飽和点」は、1回や2回のインタビューや調査ではとても見極められないことがほとんどです。3年や5年をかけてフィールドに関わり、やっと身につけられるかもしれない感覚と言われていました。
その感覚が備わると、例えばインタビューの時に、「あ、この人は今建前を言っているな」とか、「あ、今この人はとても重要なことを述べたな」というように、ある種の「うそ / ほんと」が理解できるようになります。こうなって初めて、科学的に、また有益に、質的研究の分析が行えるのかもしれません。
「調査者」という立場にしても、サンプリングにしても、方法論的な善悪を考えるだけではなく、その調査の意味や目的、影響を丁寧に考えて、研究や調査を自らコントロールすることが非常に重要なのでしょう。来週は、それを乗り越えるための技法でもある、半構造化やナラティブの手法を学ぶことができるようです。
参加者の皆さんからのコメント
今回はフィールドのアクセスとサンプリング戦略についての内容でした。フィールドのアクセスに関しては大きく分けて三つの体系があること、また調査者は中立の立場を取れないことからどのような配慮やコントロールをすべきなのかなどが話されました。またサンプリング戦略に関しては、研究設問との関連によって判断をする必要があり、その選択されたサンプルが適切かどうかはその研究が目指す一般可能性の程度に関して判断していくものだということが述べられていました。またサンプリングにも抽象的なもの・具体的なものなどがあり、理論的サンプリングでは理論的な基準に従ってサンプルを限定することが説明されていました。その中では一般的な概念図式と発展途上にある概念構造に基づいて絞るという例も提示されていました。また、理論的飽和状態になったとき=事例の取り入れをどの程度で止めるのかということも重要です。
前回に引き続き参加させていただきました。私は1年生です。卒論などのでどのようなことをす流のか全く無知な状態で受けました。しかし、今回の購読会を通して研究をする際の問題点を知ることができとても良い機会になったと感じています。「サンプリング」などわからない言葉も多かったのですが、最後の柴田先生の具体的なお話を通して、レジュメに書かれていたことの理解を深めることができました。ありがとうございました。
初めて参加したが、学部で勉強している地域研究の手法とつながることろがあり、非常に興味深かった。まだ二年生なので考え中ではあるが、ゼミや卒論で外国の地域について研究することも視野にあるので、今回のフィールドへのアクセスについての話が聞けて良かった。次回もまた参加したいと思った。
今日は質問に答えていただいてありがとうございました。より説明を聞くことができてこの場で質問してよかったです。調査者へのアクセス、ということにおいての役割について、NPOに入る大学生の例がとても分かりやすかったです。
どの程度集団に入ってどのくらい役割を担うかということは、得たい情報をできるだけ歪ませない、できるだけ影響を与えない形にコントロールすることと関わると分かりました。
また、役割を明かすかどうかの話で追加質問ですが、例えばNPO法人にアクセスするとして、責任者のレベルには本当の役割(=調査者である)ことを明かし、人々のレベルにはボランティアとして関わる(調査者としての役割を隠す)、などということも、得たい情報を得るためには、あり得る、ということですかね。この調査者へのアクセスについてと、研究の倫理的問題についてはある程度分ける必要がある、というのも勉強になりました。
ギャングの研究で、全て終わった後に立場を開示して出版について承諾をとった、という話もなるほどなと思いました。ある意味、「”正しい””ベストな”手順があるはず」と思いすぎている所があったかもしれません。得たい成果を得るためには、ある程度ベターな選択、手順というのが選ばれる場合もあるのかなと思いました。
今回の購読会では質問とそれに関するお話が一番学びを深められました。調査者は中立の立場をとれないというお話の中で出てきた、観光ガイドがガイドされる側としてあえて自分も観光客として参加することで分かることや、ボランティア団体やNPOなどに純粋な調査者として行く場合とお互いに交流をする場合における、その機関に与えてしまう影響をコントロールする意識や力が必要になってくるということを学ぶことができました。またそのコントロールは非常に難しいことであると個人的に感じました。
第10章のまとめで「インサイダーとアウトサイダーどちらかの視点をとるのか、その両方を取るのかを決めなければいけない」とありました。調査の期間が長ければ長いほど、アウトサイダーの視点を保つことは難しいと思ったのですが、その点の助言を頂きたいです。
フィールドへのアクセス方法に様々な問題点がある。自分が調査者としてフィールドに入るのと、ボランティア、または参加者として入るのとでは自分が集めることのできる研究結果が変わってきてしまう。だが、質的研究では自分が調査者だということを隠すことで内部の情報を集めることができる。その一方で、参加するフィールドの信頼や利益、権利が損なわれてしまわないかもう一度考える必要がある。
ヴォルフによる調査フィールドとして機関に入る際の問題点が興味深かった。調査される側としてはいつもの日常にいきなりよくわからない他者が侵入してくるので、不信感を抱くのは当然だと思う。限られた時間の中で調査対象者と如何に信頼関係を築くことができるかが鍵になってくると感じた。
私は、個人への調査の方が難しいと思っていたが、今回の授業で機関や施設への調査の方が難しさを感じた。個人への調査の場合は調査対象者を見つけること自体に苦労してしまうものの、見つかってしまえば、新しいことを話してくれたり、なんのフィルターにかかっていないことを率直に話してもらえる可能性がある。そのため、得られた結果は調査対象者の本当の真理に近いものが得られる。一方で、機関や施設への調査の際は、調査対象者を見つことは簡単であるが、調査対象者は自分たちの仕事の限界が明るみに出されることや、関係構築の問題、仕事上の協調関係などがフィルターにかかって、対象者の率直な結果が得られにくいと考えた。そのため、調査者は機関や施設へ調査する際は、彼らの調査にフィルターがかかっていることを理解した上で、彼らに率直な意見を引き出すような質問の仕方も考えなくてはならないと学んだ。
インタビューにおいては、質問者側のコミュニケーション能力が不可欠であると知りショックでした。コミュニケーション能力が必要であることはよく考えればわかる話だけれど、実際に認識してしまうとぐさっときました。将来、インタビュー調査などをするのかどうか分からないけれど、自分はコミュニケーション能力がないので、あらかじめ質問をいくつか用意してもし相手がこう答えたら、次にこういう質問をしようと他の人よりも念入りに準備しておく必要があると思った。
正体を隠して研究をすることに関する倫理的な面に関しては、”誰にとって”の問題になるのかを考える必要性があることも学ぶことができました。また、サンプリングに関しても、理論的飽和点を見つけること=全員に話を聞かなくて良いということから、サンプリングの重要性に関しても学ぶことができました。
(ボランティアと調査の区別が難しいといった)
最後の話し合いが特に考えさせられました。調査者としていった時と普通の人としていった時では、何か調査対象の行動が変わってしまう可能性があるから、時と場合で変える必要があるなと思いました。しかし、その研究結果を使い、何か論文などを書くときに、許可が必要なため、もしも危険なところで調査するときはどうするのかなと思いました。

ポイントとして挙げていた調査者が現場で受け入れられるのか、そして現場に影響を与えないか、という点は実は、量的研究でも同様に考慮されなければならないことです。というか、量的研究では「調査者が望むように対象者も答えてくれている」という前提で解釈されているようなもので、本当の意味でコントロールされているとはいいがたいといえるでしょう。本当に対象者がアンケートに「正しく」答えてくれているかは何にも保障されていないのです。だからこそ、AIや行動履歴をみるような、観察的で限定的な方法が今、注目されているといえますが、この方法論ではおそらく主体の認識には迫ることはできないのです。その意味で、量的研究の限界は高まっているといえるでしょう。一方で、質的研究は、さまざまな方法論などを通じて、どうにかこの課題をコントロールしようとするわけです。それによって、妥当性や確かさを増している方法論と見なせるのです。
サンプリングについても同様です。100人いたら10人に聞けばいい、とかそういう形で対象者数が決まるのではありません。理論的飽和点(これ以上、インタビューいても結果は変わらないと思われるところ)で、サンプリングを打ち切るのです。その意味では、質と量とでサンプリングは同一のものと捉えることはできません。また質的研究のサンプリングは、何を以て「理論的飽和点に至ったか」が分からないと、調査そのものも始まらない、ということを意味します。
理論的飽和点を見抜くためには、そのテーマをよく理解する必要があるわけです。理論であったり、先行研究であったり、事前の勉強が重要になるのはそのためです。
また、倫理的な問題と事実を知ることのどちらかに偏ってしまうことなく、バランスを保って議論することは恐らく可能なはずです。また、フィールドに関わる期間の長さが、going nativeに影響を与えるとも言い難いでしょう。フィールドに身を置く時間が長かろうが、調査者がコントロールやマネジメントすることは可能なはずです。また、インタビューはコミュニケーション上手でないとできない、ということもないでしょう。私たちが「いい店員さんだなあ」と思う人がすべからくおしゃべり上手ではないことからも伺えます。
大事なのは、ごつごつ建前のように大仰に捉えるのではなく、嘘をつかず、人間として求められる「普通」や「自然さ」を大切にふるまっていく、ということなのかもしれません。
第五講| 第13章 半構造化インタビュー/第14章 データとしてのナラティブ 2023年6月13日
当日資料はこちら
当日リポート
今日は前回のフィードバックにも白熱しつつ(フィールドに入っていく際の、じしんが調査者であることを明かすかどうか、については、調査の倫理にも大きく関わりそうな部分でたのしみですね!)、半構造化インタビューとナラティブとインタビューに、さまざまな種類があるということを必死に受け止めたような会でした。
というわけで、今回は購読会後のディスカッションを参考にシェアさせていただきます。
私たちは、今回の購読会の中で質的研究がある種、量的研究の限界を受けて発展してきた、ということを意識し続けてきたように思います。実は、今回見た半構造化インタビューや、ナラティブもその流れの中に位置付けると少し分かりやすくなるのかもしれません。

と書きましたが、半構造化インタビューとされるもの(現在、実践されているインタビューで、構造化されていないものは、すべて半構造化インタビューとしてみなされているのが現実、とも説明がありました)と、ナラティブは、まったく別物と捉えるとよいようです。
半構造化インタビューやナラティブは構造化された調査票やインタビューの中からだけでは、対象者にとってのリアリティを把握しきれないという問題意識から生まれました。さらに、ナラティブは、半構造化インタビューで努力をしてもなお、「インタビュー」という形式をとる以上、対象者にとってのリアリティは得られないのでは?という指摘から展開されていった方法です。
対象者に対して、調査者が前もって用意した質問に回答していってもらうのではなく、対象者にすべて語ってもらう…というところから明らかにできるものがあるのではないか、という発見は本当に革命的なことだったそうで、調査者の介入を極力控えて丸ごと対象者にあることを語ってもらうということを目指したのがナラティブです。
だからこそ、キークエスチョン(ナラティブを生成させる質問)とも言われるような、語りを始めていただく際の切り口を作ることと、ひたすら対象者の語りに耳を傾けて相手の語りに委ねることが、とりわけ調査者にとって重要な仕事のひとつになるわけです。

「キークエスチョン」といった、質問の投げかけすら、ナラティブを原理的に捉えればNGなわけです。調査者の存在は「ゼロ」にすることを目指し、ひたすら、ただ相槌を打つ、程度にとどめるのが、ナラティブだ、と改めて解説がありました。
ナラティブにおいて対象者が語ることは、何の縛りも方向づけもないので、もしかしたら調査者が知りたいこととはかけ離れていったり、遠回りしたりすることになるかもしれません。だからこそ、キークエスチョンの設定も大事になってくるわけですが、もうすこし、語っていただく内容を調査者自身がかかわることで絞り込んでいく、というようなことが行われます。ナラティブをちょっとコントロールしたものが、エピソードインタビューとして説明されていたようなことに近いものかもしれません。
さらにナラティブを語っていただくための一方で、構造化インタビューの反省を受けて実践されるようになったのが、なるべく対象者が自然に語ることができるような場面を作っていくような、構造化の度合いを下げた半構造化インタビューです。設定を細かく設定していくことでインタビューガイドを設けるような半構造化インタビューになりますし、語っていただくべき問題やテーマをしっかり共有するインタビューは問題中心化インタビューと捉えることができるかもしれません。
さらに「ここについて語ってほしい」と、いわば舞台を設定してしまうようなインタビューは、焦点化インタビューとしても理解することができるかもしれません。
SLT(the structure laying technique構造敷設テクニック)という方法も、インタビューを構造化していく中で調査者の意図が入りすぎてしまうかもしれないという状況を受けて、対象者の力も借りて、妥当性を高めるという目的から編み出されたものです。ただし、修正過程のやり取りなどはトランスクリプトに書き起こされにくく、それゆえに「語られたもの」として論じる対象にしていけないという問題から、近年ではそこまで実施されていない傾向もあるようです(その代わり、あえてインタビューの中でカウンタークエスチョンを設けるなどして、やり取りの記録をしっかりインタビューとして残すようにするなどの手が取られることもあるのだとか)
こうして、さまざまな手法があることが分かりましたが、厳密にその方法論に型通り合わせるということはなく、その時々、調査対象や状況に合わせて柔軟に紹介されたような方法が組み合わされることも多いそうです。
実際、ナラティブを厳密に実施しようとすれば、調査者は対象者が語り終えるまで口を挟まず、ひたすら話を聞くことしかできません。それは実際の「自然な」インタビューの場面においては現実的なことではないのかも、という指摘もあるわけです。
むしろ、「定型的な語り」を見抜き、いかに自然に語っていただき、理論的飽和点に至らしめるのか、が大事になるのかもしれません。
そのためには、調査者が理論を学ぶことや、あえて対象者に対してナラティブの場を設けること(自由に語っていただくことで、理論的飽和点を探るヒントを得る)が大事になってくるようです。
対象者の代弁者になるのでもなく、表層的な偏った議論をするのでもなく、誰もが「確かに」と納得できるような、対象のリアルを確かに示すことができるような調査、というものをできるように、ぜひ鍛錬していきたいですね。
参加者の皆さんからのコメント
インタビューする内容、相手、インタビューをすることで聞きだしたいことによって、インタビューの方法を変えることが必要である。半構造化インタビューとは、あらかじめ質問を決めておくが、状況やインタビューされている人の反応によって変えていく方法であることを初めて知った。それぞれのインタビューには限界があり、さらに、柔軟にインタビューを進める必要があるため、ある程度回数、経験が必要であることがわかった。また、振り返ってみると今まで私がしてきたインタビュー形式のものは、アンケート回答のような構造化インタビューであったことも知ることができた。
インタビューとは、全てがインタビュアーによって構造化されるものではなく、インタビュアーとインタビュイー双方向の意識、考え、状況また、インタビューの方法によって変わってくることを学んだ。こんなにもインタビューの方法が多様であるということを初めて知った。また同時に、インタビューアーはいろいろな部分に意識を向けなければならず、練習が必要なくらい難しいものであることも学んだ。
専門家インタビューの失敗例には、準備不足、誤った前提、コミュニケーション不足、専門用語の誤解などがあり、これらは質問の不適切さや情報の不明確さにつながり、効果を損ねる可能性があるということを学んだ。
講読会には初めて参加したが、見やすいレジュメで、話も分かりやすく、すべてを理解することはできたわけではないが、多くのことを学ぶことができて面白かった。
ひとまとめにインタビューと言っても、状況によって方法がいくつかあることを知った。また、方法によってはそれ独自のやり方が原因で本来の情報が隠蔽される可能性があることを知り、正しい情報が世間に広められるために、情報の隠蔽が行われないように対処法を設ける必要があると思った。
個人的に印象に残っていることとして、インタビューが上手い人=話すことが上手であるという事ではないとお話しされていた事です。今まで私は話すことが上手な人の方が会話もスムーズにいくし、インタビューも楽しみながらできるから憧れを持っていました。しかし、寡黙な人=聞き上手な人の方がインタビューする人として向いているということを聞いてから、話し上手もいいけれど聞き上手になることも大切なことなんだなと勉強になりました。どちらもインタビュー以外にも重要なことだと思うのでさまざまな経験からそれらの力をつけていきたいです。
今回の内容について、まず半構造化インタビューという言葉を初めて耳にしたが、沢山の種類を詳しく説明していただいて、一言でインタビューと言っても事実への迫り方は用途に合わせて手法があることを学べた。しかし、それをする際にも(今回の講義全体に言えることだが)、その分野全体の背景知識をしっかり頭に入れ、訓練をして、事実を歪めないまま突き詰めることが重要であることを再確認させられました。
インタビュアーは、インタビューの進行とガイドとの間で常に仲介する必要があると学んだ。インタビュー中はすでに言われたことを把握し、研究設問と関連しているかどうかを把握する力も求められている。つまり、インタビュアーに重要なのは、自分がどのような調査を行なっていて、どのような結果を求めているのかということと、それとの関連性を見つけ出す能力が必要であると勉強した。ガイドを優先することだけでなく、柔軟なインタビューが求められると考えた。
“質問紙の配られ慣れによる質問参加者の劣化が問題視されているという話は今まで考えたこともなかったため新しい気づきになりました。一見、量的調査は効率よく、数値として欲しい情報を得られるものです。しかし質問参加者が正直に元の意見や気持ちを質問しに答えている保証はないことは思い当たります。欲しい情報を正確に手に入れることと、倫理的問題ないかどうかを調査者は常に考えなくてはならない
先生がおっしゃっていた「調査結果を全て信用するわけではない」という言葉がすごく印象的でした。調査者も建前があるように、調査対象者も建前があって全て本当に思うことを言ってくれているわけではないというのは自身の調査を通じて実感することでした。そもそも調査する前に理論飽和点がわかる状態に持っていくというのを聞いて、巷に溢れる質的調査はどれだけ信憑性のあるものなのだろうかと思いました。
質問です。焦点インタビューの問題点のところで、問題点を埋めるにはインタビュアーの判断能力を高める必要性があると書いてありました。インタビューという方法を取る時点である程度は仕方ないことだと思うのですが、インタビューをすると決めた瞬間に完全な客観的視点で調査するということは困難になりますか?質問内容を自分が答えて欲しいと考えた答えに寄せて作ることが可能だなと思い、このような質問をさせていただきました。

難しいのですが、構造化インタビューの反省を受けて半構造化インタビューが、そしてさらにその半構造化インタビューも、「決して生の現実や生のリアルは聞き取れない=ナラティブではなく、ストーリーでしかない」として、ナラティブが発展されてきたのであって、その区別はしっかりしておけたほうがよいのかもしれません。
結局、半構造化インタビューで得られるものとは、調査者の私見が入ることで対象者と調査者のふたりでつくったリアリティになってしまうという批判が出てきたわけです。
それで生まれたのが「ナラティブ」で、インタビュイーの存在を消したうえで語ってもらうことが目指されました。「ナラティブ」が活きてくるのは、例えばライフヒストリーなどですね。ただ、話をしていて、聞き手に意見を求めてくる場面なんかも現実的に考えたらあり得るわけです。でも、原理的なナラティブにおいてはそれも許されないことになるのですが。また、逆に聞き手の反応を抜きにあまりにも立て板に水的に話されることとは、もしかしたら「定型化された語り」になっている可能性もある。震災研究などでも散見されるのですが、あまりに語る機会があったことで逆にドラマティックに語りすぎてしまうようなことが起こったりしてしまう。
そして、「ナラティブ」が調査者の介入が入らないようにと思っていても、最終的に得られたナラティブを調査者は分析し、まとめていくわけで、そこでどうしても解釈が入ってしまうことは避けられません。pureなナラティブというものがありえるのか、半構造化インタビューとナラティブの境界が見えにくくなっている、という現実はあるのかもしれません。
また、インタビューでは、インフォーマントが語ることも、調査者が設定する質問も「事実」ではなく「その人にとってのリアリティ」となります。自分が偏った考え方や見方、解釈に陥ってしまうことはないか、そういう可能性はないか、ということに留意することが大切になってくるのかもしれません。ですから、先行研究が大切というのも、ただ単に勉強したことが正しかったかどうかをフィールドで確かめるためにする、というものなのではなく、理論的飽和点を探るヒントとすること:対象者が語ることや、自分の解釈など、「これは確かといっていいのか」を判断する基準としていけるとよいのかもしれません。
第六講| 第15章 フォーカス・グループ/第17章 観察とエスノグラフィー 2023年6月20日
当日資料はこちら
当日リポート
今回も、前回のフィードバックが白熱して…というと聞こえがよいのですが…、まとめ方に訂正をしていただきながら始まりました。とはいえ、まとめに書いた内容は、延長戦の居残りの中で話されたことであって、皆さんは聴くチャンスがなかったものであって、改めて柴田先生から説明がいただけた、ということで、こういうのを、「怪我の功名」とか「糾えるは縄のごとし」というんですかね…(ちょっと違う気もする)
※前回の訂正部分は、取り消し線や赤字と吹き出しで補足させていただきましたので、よかったらご参照ください…。
とはいえ、前回指摘があった「半構造化インタビュー」と「ナラティブ」の違いというのは、今回の内容にも大きくかかわっていたことでもありました。
今回も、ディスカッションする時間自体は非常に少なく、今回も延長戦からの内容を反映することになりますが、取り扱っていたのが、グループを対象にしたインタビューについて(15章)と観察(observation)について(17章)になっていたかと思います。いずれも、複数の集団を対象にしたものです。
グループ、いわば集団を対象に聞くインタビューということで、グループインタビューがまず登場します。一人一人にインタビューするのだったら、一気にまとめてやってしまえばいい、ということで実施されたもの、と思ってしまいがちですが、実は調査者と対象者が1対1でなされるインタビューと、複数名の対象者が一緒に回答するグループインタビューで得られることは全く違っていることに注意する必要があります。
一人で語ることと、他人がいて語ることは全く違う可能性があるのです。対象者がどのようなコンテクストで、関係性の中で語るのか、ということに配慮する必要がでてきます。
1対1でセッティングされるインタビューでは、「本人がどう思っているか」が語られることになりますが、グループインタビューでは、「グループの中で、他の参加者が見ている中で、どう言う語りをするのか」ということがわかってくるのです。
これは結果的に、他の参加者からの修正や補足が入ったりすることで、独りよがりの発言が出てきづらかったり、内容の妥当性が上がる、という点で有効と捉えられるともいえるでしょう。そして同時に、なんとなくその参加者間の関係性にも見えてくるものがあるのかもしれません。
ということで対象集団の関係性によりフォーカスしたものが、グループ・ディスカッションとして位置づけられます。グループの中で議論をしてもらうのです。そうすると参加者のポジショナリティや意思決定のプロセス、組織に対する考えなどが見えてきやすくなる、という指摘もされているわけです。
ただ、やはり、インタビューという方法をとる限り、現場への介入は避けられず、本当に知りたい集団にとってのリアリティがわからないのではないかという指摘も出てきます。
そこで登場するのが共同ナラティブ(joint narrative)です。ナラティブの集団版として位置づけられるこの方法では、自然発生的なグループに主体的に語ってもらう、ということを重要視します。
具体的にどんな場面で共同ナラティブが行われ得るのか、というと、例に出されていたのが、家族という集団を対象にしたナラティブでした。
「ご家族でご参加ください」と調査者が依頼して、調査場所にどんなメンバーが訪れるか、でまず、対象者が家族をどのように捉えているのかが見て取れることにもなりますし、家族であれば、自然な形でナラティブが得られ、ポジショナリティなども出てきやすいわけです。
さて、このように集団/グループを対象にするのであれば、やっぱりインタビューという方法をとること自体、それが共同ナラティブであったにせよ、やっぱり日常的なものとは言い難いのではないか、ということでobservation観察の方法が挙げられます(とはいえ、観察という方法はかなり古くから確立している方法です)
まず、一つ目が非参与観察と言われるものです。ある種、動物の生態などを観察するときに、観察者は自然に擬態しながら対象物を観察します。いわゆる忍者のように、調査者としての存在を察知されないよう気配をけしながら、隠れながら対象者の観察を行うわけです。
が、観察対象が人間である場合、倫理的に隠れて実践することはアウトになります。(なので、非参与観察の例として公衆の場などで行われる観察が挙げられていました)
次に、挙げられていたのが参与観察です。集団の中で自分の存在を明示して役割を持ちながら対象を観察するものです。この方法において調査者は、ある役割を担ったことで現場が受ける影響を引き算して、コントロールしながら観察をしていくことになります。外来者としての自分が現場に介入することで、現場は変化してしまうわけですが、その影響の度合いを考慮して分析していくという手法といえるのかもしれません。
そして、最後に登場したのが、ナラティブ的に革命的であったエスノグラフィーです。(エスノグラフィー自体は、人類学の手法としても古くから採用されていたものです)
この方法論では、隠れて観察をするわけではなく、その存在をフィールドは認知しているのですが、参与観察のように役割は持たず、ただその場にい続けることで、自分の存在が「いても、いなくても変わらない」という状態になってから観察に至るーーいわゆる調査者の存在をゼロにして実施する観察のこととして説明がされました。
調査者としての存在を極力なくす努力をして、それでも残ってしまう部分をコントロールしながら分析をする方法といえるかもしれません。
延長戦の中では、具体的な調査時のエピソードやエスノグラフィー的シチュエーション、通訳などが介在したときのリアリティの問題なども議論されていたりもしました。
また、次回は次回で、次回のテーマでみなさんと楽しく、みっちり?議論していけたら、と思います。また、間違えていないとよいのですが…涙。引き続きよろしくお願いいたします。
参加者の皆さんからのコメント
グループでのインタビューでは、もともとの文脈から人工的に切り離した形の単独インタビューに比べて、日常生活に近い環境の中で意見が生まれるため、より日常的文脈に関連性が高いデータを収集できる。また、フィールドを観察する方法については、どのようにアクセスするかの問題はつねに共通するが、どのような姿勢で「観察」するべきかという問題が方法を細分化している。
今回は個人的に混同しがちだったグループ・インタビューとグループ・ディスカッションの違いについて理解を深めることが出来て良かったです。非参与観察や参与観察、エスノグラフィーについての理解も深まりました。今回のレジュメや解説も簡潔でとても分かりやすかったです。ありがとうございました。
グループインタビューでは、1対1の時に語られる話とグループの中で話される話で異なることを学んだ。確かに自分自身、友人と個々で話すときと友達数名で話すときとではその関係性などを考えて話すため、内容や反応が異なることがある。グループの中での意見として聞きたいのか、個人の真の意見を探りたいのかによってインタビュー方法を使い分ける必要があると考える。
インタビュアーはよく話す人よりも口下手な人の方が向いていることを学んだ。また、グループ・ディスカッションはどの地点で議論し尽くしたかの判断を司会者が臨機応変に対応するなどの点から考えると、実際はそれほど効率的な方法ではないことに驚いた。グループ・ディスカッションは曖昧な方法なので、学校教育で推進されているにも関わらずなかなか浸透しない理由はこの点なのではと感じた。
グループインタビュー、グループディスカッションをする際にも、(柴田先生がおっしゃっていた)自分よがりにならないということが大切なのかなと思いました。観察することも日常的スキルであることを学び、今後論文の作成などに挑んでいく私にとって重要なことだと思うので、今回示してくださった観察の手続きなども参考にしたいと思いました。
フォーカス・グループの手法は、グループの人数によっては意見を述べる人とそうでない人の偏りが出てくると感じました。私の感覚になりますが、10人近くになると主に発言する人は5人以下になるため、3人から6人ほどのグループが適していると思いました。
調査対象に”調査されてる”ことを意識させず、普段通りに過ごしてもらうことで得られるデータが望ましい一方で、倫理的な問題から断りなしに観察できない、ということは非常に難しい問題だと感じました。両方の間を取る手段として、観察者が現場に姿を現して(観察対象に影響を与えて)いる状況で得られたデータを、その状況を考慮に入れ、”引き算したうえでも言えること”がデータとなる、という話が印象に残りました。 (単独インタビュー、グループインタビューともに)調査対象への影響に関係する部分で、以前から気になっていたことがあるため、この機会にに質問させていただきます。調査者は調査対象に、(信頼性や親和性を高める等の目的で)自己紹介や雑談の中で、調査者個人の情報や話をすることもあるかと思います。その際、対象者への心理・思考的な影響や調査者自身の(プライバシー保護などの)倫理的問題から、どの程度調査者が個人的な情報を伝えるべき、あるいは伝えても良いのでしょうか。

考えてみると、この時代になってオンラインでインタビューをする、ということも可能性や選択肢として広がってきましたよね。デジタルを使った方法として一つの応用事例として捉えられるようにも感じられますが、実は、使い方によっては劇的に変わる側面もおそらくあるのだろうと思います。ただ、「デジタルだから」という前提を考慮したり、それをうまくコントロールしたインタビューや観察、といったことについての議論はまだまだされていないのかもしれないですね。
ここまでいろいろな質的研究の技法を観てきましたが、対象がどのような文脈や設定に置かれているかで、「真実」も異なってくる可能性にうまく配慮しようとしたからこその選択肢の抱負さであったのだろうなと思います。例えばインタビューが1対1で行われたほうが、第三者に忖度することのない「真実」が手に入るように思われますが、一方グループインタビューでは、お互いの会話が記憶を想起することに役立てられたりして、こちらでもやはり、より「真実」が語られる可能性もありえます。いずれにしても、自身の存在や介入が対象に与えている可能性に自覚的になって、コントロールしていくことが大事になるのでしょうね。また、ひとつの方法ですべてが明らかになると考えすぎず、いろいろと組み合わせながら調査対象者に迫ることができるとよいのかもしれません。
グループディスカッションの人数ですが、参加者の人数が多ければ多いで、そこでは、発言の主導権を握るのは誰なのか、といった構成メンバーのポジショナリティを把握することができる、という側面もあるかもしれません。
また、調査者の自己開示についてですが、アイスブレイク的に自分のことを開示することは、対象者とのラポール形成にもつながり、相手が自分を信頼することができてはじめて語りやすくなる、ということもあるかもしれず、大事な側面も出てくると思います。ただ、これをやりすぎてしまうのは、やっぱりバランスを崩す要因になり得ますし、必要な分だけ開示する、という形でここもうまくコントロールしていくことが大事になりそうです。
第七講| 第22章 データの記録と文書化/第23章 コード化とカテゴリー化 2023年6月27日
当日資料はこちら
当日リポート
じめじめお天気の今日この頃ですが、沖縄で開催される暑い/熱い企画も楽しみな今日この頃です。
今日も、インタビューや観察の振り返りから始まりましたが、自分が調査対象者に与える影響について自覚的に捉え、コントロールしていく必要があることを改めて確認することができたのではないかと思います。
<自分が調査対象者に与える影響について自覚的になり、コントロールすること>は、調査を実施する場面で求められるわけですが、おそらく結果を解釈していくときにも必要になるものといえるのでしょう。現場の状況がどのようなものであったのか、何に「気を付けなくてはならない!」と観察・インタビュー時に意識していたのだっけ?ということを思い出すことができて、初めて自身の影響を考慮しながら、解釈や分析をすることになるのかもしれません。
そんなわけで、今日は、「データの記録と文書化」と、その後の分析の方法として「コード化とカテゴリー化」を取り扱った回となりました。
実際の文献の内容については、ぜひ、K原先輩がつくってくださった資料を参考にしていただけたらと思うのですが、講読会の中では、記録をとることや、現場でメモをとること、ノートテイクは、その都度、調査者としての思いを記録していくことでもある、と説明されていました。
インタビューをする際も、聞き手は、じしんが気が付いたり、考えたりすることの影響を避けることはできません。調査者が感じられたことや考えたことを、メモに残していくということによって、より立体的に、当時の状況をよりあざやかに思い浮かべられるようになりますし、その後の分析でも、整理しながら検討していくことができるようになるのかもしれません。
講読会後にも、少しだけノートテイクのやり方や工夫などがシェアされていたのですが、その実践の方法も、人によっても、さまざまです。対象者にとっても違和感がなるべくないような形で、自然にメモを取ることが許容されるような設定を自分で工夫して作ってみたり、メモを残すことに捉われず、しっかりドップリと、そのフィールドに向き合うことの大切さもシェアされていました。
やり方は、本当に経験的に自分なりのやり方や流儀が出てくる部分だとも感じたので、形にとらわれず、対象のリアリティと誠実に向き合うための努力や工夫に一生懸命取り組みながら、少しずつ自分なりになるべく詳細にメモを残していけるとよいのだろう、と個人的には感じられました。
講読会で取り扱った内容の後半は、得られたデータのコーディングに関するものでした。「オープン・コーディング」という、<得られたデータや事象を概念化していくプロセス>をベースに、さまざまなやり方や技法が展開してきたことを確認することができていたと思います。
(量的研究で出てくる「コーディング」は、もともと用意したコード表(この回答は「1」と振り、別の回答は「2」と振るなど、設定したもの)に則って、質問票の回答をコードに振りなおしていく作業のことですが、「オープン・コーディング」は「オープン」とつくとおり、その逆で、データに根差して少しずつ概念化を目指していくアプローチ、と理解することができるかもしれません)
そもそも「オープン・コーディング」は、グランテッド・セオリー・アプローチが大事にしてきた、理論ありきでデータを理解するのではなく、データに根差して理論を開発しようとするからこそ、生まれてきた発想なのだ、ということも、確認されていたかと思います。
「オープン・コーディング」を経て、その後の「理論化」をどのような方法で実践していくのがよりベターなのか、その方法論が、たくさんあることも、文献の中で紹介されていたことが講読会でもシェアされていました。が、今回の講読会では、そのいろいろある方法論に優越をつけたりするのではなく、いろいろなコーディングの方法があることを理解し、それをいろいろ組み合わせて試してみたりすることが大事、ということが確認されていたかと思います。
また、一回のコーディングで終わらせるのではなく、やり方やコーディングのタイミングを変えるなどして何度もコーディングを繰り返し、精度を高めていくことが大事であるとも指摘されていました。
(難しく考えてしまいがちですが)あまり、コーディングを難しくとらえすぎず、丁寧にコーディングしながら、コードとコードがどのように関連しあっているのかを考えてみたり(軸足コーディング)、どんなふうにコードとコードをまとめて捉えられそうなのか考えてみたり(コード化ファミリー)、どのコードが重要そうなのかを考えてみたり(選択コーディング)しながら、現実の再構成を試みていくことにチャレンジしていけるとよいのかもしれません。理論的飽和点に至ったとき、「現場からわかったこと」として、妥当な現実や理論が提示することができる、ということも確認できた回であったのかなあと思います。
また次回も引き続き分析法について確認していく回となります。講読会も終盤に向かいつつありますが、よい汗をかいて、頑張っていきたいですね。(今日も間違えていないといいな…)
参加者の皆さんからのコメント
録音・録画・フィールドノーツそれぞれの記録方法は一長一短であるため、どの手法もバランス良く活用すべきだと学びました。録音・録画からは実際の現場をそのまま記録でき、メモを取ることで記録と併行して理論構築を進めることができます。またメモを取るというのは聞いた事柄を一度自分の中で解釈する必要があるため、何もしないで聞くよりも遥かに注力して話を聞くことができると思いました。
研究者や質問者がメモをして記録する方法には、一過性を失わせてしまうというデメリットがあることを知った。データから理論を組み立てるプロセスをコード化と呼び、さらにその中でも2つに分けられていることを初めて知ったが、これらを頭に入れて情報を収集するとより良い研究、分析を行うことができるのだと感じた。質的内容分析と包括分析では、客観的ではなく主観的な目線で要約、データの選択が行われるため、他の方法の代替にはならないことを知った。
M先生は,「忘れていたり,性格が曲がっていたりするため,人間は真実を語ることはできない。だから,インタビューは限界がある。しかし,グループディスカッションは相手の言っていることを考え,自分の間違えを認識したり,考えて自分で訂正できたりするため,より事実を反映させられる,という考え方がある。」と言った内容を話していた。K原さんは,「どうデータを記録するかについてで,記録者がその場にいなくても、日常的なデータを記録できる録音や録画が最近できた。しかし,ずっと日常を記録するのではなく,必要最低限でデータは記録するほうが良いとされる。現場でノートをとったり,メモをしたりすることはとても大事。」という話をしていた。
自分の取ったデータを頼りに分析する際、状況の捉え方や言葉の受け取り方、自身の分析の仕方が主観的になっていないかと問うことは大事だと思う一方、今回の購読会でそのような”歪み”を完全にコントロールすることの難しさを改めて感じました。つい客観性を追い求めた結果、様々なプロセスで自分のやり方に批判的になりすぎてしまう傾向があり、どこでキリをつけるべきか悩むことが多いのですが、自分の調査や結果は「後から是正されていくもの」と割り切ることも大切なのだとわかりました。またメモの取り方もその都度、状況や相手、自分の立ち位置などを考えながら模索し、自分にあったやり方を見つけていきたいと思いました。
収集したデータの記録方法を学んだ。今回の講演を通して、コード化とカテゴリー化、質的内容分析の2つの分析方法をはじめて知った。コード化とカテゴリー化のうち、特にテーマ的コード化に興味を持った。事例ごとの分析を実施し、次に事例を超えた分析を実施するというように比較可能性が上がることを理解した。これは世界の民族研究や文化研究にぴったりな方法なのではと感じた。

質的研究をしたあと、こんなふうに分析をしていかなくてはならないのか、大変そうだなあと思ってしまうような内容になっていましたよね、でも、実際、前回フリックがかいていたような内容は、「理想」みたいなところも正直あるような気もします。そもそも、やっぱり質的研究は、「ある種のあきらめ」を受け入れるところから始まる(量的研究が、世界を明らかにする、みたいな自負が大前提にあるのと正反対、みたいなニュアンス)ものですし、対象に対して、「世界のすべてを記述することは不可能、と自覚する」という意味で、誠実である必要がたぶんあるのです。
インタビューなどをしても、その場でその内容を受け止めた調査者が、一番そのリアリティを実感しているのです。現場の空気感や、姿勢や目線、呼吸みたいなものをまざまざと目の当たりにしているわけですから。でも、その結果を第三者に届けていこうとすると、どうしてもその程度も精度も落ちていくのです。摩擦してリアリティは損なわれて行ってしまう。そういうある種の諦観を持ちながらも、現場での「空気感」を残す工夫が語られていた、と捉えられるとよいのかもしれません。ノートをとったり、録音したり、どうrealityを再構成するか、というその工夫をしておく必要があるということですね。ただ、本当にショックな、衝撃的な事実というものは、脳にいやおうなく刻まれるものであったりもします。
また、コーディングのところでは、残さずgrountedになるようコーディングをするためには、という点が議論されていたともいえるかもしれません。ある意味で、みんな無意識に自然にやっているような「抽象化」のプロセスでもあるのかもしれませんが、それを段階を踏んで丁寧に実施していくことについて触れていたともいえるかもしれません。一見、キレイに概念整理できた、と思ってしまうようなことでも、もしかしたら、「間違っているかもしれない」と自省的に丁寧にコーディングしていくことが必要ですね。
記録のとりかたも本当に一長一短だったりするのは本当にそうですね。録音や録画は便利なようですが、調査者の集中力を削いでしまうような(無意識に)ところもあるかもしれないです。録画/録音できない環境だったら、一言も聞き漏らすまいとすごく集中してインタビューに乗れたりすることもあるわけで、そのテンションをどのような環境でも保てるように己をコントロールすることは結構難しかったりもします。
また、ゆがみのコントロールは、自分でも一生懸命する必要はあるのですが、他の共同研究者と一緒に考えていくことも一つの方法かもしれませんし、publishされていく過程でも是正されていくことになります。その意味では、AIは自分が間違っている可能性を考慮できないですし、それゆえに結局は定型的なまとめに逃げざるをえない、という欠点をもっているともいえるのかもしれないですね。私たちは、ドン・キホーテであることを自覚したドン・キホーテ的に切り込んだ議論をしていくことを目指したいですね。
第八講| 第24章 会話、ディスコース、ジャンル分析/第25章 ナラティブ分析・解釈学的分析 2023年7月4日
当日資料はこちら
当日リポート
いやあ、難しいよね…という悶々した雰囲気???で始まった今回の講読会。特に25章をどう理解したらいいのか、戸惑いながらの進行となりました。
が、今回の講読会の内容を一言で整理?するとしたら……
前回がインタビューなどで得られた「内容」や「中身」に関する分析だったとしたら、今回は、どのように・なぜ、それが語られたのか、という「形」に着目する分析、日常性の背景にあるものの分析であった、といえるのかもしれない、と解説されていました。
たとえば挙げられていた分析方法のひとつ、「会話分析」は、対象となっている複数の人たちが、どのような会話を繰り広げているのか――ストレスの置き方、間の取り方、沈黙などなど、に注目し、その会話を成り立たせている集団の構成や、集団の中で大事にされている「秩序」を分析しようとしているものと紹介されていました。そこでは、「何が」会話されているか、は分析対象にしないわけです。
例えば、Aさんが話しているところに、Bさんがかぶせて発話をしてみたり、そのBさんの話につづいてCさんが同調していったり…という会話の「されかた」に着目していくことで、その本人たちにも自覚されていないような日常の秩序や、当然視されていながらも意識されていないような秩序を浮かび上がらせられる、という特色を持つ分析方法なわけです。
この会話分析は、近年では広くエスノメソドロジーの代表的なものとしても捉えられている、とも紹介されていました。
そして、つづいて解説されていたのはディスコース分析です。談話分析、とも言われるものですが、これは、内容についても少し言及するものの、分析の焦点をおくのは、「なぜ、そう語られる/語られたのか」という点になっていきます。
言説として、語られたことの背景にある理由を探っていくような分析の方法で、語られた内容だけではなく、その裏側にある事情や理由--権力関係などをみていくようなものといえるのかもしれません。
例えば、インタビューで対象者が誰かのことを「あいつ」とか「お前」と語っていたり、誰かの振る舞いを「~されていた」などのように丁寧に敬語を使って説明していたりしたら、「なぜ、そのように語るのか」というところから、対象者の主観やポジショナリティ、関係性を分析していくことができるのかもしれません。それはある種、語っている本人にとっても「自覚的」に、その人の主観を反映させる形で、特定の語り方/語られ方に至っていると、理解することができるものといえるでしょう。
対象者じしんもある種、自覚的に「特定の語り方」をすることがあるわけですが、対象者じしんも無意識に特定の「語り方」をすることがあるかもしれません。社会状況や所属コミュニティで前提とされている他の客観的状況によって、本人がなぜ「そのように語る/語ったのか」を分析しようとする試みとして、客観的解釈学として説明されていたように思います。
語られていることが、完全に主観的ではないようなとき、(間主観的とも解説されていましたが、)語られていることの背景にみられる裏側のロジックに着目していく、というような…、そのように語った背景にある知識体系のようなものを、インタビューなどで得られたデータ以外の資料なども用いながら分析していくようなものとして紹介されていたように思います。いわば、インタビューで得られたことを字面通りに理解するのではなく、その裏側の意味構造を分析していくようなものとして解説されていました。
「語られたこと」を、そのまま、その人の本音として捉えるのではなく、そのように語らせるほかの要因や社会的背景や権力構造のようなものを意識しようとする見方は、ポストコロニアルな議論が出てきていたことにも影響している可能性がある、と延長戦の中で指摘されていました。
その意味でナラティブを、「生の声」や「本音」と捉えたとき、ナラティブとみなせるようなものは、語られたものの中でほんの一部にしかならないかもしれないのです。
また、なぜそのように語るのか・語られたのか、ということに注目しようとする以上、分析される対象は自然発生的に得られたものである必要もあるといえるのかもしれません。
その本人の考えや主観によって、「語り方」が規定されることもあれば、他の客観的な状況や共有されている前提条件によっても影響をうける、と想定していくと、より共同性に開かれた、社会的文脈や歴史的文脈に考慮して分析していくことにもつながるのかもしれません。
内容や中身に関して、コーディングを丁寧にしながら分析を実施していくことの末に、なぜ、そのように語られたのかという背景を探る分析を組み合わせていくことも、質的研究の中ではあり得ることのようです。それぞれ、ステップを踏みながら、丁寧に、自身の歪みを自省しながら、でも切り込んだ分析をしていけるようになりたいですね。
参加者の皆さんからのコメント
今回はデータの記録と文書化、コード化とカテゴリー化について学習できて勉強になりました。レジュメやそれに関する説明も非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。
会話分析では、会話の内容より構造を見ることで話している人たちの関係、立場や地位を分析ができることである。例えば、多く発言している人がグループの中で中心的な人物であるようなことです。また、話している人たちはグループの中での関係に対して無自覚であっても会話分析によって関係が分かってしまうということを学びました。
食ぱん子さんは、「会話・ディスコース・ジャンルについてと、ナラティブ分析についてであった。会話分析やディスコース分析をやることで、内容を覚えやすかったり、社会の組織化に当てられたり、するため考察に反映しやすい。ただ、この分析方法にも弱点はある。」と言う点まで理解できた。
全体的に、分析方法にはメリットと、デメリットがある。質的研究においては、調査中の記憶をより鮮明に思い出し、その記憶を考慮して考察することが大事だと理解した。(しかし、細かいことはあまり理解できていません。)
プロでもデータの分析や調査をするのはすごく難しく、完璧にやることは難しいと言うことを学んだ。私は、大学に入った時、レポートでアンケートをやる方がいいのだと思っていた。しかし、バイアスがかかっており、上手く調査はできなかった。その後データの分析について勉強したが、難しく素人には無理だと感じた。しかし、プロの先生も調査は難しいと言う話をしていて、自分ができないだけではないのだと知った。加えて、今回の授業でそのバイアスなど調査した時の心情を踏まえて考察することが大事だと、学んだ。

まとめについて、もし気になる点があるとしたら、「ナラティブ」の受け止め方ですね。
一般的な質的研究の考え方でいうと、ナラティブに影響を与える可能性があるのは、調査環境であったり、調査者の介入によると考えます。社会背景や権力構造を反映したような語りも含めて「ナラティブ」と捉えることのほうが多いのです。
ただ、講読したフリックの文献の中で、客観的解釈学とナラティブ分析を区別していたということを考慮すると、「確かにそうともいえる」という区別の仕方ですね。ただ、フリック自身もこの区別については再考したようで、新版(英語版の第七版)では、ナラティブ分析の項目は客観的解釈学に含めて説明されているようです。
今回挙げられていた分析の仕方は、英語の第7版ではnaturally occuring dataという項目として整理されています。つまり、インタビューなど調査者が人工的に作り出したデータではなく、日常の中で繰り広げられる会話など自然発生的に生まれたやりとりをデータとして取り扱っているのですね。その中で日常の中の権力構造であったり、発言の背景にあるものであったり、二者・複数間の中で関主観的に持たれているような意味や背景を探る分析を「やりとりのされ方」という形に着目して分析していくのですね。会話分析も最近はビデオカメラなどを設置して動きなども含めて分析に盛り込んでいくような展開をみせています。
会話分析は、これまでにもジェンダーや支援・被支援の関係性の中にあった権力構造のようなものを浮き彫りにするような、とても意味がある劇的な研究として展開してきたのですが、実は有効な射程範囲が限られているものだったりします。取り組みどころを間違えると、コストも多くなってしまう、という弱点もある方法だったりするんですよね。
第九講|第28章 質的研究の評価基準/第29章 質的研究の質-基準を超えて 2023年7月11日
当日資料はこちら
当日リポート
連日の早速の酷暑で、体調を崩しがちな皆さんも多い今日この頃かもしれません。水分だけでなく(コーヒーばかりはダメ)、ミネラルもとって、いい汗をかいていきましょう。
講読会の冒頭、柴田先生から、近年みられがちな傾向として、「データ・サイエンス」が無邪気に”真理”を示すものと捉えられがち、という指摘が挙げられていました。今回の講読会の中では、「節度」というキーワードも挙げられていたように思います。
今回、講読していった内容は、質的研究を評価していくうえでの基準や指針となるものについてでしたが、そもそも、質的研究は、量的研究における本質的限界を明確に自覚した中で確立していった方法論です。そうした背景を踏まえたとき、どんなふうに質的研究の質を考えられるのか、ということをしみじみ考えさせられる回となったように思います。
とくに、象徴的に振り返られていたのは、29章のタイトル「質的研究の質-基準を超えて」です。英語版の(本当の意味での2023年時点での)新版(7版)では、Quality of Qualitative Researchとなっているそうですが、「量的研究の限界を踏まえて確立されていった質的研究こそ、その質が保証されている」、という意味も込めて、ダブル・ニュアンス的にフリックさんはこのタイトルをつけていたのかも、と指摘されていました。
一見、質的研究というと、その信頼性や妥当性など疑問視されがちなのかもしれないのですが、量的研究で、ある種”盲目的”に、重視されている「信頼性」や「妥当性」などの指標が持つ限界を踏まえ、その限界を克服し、乗り越えていこうとしたところにあるのが、質的研究の方法論です。量的研究で克服できていないかもしれない課題(しかも、認識されていないかもしれない/見逃されているかもしれない)を克服するために、どのような手続きをとるべきなのかが熟慮のうえ確立されてきたのが質的研究、といえるのかもしれないのです。
質的研究を実践していく中でのquality management(翻訳版では「品質管理」とされていましたが、「質的管理」のほうがbetterかも、などとも言及がありましたが…)--質をどう保証していくか、という観点からのマネージメントや、process evaluation reflexiblityなど自己のありようが結果にどう影響を与え得たのか、その可能性を考慮しながらバランスをとって質的研究全体を振り返っていくことそのものが、質的研究の本質でもあり、かつ、質を保障するために確立されてきた技術で、それゆえ質的研究は「説得力」を備え持つ方法論になっているのかもしれない、と整理されていたように思います。
延長戦の中では、「節度を持ってコントロールしながら研究を実施していくこと」は、生き方にも通じるようにも思う、という指摘もされていました。私たちにとって「科学」とは、データに対して誠実に、あらゆる可能性に開かれながらmanageされていくものなのかもしれません。
質的研究の質が担保されるのは、対象に対しても、データに対しても誠実に向き合っていくからこそなのだと思いますが、そのあたりがおそらく次回の研究の倫理にもつながってくるものなのかもしれません。次回は最終回となりますが、ぜひ、Learning Crisisに対峙できるような、「アカデミックな誠実さ」について考えていけたら、と思います。
(あと、「間違える」ことで、より深い議論につながっていく。「間違える」ことを恐れずに、本当の意味での対話をしていこうね、的なやりとりもあったりしました。より妥当な回答/発言/提案を考えていくことも諦めずに、でも、その反応として得られる再提案や助言、新たな可能性を楽しみながら、理解を深めていきたいです。…ということで、今回のフィードバックも(そうはいってもドキドキですが)ご指摘のほど、よろしくお願いいたします。)
参加者の皆さんからのコメント
質的研究は単純な枠に収めづらいために、ジレンマが生じることを学んだ。また、評価基準の適用を超えて質的研究の質を高めるためには5つの戦略があることを知った。その中でも、とりわけ質的研究における一般化で、どの程度の一般化を目指すのか、達成可能かどうかを明確にしておく必要があることが印象的だった。
信憑性とはある現象の測定結果や観察が時間の経過の中で安定していることであり、質的研究の対象が該当することはめったにないことを学んだ。また、質的研究を最も効果的に実践するためには、研究の諸段階を全体の研究のプロセスに位置づけて定める必要性があることも学んだ。質的研究を実践するには様々な工夫が必要だということに気づくことができた。今回、教えていただいた方法の中で継続比較法が印象に残った。しかし、実際、絶えず疑いい、比較し続けることは難しいのではないかと感じた。
質的研究の評価基準について考えるとき、質的研究と量的研究では「現実の理解の仕方」の相違点が大きいため、質的研究に合った新しい評価基準をつくることが求められていることが分かった。質的研究の評価基準に対する様々なガイドラインは存在しているものの、質的研究の「本当」の質を基準の中で把握することは難しいということを学んだ。
今回は質的研究の評価基準に加えて、質的研究の質をいかに高めるかという話について学ぶことが出来て勉強になりました。個人的に、質的研究は一定の質を保持しつづけることを苦手とするイメージがあったので、「質的研究は質を保障することが得意なのではないか」という言葉を聞いて最初は意外に思いましたが、よく考えてみると確かにそうなのかもしれないと後から考え直しました。また、補足で話されていた第29章のタイトルに込められた意味や、「品質管理」という訳についての話も興味深く聞かせていただきました。今回も非常に興味深く、為になる内容でした。ありがとうございました。

quality managementって定訳があって、それが「品質管理」になるんですよね。でも、フリックは研究や調査を「品物」とは考えていないと思うんです。「生産物」ではないんです。なんだか、「研究の質」というと、どうしても「論文の質」についての話かなあと思ってしまいがちなんですけど、そういう話じゃないと思うんですよね。ここでの議論は「研究全体の質」--全体の在り方やプロセスーーをどうマネージしていくかということなのですよね。だから「質的管理」のほうがきっといいのだろうと思います。そうした「研究全体の質」をあげていった結果としてよい論文が生まれ得るのでしょう。
「研究全体の質」をあげていくにはどうしたらいいのか、というと、外的な基準では対応しきれないものが質的研究にはある。そこで自分の中での基準としての内的基準を設け、グラウンテッド・現場に根差して、マネージメントしていく必要があるのでしょう。
そして、量的研究が悪い、というわけではないんです。よい研究もたくさんあるし、自省的に取り組まれてきたものも多い。ただ、「調査者が相当頑張って質的管理をしないといけない」ということに自覚的で、自省的に取り組むことがより明示的な方法論が質的研究ということはいえるのかなあと思います。
「一般化」については、まさにそれが質的研究の弱点として指摘されていることではありますよね。ただ、その「一般化」について量的研究は無自覚に、安易に、「日本社会」について論じてしまいがちです。本当に日本を代表している結果として論じているのか、は問われる必要があります。そういう意味で、取り上げている事例や分析対象が「一般化できない」とそもそも批判されることがある質的研究は、その指摘をどう受け止め、コントロールすべきか考えるところから始まるので、アドバンテージがあり得るのかもしれないのです。
質的研究の質を担保するために指摘されていることは、おそらくどの研究においても求められるようなことです。そして、万能な基準というものも存在しません。そもそも、基準を守ればよい研究ができるわけでもないのです。そのことに自覚的になって、内的基準をしっかり持っていくことが重要なのかもしれません。
質的研究は、自らの「質」に懐疑的であるがゆえ、その結果を提示し、読者に共有してもらえるように多くのステップを丁寧に踏んでいかねばなりません。求められることは多いですが、その分、すべての要件を満たしたときに研究が持つ説得力は大きなものになるように思います。
第十講| 第30章 質的研究を書く/第4章 質的研究の倫理
当日資料はこちら
当日リポート
いよいよ最終回となりましたが、今回の講読会で議論されていったのは、質的研究を実践していくうえでの倫理にかかわることでした。
議論は、主に第30章の「質的研究を書く」で取り上げられた《書くことの正当化》の内容確認から始まりました。この《書くことの正当化》とはいったいどういうことなのでしょうか。
私たちが調査をしたり、研究をして、その結果を記述していくことになりますが、それを「書く」ことの意味はどこにあるのでしょうか。
おそらく、「それが正しいと認めてほしい」と思って書いているのです。その意味では、「書く」ということは、そのまま「正当化の機能」なのです。そして、同時に自分の考えや主張を書いていくことになるので、おおよそ中立的にはなり得ないのです。どんなに気を付けていても、こじつけ的な正当化からは逃れ得ない。
こうした限界や課題はこれまでも多く議論されてきたといいます。例えば、人類学においては、「固有性と全体性」という観点から課題が提起されていました。記述したある事柄が、全体を説明したことになるのだろうか、といった問題提起です。また、「書くことのポリティクス」もこれまでに挙げられてきた論点として挙げられていました。
そうした限界はありながらも、そうはいっても、「書く」こと抜きには始まりません。
「書く」という行為は罪深いものである。でも「書かない」というわけにはいかないのです。だからこそ、いかに、自覚的にコントロールしながら書くのか、が問われてきます。《書くことの再帰的機能》についても議論がされましたが、このこともまた、自己反省・自省のプロセスを通じて、質的研究の精度を上げていく、ということにほかならないのだろうと思います。
そもそも、こうして「自省」を重ねながらアウトプットされていく/書かれることを目指すのは、なぜなのでしょうか。そこまでして「正当化」して書くことを目指す理由は何なのか。
研究の倫理を考えていくうえで最も重要なことは、この「正当化」は、<アカデミックな成果を得るため>になされるのではなく、<学術に貢献するため>に、ただそのためだけに、なされるべきだということだったのかもしれません。
労力をかけて、限られた資源を用いて、なされる研究というのは、その結果として得られるものが、社会にとっても、歴史的な文脈においても、「求められる」ことでなくてはならない。
意味のない研究をすることも倫理的な問題としてフリックに指摘されていたとおり、私たちは<何のために研究をし、資源を使い、強調しながら記述していくのか>を自省的に捉えていくことを常に求められているのかもしれません。
現実には、生活をしていかなくてはならなくて、すべてを、研究に捧げることはできないかもしれません。
ですが、「ノルマを果たす」ことと「顧客の満足を得る」ことの両方の目的がかなうポイントを探るのと同じように、私たちも「書き手」や「調査者」としての責任を社会に対して負いながら、そうした研究活動を継続していくことができるようなポイントを探っていく必要があるのかもしれません。
何に対して責任を果たすのか、何のために、このように書かれることが求められるのか、ということを常にみずからに問いながら、対象やテーマに対峙することが、結果として質的研究の質を保ち、倫理を果たしていくことにもなるのかもしれません。
と、7回目の講読会も無事に終えました。ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
次回は、ミシェル・フーコーの講義録『ミシェル・フーコー講義集成〈11〉主体の解釈学 (コレージュ・ド・フランス講義1981-82)』(2004, 筑摩書房)を取り扱っていきたいと考えています。
ぜひ奮ってご参加くださいね!
参加者の皆さんからのコメント