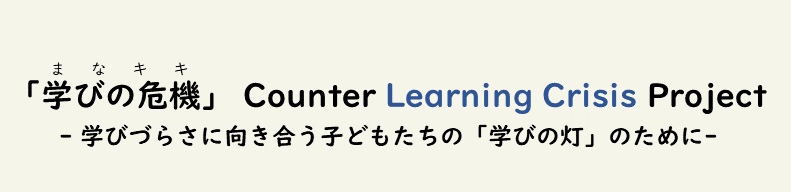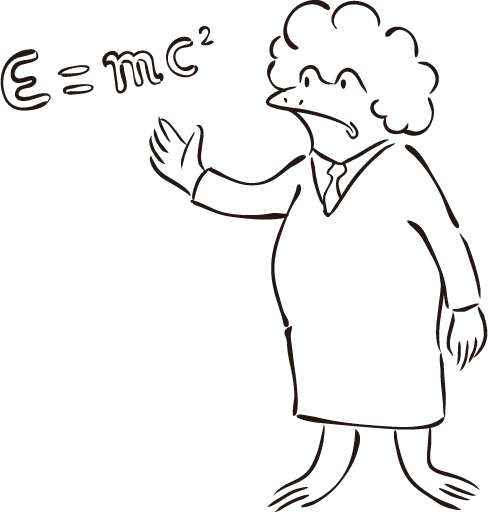▶ を押すと文が増えます
上記目次で該当項目をクリックしていただけますと、希望される講読内容ページに簡単に移動できますのでご活用ください。
新型コロナウィルスの危機からの再起が遅れ、“愁い”と“畏れ”に覆われつつある時代。
今こそ必要なのは、周りに左右されず「自分で考える力」を養う学問・科学なのではないか。
私たちにとっての学問の、科学の重要性と必要性を、もう一度考え、それを身につけるための好書を購読します!
「学びの危機」に抗うきっかけづくりのために、一緒に読んでみませんか?
(どなたでもご参加いただけます!)
講読会フライヤーPDFはこちら
オンライン講読会スペシャルのお知らせ
スペシャル回フライヤーはこちら
第五講 2020年10月27日 討議:大学の”危機”を考える―第6章「科学の制度化」から―
17:30-18:30 テキスト6章講読
18:30-19:30 パネルディスカッション
パネリスト:服部 哲さん(駒澤大学)、柴田 邦臣さん(津田塾大学)
「科学哲学への招待」第6章は、「科学の制度化」として、大学が科学・学問の場として成立してきた過程をテーマにしています。その時代から約800年、2020年のCOVID-19 Crisisは、大学のあり方にも大きな影響を与え、その社会的価値、ひいては存立基盤を問うところまで来ています。講読会後半で、情報教育にお詳しい服部先生をお招きし、大学の“危機”と役割について、皆さんと一緒に考えたいと思います。
第十二講 2020年12月22日 討議:”危機”下の学問―2020年を振り返る 補章「3・11以後の科学技術と人間」から
17:30-18:30 テキスト補章講読
18:30-19:30 パネルディスカッション
パネリスト:松本 早野香さん(大妻女子大学)、柴田 邦臣さん(津田塾大学)
まなキキ講読会、2020年の最終回は、「クリスマス・スペシャル版」として「科学哲学への招待」補講:「3.11以後の科学技術と人間」を購読します。科学技術と現代社会を論じる本章の購読を入り口に、後半では、“危機の時代”の情報技術と、学問・科学のあり方をディスカッションしたいと思います。パネリストとして、東日本大震災における災害情報支援を専門とする松本先生をお迎えし、Learning Crisis研代表の柴田をあわせ、皆さんと議論していきます。
講読書籍
『科学哲学への招待』, 野家啓一著, ちくま学芸文庫(2015年)
講読期間
2020年9月29日(火)~2021年1月26日(火) 全15回
開催時間
18:00-19:30ごろ(入退室自由)
参加方法
Google Formを通じてご参加いただけます。
(1回のみのご参加でも、お申込みいただけます。)
ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りさせていただきます。
第一講| 第一章 「科学」という言葉 2020年9月29日
担当:M先生
当日資料はこちら
当日リポート
「科学」ってそもそも何なのか―よく読んでみると20頁には、「すなわち『信念(belief)」や「意見(opinion)」に対する「知識(knoledge)」の意味である。」とあります。
この、「信念」や「意見」とは区別して捉えることが「科学」とされたことが、まさに革命的なことで分水嶺ともいえるような出来事だったのかも…という議論が展開。
でも、私たちが卒業論文や研究をしようとするときの「仮説」のもとにあるのは、意見だったりするのでは??という意見も出されます。
「意見」や「信念」と「知識」の何が違うのか―。実は主体となるものが「個人」であるか「集団」であるか、の違いに依るのかも、と柴田先生より一言。可算名詞としての「opinion」と不可算名詞としての「science」。ひとりひとりにとって固有なものとしての「意見」ではなく、皆にとっての普遍性のある「知識」を確立していく…ということこそ、ヨーロッパの科学革命で繰り広げられたことだったのかもしれません。
今後につながりそうな論点 -当日あげられた質問から
科学技術と社会の密接な関係について
私は以前「科学技術と社会が密接に関係したがゆえに、社会に貢献する研究のみが重視され、その結果、大戦中に軍需産業が発展し、たくさんの人が亡くなったため、科学を役に立つか否かで定義するべきではない」というような内容の文章を読んだことがあります。これに関連して、科学技術と社会が関係することに関するメリットやデメリットとして何がありますか。
アマチュアから専門の「科学者」が登場したというところに興味があります。
科学は、王様や聖職者の権威によらず、だれもが確かめうる方法によって、論じることができる。そういう意味ではとても「民主的」な手段だと思うのです。でも一方で、科学者という専門家の力が行き過ぎてしまうと、それも一つの権威になってしまう。どうしたら、科学は、イリイチの言うような、手の届く道具になるのでしょうね?近代以前には、民衆にとっては「科学」的な営みというのはあったのでしょうか?
参加者のみなさんの感想(一部)
レジュメから得たなるほどは勿論たくさんありましたが、参加者の方からの質問に対するなるほども多くあったのが面白かったです。「こういう発想や疑問点・着眼点もあるのね」と感じる一方で、その疑問に対するさらに面白い答えが返ってきていたのが、講読会ならではの雰囲気だったと思いました。
科学という言葉を普段から頻繁に聞いたり使ったりするが、こうやって改めて科学という言葉の意味を考えたことがなかったので、難しかったです。意見はひとりひとり持っているものであり、知識はみんなに共有されている普遍的なものとすると、どのようなものが知識にあてはまるのだろうと考えさせられました。
科学は民主的という話に関連しての感想です。コロナ渦において、21世紀とは思えないような非科学的な情報がたくさん出回りました。これまで、それは発信側のみの問題だと思っていましたが、科学が人々から離れすぎたところに存在していることも要因なのではないかと思いました。科学が人々から離れ、その信用を失っていることも、コロナの混乱を加速しているように思います。
個人的には「実学」という言葉、「役に立つものであるか」というお話が印象に残りました。文系のような学問も「実学」なのではないでしょうか。確かに、世間では科学のような理系の学問のみが「実学」と見なされ、「役に立つもの」であると思われています。ですが、個人的な話になりますが、私は文系の分野の講義を受けて、楽しいと感じます。文系の講義で学んだ考えが、物事を判断する際に生かされていると感じることがあります。それらのことは「役に立つ」といえるのではないかと思うのです。「科学とは何か」というテーマとずれていると思いますが、「実学」とは、「役に立つ」とはどういうことかについて考えさせられました。物質的であっても、精神的であっても、「豊かにしてくれるもの」であることはどちらにも共通しているのではないでしょうか。

「役に立つ」かどうか、という問いは物事の観点を問うことにもつながるのかもしれません。
なんとなく「科学」というと「役に立たない」という印象も持ってしまうこともあるかもしれませんが、この『科学哲学への招待』では、役に立つとはどういうことか、どのようにものごとを考えていけるかも問うているのではないかと思います。
私たちが最近よく使う「実学」とは少し意味が異なるものとして、論理がどう導かれるのか、一緒に確認していけたら、と思います。
第二講| 第二章 アリストテレス的自然観
担当:K原さん
当日資料はこちら
当日リポート
「アリストテレス的自然観とは結局何なのか?」という疑問から始まった今日の講読会。
この章では、「アリストテレス的自然観」として説明されるひとつの「見方」が紹介されていたのだろう、と議論が進みます。
いわゆる常識、日常感覚として認められ構築された「セントラル・ドグマ」がまさにそれで、古代天文学や古代運動論がどのように理解されてきたのかを振り返ると、それが日常的な感覚から”しっくり”くるものであったから、ドグマとして確立し得たことが分かります。
ですが、セントラル・ドグマでは説明できないような変則事例が増えていくことで、日常感覚の誤りが否定されていった―例えば天動説がコペルニクスの地動説にとって代わるなど―のです。
この、日常感覚では違和感のない”常識”に対し、観察を通じてその「変則性」を指摘し、論理的な筋道をたどってセントラル・ドグマを否定するに至ったということは、実はなかなかできないことなのではないか、と盛り上がりました。強い自己否定も伴いながら論理的帰結を目指す知的勇気は、「ロマンチック!」というところで、今日の議論を終えたのでした。
これからの章も、そのロマンチック冒険譚として科学哲学の変遷を楽しく読み進めていけたらよいですよね!
参加者のみなさんの感想(一部)
自分は地動説が当たり前として過ごしてきたので日常や常識から逸脱することの難しさを感じました。日常を科学に変える力、またそれをひっくり返す自己否定力が科学には必要なのだと感じました。
科学の話から違和感を感じる自分など「自分」についての話にまで及ぶとは思いませんでした。とても面白かったです。
私たちは日常感覚や見かけで”当然だ”と思い込んでいることがあって、それを理論で説明しようとしがちです。しかしそれは科学(science)ではないのだということをアリストテレス的自然観を通して体感できました。そう考えると今まで自分が大学で書いてきたレポート課題は全く論理的ではなかったです。「説明できる」ということが論理ではなく、その根本を検証することが重要であり、そのためには自分の感覚を疑うことから始めるべきなのかもしれないなと思いました。
私たちが現在当たり前だと感じている自然現象の原因は、こうした仮説と実証の繰り返しのもとで確立されたものであり、科学の確立はものすごいエネルギーと時間がかけられるものだと思いました。また、天動説のセントラル・ドグマから逸脱する変則事象から、地動説へと繋がっていく話を聞いたときに浮かんだのが、数学にあった「証明」の問題です。ある事柄を証明するために、自分がこうなるだろうと思う結論の逆を仮定に立てて、否定することで結論を導き出すような問題があったなと思いました。科学の話はもっと壮大なものではありますが、コメントでもあったようにアリストテレス的自然観から逸脱する仮説を立てることがとても難しいものであったと感じるとともに、日常の当たり前を説明することの難しさも感じました。
「科学」や「学問」と聞くと、「真理を探究する」というイメージがあったのですが、「セントラル・ドグマからはずれないように物事を説明しようとする」ということは、それとは逆の行為ではないかと思いました。感覚的・感情的な意見になってしまいますが、「セントラル・ドグマ」という、「真実だと思われている」仮説を無理やり「真実」にしようとしている感じを受けたからです。ただし、「正しいものはない」と言ってしまえば、「自分が納得できればいいのだ」ということになる可能性もあり、今日のお話にもあったように、あらゆることをこじつけて説明することもできてしまいます。それこそ、トンデモ科学が成り立つような世界となり、現実を歪めるようになってしまうでしょう。「これこそが絶対的である」と言っても、「絶対的なものは存在しない」と言っても、どちらの場合も問題が発生するのではないかと思います。素人の意見であり、一般論的な考えとなってしまいますが、「真実は確かにあるけれど、それが作られたものであるという可能性もある。なんでも疑えばいいというわけではないが、疑いを持つことも大切である」ということでしょうか。
今回初めて参加させていただきました。結構難しい話だなと感じました。発表後の皆さんの話で感じたことは、説が出て、その説の欠点を見つけ、次の説へと研究していたと聞くと大変だなと感じましたが、とても大切なことなのではと思いました。このコロナ下で5月までに収束する、今年中には収束するとだんだんと話が変わっていきました。コロナに対しての各国の対策、考えの共有を行い、その考えに欠点はないのかなど考えることが大切であると感じました。変則現象を見つけることさえ、今のコロナ化ではできていないように思いました。
セントラルドグマの意味が前提の前提、感覚的な正しさであるならば、(天動説があったという記録が残っているので、現在の私たちのセントラルドグマと言っていいかは分かりませんが)現在の私たちのセントラルドグマ(仮)は、例えば地動説ですが、それは昔のオリジナルのセントラルドグマの天動説に反した変則事例が積み重なってきたものであるということを改めて考えさせられました。私たちは今COVID-19が出現した未曾有の出来事に直面していて、まさにセントラルドグマの変則事例であると言えると思います。つまり私たちは今、セントラルドグマから逸脱した冒険を体験しているのではないか?そのように考えると購読会の中でもワードがあったようにロマンがあるなと思いました。

「なんだかいろいろなことが言えそう」「自分が納得する考え方はこう」「いろいろ考え方があってよい」とかそういうことではなく、
それでも絶対に言えることがある、ということをみていくのが科学であり、科学の魅力なのだろうなあ、と思いますね。
第三講| 第三章 科学革命(Ⅰ), 第四章 科学革命(Ⅱ)
担当:H松さん、M先生
当日資料:第三章はこちら、第四章はこちら
当日リポート
第三章と第四章の2章分にチャレンジした今日。
コペルニクスやガリレオ・ガリレイ、ニュートンが提示した具体的な話にフォローしようとすると、難しいところもあったかもしれませんが、大事だったことは何かというと、
1.全員に共通して見られたのが「論理的一貫性」であったということ
2.さらに「実験精神」が備わって、セントラルドグマが乗り越えられた、ということ
だったのだろう、と議論は展開していきました。
論証精神の宿ったギリシア哲学がアラビア世界にわたり、アラビア世界由来の実験精神が組み合わされた形で知識がヨーロッパに逆輸入されることで、ルネサンス―近代科学が確立していく母胎が生まれた、という話がありました。ここからは、「科学革命はなぜ、アラビア世界ではなくヨーロッパから起きたのか」という質問も飛び出します。
おそらく、活版印刷技術など含め批判的に議論していくことを可能にする条件が偶然整っていた、ということもあるだろうが、もしかしたらヨーロッパにおける批判精神などといった文化的な条件も影響していたのかも…といった仮説も話題に上がったりしました。
ガリレオ・ガリレイにしても、ニュートンにしても「信じがたいものであれ、説明することができる」ということを、まさに「論理的一貫性」と「観測/実験・実証的検討を通じてのエビデンス」を通じて指摘してきていました。これが、本当に革新的なことだったのですね。
もしかしたら、生活知として共有されてきた理解もあったかもしれませんが、この生活知に対して妥当性のある説明をしていく―そのことが科学の試みであったのでしょうし、それがメインストリームとして花開いたのがたまたまヨーロッパであった、ということも大変興味深いことでした。
「科学は偶然を語らない。でも科学は偶然に生まれる」という柴田先生の言葉も印象的でしたが、サイエンスの重要要素として、論証精神と実験精神が鍵となりそうだ、ということをみなさんと確認することができたと思います。コペルニクスやガリレイ、ニュートンを部分的に学ぶだけだと、単なる偉人の業績としてインプットされてしまいがちですが、科学史として学んでいくことで、紆余曲折や葛藤や彼らの挑戦、勇気を垣間見れるようにも感じます。そのことが、私たちの「学び」を支えることにつながっていくのかもしれませんね。
参加者のみなさんの感想(一部)
現在、科学は基本的で不可欠なものとして存在しているけれど、人々に当たり前の知識として共有されている法則だったり偉人の名前やその考え方の誕生の裏側みたいなものを、この2つの章から学ぶことができました。
まず、前提となる法則を発見することができる凄さに改めて気づくとともに、繰り返し行われた批判が新しい法則や考え方のきっかけになっているのだなと思いました。また今よりもずっと昔のことなのに、アラビア世界やヨーロッパで明らかにされたことが今の科学の根底にあるということに、世界史の教科書で表面的に学んだ時にはあまり理解することができなかった凄さを感じることができました。
自分は文系なので途中全くわからないタイムがありましたが、実は少し興味のある宇宙の話の時は、思わず前のめりになって聞いてしまいました。重力との大きさとかはもちろん気になりますし、そもそもなんでそんなに都合の良い(ものを置けたり、速度を変えて人が進むことができる点など)仕組み・原理が在るのか、すごくすごく気になります。今日はそういうところに触れていたので、より楽しむことができました。ありがとうございました。
サイエンスが論証精神と実験精神が合わさってできたという話から、科学は嘘つきや忖度をする人にはできないと思いました。よく考えると、ガリレイも宗教裁判にかけられたりと、やはり権力側からは疎まれていたわけで、たとえ論理やデータが都合の悪いものであったとしてもそれらに対して誠実でないといけないのだなと感じました。そこが「ロマン」のあるところでもあるのだと思います。授業で科学史を扱う時に、法則だけではなくてそうしたダイナミックな視点を伝えられたら、生徒にももっと興味をもってもらえたかな、と反省しました。
ヨーロッパでルネッサンスが起こった主因の一つに「批判精神」があるとのご回答に、眼から鱗が落ちました。ギリシャ文明がペルシャとの相克を通して発展した様に、異文化・他者からの批判とせめぎ合いによって、文明の発展はある様に思われます。そこに包括的なダイバーシティの重要性がある訳です。
アリストテレス的自然観が常識の時代に、地動説を唱えるコペルニクスの勇気は相当だったでしょう。尤も教会はこの異論を受け入れたとされており、社会の包容力と命懸けで追求する科学者の信念と勇気が、社会・文明を発展に導いたと考えられます。
逆に批判・異論を排除する社会・文明に、発展は望むべくもありません。もし国が(科)学者を選別するならば、自縄自縛になりかねません。忖度社会の御用学問からは、コペルニクスは元よりガリレオもニュートンも輩出できなかったでしょう。図らずも科学史は前半の「科学革命」で、さらりと教えてくれている気がします。

本当に科学の発見が文化史の一部にせずに学んでいくと、より多くの学びが得られるような気がしますね。
また、文系の学問の強みは、ひとつひとつを型にあてはめることなく論じていくことにあるようにも思います。
コペルニクスが自身の仮説を述べ、しっかりと議論していくことができた、という姿からは学問というもののありようを本当に考えさせられますね。学問とは、しっかり考えて常に前提を壊していくようなものなのだと思います。そういう意味では反権力的なものだとさえいえるようにも思うのです。それが達成されるためには、相当程度の自由と発想力も保障されている必要があります。よく学問は「象牙の塔」などと批判されることもありますが、実は中身はとてもラディカルで、オーソドックスへのカウンターであってほしいし、そうあろうとしているようにも思います。考えること、学ぶことの自由は、本当に大切なテーマ。しっかり考えていきたいですね。
第四講| 第五章 科学革命(Ⅲ)
担当:Sさん
当日資料はこちら
当日リポート
第5章では、アリストテレス的自然観がコペルニクス、ガリレイ、ニュートンによって転換させられた後、その背景にあり且つ近代科学の成立を促すこととなった考え方―自然観の根本的転回について触れられています。それがガリレオの「一次性質」と「二次性質」の区別によっても先鞭をつけられ、デカルトによって発展させられた「物心二元論」の考え方。
デカルトのすごいところは、究極の命題を求めた、というところにあるかもしれない、と議論は展開します。「方法論的懐疑」と呼ばれるようなデカルトの手法は、少しでも疑う余地のあるものは前提/命題とせず、どこから思考を展開していけるのかをとことん突き詰めて迫ったものでした。たどり着いたのが「『疑っている』という思惟は疑いようがない」という一つの事実です。そこから【疑う主体】―「思惟実体」を見出します。
その後、疑う「私」の外部の存在の証明に取り掛かったデカルトは、神の存在証明を行います。「神様は万能」=「神様は存在する」。しかし疑う「私」は神ではない。ということは、「疑う」私の外部が存在する!、という理解です。
感じたり思ったりすることは、人によって異なり一様ではないですが、私の外部にあって量的に把握できるものは、まぎれもない客観的な事実。この「絶対にある」ということをデカルトは証明することで、その後の科学的思考の発展を支える礎を築いたともいえるかもしれません。
当日は、物質一元論などの議論までは展開することができませんでしたが、次回、もし可能だったら少し考えられたりするといいな‥‥とひっそり思う中の人でした。
参加者のみなさんの感想(一部)
デカルトの方法的懐疑で、自分が疑っているということは疑えないという考えが深いなと思いました。また、考えれば考えるほど分からなくなっていきました。そして、物の存在について全員疑わないとは限らないが、量については全員疑わないことが不思議だなと思いました。
自分が見ているものが正しいと思いがちだけど、実はそれは違うかもしれない、ただ私がそう疑っているという状態は間違いない事実である、という考えを今回の講読会で知りました。ただ、実際にそう考えてみると頭の中で堂々巡りが始まってしまいそうになりました。また、神というのは科学とは正反対にいる存在だと思っていたので、神が登場してきたのは興味深かったです。物事をどう捉えたり考えるかの土台が形成されていく過程が面白いと感じました。
皆さんの議論を聞いていて難しいな、と思う場面はいくつかあったのですが、神の存在の証明に関するところはとてもわかりやすく、面白く聞かせていただきました。ありがとうございました。
二元論を考えるプロセスとして、これまで確実と見なされてきた感覚的経験や数学の定理等のあらゆる知識を疑い、否定する、というものがありました。もし、この考え方が提唱されなかったら、現代のあらゆる研究がなされることはなかっただろうと思います。何かを研究するということは、その研究目的に対して否定的な目を持つことは大変重要なことですし、そうでなければ、新たな研究や発見は決してなかっただろうとレジュメを見ていて思いました。
デカルト本人でさえも説明できなかった、「心身問題」の話が印象に残りました。確かに、精神と身体が独立した存在であるのなら、相互に影響を受けることはないはずです。ですが、私たちの身体は日々、ストレスなど精神の影響を受けていますし、身体にダメージを受けたら精神が弱ってしまうことは頻繁にあります。精神と身体がつながっていることは、否定できないと思います。個人的な意見になってしまいますが、精神と身体は二つで一つの存在なのではないでしょうか。完全に同じではないけれど、つながり影響を受け合ってはいる。精神と身体の二つがそろっていなければ、「私」ではないような気がします。ですが、お話でもあったように、精神のみでも「私」は成り立つのかもしれません。身体と精神のどちらが「私」にとってより重要なのかと聞かれたら、「精神」と答えると思います。「身体」という要素が大事なのか、「精神」という要素が重大なのか、個人によって違う気がします。

デカルトはさまざまなものを疑っていった、とありましたが、逆に言えば、「疑いようのないもの」をひとつひとつ確認していった、ともいえます。その中の一つが量的に示すことができるものだったのですね。度量衡の統一が世界史的にも大きなインパクトを持った出来事であったことは、みなさんも学んだことがあったのではないでしょうか。
また、神様というのは”普遍性”を示す象徴的なものでもあったのですね。信じるかどうか、といった議論というよりも、そうした概念を使って論じていったことが特徴的です。
この「疑う」姿勢…よく批判的に物事をみる、などといったことが聞かれますが、これは決してネガティブな評価をすることを意味しているわけではないですよね。「確実に言えるライン」を形成する、ということでもあるわけです。この批判的精神があったから科学が確立し成立してきたともいえるでしょう。
精神と身体に関してですが、これらを分けて考えるようになったのは、この科学革命黎明期が初めてだった、ともいえるわけです。それまで同一のものと思われていたものを切り離して考えていく過程で「知性」が生まれてきた。最近では、改めて身体と精神が相互に作用しあっている、という捉え方が回帰してきているわけですが、科学がどういう経緯で展開し、何を築き上げてきたのか、大切なものの見方とは一体どのようなものだったのか、COVID-19の感染拡大の影響を受ける今だからこそ、見極めていきたいと思いますよね。
第五講| 第六章 科学の制度化
担当:N川さん
当日資料はこちら
当日リポート
五章までで近代科学の成立についてさまざまな「科学者」たちの試行錯誤を見てきましたが、この変遷を「科学の制度化」という観点から見てみようとするのが六章の概要でした。
アリストテレスの時代、「スコラ哲学」とも言われるような学問は、快楽のためでも実生活のためでもない知識であり、余暇のひとつとして持たれるような種類のものでした。今でこそ、学問とは「役に立つ」ものでなければ‥‥といった議論があることを考えると、違和感があるよね、などという話も出されたりします。
やがて、ルネサンスがもたらした科学革命の胎動は、「大学」の出現にも影響をもたらすわけですが、この「大学―university」は普遍性とか宇宙とかを意味しているのではなく、「一つの目的に向かう共同体」、「学生と教師の共同体」という意味であった、というところにハッと思い至った、という意見も聞かれました。ここではこれまで全く重視されてこなかった「役に立つ」ような知識や技術そのものを考える対象にしていった、ということが、大学が果たした役割であり、「科学者」が職業としての科学者たりえるきっかけをもたらしたのですね。ただし、それが「制度化」していく過程で、「学んだ気になってしまう」という弊害ももたらされた、ということも議論されます。
当日はそのまま駒澤大学の服部哲先生をお招きした討議へ。この2020年度の大学がたどった経緯を改めて振り返る機会を持ちました。この講読会。実は津田塾大学に限らず、他にも多くの大学から学生の皆さんが参加してくださっています。皆さんの思いや感想、疑問や実情などもQ&Aやチャットでお寄せいただきました。野家先生がおっしゃるそもそもの大学のありよう、を考えてみると、今私たちがここで主体的に選び取り実践していこうとする「学び」はどのような形をしているものなのか―一つの視座を与えられるような気持ちになります。「消費」されるのではない「学び」とはどのようなものでしょうか。ときどきさみしかったり悲しいけれど、強いられるものではないようにしたい、と励まされるところもあるね、という形で、スペシャル回を終えたのでした。
ではどんなふうに…??というのが二部以降。ここからも楽しみですね!
参加者のみなさんの感想(一部)
すみません、スペシャル回だったのでちょっと多めにご紹介させてください!
私は今まで、科学というもの自体を考えることはあまりありませんでした。ですが、今回の講演会でそれらが学問として発展してきた流れやその過程で成立した大学の歴史について学んでとても面白かったです。また、役に立つ学び、役に立たない学びについても最後の方で議論していらっしゃったのを聞いていて、私の今までの学びについて振り返ってみて、「この科目、絶対将来使わないし」などとぶつぶついっていた時期があって、なんだか痛いところを突かれているな、と思いながら聞いていました(笑)
初期の大学では「自由学芸」がスタートであり、「機械技術」が初期ではネガティブなイメージをもたれていたことは驚きでした。現在は理系(機械技術の分野)が重視されていますが、その流れは始めの時代から続くものであると思っていたからです。階級が要因であるとはいえ、機械技術が下と考えられる時代(短いとはいえ)は想像しづらいです。裏を返せば、階級や地位は学問のイメージに強く影響を与えているのだと思いました。
今回の講読会で大学の原点は学生と教師の共同体であったということや近代以降学問が制度化されてきたことを知り、私自身が今大学で学んでいる状況と大学での理想的な学び方について考えるきっかけになりました。また現在の大学はどのような変遷をたどってきたのかを知ることで本来の大学の目的が分かり、今までの自分の学びへの姿勢に喝を入れられた気分でした。オンライン授業で不便な部分もありますが、それでも主体的に自分からできることを学んでいく姿勢や分からないことをすぐに人に聞くのではなく自分の頭でじっくり考えることを大切にしたいと思いました。
教育の制度化、について理解できたようなできていないような。難しかったです。制度化された中で、学んだ気になっていた、というところがその通りだなと思っています。コロナ禍(この言い方してすみません)オンライン授業の中で、一体何が身についたのであろうか、と考えて、何もできていないかも知れない自分を感じて辛くなる、ということがあります。出された課題をこなすだけ、意欲のでない映像授業をみているだけ、本質的には何も残っていないのではないか、と感じてしまうことがあります。
そうならないためには、学生側の意欲はもちろんですが、環境と教える側の意欲が必要なのだろうと思いました。
(当日のチャットより)
生徒の学びたいという情熱と先生の学ばせたいという情熱(もしくはこちらも学びたいという情熱)がかみあいにくいのが今なんじゃないかなと思いました。
恐らくみんな学びたい情熱はあるはずです 今日話を聞いていて尚更思いました。
でもそれが様々な要因ですれ違ってしまっている部分が往々にある気がします。それが生徒側に要因があるのか先生側に要因があるのか、大学という組織か社会かはケースバイケースですが…
しかし学びたい情熱と学ばせたい情熱は捨てちゃいけないと思ったし、捨てたら勿体ないなと思いました。孤独のなかで心がおれて情熱を持つにも疲れてしまうけれど、それでもそれは無駄ではないと本日強く思いました。
遠隔授業になり、実技授業を受ける際、精神面での負担が大きいなと個人的には感じています。
様々な原因があったとは思いますが、機材の導入や、遠隔特有のなかなか相談できない距離感が主な原因で、友人が精神疾患を患い退学しました。
その子にとって、一番相談相手として近くに居たのが自分で、助けられなかったことが悔しいです。周りを取り囲む環境の問題だったため、いくら手を差し伸べてもどうすることもできませんでした。
オンラインになってから授業の課題形式や発表形式が変わったため、今まで以上に課題に費やす時間が増えました。
私自身も精神面が強いわけではなかったため、元から少し不安定でしたが更に精神面で悪化することが増えました。画面を見続けることで睡眠が十分に取れず、授業、課題を終わらせる時間が遅いため、画面からほとんど動かない不健康な生活を繰り返しています。
授業に集中できず、記憶する力も考える力も前より落ちてしまい、味がわからなくなったり幻覚が見えることが多くなったので、そろそろ心療内科にかかる一歩手前まで来てしまったかもしれません。
対面より負担が少なくなる人もいる中、精神的な面で負担が大きくなる人もいます。どういった対策を先生は考えますか?
オンライン授業の良い点悪い点について様々な意見が出ていましたが、私はオンライン授業をとても肯定的に考えていて、2時間半かかる通学時間も必要ないし、座学の勉強もいつも以上に積極的に学習していました。実習に関しても週一程度の作品の途中講評を教授にしてもらえたり、友達の制作過程について聞けたり、大学で学んでいた時以上に創作意欲を下げることなく制作できて、オンライン授業でよかったなと安易に思っていました。しかし、教授から講評を頂いたり、友達の意見を聞くことは大学でもできたことです。それをしなかったのは大学に通うという行為に満足していたからなのではと今日のイベントに参加して気がつくことができました。また、オンライン授業をすることで生徒の得意不得意によって差が出てしまうというお話も興味深かったです。私のようにオンライン授業が合っていたという人もいれば逆にそうではなかったという人もいて、多様な学ぶ人々が集まるからこそ発生する問題だと思いました。どうすれば多くのひとが学びやすいく、そして能動的に学べる環境を作るか考えなくてはと強く感じました。
今回の講読会で自分自身のコロナの中での学びの影響について考えてみました。私は、大学で授業を受けたことがない、実際に大学の友達に会ったことがない、すぐに授業のことを相談できる子がいないというようにネガティブことばかりが出てきてしまいます。しかし、この状態をポジティブに考えてみても良いのかもしれないと思いました。コロナの影響を受けたことで、これまで当たり前だと思っていた、友達にいつでも会えるということ、新しいことを学べるということは幸せなことだったのだと気づいたからです。このつらい状態を経験したからこそ考えられる新たな発想や見方が私たちにはできるかもしれないと思いました。その見方を生かして学んでいくことで、本に書かれているような、学ぶ人たちの集団という本来の大学の形になると思いました。
駒澤の先生の普段は聞けない意見や苦悩を聞けたので、駒澤の学生としてはより貴重な時間でした。日本の大学の授業の質は平均的に低いと言われてしまっていますが、この災禍が収束した後どのように変わっているのか、私はとても楽しみです。

それこそ、役に立つべき学問が重要と思われるような科学万能主義の時代はそこまで長い歴史を持ってきたわけではないのですよね。そうしたこともこれまでの議論で振り返ってくることができたのではないかと思います。
また、今まさに実施されているような大学での学び…遠隔教育でのリアルタイムやオンデマンドの学びは、受験対策的に用いられるようなポイントを押さえてサクサク学ぶ「スタディサプリ」的な技術が一番効力を発するようなものだったりするかもしれません…が、大学での学びとは果たしてそのような種のものであったか…というとやはりそこには「?」があるわけです。だからこそ、このような学びの状況に「危機」意識を持つ必要があるのでしょうね。
オンライン上で教師と学生の側の「情熱」を一致させようとすることも本当に難しい問題ですね。ただし、こうした危機下の中にあるからこそされる工夫や努力はおそらく新たな気づきや見直しの機会にもなっているはずです。その意味では、危機というものは乗り越えて/克服していくことで得られるものがあるのだと思うのです。「カタストロフィー」や「悲劇」などと「クライシス」は異なるはず。
この危機としっかり向き合いながら考えていくことを続けていきたいですね。