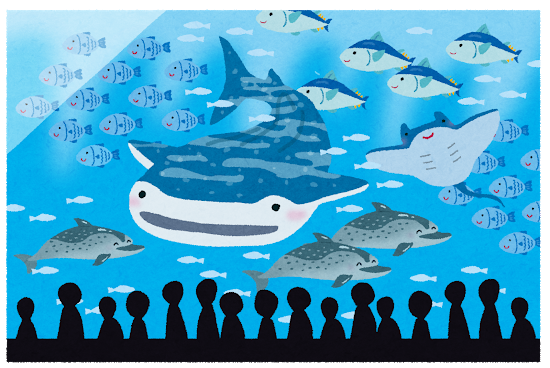▶ を押すと文が増えます
鰰 はたはた

ハタハタは北日本で多くとれる海魚。うろこがなく、腹は銀白色。
背に褐色の斑点がある。

ハタハタって、なんでハタハタっていうのでしょう?
なんだかかわいい…!
ハタハタは、雷の擬声語である古語。
現代の「ゴロゴロ」にあたる「ハタハタ」に由来するといわれています。
実は、ハタハタは秋田の郷土料理には欠かせないお魚。
(秋田の県魚にもなっています!)
そんな秋田県で雷がなる11月ごろに獲れることから、カミナリにちなんで「ハタハタ」と呼ぶのだそう。またの名を「カミナリウオ」とも。
また、冬の日本海の荒波の中を獲りにくいことから、「波多波多」とも表記されるのだそうです。
ぎせいご【擬声語】
オノマトペ。
自然界の音・声、物事の状態や動きなどを音で象徴的に表した語。
音象徴語。擬音語・擬声語・擬態語など。
ぎおんご【擬音語】
自然現象の音にまねて作った語。
例)がたぴし・こけこっこー
ぎたいご【擬態語】
物事の状態・身ぶりを、それらしく表した語。
例)にこにこ・べったり
ハタハタが登場する秋田の民謡とは、「秋田音頭」。
普段は姿を見せない魚だが、冬の食べ物が少ないときに沿岸にくることから、神様から贈られた魚と感謝されてさまざまな形で味わわれていた魚だそう。
昔は一家で4箱も5箱も買ってお味噌汁にしたり、焼き魚として食べたり、鍋物になったり毎日のように食卓にあがるお魚で、「今日もハタハタ明日もハタハタで、もう飽きた」、「道にハタハタが落ちていても猫もまたぐ」というエピソードが生まれるほどだったそうです。
いずれにしても、冬の間の貴重なたんぱく源として重宝された庶民の味。
最近は、漁獲量が減少し、「まぼろしの魚」になりつつあるようです。
おいしいいただき方
しょっつる鍋
秋田名物として名高い料理です。
魚と塩、麹などを漬けこんで、約2年間自然発酵させ、その上澄みを濾して調味料にしたものが塩汁(しょっつる)。
材料になる魚にはハタハタのほかにイワシやニシンなど。頭も内臓もすべて漬けて最後は骨だけが綺麗に残るのだとか。独特の香りがあり、旨味とともに濃く塩味も強いので、約30倍から40倍に薄めて使います。
しょっつる鍋は、ハタハタなどの白身魚と白菜、ネギ、セリ、豆腐、糸こんにゃく、キノコなどを入れた鍋料理!
リンク先では、鍋だけではなく、しょっつるを使った他のアレンジレシピが紹介されています。
鰹 かつお

かつお節・なまり節の原料として知られる海魚。
体長90センチ以上になる。
黒潮に沿って群棲。回遊する。肉は赤黒く、さしみ、たたきなどにもする。
堅魚から出た語。

黒潮、ということはあたたかい海で暮らすお魚、ということでしょうか。
カツオ、ときくとどうしても「カツオのたたき」を連想して、高知県のイメージが湧いてきます…。
まさに高知県は、黒潮が土佐湾沖を流れていることもあって、まぐろはえ縄やかつお一本釣をはじめいろいろな漁業が営まれているといいます。
かつおはまさしく土佐を代表する魚として、「県の魚」に指定されているそうです。
一本釣りとは、文字通り釣竿一本でカツオを釣り上げる釣り方のようです。
カツオの群れを発見したら、イワシなどの餌をまいて群を舟に引き寄せます。
船からは海水を勢いよく散水し、小魚がはねているように見せかけてカツオをだまし討ちするのです。
一方、まぐろはえ縄とは、幹縄という太い縄に、枝縄という釣り針をつけた縄を海に入れて魚をつる漁業だそうです。
遠洋まぐろはえ縄では、幹縄の長さは120から150㎞にもおよび、ついている針も2000~3000本になるそうです。

120~150キロとはとんでもない長さですね…!
東京からH松さんの地元の静岡までが約150キロです。
そんな距離にわたってまぐろと闘うんですね…。
そんなカツオ漁が栄えたのは江戸の繁栄とも関りが深いようです。
かつお節の登場ですね。この時代にかつお節が改良され、最高の調味料として料理方法の改善に貢献したのだそうです。
もしかしたらかつお節がカツオからできている、ということにピンとこない人もいらっしゃるかもしれませんね。
かつお節とは、三枚におろしたカツオの身をゆでていぶし、発酵・熟成させ、固く乾燥させたものです。
これを薄く削ってだしに使用するのです。
さて、そんなカツオの語源ですが…
冒頭にさらっと書いてしまったとおり、「堅し」の「カタ」に「魚」の「ウヲ」で「カタウヲ」となり、転じて「カツヲ(カツオ)」になったといわれています。
かつお節の動画を観ていただけると、その「堅さ」には納得できてしまいますよね。
でも、もともとはかつお節として味わわれることはあまりなかったため、鎌倉時代までは低級な魚として扱われていたそうです。
主に干し固めて食用とされていました。
おいしいいただき方
だしとして
かつお節は、高たんぱくでビタミンやミネラルが凝縮した食品。
かつお節からとれる「だし」には3種類があります。
①かつお一番だしは、
お吸い物やお味噌汁、茶わん蒸し、そばつゆ、うどんつゆなどに。
②かつお二番だしは、
煮物や炊き込みご飯、鍋物へ。
一番だしのだしがらの削り節を再活用してとるだしですね。
③かつおと昆布の合わせだし
煮物や鍋物へ。
リンク先のホームページからは、それぞれ三種類のだしの取り方を動画からでも確認できます!
「かつおのたたき」の”たたく”とは、皮をパリッと炙ったかつおに、塩やポン酢、薬味などをのせてから、抑えて(=たたいて)味をなじませることで、本当に包丁の腹などでパンパンとたたいたりすることなのだそう。
リンクしたホームページでは、自宅でかつおを炙る方法も紹介しています。
直火で炙る必要があるとのこと。もしも、自宅で試してみたい!という場合は必ず大人と一緒にチャレンジしてみてくださいね。
鮪 まぐろ

まぐろは、大型の遠洋性回遊魚。
形はカツオに似て、体長は1~3メートル。
背は黒灰色、腹は白色。
クロマグロまたはホンマグロとも言い、刺身用など。

マグロもファンが多いお魚ですよね。
お魚の話題といえばやはりおさかな君。おさかな君もマグロについての動画を挙げているようなので、見てみましょう。
サバなどとも同様にマグロも赤身魚。筋肉が発達しているお魚です。
特にマグロは餌の乏しい外洋を回遊することが多いため、餌を捕まえるために高速で泳ぐ能力が備わっているようです。
おさかな君も、背びれや腹びれを普段はたたんで泳いでいると話していましたが、それは水の抵抗を少なくするための完全紡錘形の形をとるため。最高で時速160キロで泳ぐともいわれているそうです。
そんな筋肉の発達しているマグロですが、実はえらを動かすための筋肉はないそうなのです。
マグロは泳ぐのを止めると死んでしまう、というのは、口をあけてエラを通過していく酸素を取り入れる方法で呼吸をしているからなのだそうです。
そんなマグロの語源とは…?
おさかなくんも「まんまるお目目」と表現していましたが、目が黒いことが由来となって「眼黒」となった、という説が一つあるそうです。
もう一つは、背が黒く海を泳ぐ姿が真っ黒な小山にみえることから「真黒」となったという説があるとのこと。
一方、漢字では魚へんに「有」と書いて「鮪」と読みます。
この「有」という語は「外側を囲む」という意味を持つのだそうで、大きく外枠を描くように回遊する魚、というところに由来しているといわれていうようです。

マグロといえば、呼び方もいろいろありますよね。
トロとかツナとか…!
まず、ツナは、マグロ族の魚のことを総称する英語です。
tuna
a large sea fish that is used for food: fishing for tuna
マグロ族の中にはカツオも含まれてくるので、いわゆるツナ缶は、マグロの缶詰とは言い難いようです。
そして、「中トロ」「大トロ」などの呼び名はマグロの部位を示しています。
ちょうど、マグロの背中にあたる部分が中トロ。
魚の身の中央部にあたるのが「赤身」です。
そしてお腹の部分が「大トロ」と呼ばれる部分です。脂が多く乗っているところが高級とされる部位なのですね。
マグロがどれだけ大きいお魚で、余すところなくおいしく味わわれてきたものなのか、ということがうかがえますね。
同じお魚でも、こうやってたくさん名前がつけられるということそのものが、日本人のマグロ愛のようなものを物語っているようにも感じられますね。
おいしいいただき方
なんとなく、やっぱりお刺身でいただくのが一番美味しいような気がするのですが、マグロのレシピを眺めていて「…おいしそう‥‥!」と思ったものをご紹介します…!
よかったら写真や文章で味わってみてください。笑。

食欲の秋…!
もりもりご飯を食べて、体調など崩さないように頑張っていきましょう!