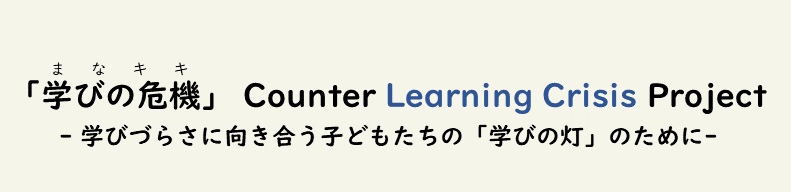▶ を押すと文が増えます
- 第一講| 一九七六年一月七日「従属化された知」他 /2021年5月25日
- 第二講| 一九七六年一月十四日「戦争と権力」他 /2021年6月1日
- 第三講| 一九七六年一月二十一日「永続戦争の言説」他 /2021年6月8日
- 第四講| 一九七六年一月二十八日「人種闘争の対抗史」他 /2021年6月15日
- 第五講| 一九七六年二月四日「ホッブズにおける戦争」他 /2021年6月22日
- 第六講| 一九七六年二月十一日「歴史の新しい主体」他 /2021年6月29日
- 第七講| 一九七六年二月十八日「戦争の諸制度」他 /2021年7月6日
- 第八講| 一九七六年二月二十五日「知の規律化」他 /2021年7月13日
- 第九講| 一九七六年三月三日「野蛮なるものの濾過」他 /2021年7月20日
- 第十講| 一九七六年三月十日「闘争の市民的背景」他 /2021年7月27日
- 第十一講| 一九七六年三月十七日「生権力の誕生」他 /2021年8月3日

…社会を覆う「コロナ禍」、遅延する「ワクチン」、長引く生徒・学生たちの「学びの危機」…。
だからこそ「社会は”防衛”されなければならない」…。では、「誰」によって?「どの」ように?
混乱し激変する今だからこそ、私たちに求められているのは、揺るがぬ思索の支柱なのではないか。
上から目線の専門家抜きで、「生権力」を自由に論じ合う、ユルく挑戦的な講読会をめざします。
「学びの危機」に抗うきっかけづくりのためにも、ぜひ、一緒に読んでみませんか?
※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
(どなたでもご参加いただけます!)
講読会フライヤーPDFはこちら
講読書籍
『社会は防衛しなければならない』, ミシェル・フーコー著, 石田英敏・小野正嗣訳、筑摩書房(2007年)
講読期間
2021年5月25日(火)~2021年8月3日(火) 全11回
開催時間
18:00-19:30ごろ(入退室自由)
参加方法
ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。
- ①一般参加会員
その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。
当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員
継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。
講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
※ 参加登録は一度のみで完了いたします。
※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。
お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加
特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。
一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。
ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。
お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!
第一講| 一九七六年一月七日「従属化された知」他 /2021年5月25日
担当:大学生Mさん
当日資料はこちら
当日リポート
講読会のタイトルのとおり、「ゆるゆる」と始まった講読会。
初回から100人以上の方に参加していただいて、ややドキドキしながらもスタートしました。
取り上げるのは、本当に現在の私たちを様々な面で思想的に牽引し続けているミシェル・フーコーの議論。特に、コレージュ・ド・フランスが一流の教員たちに課す「最新の知見を反映した講義」のフーコー版ということで、著作とはまた異なる形でフーコーの議論に触れていくこととなりました。
冒頭S先生からご説明いただいたとおり、今回取り上げる講義録は、フーコーがコレージュ・ド・フランスで教鞭を執るようになってから6年目のもの。この年の講義がまさに「生-政治」の議論の端緒となっていく、ということを受けてのセレクションとなりました。
さて、大学生Mさんに報告していただいた内容を通じて――特に、フーコーが最後に提起した「政治とはほかの手段によって継続された戦争である」(P19, l1)という言葉と、それを受けての「社会を防衛することの意味」を理解しようとするところから議論は始まります。
フロアからも「権力を行使することが戦争なのだとしたら、国家に存在する憲法や法律はどのような役割を持つのだろう?」という質問が挙げられました。
そもそも、ある種、衝撃的な「政治とはほかの手段によって継続された戦争である」という言葉は、フーコーが戦争に関する議論を実施してきたクラウゼヴィッツ(『戦争論』などを執筆)の「戦争は、他の手段によって継続された政治である」という言葉を逆転させて提起したものです。そしてその狙いは、まさに、その「権力」というものを論じようとするところにありました。
また、「ローカルな性格」とはいったい何なのだろう?という疑問もチャットで投げかけられました。フーコーは、この「ローカルな知」と位置付けたものを、「学問的知識」と戦わせていこうとするわけなのですが、ここでの「ローカル」は、権威から一番遠いものと捉えることができて、「グラスルーツ的なもの」とも解釈しうるようなもの、という説明もされました。
「学問的知識」が規定されていくことによって、”資格を剥奪された”一連の知は、それぞれの場所でバラバラにあったともいえます。フーコーは、諸々の従属化させられた知をまとめていくような試みとして「系譜学」を提起し、それが「学問的知識」に対抗していく試み――「知の回帰」と位置付けるのです(p12)。
フーコーは、「従属化させらていた知」のことを、「機能的一貫性や形式的体系化のなかに埋もれ隠されてきた歴史的諸内容」のこと、ともしています(p10, l9)。まさに、「系譜学」は「従属化した諸々の知を働かせる戦術」(p14, l5)なのだとして、その「新たな科学」を考えていくためのissueとして、「戦争」のはなしを提起したのです。
参加してくださった多くの方にとって、フーコーの「政治は戦争」という仮説が、ある種、衝撃的なものとして受け止められた背景には、まさに、これまでの「権力」論では議論されてこなかった、見えてこなかったある一つの抑圧構造を明らかにしようとするからこそであったともいえるかもしれません。
これまでの「権力」理解では、「支配における闘争」--誰かが誰かを支配する契約関係にあるものでした。ですが、「戦争」とは、我々が「防衛しようとする」ことがすなわち我々を「抑圧し、追いつめる」ある「権力」の形であるのではないか、とフーコーは議論しているようなのです……。
あっという間の90分で(本当に冒頭の冒頭で、ごにょごにょ言っていたせいかもしれません…。すみません)、時間が足りないと思わさせられるのは、さすがというか、やっぱりフーコーといったところでしょうか…(フーコーに失礼な気もする…)。
来週も楽しみにぜひご参加くださいますとうれしいです。
参加者の皆さんからのコメント
ミシェル・フーコーは昔のひとであるのに現在にも通じるところがあって、考えや理論は時代を超えるのだとわかりました。戦争とは何か、政治とは何かなど突き詰めたら簡潔に一つにはまとまらないようなことでも、今回のイベントのようにみんなで考え、議論することに意味があるのだと思いました。知の在り方とは何かという点では、今までは科学的な実証をもとにしなければ根拠を持たないと、反科学的なことは排除されてきたけれど、本当の意味で理解するには排除してはならないのではないかと思いました。ローカルな性格とは最も権力から遠いことであると学び、なるほどなと納得しました。誰かが権力を持たなければ、人や国をまとめることができないので、権力は必要不可欠だけれど、権力からはなれて生活しているひとも、権力に服従せざるを得ないひともいるのだということを頭にとどめておきたいです。だからこそ、権力を持つものは乱用せず、なるべく多くの人の幸福を考えてほしいと思います。この感想を書いていて、本当に今のコロナの時代と同じことを言っているなと感じました。国や政府という権力の下に置かれた私たち国民は、権力に従わなければいけない。緊急事態宣言、休業要請を受け入れ守らなければならない。しかし、権力を持つ者には相応の責任が伴うと思うので、給付金はどうするのかなど、しっかりと国民の声に耳を傾け、対応していくべきだと思います。
抑圧としての権力、戦争としての権力は、今のコロナ禍での行動制限についても言えると思った。海外で行動制限に対する大規模なデモもこの考えが根底にあるということなのでしょうか。
フーコーにとっての権力の主体は市民である、我々が我々を抑圧する、という話がありましたが、それについてです。今、COVID19とか緊急事態宣言とかまんぼう、ですごく息苦しい日々です。何か一つするのにも、すごく気を使うし、正体の分からない息苦しさがあります。それは、緊急事態宣言とかまんぼうとかの、所謂、政府とか県とかの権力側からのものによってか、といえば、実際それもありますが、でも違う。この息苦しさの正体は、政府によってだけでは説明しきれません。おそらく、自粛しろ、とかマスクしろ、とかマスクするなとか、とか密になってるとかなってないとか、消毒したとかしないとか、人々の色々な声全てによって作られていて、つまり、今我々を縛っている息苦しさ、は市民、もっと言えば自分の周囲の人たち、によるものかなと思いました。
今回の話はそれと似ているのかな、と思ったのですが、そんな感じなのでしょうか?
ローカルな知について、私は単純に、全員が共有しているわけではなく、一部のみで共有された限られた知と理解したのですが、間違いでしょうか。
今回のお話は中心と周縁についてのものであるように思えました。権力、科学、制度は自身を中心としそれ以外を周縁に追いやり抑圧していく性質を有しているもので、フーコーはそういった中心ー周縁といったあり方を否定し、中心のない知を確立しようとしたのではないかと考えました。権力は、それを有する者を防衛するための制度を構築し、その地位を固定化する、それが戦争の一形態としての権力の本質なのだと思いました。
戦争は抑圧が生まれることを知らずに自分のことを防衛しようとする市民によって起こるものだという考えを聞いて上流階級の人が持つ権利とは違う恐ろしさが市民が持つ権利に潜んでいるのだと思いました。
支配と被支配は対立しているものではなく、場合によっては同義なのかもしれないと考えた。つまり支配すると支配されたり、支配されると支配したりするということだが、特に後者が自分で仮説をかてておきながらもよくわからなかった。また、権力がこのように流動的であるとしたら、これは単なる支配闘争といいきれない複雑な構造をしているのだと思う。

フーコーは「知」というものには2つの種類があって、一つが時には権威的にもなりうる「学問的知識」、もう一つがそうではない「現場知」のようなものだと言っているのかもしれませんね。特に、「学問的知識」のような知は、権力の在り方とも強く結びついているのかもしれず、その代表例として「戦争」を挙げ、議論して以降としているのかもしれません。
コメントを拝読していても「権力観」というものについて考えさせられますね。「権力」とは誰かに持たれるものなのでしょうか?実はフーコーは、そうは言っていないようなのです。我々のことを考えてみると「自粛する主体」として生きています。これは「生かされている」というよりもそのような「生き方」を選んでいるのかもしれません。コロナウイルス感染症が拡大する中で、路上飲みする人たちに対して警察が取り締まっているわけではないんですよね。それを「やめさせようとする人々」がいて、そこには、権力の在り方を考えさせるヒントがあるような気がします。
また、「中心のない知」というコメントをいただきましたが、まさにフーコーはそれを目指そうとしたのかもしれません。また、「ローカルな知」が「全員共有しているわけではない」のではないか、というコメントもその通りだと思います。一部のみしか持たないがゆえに「分断」が起こってしまうのかもしれません…。
単純化しきれない複雑な構造を、まさにこのあたりを読み解いていこうとフーコーはチャレンジしているのだと思います!ということで今日も頑張っていきましょう。
第二講| 一九七六年一月十四日「戦争と権力」他 /2021年6月1日
担当:H松さん
当日資料はこちら
当日リポート
かわいい似顔絵付きのレジュメを準備してくださったH松さんの明朗な声で報告をしていただき、今日もゆるゆると始まりました(似顔絵入りは、恥ずかしいそうでwebにはアップされていません)。
議論は、なぜ「主体化=従属化」というキーワードなんだろう?という問いから始まります。なぜ「主体化」と「従属化」が=でつながるのか――、これは、個人が権力の主体にもなっていくからなのかもしれない…確かに、「人々はつねに権力の中継項でもある」(p32, l5)…とも書いてある、と話が弾みます。チャットにも「自粛警察」の権力について指摘するコメントが挙げられます。自粛警察は、本当の意味での警察=国家権力ではありません。つまり法に書かれた「主権」とも異なるものです。権力のシステムの内側にいるわけではない、司法のなかの存在でもない、私たち個人個人がとる行動が、「自粛警察」という形をとって権力を生んでいるようなのです。
そして、「自粛警察」のような行動――マスクをしていない人を咎めたり、路上飲みしている人たちに対して「いかん」と思うようなこと――は、このコロナ感染拡大下にあってよろしくないことだから、健康の問題として受け入れ難いことだから、ということで正当化されます。フーコーは、実はこのような形で「権力」が生まれてきている、と指摘しているようなのです。
こういう形で、権力が発動しているのだ、ということをフーコーはまず、指摘したかったのかもしれません。私たちは、マスクをして行動したり、アルコール消毒をしたり…「何かを守るように動く」よう「統治」されている、ともいえるのかもしれません。「みんながやらないとだめだ何かを守らないといけない」と思わせる、この統治の在り方は、従来型の統治とは全く異なるものです。そしてフーコーは、これが新しい権力:「規律型権力」と呼んだのです(いわゆるパノプティコン[ベンサムの一望監視装置を発展させたもの]など)。
フーコーは、この「規律型権力」について、法律では議論したり、対抗していくことができない、とも指摘しています。この章では、この規律権力に立ち向かっていくためには、「新しい司法、反規律的だが同時に主権の原理から解放された司法の方向にむかうべき」(p42, l10)とも触れていますが、その”新しい司法”のあり方については、簡単には明らかにはならないようです(コレージュ・ド・フランスでの講義が10年目を超えたころに、その答えと受け止められるような議論があるとか…ないとか…。頑張って読めるといいですね…!!!)
この「規律型権力」について、”異常”、”病気”、”差別”などの文脈で考えてみるとわかりやすいかもしれない、という説明もされました。この異常や病気、差別などの「排除」の動きは、法律で定められているものではありません(むしろ、その逆ですね)。でも、そういう「排除」の動きが発動している。これは、私たち、個人個人の内側のほうから発動されていることなのかもしれないのです。
「権力」がどういったルートで発動しているのかを、フーコーのテキストを通じて考えさせられた時間となったのではないでしょうか。
参加者の皆さんからのコメント
「司法システムとは、全面的に王が中心に合わされていて、最終的にはその事実およびその結果を消し去るためにこそ作られているのです。」というフーコーの指摘がとても印象的でした。現在でも、政治家が国民の税金によって捻出された国家資金を私的なことに不正使用していたことが問題になることがありますが、このようなニュースを見ると、法律を作る政治家が私たち国民は気づかない、自分たちにだけわかる抜け道を作って政治家が得をするようにしているのではないかという考えも生まれてしまいます。
H松さんのレジュメがわかりやすく整理されていて、説明も丁寧でとても理解しやすかったです。ありがとうございました。
私たちには権力は一切ないにもかかわらず正当性を持たせて他人にいわば疑似権力として自粛を押し付けている。このような問題が起こった原因はマスメディアにあるのではないだろうか。そもそもマスク警察、自粛警察などという言葉自体を作ったのはメディアであり、その存在を作り上げたのも彼らでではないのだろうか。フーコーの言説にマスメディアの話は出てこなかったが、現代社会ではマスメディアは多大な権力をもっており、このような権力の話をするにあたって彼らの存在は無視できない。
“「規範化社会」というものが現在のコロナ禍において大きく関わっているということに驚いた。
また、最後に柴田先生がおっしゃっていた、何を差別するのか、何を我々は排除しようとするのかということに私たちの「権力の行使」が関わっているということにとても興味を持った。法律上では差別や排除はいけないものであるということになっているのに、実際にはそれが完全に解決する見込みはない。これが「権力」と繋がっているということをもう少し考えて見たいと思った。”
今日もテキストが難しかったですが、違う時代を生きたフーコーの話が現代の文脈でも当てはまることが面白かったです。今まで自分が権力の中継点となっていることに気づかずに権力を使っていたことも結構あったのではないかと考えました。
H松さんの声が聞き取りやすくて、ずっと聞いていたいくらいでした。レジュメもわかりやすかったので、難しい内容でしたがなんとか議論を追うことができました。
フーコーが考える支配というのは、社会集団の内側に位置して機能する従属化の構造だということと、権力を分析するには支配戦術・技術(規律型権力)を起点とすべきだということをH松さんの見解から学んだ。そして、H松さんのレジュメ・説明にあった、新型コロナウィルスによって生まれた「マスク警察」「自粛警察」とフーコーが論じていた「規律化社会」の関連付けについて関心を持った。フーコーの論考が現在の状況に重ね合わせて考えられることにすごさを感じた。フーコーが論じたことを深く考えるほど、私たちが置かれている状況も見えてきて、「今」を考えるきっかけとなった。
「社会は防衛しなければならない」のように、内容が抽象的で理解しづらいものに関しては、H松さんが挙げてくださった「マスク警察」のような分かりやすい具体例を示すことが、非常に有効的だと改めて学ぶことができた。権力は上から下に降りてくるのではなく、私たちの行動で発せられるということが、権力の性格が弱まる末端のところ、最低のレベルのところで捉えなければならない理由の納得につながった。
初めは全く訳が分からなかったが、具体例を聞いているうちになんとなく意味が分かった。私が学んだことは規律的権力はどこにでもあると言うことであり、これは学校にもあるのではないかと考えた。校則は法的拘束力はないが、守らなくてはいけないものであり、自由を制限しているものである。しかし生徒を守るためには必要なものだと多くの人は考えている。この解釈が合っているかどうかは分からないが、規律的権力について知り、考えることができて良かった。
権力を行使できるのは国民の上に立つものだという固定観念があったので市民も権力を発しているということを聞いた時は新鮮な感じがしました。SNSが普及している現代はより規律的に発せられた権力が力を持つのかなと思いました。また市民が市民を支配しあう世界がどうやって崩壊するのか疑問に持ちました。
規律型権力の話を聞いて、コロナ禍における自粛警察、マスク警察もそうだが、SNSにおける誹謗中傷を思い出した。自分の価値観や信念に基づいて、それに合わない考えや行動を批判する。こうした規律権力により、奪われている自由を取り戻すには、どのような司法が必要なのか考えなければならないと考えた。

たくさんのコメントをありがとうございます。
最初の3人の方のコメントを拝見していると、よく理解してくださっているんだなということがわかりますね。なんとなく私たちは権力というと、権力者であったり上の方から何者かに統治されている、というようなイメージを持ってしまいがちなのですが、<権力の発動>とはそのようには考えない、そうではない権力の在り方があるのではないか、ということをフーコーは指摘しているんですよね。
個人が中継点として権力の発動に機能することもあるんだ、ということに気づいて触れてくださったコメントだと思います。
そして、私たちは何かを「守る」という闘いをしているのですね。防衛するとはつまり戦争のことなのです。私たちを、何かから守ろうとするようにさせる…それが権力なのだとフーコーは言っているようです。いわば、我々は戦に動員させられている戦争の担い手なのですね。誰もが何かを守ろうとする中で、その総体を戦争状態であったり、総動員体制などと呼べたりするようなことが起きているのかもしれません。
第三講| 一九七六年一月二十一日「永続戦争の言説」他 /2021年6月8日
当日リポート
イケメンボイスにあこがれながら、本日もゆるゆると議論がスタートしました。
今回のテキストに出てくる「哲学や法」、そして「歴史的=政治的言説」は今回取り扱っている文献の第一講の「学問的知識」や「ローカルな知」に相当しているのだろうか?など、そのあたりの確認からスタートします。
合理性を伴った「哲学や法」のようなものに対して、非合理的でありながら、ドロドロとした剥き出しの「ローカルな知」が神話(ストーリー)の力を借りながら正当性を持った真理を守ろうとしていった――ということが確認されますが、もともと「哲学や法」のようなものから「我々は社会から自分たちを守らなければならない」とされたものが、やがて、自らの内側(同じ社会の構成員のなか)に社会の敵を想定する人種主義を展開させて「社会を防衛しなければならない」という議論に至った、その展開について考えさせられます。
また、56-57頁のあたりで触れられている重要なキーワードとして「真理」という言葉も挙げられます。上述した「哲学や法」のようなものも、「歴史的=政治的言説」も、どちらもそれぞれの「真理」を持っていて、それを正当化しようとした――だからそれぞれがそれぞれの真理を守るために戦ったのだ、ということに気づかされていきます。もはや、中立的な普遍的な「真理」というものは存在しないのだ、ということをフーコーは指摘しているようだ、ということにも気づかされます。
オリンピックに関する議論もそうです。開催しようとする側にも「真理」があり、反対する側にも「真理」があります。どちらにも、双方に正当性があり、その正当性を主張しあっています。こうしたプロセスこそを、フーコーは新しい統治の形なのだと指摘しているようです。
自分が守ろうとしているものも、何もかもが誰かを傷つけたり、損なっているかもしれない「真理」でしかないのかもしれない、となったとき、どうしたらいいのでしょうか。フーコーは、安易に解決方法のようなものを提示しません。ですが、ロジカルに考え抜いていった先に、今回の「生権力」に関する指摘がされるのだと、そうした話にも至りました(私たちもじっくり考えていきたいですね、)。
また、53頁に書かれた内容を振り返ってみると、例えば6行目には「戦争、それは平和の暗号そのものである」とあります。「戦争、それこそが平和だ」なんて変な感じがしますが、私たちが「改革」を声高に叫ぶとき、実は平和だからこそ改革の必要性を叫ぶことができたのかもしれない、と気づくことができます。現在の平和を守り続けるために、改革という名の戦争が必要となるのだ、と考えると少しわかりやすくなるかもしれません。
自分のよしとするものと、他人のよしとするもの――すなわち真理と真理がぶつかり合うから「戦争」だというのですが、実はその両者は全く異なるものではない可能性についても触れられました。例として出されたのは青森の南部地方と津軽地方の争いでしたが、異なっていることよりも、共有しているもののほうが多い可能性には、多くの人がうなずくことができるのではないと思います。国連の安全保障理事会の例も出されました。たくさんの真理と真理の衝突が内戦という形でさまざまに現れながらも、均衡が保たれている可能性…。対立し続け、闘い続ける――そのことが「統治」であり、現在の平和を保つのかもしれない、ということ。そして、何かを守ろうとして闘うということは、守られずにいるものがある、ということでもある…、そこに隠された意味も、実は非常に含蓄があるものなのかもしれない…といったあたりで議論がひと段落しました。
ただ、何者かが敵を作り出しているわけではない、ということ。「真理」や「平和」を求めようとすることが、こうした闘争や戦争状態を生み出し、「統治」を実現させている可能性…そのようなことについて、考えさせられた回でした。来週も楽しみですね!
参加者の皆さんからのコメント
フーコーの思想は、戦争の脅威を改めて気付かされるものでした。歴史を振り返ると、法律や条約の制定で戦争は終わったと言い切る場面があります。また、私自身も法律ができたら戦争終結、問題解決と考えていましたが、それは単なる思い込みで、形で区切りをつけているだけなのだと気付かされました。また、今のコロナ禍でもマスク警察がマスクしていない人を見つけ出して咎めたり、オリンピック開催を狙うIOCバッハ会長から日本を救おうという敵を作って一致団結している気になる傾向があります。これは本当の敵COVID-19から身を守るという本当の目的を履き違えて間違った敵を作っているのに、合理的だと思い込んでいるのだと思います。しかし、オリンピック開催もマスク着用を呼びかけるのも必ずしも悪いことではなく、正当なことなのでこれをするなとも言えないと思います。対立するようでそれは実は正当同士の対立、そしてそれは真理によるのでどちらが正しいとも言い切れない。そして真理が統治にまで及ぶと本当に正しいものはどれなのか、あるいは正しいと言い切れるものなどないのではないかと今日の講義を受けて考えました。
東京オリンピック・パラリンピックという世界の祭典の開催に対して世論が分かれているが、私たちの命を支えている医療従事者た日本の経済を支えている人たちを天秤にかけることはできないと感じた。フーコーはある問題に対してすぐ解決せず、何度も繰り返し、徹底に一つ一つの事柄の問題を潰していっている。すぐ答えを出すことは安易な考えで疑問を一つずつ遠回りでも近道であることを学んだ。
「何かを守るということは何かを守らないということ」など暗い意見が多い印象を受けたのですが、一方そのなかであった「対立・ぶつかり合いによっても社会は彩られている」という意見に興味深く感じました。そして、講演会中でも述べられていたように、東京五輪開催についても「自分にとっての真理が相手にとっての真理ではないことがある」という論点は通じると思いました。五輪開催によって企業は利益を得ることができ、選手は日ごろの練習の成果を発揮できる機会が増えることになります。しかしそれに反して、Nomさんも述べられていたように、見落としたりしていることが多くあると思いました。
某競泳選手のお話を聞いて、歴史と合理性に支えられた(証明された)真理について、ふに落ちた気がしました。 ・[コロナ感染予防のために開催しない]という合理的な真理、と[選手自身がこれまでの人生において水泳選手として生きてきた]という選手の人生の歴史、及び[オリンピックという舞台で戦うことの神聖さ]というオリンピックが持ってきた歴史的真理たちが、衝突しているんだなと思いました。今回のオリンピックにおいて、「選手たちがオリンピックに参加したい気持ちも分かるけど、コロナの感染拡大も怖いから医療事業者の気持ちはわかるな」という気持ちは、合理と歴史に支えられた2つの真理のいずれも正しいためだと感じました。 ・オリンピックを開催することで失ってしまうものは何でしょうね・・・。オリンピックの開催を強行する過程の中で、失うものはあまり思いつきませんでした。 一方、今回のオリンピック開催の強行→成功というように順調なストーリーが出来上がってしまうと、犠牲になったものや命に対する思いや怒りが、不自然な形で、強制的に失われてしまうのではないかと思いました。それはまた、「困難を乗り切る日本」という日本の神話的側面がより強くなることでもあると思います。震災のときと同様に、失われた命や物が、「オリンピック成功」という輝かしいストーリーで上書きされてしまうんだろうなと思いました。
自分の心理と他人の心理は一緒ではなくて、そのために闘ったり守ったりしなければならない。守ろうとすることが他から考えたら、傷つけることにつながることになるかもしれないと学んだ。社会を守ろうとしている正当性がいつも正しいとは限らない。物事は様々な方面から、様々な人の心理を考えなければならないと分かった。 最初の方は難しかったんですけど、例えとか具体的なことを示していただいたので、理解することが出来ました。ありがとうございました。
フーコーが言っていることは、今まで習ってきた戦争を振り返ってみると戦争が起こる原因はそれぞれの人たちが自分たちが信じているものや受け継いでいるものが正しいんだという正当性が、自分たちとは違う考え方だったり、信じているものや使っている言語が違うと、自分たちとは違うからそういう人たちを敵とみて排除しようとなって戦争に発展するというようなことと似ている部分があるのかなと思いました。
「戦争は権力者が起こすのではなく、戦争は市民が起こす。権力の主体は市民。我々が我々が統治した結果、我々を抑圧し、追い詰めている。」という言葉を聞いてドキッとしました。権力者のせいにしてきたが、実は私たち市民が起こすことなのか?と続きが気になりました。
自分が持つ真理が必ずしも相手の真理と一致することはなく、だからこそ衝突が常に起こり、自分の心理を守ろうと動くことは現代にも見られます。これがフーコーが生きた時代からすでに考えられており、その解決策というのは簡単に見出されるものではないということを学びました。またこの対立はさまざまな考えが存在する限り無くならないものだと思いますが、だからと言って完全にこの対立がなくなってしまったら世界が均質化されることになるので、それもどうなのかなと思いました。

オリンピックに関して皆さんがコメントしてくださっていることは本当にそのとおりですね。どちらの立場についても、条件さえ合えば歓迎したいと思っているわけなのですが、なかなかうまくいかない。そしてフーコーは、すぐには解決に結びつかない問題を、そのままそれを、どうしてなかなか解決に至らないのか、成り立たないのかを議論しようとしているのですよね。私たちもぜひそこから学んでいきたいです。
いわゆる戦争に関するコメントですが、まさにフーコーがここから議論していきたいと思っているわけですよね。内部に向かっていく葛藤から疑似的な平和や市民性のようなものが生まれているのかもしれません。また、「対立」がなくなればいいというわけでもない、というコメントもおっしゃるとおりで、そもそもなくせなかったり、喚起されているというか、なくなれば解決するのか?というとそうでもない(日本でそのような対立がなくなったら、日本は単一民族国家、みたいな議論になってしまうのかもしれません)ようで、ぜひ考えていきたいところですね。
第四講| 一九七六年一月二十八日「人種闘争の対抗史」他 /2021年6月15日
担当:K原さん
当日資料はこちら
当日リポート
イケメンボイス談義の中からクールに始まった今日の講読会。議論は主にK原さんが挙げて下さった疑問点から展開していきました。
特に話題になったのは、フーコーが後半の82頁くらいからドドドと展開する「人種差別主義」が生まれてきたのはなぜか、というあたりでした。「ナチス以前」と「ナチス以後」とでも分類できるこの変遷の背景には何があったのか、というところから議論がスタートします。
「ナチス以前」と「ナチス以後」の変遷の背景には、まず、対抗史の中で「真理」を正当化する理由が歴史的=政治的言説/神話のようなものから、科学・生物医学的なものへ変化した、ということにあったのではないか、と指摘がされます。対抗史を語るうえで根拠となった「民族」の意味がまさに変容していったのだ、ということも挙げられます。ナチスが当時用いた科学・生物医学的な言説は、優生学的な思想で、それが当時はscienceの最先端であったわけです。
「ナチス以前」と「ナチス以後」の変遷の背景にあるものの二点目は、「対抗史」がメインの語りになったこと、という点が挙げられました。これは、なぜ戦争が内部に向けられるようになったのか?という問いにもこたえるものになっていきます。テキストの中で明確にこの点について触れられているわけではないのですが、S先生の解釈も含めて解説していただきました。具体的に、「対抗史」がメインの語りになった、とはどういうことなのでしょうか?
これまで、対抗史を語ってきた民族は、常に敗北しているような存在(P73L2)――統治されてきた存在・被統治者であって、対抗史とは”弱者”の議論であったわけです。それが、「ナチス以後」は対抗史を語る側が統治する側に代わりました。アーリア人という民族を守ろうとするナチスが統治する立場に代わりました。ソヴィエト連邦は革命を経て樹立した国家です。革命する側が統治する側に代わり、権力を握るようになったわけです。統治する側に立った「統治されてきた存在」は、彼らの統治を妨げる要因を排除しようとする。それが、「ナチス以前」と「ナチス以後」を分け、人種差別主義が展開していった背景にあることなのかもしれない、と確認がされたように思います。
フーコーは、今回のテキストの中で、権力がその正当性をどのように主張してきたのか、その変容について指摘していたともいえるでしょう。ローマ的な歴史が語られる「古代」は、権力は然るべき立場の人間たちによって継承され続けてきたということが、正当性を語るうえでとても重要なポイントでした。一方、対抗史のプロセスにおいては、「支配されてきた/被統治者であった」ということが権力を握る正当性として主張されるようになるようなのです。いわば、私たちが権力を守ったり、統治する可能性を持つようになった――そのような形で、「主権」のありようが変化したことをフーコーは指摘していたといえます。
フーコーは、権力が生みだされるプロセスやそのありようを考えていくことを通じて、例えばなぜ差別がなくならないのか、あるいはマイノリティの権利が回復困難な理由を考え、論じようとしているのかもしれません。そこから、私たちも学んでいくことができたら、と思います。
参加者の皆さんからのコメント
フーコー以前の歴史からも、フーコーの時代にも、今の時代にも、個人とは違う意見を持っているものがいることがわかった。
そして、それを認めなかったり、自分のものだけが正当だとするから対立するのだとわかった。コロナはもちろん、宗教や改革に関係することがわかった。
また、意識をしていないだけで私たちが信じている歴史、教師のする授業も、特定の側から見た意見、一定数以上が認めている知見であって、たとえばイスラム教からみた世界史とキリスト教からみた世界史が違ったり、私達日本人と、韓国人や近隣国の認識する国の領域の違い、歴史に対する考え方の違いや偏見もそこからきていると思った。
自衛しなければならない、というのは私達の知見も相手の知見も守ることだし、それが自我同一性だったり個性だったりすることもあり、押し付けあうことや画一化がいつも正しいとは限らないということだと考えた。
そもそも言説に種類があると知らなかったためすべてが新しいものに感じた。歴史では言説を用いて人々を支配したり迫害したりしていて、現代のヘイトスピーチ、差別などにつながっていると分かった。また、今回の内容とは関係ないが、はじめのコメント紹介を聴いていてフーコーはすぐには明言しないことにもどかしく思っていたが一つ一つ明らかにしていき、私たちに考えさせるようにしているのだと分かり納得した。
K原先輩が問題提起をしていた、「差別をなくそう」と⾔われているがフーコーの⾔う⼈種差別主義的⾔説をふまえると、歴史的⾔説と、差別は歴史的必然であるかもしれないため、表⾯的に「差別をなくそう」と⾔っても、それを根本から問い直す必要があるのか。と言う問いに考えさせられた。 現在の日本では差別をなくしていこうといった取り組み(目標の提示)が行われているが、その結果が顕著にでているとは考えられない。権力の正当性などが複雑に絡み合い、ただ、差別をなくすと言うだけでは解決につながっていかないと言うことは、潜在的に差別の気持ちがあったりだとか、差別がなくなっていかない理由なのかと思った。
差別は過剰な自己防衛の一環なのかもしれない。民族や性、障害などでも「らしさ」が植え付けられる。革命や言説では、あえて自己主張を正当化することで異質な者を排斥し自分たちに都合の悪いことには耳に蓋をしているのだ。助けているフリもいくらでもできる。私たちも政治的に全面的に関わるし日常生活でも知らずのうちに差別意識を兼ね備えている。分断が深刻化する前に市民から根本的にALIANATIONを当たり前とすることが必須だ。
勝者の歴史と敗者の歴史は異なるものであり、歴史は敗北の立場から語られることも多く、ある人々にとってはその視点から語られる歴史が重要な役割を果たしているということに初めて気づいた。また、対立は問題視されることが多いが、対立がなくなることにも問題は生じるという指摘があり、対立や闘争をなくす方法を論じるだけでは解決できないものがあるということを学んだ。
「歴史を語るということは、歴史を正当化し、かつ強化すること」という言葉が印象的であったが、歴史はただ過去を記録するだけのものではなく、過去を引用することでその後の権力をより確実なものにしているのではないかと感じた。また生物学・医学的視点からの人種間闘争にばかり目を向けていたが、ナチス前の世界ではこのように歴史・政治的な人種間闘争があったという点もとても興味深かった。
⼈種差別主義的⾔説が登場した。美しく感じる歴史の多くは、敗北、抑圧の歴史であることを学んだ。抑圧されていたことが、核となり、その核を中心に民族ができていくことがわかった。マジョリティがマイノリティ意識で生きていることが問題であり、非統治者であることが正当性を生み出し、権力のあり方を変容させたことが興味深いと思った。

歴史はすべていずれも正当化されてきたもの、といえるのかもしれません。それが美化されることで対立することになる―ーちなみに、フーコーが指摘している「歴史」は、いわゆる歴史的事実を並べていく意味でのいわゆる歴史とは少し異なる側面があると思います。自分たちの主張する歴史を「正当化しようとする」こと、自分たちにとって「正しい」と思う歴史やものを守ろうとする――その正当化の欲求がエンジンになって防衛しあう/戦争状態/政治が行われているというようなことを論じていこうとしているのでしょうね。
また、差別についてもコメントくださっているとおりですね。差別はよくないと知っていて、差別をしない方法も知っているはずなのに、差別がなくなることはない――この状況をどう考えていくべきなのか、という問いに、権力という装置の議論が重要になってくるのかもしれません。
第五講| 一九七六年二月四日「ホッブズにおける戦争」他 /2021年6月22日
担当:M先生
当日資料はこちら
当日リポート
この日の議論は、「む、むずかしい…」という雰囲気から始まってしまいました。うーん。レジュメを切った担当者としては申し訳ない気持ちでいっぱいだったわけですが、議論は特に「意思の表明」に関するところ(96頁)からスタートします。
ホッブズは、主権が獲得されていく背景には①制定による主権、②獲得による主権、③母親による主権の3つがある、と整理し、いずれも「意志の表明」――ナイフをのど元に突き付けられていようが、自分の意志を明確に表明できようができなかろうが、「生きたいと願う」意志の存在が必要であり十分だ、とします。つまり、生きるということを担保に権力を手放す…生きるということの意思表示が常にとられてきたのだ、というのです。
国家とは、ホッブズに言わせると「意志の表明」に基づく『契約』によって成り立っているのだ、ということなのかもしれませんが、フーコーは、そうではなく、どんな状況であれ、自分の敵を前にしても「生きたい」という意志表明・意思表示をし続ける…そのことで戦争が避けられ、「戦争状態」に至るんだ、ということが説明されていたのかもしれません。
さらに言えば、実はお互いの力が拮抗しあい、けん制しあいながら、にらみ合いを続けているような状況…意志の表明をお互いにし合っているような状況が、血や死体が生まれる「戦争」ではない、「戦争状態」として保たれ、平和がつづくのだ、とも今回の議論の中では読み解くことができたように思います。このことから、実はこの章がスポーツ論としても語ることができるのだ、という話にも展開しました。スポーツもまた、闘争的デモンストレーションーー美化された形で、スポーツという形態を通じて、意志を表明しあっているともいえるのでしょう。その意味では意志と意志がぶつかりあう戦争状態、皮肉にも聞こえてしまうかもしれないですが、まさに「平和の祭典」なのかもしれない、という議論にもつながりました。
M先生が論点をいくつかあげていたうちの2点目にホッブズの主張がなぜ、「歴史的=政治的言説」にはならないのか、という点は、歴史的=政治的言説が二項対立の中で自身にとっての「真理」を正当化しようとするプロセスの中で用いられてきたものであったということから説明できるということも解説されました。ホッブズは、戦争が起こらないようにするためにどうしたらよいのか、ということを議論しようとしてきたことを考えると、ホッブズは「対抗史」の文脈にいたわけではなかったのです。ですが、こうしたホッブズのような「戦争を避けようとする」観点からの言説ではなく、互いの「意志」を表明しあい、拮抗しながら、「戦争状態」を続けていくようなあり方、これが、これまでの統治の在り方(ホッブズが考えていたような古い権力観)とは異なる、新たな権力の在り方であり、近代において席巻してきたものであったのかもしれない、という形で、議論は落ち着いたような回でした。
なかなか難しい議論となっていましたが、次回はフランスの側から目を向けた章になるということで、併せて理解していくと、今回の講義の内容の理解もより深まるとのこと…楽しみに来週も読んでいけたら…と思います!
参加者の皆さんからのコメント
難しい内容であったため、講読内容についていくのが大変でした。戦争と聞くと残虐なイメージだけだったが、戦闘や血、死体のない「戦争状態」というものが身近にあるということを学べたことはとてもタメになりました。綺麗にまとめられたレジュメがとても役に立ちました。ありがとうございました。
平等が存在するから戦争が生まれるというのが戦争状態であるとわかった。今まで対立や戦争と聞くと民族的、宗教的問題が背景にあるという印象が強くありましたが、平等が存在するからというのを聞いて確かに少しでも差異があれば戦う必要はないし、戦争は起こらないなと思い改めて戦争の捉え方を考える機会になりました。また、統治されたとしても死への恐怖、生き残りたいという意思があるからこそ戦争がなくなっていくことに繋がると思うし、そういう意思があるからこそ国家が生まれるという点が分かりました。フーコーの戦争は生きることが前提とされているものであることも分かりました。
政治は対立し続けることによって成り立っていて、その状態が戦争だと学んだ。社会は国会の与党、野党の対立だけではないと思うが、国民が意識もせずに国によって統治されていることに対して国民は対抗心があるわけではない。なぜなら国民は生きたいという意志があるため、自動的に統治を受けることを容認しているのである。
私は戦争という言葉を聞くと、死という言葉を連想します。第一次世界大戦や第二次世界大戦などは国のために命を捧げることが当たり前の時代で、死に戦争へいっていたと言っても過言ではないと思います。しかし、今回の議論の中では、「生きることを前提とした戦争」というワードが出できて、戦争というイメージを覆すようなもので、とても印象的でした。生きることが前提で、血も流さない戦争というものは、大きく考えた場合統治や服従につながると思いますが、このような戦争は日常の中にも隠れているとも思いました。戦争というと、事が大きくなりますが、権力のあるものを恐れ、自然と服従する形が形成されるのは日常の中の社会でもよくある事だと思いました。
さまざまな形の対立があることに気がつくようになった。今、顕在化している問題の多くが、形だけは解決したように見えるものである。つまり、本心のところは解決していなかったということである。何かを守るために、ここでは自分が正しいと思うことのために私たちは戦っている状態にあり、なんとか表面だけは、誰かに自分が正しいということを認められたい、と思うのだと考えた。
母親に対して死んでやる!と叫んでも、もう生きたくない!とは言わない。つまりこれは闘争である。ホッブズ的ではなく、逃避をせずに、生きること、納得のいかないことや、自分を脅かしていることに抵抗すること、正面から受け止めることをしている。これは大変わかりやすいことで、行きたいがための証明や発言。殺し合いではない。
途中の前回のコメントへの先生の意見で差別についてのおっしゃっていたことが確かにと思いました。大多数の人がいけないことと分かっているのになくならないのはいつになったらなくなるのかと考えてしましまう。私はもちろん差別はいけないと思っているのですが、区別は必要だと考えています。男女差別、障害者差別、ワクチンを打ってる人打ってない人の差別はダメですが、男女の区別、障害者の区別、接種したかしてないかの区別は必要です。最近の世の中は差別と区別がごちゃごちゃになっているように感じます。 今回のオリンピックの話が興味深かったので、これからオリンピックの話にも議論が進んでいくと面白そうだと思いました。

ワクチンも残数が限られてきたという報道もされていますね(2021年6月29日時点)。オリンピックのボランティアのためのワクチンは確保する、といった報道を見たときに、《何を守ろうとしているのか》という観点を以て考え続けていくことが求められているのかもしれないですね。
私たちは何かを守ろうとすることを通じて「統治」されているのです。何かを守ろうとすること自体が、私たちが生かされている理由にもなっているともいえます。ホッブズは平和に統治されるありようを主張した(戦争はよくない)のに対して、フーコーは、よくないとわかっていながらも、相手を攻略したりする征服の論理はずっとあり続けている、ということを指摘しているのだと思います。ひとりひとりが何かを守ろうとして…防衛戦を続けている、それが安定的な統治にもなっているのかもしれないのです。
第六講| 一九七六年二月十一日「歴史の新しい主体」他 /2021年6月29日
担当:大学生M
当日資料はこちら
当日リポート
ワクチン接種の話から、だんだんとフーコーの議論へと誘われた今日の講読会。大学生Mさんの「反乱」という言葉と「侵略」という言葉はどのように使い分けられているのだろうか?という疑問に答える形で始まりました。
前回の講義がイギリスの話で、どちらかというと「侵略された」側の話であったとすると、今回は「侵略する」側の存在に触れたフランスの例が大きなテーマになっていた章だったのかもしれません。ローマからの継続性を正当性として主張する存在と、それに抗う存在――貴族たちによって、さまざまなストーリーが展開されていたようにも思います。
今回のテクストでは、絶対王政が確立するまでの過程とその後について触れられていたともいえるかもしれません。そのあたりについても先生から補足的に解説をしていただきました。
貴族達は「侵略した」ということに由来して「権力」を持ち、そこから派生した一人の”王”が統治を始めます。ところがその”王”は、自らが”王”であり続けるために行政や法の知を必要としたかもしれないのです。この行政や法とは、国家の意志を反映させるようなシステムであり、かつ貴ばれるべきものでもありました。それは、これまでずっと継続されてきたローマ法に基づくものだからです。
これまで読んできたテクストの中でもかつての歴史は「権力が自分自身について語る物語」であるということが触れられていたと思います。歴史でずっと主題とされてきたのは、ローマからの継続性によって維持される正当性だったのです。王様は、ローマを背負ってきている、ということが歴史で語られてきたといえるのです。
フーコーは、そこに「歴史の新しい主体・主題」が現れたことを説明していました。それがいわゆる「対抗知」などとして私たちも読んできたものであったといえると思います。今回のテクストーーフランスの歴史においては、貴族たちが…かつて侵略/征服をする側であった存在が対抗知を生み出していきたことが指摘されていました。
貴族たちのモチベーションとなったのは、まさに今、”我々”が生きているこの土地を治めている、という事実でありました。そして同時に、貴族たちに「権力の正当性」は保障されていない(王にとって、貴族たちの存在は邪魔)という実態もあったのです。まさにその土地/国を治めている主体として、生存の権利を主張するような形で、<法的な知>や<代官の知>に対抗していった――そこから歴史の新しい主体・主題が生まれていったとフーコーは指摘しているのだろう、という確認がされたと思います。
フーコーは、「私」および「われわれ」が歴史の新しい主体になっていった、としていますが、その「私」や「われわれ」とは誰のことなのか、ということにも議論が及びます。それは対抗した、抑圧されてきた歴史を持つ”民族”のことであり、”社会”なのかもしれないのです。フランスにおいては、まさに貴族の集合体が”society”として機能していったということが触れられていたと思います。このことから、society≠国家、国家に対抗するものとしてsocietyが生まれた、ということを、確認して今日の議論は終えられていたと思います。
また、次回もフランスの中での話が繰り広げられていくことになりそうです。読めば読むほど、「そういうことだったのか~」的な気持ちよさもあったりするフーコーの講義。折り返し地点を終えて今後の展開がますます楽しみですね。
参加者の皆さんからのコメント
フーコーについての報告の前に柴田先生が話す話がいつも楽しみです。今回もクスクス笑いながら聞かさせていただきました。これからもよろしくお願いします。
フランスの歴史などの本編は、内容が難しく、講演後に再度読み直してみても、理解することが難しかったため、復習についてをメインで書かせていただきました。 私も戦争について考えると、「死」や「心身を傷つける」ことを連想しました。今まで自分が言い争いをしたり、国規模での争いのない時間(俗に言う平和)は「戦争」と言う言葉とは無縁のように考えていましたが、平和な時間や、自分が言い争いをしている間も、自分の意思表示をして見合っていたり、牽制し合っていると言う面では戦争を続けていることになるのだと改めて感じました。
歴史を語る新しい主体が生まれ、それは「過去」を話すのではなく、「今、歴史を背負い治めている」という貴族たちに変わった。貴族は自分たちの生存の権利を求めて集団を作り、民族が成立し、やがてそれが社会となっていった。元々は、貴族の集合から社会が始まるといった観点は興味深かった。
王の絶対主義を制限しようとする貴族の企てが歴史のモデルに繋がっていることを学んだ。また国家に対抗する社会が貴族の同盟であることもよく分かった。侵略は征服する目的だけではなく、均質性を防衛する目的で行われることも理解した。日本では対抗するという概念がなく政府の思うままに誘導されているような感じがした。
都議会選挙が7月4日に行われ間近に迫っている。私も、政治的に国民の意思を示されるようにしないといけないと思う。コロナ禍で大変なことになっている中、この選挙の投票率に注目したい。私自身、この世の中で投票をして政治に参加した人たちの意見はとても貴重だと感じる。東京オリンピック、10月には衆議院選挙もあり政権の命運を分けることになると感じた。

実は、先週はちょっと先走って、第七講の内容にもさしかったような解説になってしまっていたかもしれませんね、まさにちょうどフーコーの議論は、防衛するといったときに「何を」防衛するのか、という部分に入ってきているのだともいえるかもしれません。
フーコーは「新しい歴史の主体・主題」と言っていますが、”新しい”とは、つまり”古い”歴史の主体・主題もある、ということなのですよね。それがローマ法であったりしたわけです。統治の正当性は歴史的に検証されるべきものだったのですが、その統治の主体が根源的に変わり、「我々」が統治していかなくてはならないという主張につながっていった、このターニングポイントをフーコーが注目して見出していったということが面白い点ですよね。そして、「我々」が統治する際にとられた行動様式が「防衛」であった…と。自分たちの運命は自分たちで決めていく、という考え方は、民主主義的な考え方とも通じる部分がありますが、「日本では対抗するという概念がなく政府の思うままに誘導されているような感じがした。」というコメントを見ていますと、現代においてはこの民主主義的なものも換骨奪胎されてしまっているといえるのかもしれないなあ、、と感じてしまいますね。フーコーの議論もまた、これからどんどん少しずつ現代的な観点からも議論していけるとよいですよね。
第七講| 一九七六年二月十八日「戦争の諸制度」他 /2021年7月6日
担当:Nomさん
当日資料はこちら
当日リポート
ワクチンの話、オリンピックの話とを交えながら今日の議論も展開していきました。特に、議論は158頁のあたりに出てくる「自由」の議論を通じて白熱します。
フーコーが読解していくブーランヴィリエは、「自由」とはそもそも平等に反したものであるということ…自由とは「奪うことができること、わがものとできること、利益を得られること、命令できること、従わすことができること」(L15)と説明しています。これは、柴田先生が言うところの《ジャイアン理論…「お前のものは俺のもの、俺のものはもちろん俺のもの」…》にあたりますが、このジャイアン理論の「自由」を主張していったのが、フランスにおいて新しい歴史の主体:フランス人貴族に該当していました。彼らは、自分たちの自由を縛る法の知や代官の知に抗おうとしたわけです。
翻って現代の議論を考えてみると、ワクチンを接種していく順番や経緯は国や社会によってずいぶん異なっていることも議論の中で指摘されました。アメリカなどは特にエッセンシャル・ワーカーと呼ばれるような人たちに優先度を置きながらワクチン接種が実施されてきたわけです。日本においては「個人の自由」(ワクチンを打つ自由/打たない自由)を尊びながらワクチン接種が進められてきた(?)わけですが、実は日本の”自由”はほぼ「自己責任」という言葉に置き換えたほうがいいような代物であるかもしれず、それは、フーコーが指摘していたような「奪う自由」に相当するようなジャイアン理論的な発想であったともいうことができるのかもしれません。
かつて、ジャイアン理論における(奪う)自由は、国王/国家権力/ローマ法に由来して禁じられ、制限されていました。人々はローマ法(王)に由来して平等、とされてきたのです。ですが、「平等」といえるような実態はこれまでかつて歴史上で起こりえなかった、ということもブーランヴィリエおよびフーコーによって説明されています。これまでの議論を踏まえれば、「自由であること」、「自由であろうとすること」は防衛戦を張ることとほぼ同義であり、戦争が常態化していた、ともいえるわけです。以上より、ブーランヴィリエのこの指摘を通じて、戦争の一般化の一つ目がフーコーによって指摘されます。(今回の講義の冒頭に出てきたクラウゼヴィッツの「政治は戦争」と通じてきますね)
さらに、軍事的整備/武装をdisplayすることを通じて内的制度としての戦争が第二の一般化として説明されていました。どのように運営・運用していくかという観点から考えば、選挙もまたわかりやすい戦争の例のひとつですし、ミサイルや核の配備もこの文脈から理解することができるでしょう。
そして、「力の転倒・変換」が戦争の第三の一般化として指摘されていたものでした。対抗知を以て示そうとしたフランス貴族たちは、ジャイアン理論における「自由」を主張していたわけですが、その自由を主張しなければならなかったのは、彼らが”抑圧された”、”統治されている”側だったためです。彼らは「自由な強者であるべき弱者」であったわけです。その延長で強者と弱者の転換が起こっていきました。いわば強者と弱者という構造が成立し、その中身は固定化されずに絶えず入れ替わり立ち替わるようなものとしてとらえられるようになったわけです。
いじめられる側がいじめる側に転じたりする、といった例が参加者からも挙げられていましたね。厄介なことに、いじめる側は、どこかで「我々を守ろう」という発想に立ち、いじめを繰り広げていたかもしれないのです。
だからこそ、もしもこうしたいじめの構造を断ち切るためには、「弱者」と「強者」の構造そのものに自覚的になることがもしかしたら鍵になるのかもしれないという指摘もされていました。
また、圧倒的な強者や弱者が存在しない、平等だからこそこうした強者と弱者の転換が起こりえた可能性も確認されました。
議論の最後には、「例えば知的障害でいじめられている人が、強者の側に転じることは実は難しいのではないか」というコメントもありましたが、柴田先生からは、まさにその点がフーコーが言及しきれなかった点ではなかったかと指摘がありました。弱者の側が強者に転換しえない社会構造の側に問題があった可能性――その指摘とそこからの考察は柴田先生が取り組まれた仕事にもなっています。フーコーの議論を現代の文脈で置き換えて考えたとき、新たな発展や展開を見出すこともできるのかもしれません。今後の議論の展開もますます楽しみですね。
参加者の皆さんからのコメント
難しいけど、物事の本質を考える感じが面白いと思った。時代を超えて語り継がれるってこういうことなんだと思った。
戦争の準備段階こそが戦争であるとの考え方に本当に面白く感じました。自身を守るためと理屈づけられた「魅せるための武器」を使った緊張状態がある限り戦争は続くという主張には初めて触れました。
ワクチン格差、ワクチンに関する話が興味深かった。自由と平等をこの議論に当てはめることができたり、機会は準備するもののそれ以降は個人に任せるというところは、適当に思える。しかし国や自治体によって供給状況や優先順位が異なったり、接種後のマスクの有無などの決まりは各々であり、それで本当にコロナに打ち勝つことができるのか、どのような対策が必要なのか(論点が少しずれるかもしれないが)気になった。
今回私が学んだことで特に興味を持ったのは、通称「ジャイアン理論」についてだ。自由と平等は両立しない、奪うだけでそして何も与えない、というところがジャイアンらしいと思った。私は世界史選択だったので自由のために市民が起こした闘争などについてはよく習っていたが、考えてみると自由の定義がひどく曖昧であることに気付いた。
平等と自由は違う、という勝手に類似すると思っていた事象がまさか相反するものだとは考えもしませんでした。柴田先生の言う通り、ジャイアンは奪うことによって自由を確立しているわけで、そのことは平等とは程遠いなと理解することができました。どちらも、皆欲しがっているものであると思うのに両立しないことも社会の摂理なのかなと思いました。
自由に関連しての感想です。 世の中には、他人が自由だったり、楽しそうにしていたりすることが気に入らない人たちがいるんだな、というのを感じていたのですが、その理由は全くわかっていませんでした。でも、今日の話で、我々は自由でも平等でもなくて、自由であろうとして防衛する、とあり、繋がった気がしました。人が自由であることは、自分にとって脅威と捉えるから、楽しそうな人や自由そうな人を叩くのかなと思いました。
自由と平等とは反対のものである、という考え方には初めて触れました。先生がおっしゃていた『ジャイアン理論』もとても面白く感じます。私はこの理論からジャイアンだけでなく、進撃の巨人の主人公エレンを想像しました。彼は「理屈抜きの、存在故の自由」を一貫して求め、物語の序盤では当然のように彼の正義が正しいと思われていました。しかしながら、「自由」を最後まで求めた彼は、徐々に人を殺し始め、大きな権力を持った後は全人類を殺戮するようになります。そして、作品は彼が子供を抱きながら「お前は自由だ」と語りかけるシーンで終わります。進撃と照らしあわせ、「自由」とは人類が求めるべきものだと信じて疑いませんでしたが、実はとんでもない残虐性の面を持つということを学びました。(長くてすみません!)

ジャイアン理論のところは訂正させてください!ジャイアン理論には3つの定理があるんですよね。ここではジャイアン理論の第一定理として説明させていただきました。ちなみに第一定理が「おまえのものはおれのもの、おれのものはおれのもの」で、近代所有権の否定を指しています。第二定理は「のび太のくせに生意気だ」という近代的主体の否定。第三定理は「これ借りとくぜ、ただし永遠にな!」のポストコロニアリズム的なものとして知られているのですが、今回はジャイアン理論の第一定理を用いたのですね。実はどちらを第一定理、第三定理にするか、は論者によって見解が異なるようなので補足訂正させていただきました。
フーコーは、戦争はジャイアン理論を発動できる「自由」があること、そして相手に勝てるかもしれないと思わさせるような「平等」があることで生まれ、お互いの正当性を「display」/マウンティングすることで防衛されているのだ、と主張しています。
いじめについても本当にみなさんがおっしゃるとおりで、ぜひ考えていきたいところですし、ジャイアンから進撃の巨人でまた説明していけるところもこれから出てくるのかもしれませんね。
第八講| 一九七六年二月二十五日「知の規律化」他 /2021年7月13日
担当:H松さん
当日資料はこちら
当日リポート
昨日から第4次緊急事態宣言が発動された中で始まった今日の講読会。フーコーの講義も白熱故かいろいろな話が出てきました。
この日の議論はフーコーがシェイクスピアの悲劇を引いてきたあたりの疑問から始まりました。なぜシェイクスピアの悲劇が??どういうことなのか?というところだったわけですが…
なぜ、喜劇ではなく悲劇なのか、というと、実は悲劇というものは、反論を許さない、正当化するのに最強の主張となりえるものだったからなのです。歴史が常に悲劇として語られるのはそれが「正当性」を主張するうえで強力な方法であるからなのだ、と。つまり、悲劇は「誰が正当か」を主張する=統治のための道具にされていた、ということができるでしょう。
パラリンピックにこの議論をなぞらえて捉えることもできる、という話もされていました。第4次緊急事態宣言は、6週間ということが報道されていますが、パラリンピック開催の直前までという計算になります。緊急事態宣言後にパラリンピックを実施→衆院解散、という流れがもしあるとしたら…。ここには、もしかしたら「パラリンピックを開催するための知」を武器に「統治」が行われているとわかりやすく理解することができるかもしれない、といった指摘もされました。
オリンピックについては、開催/非開催や有観客/無観客はふつうに議論されやすいですが、反面、「パラリンピックを中止にしろ」というようにはなかなかロジカルに批判できない可能性があり得るのです。「『障害』という『悲劇』に負けずにパフォーマンスする、その『感動』的な機会」を死守した、という形で”display”する「戦争」と捉えることもできてしまうかもしれないのです。
フーコーは、王様たちも、貴族たちも、それぞれの「正当性」=「真理」を主張するための<知>を求めており、実はその両者が求めている<知>とは同じものなのだ、ということも指摘しています。
時には「悲劇」という形をとり、時には「諸科学の知」という形をとっていった――その<知>が闘争における武器であり、道具になっていったことを述べていたのだと確認することができました。互いに血が流れ死体を生むような戦争をしていたのではなく、「言説」を以て戦おうとしていたのですね。
そして、それぞれがそれぞれの「正当性」や「真理」を主張する中で、知を武装化していく必要が生じたということ、その過程で4つの操作(①選別、②規範化、③階層化、④集中化)が起こり、その結果として「科学」が生まれたのだとフーコーは主張しています。
フーコーがいう「戦争」の過程では、この「科学」の奪い合いが起きていたのだ、と説明することができそうです。このことは、今日のCOVID-19をめぐってどちらが科学的かを競い合うような、マウンティングの風景と重ね合わせることもできるかもしれません。
184頁にあるような「個々人の身体そのもののレヴェルで捉えられた、権力の規律型技術」が発展していく過程で、『監獄の誕生』などで指摘されていたような「身体の統治」が「生権力」に発展していくことも確認していくことができるようです(とくにクライマックスでその議論が出てくるとか…)。
残すところもあと3回となりましたが、このタイミングだからこそ身に迫って読んでいくことができるとも痛感しています。ぜひ、しっかり読み進めていきましょう!
参加者の皆さんからのコメント
超楽しかったです!歴史の中の思想家の思想を通して現代の生活を眺めてみることがこんなに楽しいとは思いませんでした。また、思想といっても人間の気持ちの研究でしかないため、改めて歴史とは人間が起こしてきたノンフィクションなのだなとも思いました。
7/6のジャイアン理論についてですが、自由は誰かの犠牲によって成り立つとのことでしたが、自由と自分勝手はどう違うと考えられていますか。
権力は絶対的な力ではなく相対的な関係であるという部分で目から鱗が落ちました。確かに、貨幣がどうして信用されているのかや、なぜ君主が土地を支配しやがて没落していくのかを考えたとき、それを支えているのは人々が共通認識として力を認めているからで、自然や宇宙の中では全く無力のものなんだなと思いました。
「悲劇による正当化」というワードがとても印象的だった。たしかに私たちは悲劇に対抗しない。 ただ、悲劇によって正当化されている対象に対する私たちの眼差しは、哀れみに近いと思う。悲劇による正当化に対抗する術は持っていない様に感じるが、そもそも戦える相手(対抗•論破できる対象)としてみなしてないないかもしれない。悲劇によって正当化された事象に、私たちは「平等さ(戦争が起こる条件の一つ)」を感じないのではないか。 悲劇によって正当化されるその事象は、その悲劇性以外に、その正当さを保証できないだろう。なぜなら、そもそもその悲劇事象に対し、他の事象が平等性を持つことができないため、他の事象と何らかの関係性(論理的な因果関係など)を持つことが難しいのではないかと考えた。 そもそも、悲劇によってしか正当化できない事象に、正しさは備わっていない様にも感じる。
自分の主張を正当化するために科学的根拠を使うことは今の時代当たり前すぎて気にしたこともなかったが、これを知の武装化や、防衛という表現にあてはめられることは新しい発見だった。今のコロナについての主張のぶつけ合いは、国民を守るためだとか、オリンピック選手のためではなく、オリンピック、パラリンピックを何とかして行ったという功績のためにという隠れた本当の目的のための言葉の戦争と考えることもできるのではないかと思った。
「知を武装化するために知を科学化した」ということについては実感があります。昨今、意見には証拠がなければだめで、科学的な証拠がない場合はかなり権威のある人の意見を引用しなければなりません。日本がだめなのは首相以下の閣僚が大学院もでていない低学歴で、理系でないからとも叫ばれています。科学的であることは重要なのだと皮膚感覚で感じます。昨日の先生の講演、毎週の読書会を通じて、何かがぼんやり見えるのですが、その何かに触れようとするとすっと逃げられたような感じて脳がイライラします。

先週は、それぞれの真理を「どう守るのか」と考えたときに「科学」という武器が用いられるようになった、ということを確認していきましたね。それが「統治」としてのありようを示しているわけですが、社会がそれによって治められていく、ということの意味を考えさせられますよね。
「自由」と「自分勝手」の違いですが、これは結構難しいですよね。「真の自由」を行使することとは、自分の思う通りに振る舞おう、とするものかもしれませんが、はたからみたら、自分勝手の極みである可能性もあるわけですものね。
権力も、みんながどう思うか/見るかということの意識とは切り離せませんね。また、「悲劇性」についてのご指摘もとても鋭いものがありますね。パラリンピック開催についてNOを言えないということ、正当化できてしまえるということはなぜなのか、ということは結構丁寧に考えていかねばならないかもしれませんね。
また、「イライラ」してくださったとのこと、ありがとうございます(?)。「イライラ」がなぜ起こったのかを考えてみると、これまで違和感なく受け止められていたようなことが、スルー出来なくなったということでもありますし、それは好奇心や関心をもって、何とか考えてしっくりしたい、ということに由来していることだと思うので、そういう経験に講読会が少しでも貢献出来ているのだとしたらとても嬉しく、ありがたいことですね!
第九講| 一九七六年三月三日「野蛮なるものの濾過」他 /2021年7月20日
担当:K原先輩
当日資料はこちら
当日リポート
15時から第四回まなキキカンファレンスが開催された今回の講読会。長丁場のオンラインでお腹を空かせたK原さん、もろもろでのスタートとなりました。(ワーカーズホームカフェさんのおいしそうなコーヒー&スコーンを画面越しに眺める/見るだけで我慢するしかできずにいたことによる)
今回も、「難しい」、「うん、難しい…」というやり取りの中で議論が展開していきました。特に「難しい」と感じる理由は、「構成」などをはじめとする抽象的な表現が連発したことに由来するからかもしれません。この点は、まさにこの講義のクライマックスに差し掛かっていることと大きくかかわっているようです。議論を改めて整理し、展開していく準備にとりかかっているような段階…そう思いながら読むと、気合が入りますね。
今回のテクストで特に重要と指摘されたのは、「ブルジョワ階級/第三身分」の存在が歴史知を操る存在――社会の権力の担い手、構成者として明確に出てきた点だといえるかもしれません。テクストの中でも、207頁あたりに記述されていたのは、ブルジョワ階級と第三身分が「自分たちを歴史の主体として思い描くことはほとんど不可能」ということでした。それが、”歴史”という知を道具としていったのです。歴史の「知の道具化」のことを、フーコーは戦術としてとらえ、「野蛮の濾過」と表現しているのかもしれません。
前回もジャイアンの第一定理でみてきたとおり、自由は「野蛮さ」とはどうやら切り離して考えることができない。(ちなみに、未開人は収奪されていくような対象として説明されています)ですので、フーコーの講義では、フランス革命の際の例をたたき台として、それぞれの「真理」を主張する主体が、自分たちの自由を三者三様にどう主張していくのか――野蛮の処理の仕方――が概説されていたといえるでしょう。
まず、第一に「野蛮さなんて自分たちは全く持ち合わせていない」と押し切ろうとするような立場がいることが示されます。これはローマ法を正当に引き継ぐことを主張してきたような国王/絶対君主的な立場が該当しています。ですが、野蛮さなしに自由は確立しないということを踏まえれば、このような主張は詐欺師的なものでしかない、と一蹴されていくわけです。
第二に、「野蛮さこそが民主主義的な象徴なのだ」と主張する立場でした。これはフランス人貴族たちが対応していますが、貴族という立場上、民主主義的な存在ではありえない…それゆえ「野蛮な民主主義の上に君主制と貴族性という双子の形象(202頁」と説明されるような矛盾したありようが指摘され覆されていくことになります。
そして最後に挙げられていたものが、野蛮さには「悪しき野蛮性と善き野蛮性」があるという主張でした。国王や貴族たちの「悪しき野蛮性」に対して、「善き野蛮」は都市から生まれ、脈々と受け継がれているのだ、という主張です。これを担ったのが、ここから焦点が当たっていく主体となる、ブルジョワ階級/第三身分となるわけです。
ブルジョワ階級/第三身分が主張した都市人=自由といった主張は、おそらく現代の私たちの多くも同様に依拠しているような種のものかもしれません。ここでブルジョワ階級/第三身分は、ゴシック小説(講読会中に上がった例は『フランケンシュタイン』など)などを通じて歴史の解釈や依って立つ基盤を模索していった、といえるのかもしれません。
改めて振り返ってみると、こうしてブルジョワ階級/第三身分が歴史知をもって「何かを守ろう」とする存在として参画していく有様は、さまざまな主張や立場がある中で、自分たちをどう社会の中で位置づけられるのかを相対化してとらえ、主張していくことにほかなりません。ここで、力の構成関係という発想が生まれてくるのです。もしも、いずれかの立場が突出して強ければ、そのまま押し通して、その「自由」を主張すれば済む問題であったかもしれませんが、そうもいかない状況≒力の拮抗関係が生まれたことで、自らが社会の構成要素にどうなりうるのか、といった議論に発展していったといえます。そこに大きく寄与したのが「知の科学化」であったといえるでしょう。
フーコーが講義の冒頭で触れていた政治的・歴史的言説が展開していく3つの方向性(民族性/社会階級/人種)は、上述したような三者にも対応していると捉える方が面白くこの議論を(読み方・解釈の仕方として)理解することができるだろう、という確認もされましたが、それはすなわち、ブルジョワ階級/第三身分が展開していく知の武装化の議論が人種(内なる敵)に向かっていくということでもあることともつながっていくようです。
オリンピックを正当化させようとする議論(歴史的な大会であり、崇高な理念を持つイベントとしてのオリンピック)も一つの”野蛮なるもの”を濾過した結果とみなすことができるのかもしれない、という指摘も終盤されていました。単なる”かけっこ”なのか、”歴史を背負うかけっこ”なのか――
また、さまざまな人たちが”野蛮さ”を濾過しようとしているわけですが、私たち自身も、それぞれが<自らの野蛮性>をどうにか濾過しようとする一主体であるのだということ。私たち自身が、<自らの野蛮性>をどう濾過しようとしているのか、という地平に立ってわが身を振り返ってみることの重要性も指摘されたような回でした。ここからの展開がますます楽しみですね!
参加者の皆さんからのコメント
イケボだと言われている方がいると思いますが私は大学生mさんの喋り方と声がとても好きです。とても落ち着きのある喋り方で私も真似したいです。
自由は平等でないというジャイアン理論がとても面白かったです。第1定理、第2定理などジャイアン理論が真剣に分析されている事を知り、ジャイアンがどれほど凄いのかが身に染みて分かりました。私は既に一回目のワクチン接種を終えていて2回目の予約も取れていますが、バイト先の方達に聞くと「別に打たないかな」との回答が多く、売っている人は私含めて3人しかいません。ワクチンを打つかどうかの自由はいずれいじめに繋がるように感じます。実際他国ではワクチン接種者以外は飲食店利用できないというお達しも出ています。自己防衛を巡るワクチン接種やコロナの問題にこれからどのように向き合うか考えたいと思いました。
現代日本に生まれ生きている私には到底思いつきもしないような視点からフーコーは「自由」を見つめていたのだな、と感じました。全体的には難解で終始議論に追いついていくのに必死でした。しかし、「野蛮なるもの」が自由である、という議論と、オリンピックや政権に関わる権力の議論はすごく興味深かったです。野蛮と自由ということは相反しているようでそうではないことが時代考証を踏まえることで分かったのが大変面白かったです。オリンピックとパラリンピックに関しては自分と結びつけながら聞いていました。私は通訳として選手村とIBCでバイトをしているので今までは五輪万歳派でしたが、隠された権力のかげに近代的なオリンピックのあり方に限界を感じました。日本では両手をあげて礼賛するようなマーケティングの方法が取られがちなのかな、と感じますが、今回の五輪をきっかけに政治に帰依するようなあり方が問い直されるといいなと思いました。
パラリンピック中止の主張はロジカルに批判できない事は身をもって感じており、周りの大人たちもパラリンピックの開催については肯定的な方が多いように感じます。 今回の講義では野蛮の処理の仕方として三要素挙げられ、どれかひとつを選ぶことは出来ませんでしたが、強いて言うなら第三寄りの意見であると感じました。しかし、王や貴族ひっくるめて悪と見たり、市民を善と見なすことは難しいのではないかと思いました。また、何を持って悪と見なしたり善と見なすのも抽象的であると感じました。実際イギリスの起源は野蛮性を持った海賊たちであり、その祖先が王となったこの歴史を悪しき野蛮と言いきれないと思うからです。
野蛮さは自由であることから生まれる。自由であるのに、野蛮でないと主張することは詐欺師と同じである。自分自身も、野蛮さを濾過しようとしている。例えば、五輪貴族に対してオリンピック開催を反対することも、その一つであるということを知り驚いた。自分の野蛮性をどのように濾過しているのか振り返ることができた。
宮廷・市民などの階級による分断(区分・区別)がなくなったあとに、人種による市民の分断が科学的な形で行われていったという話を聞きながら、「人種差別と闘っている現代社会は、王政と闘っていた遥か昔と変わらないのか」とぼんやり思った。作り続けられる社会の階層(階級や人種)の戦いが終わらないのは、先週のコメントにあった通り、「権力が相対的なもの」でしかないからなのだろう。現代で生じている、人種や性別による差別が解消されたのち(人種での区別が意味をなさなくなったとき)、次はどのように人々の階層を、私たちは分けていくのだろうかと気になった。

これまでの議論を踏まえると「真なる自由」を求めるとき、野蛮さは切り離すことはできないことは理解していただけると思います。ですが、「自由」というものは”崇高な”理念として語られることが大いにあり得る…この野蛮さが崇高なるものになるとき――取り繕って「奪う」ために「濾過」が行われる、とフーコーは説明しているのですね。この「濾過」は「正当化」と言い換えてもいいように思えます。
ワクチンをうつ「自由」もあれば、ワクチンを打たない「自由」もある、とされていますが、感染拡大を防ぐためには集団免疫を持つことが必要になってくる、ということも同時に指摘されていますよね。そのうえで、「自由」であるというのであれば、ワクチンを打っても打たなくても制約が生じないようにしなくてはならないはずです。ですが、「ワクチンパスポート」などが発行される経緯をみても、そこには「野蛮さの濾過」とワクチンを打たない人に対するエクスクルージョンが見て取れるように思えますね。
また、最後のコメントについては、そもそも差別とは解消されるものなのかという論点と、もし現在されている差別が解消されても、また別の差別が生まれるのではないか、という二つの論点を提示しているように思えますね。際限ない戦争関係、というものをここから考えさせられるような気がします。
第十講| 一九七六年三月十日「闘争の市民的背景」他 /2021年7月27日
担当:M先生
当日資料はこちら
当日リポート
オリンピックも開幕し、ついついハラハラもしながら、わくわくもしながら観てしまう今日この頃ですが、そんな中で、講読会も終わりに近づきつつあります。
今回はチャットのコメントからの質問をきっかけに議論が進んでいきます。
まず一つ目は「歴史の語り方は、過去から現在に語る方法と、現在の起こっていることの起源を探るということで過去に遡るという方法の2つがあるということでしょうか。この2つは同じことをしているように感じるのですが、違いはあるのでしょうか。」という質問でした。
テクストの中では、二つの解読子として紹介されていたものが「過去から語る歴史」と「現在から語る歴史」に相当しています(225頁あたりからが該当)。似ているのは当然かもしれず、どちらも<誰が国家を統治するのが正当といえるのか>を説明しようとしています。
まず過去から語ろうとする歴史は、これまでフーコーの講義の中でもしばしば取り扱われてきた歴史言説とほぼ一致するものです。それは、ローマ法の継承など、過去から引き継がれてくるものに統治の正当性を求めてきたものでした。そして今回はモンロジエという人の歴史言説がその典型的な例としてテクストの中で紹介されていました。そこでは絶対王政が貫かれ、(革命を経ることで)国民たちが王位を引き継いだ――いわば、みんなが王になった、というような形で完成する歴史として説明されていたようです。
一方、現在から語ろうとする歴史は、ブルジョワ革命の主体となる第三身分/ブルジョワ自身に、そもそも国家を統治する正当性があったのだ、という「今、普遍的な存在として国家を治めている」という事実から立ち返っていこうとするものになっています(ここでは、ティエリの言説が例として挙げられていました)。なるべく存在として、第三身分が自らを統治する主体となった、と説明されていくものです。
「過去から語ろうとするスタイル」は、王位を奪うという意味で闘争状態はずっと続いていくものですが、実は「現在から語ろうとするスタイル」は第三身分/ブルジョワである存在そのものに民主主義的な機能を持ち備えていた(「職能」と「装置」を通じて:219頁)ことを主張するものです。ところがその機能を発揮することが/統治可能性は、これまで妨げられ続けてきた…と理解されるようになるのです。
「人民は統治できる(正)」が「人民は統治される(反)」という対立に対して、人民に内在する統治可能性/現実に統治の機能を果たしている事実を通じて、自分たちに内在する正当性を主張していく(合)こととなった―――それこそがフーコーのブルジョワ革命の理解とみなすことができるもの、と説明がされていたように思います。そして、統治の正当性を「内実」ともに果たすものとして「民族」が定義し直されたことも指摘されていたように思います。
二つ目の質問は「国家をうまく機能させるために『人種』があるということでしょうか。つまり日本という国を機能させるために、日本人というのがあるということでしょうか。」というものでした。
この、「国家をうまく機能させる」ために、「職能」とそれを機能させる「装置」を調整することが求められるようになった、ということがフーコーの議論の中では指摘されていたのではないか、とは確認されました。
そのようにとらえると「日本人」という概念も、日本という国をうまく統治するために生み出された枠組みに過ぎないと説明できるかもしれません。「日本語を話す人」や「日本円を使う人」という存在は確かに存在するかもしれませんが、「日本人」という概念は、社会を統治していく過程で行われた正当化のロジックの一つと説明できるのかもしれないからです。
その意味では、オリンピックも「装置」の一つと言えるのかもしれない、ということも確認されました。活用する主体によって装置としての性格は異なってくるかもしれず、例えばこの装置は、ナショナリズム的一体感を生み出したり、経済的利益を生み出したり、政治的優位な立場をある特定の集団にもたらそうとする形で機能しているかもしれないわけです。
最後に「市民の闘争性」という議論についても確認されました。Citizenshipというものには備わる闘争性、について指摘がされていましたが、その背景には、「市民」ではない人などいないはずなのに(どんな意地悪な人でも、嫌いな相手でも確かに市民のひとり)、なぜか「市民」として活動しようとするとき、仮想敵が想定されたり、”連帯”する場合も相対していく相手を想定するという不思議があります。そこには内的な緊張が発生している可能性があるのです。ある意味、「市民の闘争性」が問われるようになったこの段階は、残酷な機会としてとらえられるのかもしれない…、という議論を以て今回の講読会はいったんお開きとなりました。
この「市民の闘争性」に連なる議論が、次回の最終講にもつながっていくのではないかと思います。長いようであっという間にもう最終回ですが、みなさんと引き続き議論していくことができることを楽しみにしています!
参加者の皆さんからのコメント
歴史を語ることには過去から現在と現在から起こっている起源を遡る2種類あるという話が難しく感じた。高校で社会の授業で日本史を選考していたが歴史を学ぶにあたって過去から現在を辿っていく方法で学習していた。先生が補足でこのことについて説明していたがしっかりと理解することができなかったため、自分でも調べてみようと思う。また、人間(人種?)が多数存在しなければ国王などの権力者も存在しないということになるほどと感じた。身分差ができるにはさまざまな特徴を持つさまざまな人種がいないといけないと当たり前ではあるが今回の講義で改めて考えさせられた。
今我々が生きている世界は、全て「歴史」によって語ることができるが、歴史の語り方には2通り存在し、それぞれの違いことを改めて確認できた。そして、「国家=王」という流れにより、王が自分の支配を正当化していた絶対王政の時代から、人民が革命によって、一人一人が王となる民主主義の国民国家を形成し、それがフーコーの言う「絶対王政の完成」へとなったことを学んだ。
支配の正当化の方法は2つあることを知り、また同じように見えるが本当は異なるということを学んだ。1つ目の解読子では、全員が王様になるという点で、自由を謳歌して良いことになってしまう。しかし、2つ目の解読子では、もともと自分たちの中に民主主義があったという考え方がであり、それが発露していったと考える。ここに違いが見られる。
国家を統治するために『日本人』という概念が生まれた」という先生のコメントがあった。我々が同じ日本人という自覚を持ち始めたのは、明治以降の富国強兵の流れによるものだった。しかし、この「○○人」という枠組みで国民国家を語ることには差別が伴う。日本列島に住む人間が「日本人」であるとすると、それはアイヌ民族まで日本人に同化させることになり、アイヌ人に対する支配・差別になると感じた。
「市民は闘争的である」という話が印象的でした。国家をうまく機能させるために作られた枠組みが「内」と「外」をつくりだし、内的緊張を生んでいると解釈しました。また、その枠組みの定義が曖昧であるため、人によって解釈・区別が異なります。だから、同じような考えの人とコミュニティをつくって仮想敵に対抗しているのだと考えました。

「市民、国民のみなさん」という呼びかけを聴いていると、その発言主は自分自身を”市民”や”国民”の一人と認識しているのだろうか、と思わさせられてしまうようなこと、ありますよね。それが「市民」という言葉のもつ不思議と難しさでもあります。フーコーは、それぞれの個人が生きるとき、「統治する/統治される」という枠組みを超えた、主権的なものではない形を提起していこうとしたのだと思われます。
また、フーコーを読んでいると「歴史の生かし方」についてなるほどと考えさせられることがたくさんありますよね。構造化されているものから、今を見抜いたりしていく技をフーコーに見ることがあります。フーコー自身も挙げられていたような二つの見方を生かしながら歴史をみていたのではないでしょうか。
「日本人」という言葉が、どこまで、どの国土が誰の者で、そこは「日本人」が治めなくてはならないのだということを正当化していくためのロジックとして用いられていたといえるかもしれませんね。日本語を話しているかどうか、とか日本円を使っているかどうかとか、そういうことだけではなく、様々な点を相当洗練させて「正当化」を行っている――野蛮さの濾過をしているといえるでしょう。
citizenshipについても、私は否定しているわけではないのです。むしろ、我々が守っていくべきものは、このcitizenshipに他ならないようにも思います。私たちはすべて、何か野蛮なものを濾過して正当化して生きているわけです。その守るべき対象としてある「市民」の概念も、そもそも血塗られた歴史を通じて確立してきたものであるということを忘れずに、考えていかなくてはならないような気がしますね。
第十一講| 一九七六年三月十七日「生権力の誕生」他 /2021年8月3日
担当:H松さん
当日資料はこちら
当日リポート
柴田先生が撮影してきてくださったお台場の聖火の動画を観るところから始まった今回の講読会。揺れる炎を写真に収める疎らな通行人、プラカードを掲げるスタッフの方、揃いのTシャツで周辺を歩くボランティアスタッフの方々、そして、「ソーシャルディスタンスを保ちましょう…」と繰り返されるスピーカーの音声…。こうして始まったオリンピック。聖火は、何のために守られているのでしょうか。
長いようであっという間だった今回の講読会も最終回。今回も活発にご質問をいただきながら議論が展開されていきました。特に講読会の時間中の議論は、「人種主義」にまつわる話でした。
- 「P.5(レジュメ)の生物学的な関係は恐ろしい考え方だと思いました。集団虐殺を促すことになってしまうと思いました。」
- 「人種主義は社会主義の国だけでなく、資本主義の国に受け継がれてしまっていると思います。形を変え、対象を変え、でも本質的には人種主義なことが現在でも多くあると思います。」
- 「人口、『人間という種』という概念が生まれたことで、マジョリティとマイノリティができ、『平均、基準内』でない者は『死』意味することになるということでしょうか。」
そもそも、フランス人貴族たちが扱っていたような「民族」という歴史的な概念は、フランス革命を境に当初のような意味合いは失われていきました。そして、「市民」が生まれたのです。みんなが”自由”であって、みんなに”権利”が認められるような、そういう社会が認められたはずだったのです。
ですが、その「市民」という概念を支える背景には、内的緊張があった、と確認されます。「生きる」ということを担保に国家を統治しようとき、「生きる」ためには、奪わずにはいられない、という現実があったのです。
市民社会において、自由を謳歌しようとする「ジャイアン」的存在は認められないはずでした。しかし、「生きる」ためには「奪う」ことが不可避。「奪うことの正当化」の結果、生まれたのが「人種」と呼ばれる概念であった、ということが説明されていました。同じ市民の中で内的緊張を生み出し、「科学的」な差を理由に(例えばナチスドイツがユダヤ人虐殺の根拠としたのは、『出生率の高さ』であった、と言います。それ以外にも所得や犯罪率など、数値で示されるものによって)人口を管理する”線引き”がなされていったのです。
- 「東京オリンピックに関しては、生きるとか死ぬ(殺す)とかいう議論の前に、国際協調とか文化的な側面が強いと思うので、あまり私の中では結びつきませんでした。良くも悪くも、そこまで、個体とか人間とかは意識していないんじゃないかなと思います。」
- 「人種主義というのが、今一つ切実に、ピンときません。ナチスが台頭してさまざまな人種・民族が行き交ってきたヨーロッパならではの概念のような気がします。日本人の単一民族という『神話』にすっかり惑わされてしまっているからでしょうか。」
- 「ナチスやハンセン病患者に対してもそうですが、政治と『医学的根拠』が合わさると、我々は容易に信じてしまうと思いました。」
フーコーがいう「人種主義」というものは、もしかしたら今でいえば性差に関する議論に置き換えてみると理解しやすくなるかもしれない、という解説もされました。今回のオリンピックも女性種目の競技に出場するためには、「血中のテストステロン値(ホルモンの一種)」が一定の規準に収まる必要が条件になったといいます(関連記事として_朝日新聞2021/7/16などがあります)。
つまるところ、内的緊張をどのように生み出すのか、ということが「奪う」ためのmethodの一つとして持たれるようになったともいえるのかもしれません。
こうした形で発動する権力は、かつての法権=主権的権力の「生きるに任せ、殺す」権力とは異なる、生かすことをコントロールする権力(生かし、死ぬに任せる)でした。この新しい権力は、国家の安定のため、”どう”生きるのか、生き方を誘導しようとしたのです。生かし方のコントロールの方法として、個人を対象とする規律型権力、そして集団を対象に数/数値でコントロールしようとする調整型権力がテクストの中では紹介されていました。
今回のフーコーの講義は、フーコーが講義を続けていく中で、まさに「降臨」してきたような発想が堰を切ったかのように溢れ出たような印象を受ける、といった話もされました。前回の講義内容から、ガラリと異なる雰囲気で講義が始まるように見えるのは、その所為なのではないか、と。
生権力とは「何のために」「誰にとっての」”自由”を求めているのか、なぜ、奪おうとするのか――。そんな問いも新たに想起させられつつ、改めて、現在の日本が直面している状況を振り返り、現行の政治の舵は「何を守ろうとして」とられているのか、考えさせられました。思わず「うーむ」と唸らずにはいられないような気もします。
皆さんはいかがでしょうか。
私たちは、何かを守ろうとしたり、また何かを奪いながら生きているのかもしれません。そこで、だれもが自分自身の「自由」を守るための「正当化」を、<野蛮さを濾過>することで、果たしてきているのかもしれません。自分が何を守ろうとしているのか、自分がその「何か」を守り通すために、どんな「正当化」をしてのけようとしているのか――少しでも自覚的になりながら、生き抜いていけたら…と個人的に思いました。
また、みなさんと次回のまなキキオンライン講読会をご一緒できることを心より楽しみにしております!ご参加くださった皆様、ありがとうございました!
最終回の「当日リポート」について、加筆すべき点・修正点・コメントなどありましたら、ぜひご連絡(コメント)くださいませ!