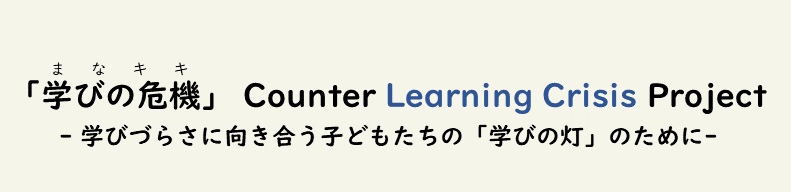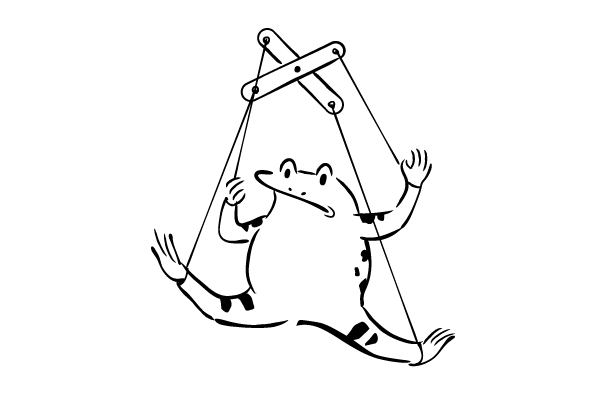▶ を押すと文が増えます

- ユルくみんなで読むフーコー スペシャル・イベント
- 講読会について
- 第一講| 一九七八年一月十一日「生権力の研究」 他 /2021年10月19日
- 第二講| 一九七八年一月十八日「一般的特徴」 他 /2021年10月26日
- 第三講| 一九七八年一月二十五日「安全における正常化」 他 /2021年11月2日
- 第四講| 一九七八年二月一日「多様な統治実践」 他 /2021年11月9日
- 第五講| 一九七八年二月八日「統治性の研究」 他 /2021年11月16日
- 第六講| 一九七八年二月十五日「司牧の分析」 他 /2021年11月23日
- 第七講| 一九七八年二月二十二日「良心の指導」 他 /2021年11月30日
- 第八講| 一九七八年三月一日「『操行』概念」 他 /2021年12月7日
- 第九講| 一九七八年三月八日「司牧制から政治的統治へ」 他 /2021年12月14日
- 第十講| 一九七八年三月十五日「国家理性の定義」 他 /2021年12月21日
- 第十一講| 一九七八年三月二十二日「新たな統治術」 他 /2022年1月11日
- 第十二講| 一九七八年三月二十九日「テクノロジーと内政」 他 /2022年1月18日
- 第十三講| 一九七八年四月五日「生 - 権力の誕生」 他 /2022年1月25日
セキュリティ、国家、人間、DX、AI…全てが揺らぎ、また塗り替えられつつあるNew Nomalの時代に、私たちの拠り所となりえる思想は何か―。
ミシェル・フーコーの生-権力論の「核心」を元に論じ合います。
※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
(どなたでもご参加いただけます!)
講読会フライヤーPDFはこちら
ユルくみんなで読むフーコー スペシャル・イベント
“Learning Crisis”とは、何だったのか?2021版
2021年11月23日 16:30-17:50
講師:柴田邦臣(津田塾大学学芸学部/Learning Crisis研究会&まなキキプロジェクト代表)
お申し込みはこちら
ちらしPDFはこちら
講読会について
講読書籍
『領土・安全・人口』, ミシェル・フーコー著, 高桑 和巳訳 筑摩書房(2007年)
講読期間
2021年10月19日(火)~2022年1月25日(火) 全13回
開催時間
18:00-19:30ごろ(入退室自由)
参加方法
ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。
- ①一般参加会員
その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。
当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員
継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。
講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
※ 参加登録は一度のみで完了いたします。
※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。
お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加
特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。
一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。
ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。
お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!
第一講| 一九七八年一月十一日「生権力の研究」 他 /2021年10月19日
担当:M先生
当日資料はこちら
当日リポート
まなキキオンライン講読会の第4弾もいよいよ始まりました。
夏の講読会に引き続き、21世紀の社会科学に大きな影響を与えたという、哲学者であり社会学者でもある思想家、ミシェル・フーコーの講義録に取り組みます。
特に前回の講義は、まさに「生権力」を概念化しようと取り組んだものでした。
今日の議論では、より「生権力」にフォーカスを当てた内容となっていましたが…
議論は「誰にとっての安全」なのか、という話から展開していきます。
これは、フーコーが権力の技術として「法」、「規律メカニズム」、「安全メカニズム」を挙げ説明してきた、という内容を受けてのものでしたが、特に、今回は「コロナ下におけるマスク着用は、一部の人にとっては、息苦しさや肌荒れに繋がってしまうものにもなりうるのではないか」という疑問から展開していきます。
議論を通じて、実は「マスクの着用」はCOVID-19のオーバーシュートを避けるためには不可欠で、協力的でない主体は許されないようなもの――すべての主体がマスクをすべきものとみなされるような、そういう種のものだったのではないか、と説明されます。
皆が自ら進んでマスクを着用したり、マスクをきちんとつけられない人を非難するくらい、自ら選択してマスクを着用している――これはまさにフーコーがいう「規律メカニズム」的な権力が発動しているものなのだ、と説明されます。
コロナ下において、国交に制限が課されたり、検閲が置かれたりするなどの対応がなされました。これは、おそらくフーコーのいう「許可」や「禁止」を求める「法メカニズム」に由来するものです。
しかし、法の力だけではCOVID-19の感染拡大と対峙できない、ということは皆さんも身をもって感じられてきたことと思います。そこで活用されているものが「生権力」であったのだというのです。
生権力は、自分が生き残るために、「規律」を内面化して、人々が積極的に自主的に期待される行動をとるように発動されるものといってもいいのかもしれません。
前回まで読んできた『社会は防衛しなければならない』も、もともとこの権力のメカニズムに注目したものでしたが、終盤で、ちょっと違った形で権力が現れてきている…いわばフリーザの第三形態ならぬ、権力メカニズムの第三形態があったのではないか、と指摘するのです。
自らが選択的にある行動をとるのではなく、人々がある行動をとるよう促していくような権力のありかた…それに注目しようとしたようなのです。
権力の第三形態なるもの―安全措置は、ワクチンの例をとると分かりやすくなるかもしれません。ワクチンを「ぜひ打ちたい」と接種した人たちもいたと思いますが、そこまで強く望んで打ちたいと思っていたわけではないが、接種に至った、という人も多かったはずです。現在は、アメリカに入国するためにはワクチン接種記録が求められるようにもなっており、明らかにワクチン接種を促すよう”環境”をコントロールしているといえます(テクストの中では、天然痘の「医学キャンペーン」が例に挙げられていましたが、まさに、なのかもしれません)。
ワクチンを打ったらライブに参加できるとか、何かご褒美があるといった報酬を用意することも、「ワクチン接種」という結果を得るために、人々が自然にワクチンを打つにいたるよう環境を整え、誘導していく…そうした権力の技術の一つのありようとして説明されました。
生権力は、人々を「生かすための権力」です。規律メカニズムは本人が主体的に選ぶよう監視や矯正の枠組みを用意していましたが、安全装置は個人の意識していたかどうかを問わず結果に結びつけるような誘導を可能にする環境セッティングの技術、といえるのかもしれません。
コロナ下における方策として、経済的な側面からみれば、「Go to キャンペーン」も、安全装置のひとつかもしれません。
コロナに関わらなくても、もしかしたら、私たちが大学で学ぶということも、「それが当然」という雰囲気に流された結果――そのような環境に誘導されて至ったもので、主体的な決定に依るものではないのかもしれない!?、という議論にも至ります。
なんだかドキッとするような話ですが、「自分の意志で決めていることって、いったい何があるのだろう」という声も、参加者の方の中からは聴かれました。
「生権力」に抗するということがどういうことなのか、自分の意志や主体的な決定とは、本当にありえるのか…いろいろ考えてしまいますが、ここから始まる講読会を通じて、皆さんと考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします!
参加者の皆さんからのコメント
COVID‐19を例に話をしていただいたことで、今回の内容が少しわかりやすくなりました。みなさんのお話を聞きながら、3つの形式のうち1は中国?、2は日本?(自粛警察警察の例えに納得です)の社会のようだとかんじました。3については、環境に介入してヒトの意識を変えていくという例えでワクチンパスポートの話が出ていましたが、「特典と引き換えに安全へと誘導する装置を用意する」という介入の方法以外にも、「個人がワクチン接種に納得が出来ない場合は、PCR検査を受けて陰性証明を取る・公費で隔離期間を保障される」などといくつもの選択肢を用意し、より個人が自身で「自分と他人の安全を意識できるようになっていく」という、誘導に依らない介入の方法もあるのではないかと思いました(実際にこのような提案の声も出ているかと思います)。この2つの介入の方法の違いは、「安全」というものを、個人が公衆衛生という視点で自覚できるようになれるのかどうかということにあるように思います。権力側が、個人の意識の変化を育てようと思っているのかどうかといった感じでしょうか。M先生がレジメの最後に書いていた「民主主義」ということばにかかわってくることなのかなぁとぼんやりと思いました。・・・COVID‐19に例えることで、わたしがフーコーの主張の読み取りを間違えているかもしれません。すみません。
今回初めて講読会に参加して、正直とても内容は難しかったのですが、柴田先生のお話を踏まえてcovid-19の問題で考えてみると、ソーシャルディスタンスやgotoキャンペーンなどの規律権力や環境への介入に関して少し理解できたような気がしました。
アレクサンドル・ル・メートルの国家を建造物に例えているのが興味深かったし、フランス革命期と第一身分~第三身分の役割が違っていて面白いと思った。都市の構造と権力の関係を理解するのは難しかったが今まで見たことのない視点で学べた。安全とは何なのか、今のように安全安心を訴え訴えられる時代に考えるべきことを学べたと思う。
自分自身の実感としても、ワクチンに関しては自分の意思で打ったのか、見えない誘導のようなものが働いたのかわからない部分があり、今回のテーマは特にタイムリーな内容だったと感じました。
周りの環境をコントロールすることによって人々を上手く誘導させるという「安全装置」の施策は、これまで自分が認識していなかっただけで、無意識にたくさん行われていることに気がついた。大学受験も就職活動も大変でやりたくないのが本音だが、それでもやるのは大卒というステータスを手に入れたり、お金を手に入れるためという、生きる上で必要不可欠であったりより豊かに生きるためであり、人間の「生」への欲求が社会や経済の基盤になっていることが分かった。

第三形態とは、まさに洗練されたバージョンのことを指しますが、安全装置がそこに該当してきます。安全装置とは、まるで「そんなものがある」とは思えないようにひっそり、駆動しているものなのです。
安全装置は、フーコーが例に出していたり、COVID-19に置き換えて考えると大変分かりやすいとおり、公衆衛生の観点からみると非常に理解しやすいところがあります。ですが、実は安全装置が射程にいれる対象は、実はもっと広く深い文脈で、自分たちが生きていくこと、この社会で生きていくことと直結していくようなものと捉えていく必要がありそうです。
生権力にはおそらく2種類のものがあるということ、その一つが規律メカニズムでありもう一つが「安全装置」です。「安全装置」は、特に、社会の形を新しい形に変え、強力に駆動しているものと考えられます。ですから、ワクチンを接種するか、PCR検査を受けるか、隔離期間を設けるかという選択肢が与えられることで安全装置という権力メカニズムから逃れられているというのではなく、そうした「自らが選択している」と思えるような余白も残したうえで安全装置が機能していると捉えるほうが適当かもしれません。安全装置とは、より深い階層で機能していて、個人がCOVID-19に対してどのような態度をとるのかということまでを記録・管理しようとするものなのです。
実は、それを最も効率よく洗練した形で実施しているものが中国なのかもしれません。私たちの「生き方」はすべて記録され、新たな行動を生み出すシステムとして加担していくことになってしまう。民主主義が成立しているかのように見えて、「安全装置」ありきの社会、という土俵に乗らざるを得ない…そういう状況があるのかもしれません。
第二講| 一九七八年一月十八日「一般的特徴」 他 /2021年10月26日
担当:ぱんこさん
当日資料はこちら
当日リポート
今回の議論は、特に、「人口」という水準と「個人の群れ」という水準で分断がなされ、安全装置は「一部の人々や一部の市場の何等かの不足・高価、困難さ、何らかの飢餓」によって、”安全”(今回のテクストでいえば、「食糧難は空想の産物」といえるような状況)がもたらされる、という点に、衝撃を受けながら展開していきました。
安全装置および統治の政治経済学的活動にとって「適切」とされる水準は「人口」とされ、一方「不適切」とされるものが「人民」として表現されていましたが、なぜ、「人民」は「人口」から逸脱しようとするのか?という疑問も挙げられました。
いわゆる「人民」とは、フーコーのテクストの言葉でいうと、
「まさに市場において、また特定の都市において、待つということをせず、不足に堪え忍ぶということをせず、穀物が高いということを受け容れず、自分が飢えることを受け容れず、価格が下がるのに充分な量の麦が到着するのを受け容れない。人々がそのようなことを受け容れず、穀物の備蓄に飛びかかり、対価を払うこともなくこれを手に入れる。また、非合理的で計算違いの穀物の売り渋りをする人々」
のことを指していました。
ここで人民と称される人たちは、「生きること」にかかわるが故に、安全装置に抗い、逸脱するわけです。そして、その人民は、「人口の安全」や安全装置というシステムを”狂わせる”ものとみなされ、問題視することになった、とフーコーは指摘しています。
これは、今回のCOVID-19感染症拡大下に置き換えても捉えることができてしまうようなものでもありました。
コロナウイルス感染症によって命を落とした方々がたくさんいらっしゃるということ。そうした方々の死を「規律メカニズム」的な見方で「本人の問題」として還元しようとする声も多くありました。ですが、実は起こった出来事は、「安全装置」の働きによる帰結として捉えるられるもので、その現実から目を背けてはならないのではないか、 ”人口の安全”を保とうとした結果、起こった出来事であったということを、忘れてはならないのではないか、という話にも至りました。
「生きること」を求めて、安全装置的なものに抗おうとすること――「生きるための闘争」は、本来、「基本的人権」として貴ばれ、尊重されるべきことだったはずですが、もはや安全装置の下では、「逸脱」になってしまう…。そうした皮肉な現実を突きつけられたことも確認することになったように思います。
社会を、安全装置として機能するようデザインしていくこと…これが第三形態としての新しい権力のあり方であったといえるのかもしれません。
一方で、『社会は防衛しなければならない』の中では、「市民」という言葉が使われていたが、それが「人口」という言葉に置き換えられたのか、という点についても指摘が挙げられました。
『社会は防衛しなければならない』の中で、市民は「自由」のために闘争し続けて、その末に「市民社会」が獲得された、ということが最後に指摘されていましたが、市民社会の獲得と同時に闘争していく「敵」を失ったことも意味していたことがポイントとなっていました。
ところが、権力を求めたり、闘争を求める「自由」――ジャイアン的な生き方は、許容されません。代わりに、あたかも皆がジャイアン的に生きられているかのように錯覚できる「自由’」を保障する「安全装置」がシステムとして求められたのだ、ということも改めて確認されたように思います。
本当の意味での「自由」が成立する社会というものはありえず、「真の市民社会は到来しない」というやはり皮肉な現実が確認された、ともいえるかもしれません。
一方で、皆にとっての「危機」のようにみえるCOVID-19に代表されるような出来事は、「安全装置」というものがどのように駆動しているのか、顕在化させることにも至ったわけです。その意味においては、実はCOVID-19は、「安全装置」にとっての「危機」にもなっているという指摘もされました。
ポスト・コロナやウィズ・コロナの社会における「安全装置」は、まだデザインの途上にあるともいえるかもしれず、私たちもこの文献を通じて、新たな展開が起こる瞬間を注視していけたら、と思います。
参加者の皆さんからのコメント
初めて参加したのですが、自分はこのような類の本をあまり読んだことがなかったので学びが多かったです。covid-19のような危機が無ければ安全装置のようなものの存在が見えなかったかもしれないというところも面白かったです。コロナ禍の状況に置き換えることで、難しく感じる文章からでも現在の社会を見ることができるのだと思い、しっかり読めたらいいなと思いました。
今日の講読会に参加して、このフーコーのテキストに描かれていることは、全てワクチン接種など、現在のコロナ禍に当てはめて考えることができると感じた。これは、コロナ禍という危機的状況の中で、社会の様々な課題や問題点が浮き彫りになるためであり、ポストコロナやウィズコロナの社会を考えると、社会の分断がより加速してしまうのではないかと思った。
社会という統治システム、安全装置にとって「適切」であるのは人口であり、人口から意思を持って逸脱する「不適切」な者が人民であるということが分かった。また、安全装置の設置を成り立たせるためには、人口からの逸脱者よりも、人口という集団的対象・主体の一部として振る舞う者のみが必要であることを学んだ。

まとめの中にあった「自由’」のことを、私は「擬制」と表現していたりしますが、結局本当の意味での「自由」は成立していないということ――「自由」がもたらされているようにみせつつ、人口を管理し調整するのが、安全メカニズムなのだということを確認したのがこの回の内容でしたね。人口が損なわれない形での「安全」や「自由」が保障されている、といえるのかもしれません。
COVID-19の感染拡大と関連付けてみることで安全装置の理解もより深められているような気がしますね。生権力にしても、安全装置にしても、政治的存在として振る舞う「人民」を嫌うわけですが、安全装置が駆動しているとき、「政治的に自らが選択した」と思わせて、安定が維持されたりします。つい先日の選挙でも、そうした安全装置が機能している様子をうかがえるようなきがしますね。本当にまずいような「危機」的な状況であっても、「政治的主体であること」が、うまく「調整」されてしまう、ということも否めないのかもしれません。
第三講| 一九七八年一月二十五日「安全における正常化」 他 /2021年11月2日
担当:H松さん
当日資料はこちら
当日リポート
今回の議論は、「正常化」という論点に関して、規律メカニズムと安全メカニズムの機能の仕方はどう異なるのか、その区別の仕方が大きなテーマになっていました。
特に、H松さんがレジュメの中であげてくださっていた「就活生がグレーや黒のスーツを着用することは、規律メカニズムによる正常化なのか?」という疑問について考えていくことから展開していきました。
規律メカニズムと安全メカニズムの区別の仕方は分かりにくくもありますが、見分ける際のポイントは、正常の分布に近づけていこうとしているのかどうか、という指摘もありました。
今回のテクストの中では、78頁のとおり、
正常化という操作は、このさまざまな正常性の分布において、ある正常性を別の正常性と作用させ、最も不都合な正常性を最も都合のよい正常性に近づけるというもの
と説明されていますが、これに関して、女性の働き方が例として説明されていました。
女性の就労率は、M字カーブを描く(妊娠・出産を機に就労率が下がり、再び回復)と指摘されていましたが、それを男性の就労率(常に高い就労率を維持する傾向)に合わせるように――「正常化」させるように、働きかけていく、ということがあるわけです。
もちろん、女性の就労の機会が広がることはよいことかもしれません。しかし、M字カーブを描くような就労のあり方が悪いとも言い切れないかもしれないのです。男性の就労率のほうが、M字カーブを描くように変化する選択肢だってあってもよいのかもしれないのです。
しかし「社会的標準」に近づけていこうとするように「正常化」は行われ、女性の就労のあり方は、より男性的な働き方に近づきつつあります。これを安全メカニズム的な「正常化」として説明できるものと、議論がされました。
(採用率がより高く、「正常」とされるのは、グレー/黒のスーツを着用した就活生だと捉えれられていたら、グレー/黒のスーツを着ることは、「安全メカニズムによる正常化」といえるし、グレー/黒のスーツを着用するべきだといった規範が内面化されたと捉えれば、「規律メカニズムによる正常化」とみなせるのかもしれません。)
規律メカニズムが、「倫理」的なものや「道徳」的なもの…「規範」を起点として、そこに人々を合わせていくよう教化したり、禁止していくような形で「正常化」をめざしたわけですが、
安全メカニズムにおいては、特定の何かが「禁止」されているわけではないものの、”よりよい”方へ、より”正常”とされる方向へ競い合うように行動やあり方が修正されていく「正常化」が、両者の違いとして説明されていたように思います。
議論の中で、「今のワクチン接種の状況とあまりによく似ていることに驚きました。私たちは日々感染者が何人とか、接種率が何%だとか、常に統計的、人口的な情報にさらされています。『安全』は、一人の権力者や政府が一元的に管理するのではなく、それこそ公衆がお互いに監視し合うような、網の目を張るような仕組みの上に成り立っているような気がします。」というようなコメントもいただきました。
COVID-19感染症拡大下においては、まさに、「社会的標準」とみなせるような数値を「正常」と見なして、そこに向かっていこうとするようなありよう―安全メカニズム的な「正常化」と規律メカニズム的な「正常化」が組み合わさった、生権力が発動していたともいえるのかもしれません。
また、安全メカニズムにおいては、「欲望」がどのように扱われたのかも、従来の権力のメカニズムから大きく異なっていることも指摘されていました。
法律で禁止したり、例えば「禁欲的であること」が善きこととされ、「道徳」や「規律」の形で教化・調教されてきたようなものが従来の法律・規律権力のあり方でした。
ところが、安全メカニズムにおいては、「『欲望』のまま」生きることが「正常」として扱われます。ただし、議論の中で、その「欲望の発露の仕方」が安全メカニズムによってコントロールされている、という指摘がありましたが、これは注意を払うべきポイントかもしれません。
「出世すること」や「地位を得ること」、「おいしいものを食べること」や「心地よい環境」で、「おしゃれでかっこいいものに身を包み」生きたい、といった形での『欲望』は巷に溢れていますが、その『欲望』は、「欲望」が枠づけられ誘導された結果、と言えるかもしれないのです…。
本当の意味で望んでいること…「政治的存在」として振る舞うことや、本来貴ばれるべき基本的人権である「自由」を求めるような「欲望」が、安全メカニズムにおいて許容される範囲内の『欲望』に調整されてしまっている可能性が指摘されたともいえるのかもしれません。
安全メカニズムについて、フーコーは今回のテクストの中で絶賛も批判もせずに、淡々とそのありようを説明しているわけですが、この権力装置をどう理解し、捉えていけばよいのか、引き続き考えていきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
今回、はじめてこのイベントに参加させていただきました。初めて参加してみると、とても興味深く、思わず何度かコメントさせていただきました。結構難しい内容ではあったのですが、コメントに返答いただいた際の解説などを聞いて理解できたことも多く、とても勉強になりました。現在のコロナの右往左往する政府の対応などもこの正常化と規律・規範の考えに置き換えて考えると、さまざまな面において納得できることが多く、私は経済学部ですが、社会学にさらに興味を持ちました。このような本を自主的に読んだことがあまりなかったのですが、このように解説をしていただいたことによって理解できました。普段はこの時間にアルバイトがあり初めての参加でしたが、前回の振り返りなどもしていただき、今回が初めての私でも参加することができました。時間のない中でコメントにも触れていただき、実のある時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
規律型権力が絶対的なものであるのに対して、安全装置はより良い方をとるものであると理解した。天然痘の話を、コロナワクチン接種に置き換えて考えてみて、今フーコーのテキストを読むことの重要性を感じた。
正常が先にあり、そこから規範が演繹されるという事に非常に納得しました。正常化を称した規範化は、ただの分離になりかねず、規範を演繹する際に考慮した「正常」についての理解が無ければ本質的な正常化にはなり得ないのだと考えました。そしてこれは正に現代の問題であると感じました。様々な問題において規範的に分離されたり更には糾弾されたりすることが多い現代ですが、それの前提条件となる「正常」に目を向けて正常化することが問題だと学びました。
『自分の「欲望」は安全メカニズムの範囲内で調整されているものかもしれない』という話にはっとしました。目に見えるもので、それの存在が一種のステータスとされるようなもの(ハイブランドの洋服・化粧品など?)は特に社会的に作られた「欲望」なのではないかと思いました。

安全メカニズムの「正常化」に関して補足すると、最も”不都合”な正常を、より”都合のいい”正常に近づける、というふうにとらえられる良いかもしれませんね。ここで重要になってくるのは「誰にとって」都合がいいのか、ということになりますね。例えば女性のM字就労が男性の就労率に近づくと社長など雇用側にとって都合がいいわけですよね。貴重な戦力を継続してずっと雇えるわけですから。でも、男性もM字就労のカーブを描くようになったらもしかしたら、子どもたちとしては大喜びかもしれないですよね。
生権力において、私たちは「規範的に生きようとする主体」として見なされているといえます。逆に法的権力においては、私たちはむしろ法律を犯す恐れのあるような対象とみなされているわけで、決して規範的主体とは想定されていない。しかし、生権力においては、「規範的な主体」とみなされているのです。そこでの「規範」とは何か。「正常」はどういう都合でどう作られているのか、ということを考えさせられますね。前回は「欲望」に関しての言及もありましたが、これはこの先も非常に重要なキー概念になりそうです。私たちにとっての「欲望」を疑似的に成立するシステムとしての安全装置が提示されたわけですが、ここからは、その安全装置を具体的に実現する統治術に着目し、なぜ、どのように力を持ったのか、その源や源泉をみていくことになります。
第四講| 一九七八年二月一日「多様な統治実践」 他 /2021年11月9日
担当:大学生Mさん
当日資料はこちら
当日リポート
今回の講義は、マキャヴェッリの『君主論』を引き合いに出しながら、「主権」と「統治」がどのように異なるのかを整理することが目指されていました。
マキャヴェッリが指摘していたような「主権」とは、唯一無二の固有・独自なものとして位置付けられていましたが、「統治」の議論がされるようなフェーズ(反マキャヴェッリの論考など)では、さまざまな形態の統治があることが指摘されていました。
その中で特に大事になったのが、「家族の統治」であったことがまず確認されたように思います。
「家族の統治」とはいったい何か…。家族をどのように統治をしていくかというと、例えば家計簿をつくるなど、家計のやりくりをすることが大事になってきます。家族の成員が生きて生活していくためには、限られた収入の中から生活に必要なやりくりをしていかねばならないわけです。
ところが、実はかつての主権者たる王侯貴族たちは、そうした「経済」に関する概念が全くなかった。しかし、市民が主権の主体となるフェーズが訪れます。そのとき、市民たち;新たな「君主」は、自分の欲望や欲求を追求するジャイアン的な立ち振る舞いが許されません。内部(例えば家族、そして国家)がうまくやりくりしていけるかどうかを気にしなくてはならなくなるからです。
実はこのとき、大事なのは「いかに儲けて、国(家族)が活動を続けていけるか」ということになります。これまでは、誰が「主権」を握るかということが大問題で、その奪い合いが続いていたのですが、市民が主権を握った途端、ジャイアンは誰かという議論/政治的な主体は誰かという議論は、大きな意味を持たなくなった、ということが指摘されていたように思います。
もはや家族たる国家の経済をまわしていくために、「儲ける」ことが、一番の関心事となるわけです。しかし、「主権を誰が握るか」を問う必要がなくなったにせよ、「誰が儲かるべきか」は主権者にしか決めることができません。
やはり、「誰が儲かるべきか」を決めることのできる「政治的な主体」になりたい、とみんなが思うようになります。ですが、ジャイアン的な主体がたくさん発生することは「統治」の観点からは都合がよくないのです。この問題を解消するための工夫が「人口」という概念でした。
ひとりひとりの市民…いわばジャイアンの願望や欲求には応えることができないが、たくさんのジャイアンが集まったジャイアン軍(群?)…いわば、人口全体を見て、人口の平均(例えばGDP)がよりよくなるように判断していけばいい、とみなされるようになった、という説明がされていたように思います。
「主権」と「統治」をつなぐものとして「人口」という概念が現れ、人口の概念を通じて、うまく「経済」がまわるようにさい配していくこと、そのための技術として安全装置が機能した、と指摘されたといえるでしょう。
安全装置は、その意味で非常に洗練されて完璧な統治の技術だということができるかもしれません。市民の構成員である人々が、実際によりよく生きていくことができるようなやりくりを可能にする統治のための技術だからです。
ただし、だからこそ、”ジャイアン軍(群)”から除去されてしまう集団が存在するということを、考えなければならない、という指摘もされました。ジャイアン軍(群)から除去されてしまう集団とは、いわゆる、マイノリティとして捉えられるような存在です。
安全装置という技術は、マジョリティのためのものとして、非常に説得力のある正当性のあるものですが、マイノリティがこぼれ落ちていくことを前提とした技術でもあるといえます。だからこそ、完璧であるかのようにみえる安全装置という技術に対峙していかねばならないのではないか、と議論されました。
マイノリティ・スタディーズの意味についても言及されつつ、今回の議論を終えることとなりました。
この後は、この統治術がどこに由来しているのか、という議論へとすすんで行くようです。実はそこには「良心」というキーワードが挙げられる、ということも少し触れられましたが、どんなふうに展開していくのかが非常に楽しみですね。引き続きぜひ楽しく読み進めていけたらと思います。
参加者の皆さんからのコメント
国家にとって、人口とは国家をうまく統治するための材料であると学んだ。また、統治が人口の境遇を改善すること、人口の富・寿命・健康を増大させることという目標を獲得するために用いるのが人口という道具であると理解した。このような安全装置の典型的な例として、健康診断があり、私たち国民は人口として生かされていると分かった。
ジャイアン的な主権者が多く発生することは統治にとっては厄介で、そのため人口を通じて人口の平均がより良くなるように取り計らえばよいとみなされるようになった。そのための安全装置は完璧そうに見えるが、マジョリティからマイノリティが除去されてしまうと思う。

ジャイアン軍/群に関していうと、まさにたくさんのジャイアンが集まって形成されるのが、群であったり、軍である、ということ…。つまり数で把握しようとすることになった、ということですね、
そして、「マイノリティ」に関する指摘はもしかしたらそこまで言い切れるかどうかは実はあやしいかもしれません。フーコーが、マイノリティにこだわり続けてきたのは、「安全装置」を換骨奪胎して反論しようとしたためだと思います。私自身もそこには深く同意しているところで/群に関していうと、まさにたくさんのジャイアンが集まって形成されるのが、群であったり、軍である、ということ…。つまり数で把握しようとすることになった、ということですね、そして、「マイノリティ」に関する指摘はもしかしたらそこまで言い切れるかどうかは実はあやしいかもしれません。フーコーが、マイノリティにこだわり続けてきたのは、「安全装置」を換骨奪胎して反論しようとしたためだと思います。私自身もそこには深く同意しているところです。
「人口」という概念があることで、人々は”疑似的な”ジャイアンでいることができるんですよね。実際、第二次世界大戦のころ、国民の健康について司る厚生省ができます。人口として国民の健康を管理しようとするようになったのは、近代になってからなわけです。群・軍としての管理ですね。
「人口」という概念によって、みんなが主人公というあり方が成立できてしまう、安全装置は非常に特殊なシステムで、統治術としてのインパクトのあるものだったといえますね。
第五講| 一九七八年二月八日「統治性の研究」 他 /2021年11月16日
担当:K原先輩
当日資料はこちら
当日リポート
本日の講読会は、インフルエンザ疑いのあるフーコーの講義がベースになっていましたが、チャット機能を通じてとても盛り上がった会となりました。議論は、まず、司牧的権力って、どんな権力なんだろう?というところから展開していきました。私たちは、けっこう、「権力」ときくと”抵抗すべき対象”みたいに想定してしまうことがあります。権力に抵抗していくことが「美」であり「善」である、というような感じで、権力観は出来上がっているところがあると思うのですが、今回の章で取り上げられていた「司牧的権力」とは、なんだか、とっても素晴らしいもののように、映りました。
そんなわけで、純粋に、本当に、人を守ってくれるような権力のあり方はあるのか?をみていきました。抗うべき権力の形とは、『社会は防衛しなければならない』の中で出てきたような「野蛮なものの濾過」であって、それは、<殺す権力>としても発動してきたようなものでした。
一方で司牧的権力とは、牧者のような権力のことで、迷子になった羊がいないかどうか、お腹を空かせて泣いている羊がいないか、探して回るような権力のあり方でした。この司牧的権力は、「善きことをする」ために存在するようなもので、それ以外の理由で存在することがありえないものとして位置付けられています。
人間たち(羊たち)を見守りながら、気を配る権力のあり方からは、「監視ともいえそう」という意見も出ますが、一望監視装置(パノプティコン)と異なるのは、パノプティコンが囚人に「監視されている」という意識を持たせさえすればよかった一方で、司牧的権力は実際に「見守り」、善行を施すことが権力側に求められている、という点です。
司牧的権力は、「教室内で落ちこぼれが一人も出ることがないよう、みんなを見守ろうとする先生」的な権力ともいえるのか?という話も出てきます。こうした司牧的権力のあり方は、ギリシアやローマにはみられないもので、ギリシアでの権力が守る対象は領土でした。つまり、領土を守ったり、拡張するためには、ときに人の命を犠牲にすることもあった。一方で司牧的権力は、自分を犠牲にしてまでも”群れ”を守ろうとする、そういう権力として描かれます。
こんないいものがあっていいものか、なにか裏があるのでは?というふうに議論は続いていきます。
「何を以て「あの羊を助けなきゃ!」となるのかが気になった。」というコメントも出てきます。
実はこの、司牧的権力は、「全体のために一つを犠牲にすること」と「一つのために全体を犠牲にすること」を両立させるために、”群”――人口を守ろうとするようなのです。
ここでの「救済」は、完全な一匹も取り残さない救済の完遂を意味していないようで、「その熱心さ、献身、限りのない専心」が現れさえすれば、司牧的権力が発動するようなのです。形而上学的な「救済」とでも言えるようなもので、「全人口を救おうとしている」ことが大切になります。
つまり、「人口」を救うために、貧しいものは飢え殺し、メインの人口を生かす、ということで「全人口を救う」ことを実現しようとするようなのです。
「はぐれた一匹を見放さずに救済することで、いつかじぶんがあの一匹になったとしても見放されないだろうと残りの羊たちを安心させる効果があるように思えた」という意見もありましたが、見放される羊はいないんだ、とおもえた時、一匹一匹の羊も、全体のために自らを犠牲にすることを厭わなくなったり、守ってもらえる羊になれるよう、牧者が牧者でありつづけられるよう、羊たちは各々「どう考え、どう生きるべきか」を考え、良心的なジャイアンになっていくのです。
一方、「守られると守られた側はそれに恩返ししなきゃ、となってしまい権力者に縛られる?ことにはならないのかな」という指摘もされます。フーコーは、テクストの中でそこまで言及をしているわけではありませんが、講読会の議論においては、救われる側は救われるように振る舞い、かつ、救われることに感謝しなければならなくなります。自由な消費行動も、権力にとっても望ましい「自由」な消費行動になりかねないのかもしれない、という話題につながっていきました。
「救われないように」生きる、という選択肢もひとりひとりがとることができる、という点では、単純に、人口に含まれずに捨て置かれる人たちを「マイノリティ」として位置づけることはできない、という点も確認されました。ただし、司牧的権力がネコタヌキやキツネは救わず、羊だけを救済の対象とする、ということは、救えない存在はネコタヌキやキツネ扱いする、ということにもなります。私たちは、みずからが羊なのか、ネコタヌキなのか、キツネなのか、どう権力者の目に映っているのかも分からないままに、羊として救済されるよう、自らの行動を変えていきます。そのような意味で司牧的権力は「自らの行動を変えさせる権力」でもあるようなのです。
最後に、司牧的権力は、余裕がある世界でしか成立しない、ということも指摘されました。恩着せがましい社会から、私たちは逃れ切ることはできません。どこかで社会を受け容れ、社会化しなければならないし、一定程度の枠の中で生きていく必要はあるからです。その意味で安全装置を全否定することはできないのです。
気を付けなければならないのは、安全装置が無限の外部資源を前提にして駆動しているわけではない、ということで、いつか、資源が枯渇するとき、安全装置の働きが逆転することがありえる、という点のようです。
今日、議論で踏み込んだ部分も、来週の2月15日の講義や、2月22日の講義でより深められていくようです。ぜひ楽しみに読んでいきたいですね。
また、来週の16:30からは、「ユルくみんなで読むフーコー」のスペシャル企画として、「”Learning Crisis”とは、何だったのか?2021版」も開催されますので、ぜひ奮ってご参加くださいね。申し込みはこちらからお願いいたします。
参加者の皆さんからのコメント
ライブ時間内で受講者の意見を取り上げそれについて話をすることで、一方的な情報の提供ではなく、イベント中に話が発展し毎回に唯一無二のオリジナリティがあるところを魅力的に感じています。
一人で読んだだけでは何を言っているかさっぱりわかりませんでしたが、議論を通して「司牧的権力は何か」ということを深く理解でき非常に勉強になりました。司牧的権力は、例えばプレゼントを贈るといった行為など、友人関係や家族内など身近な生活の中でも行われているのだと気づき、興味深かったです。それと同時に、恩を感じすぎて自分の全てを犠牲にして生きていくのではないかという危機感も感じられました。
今回のイベントを通して司牧的権力の中に恐ろしさを少し覚えました。それは安全装置を学習したときに感じたものと似ています。知らぬ内に羊の群れの中で育ち、以前の私は救済の完遂が当然であり約束された環境だと考えていました。自ら置かれている環境を知らない無知さは恐ろしいと学びました。
司牧的権力は、自分を犠牲にしてでも、群れを救済するという献身的な権力であり、根本的に善行が旨の権力であるからこそ、権力を持ち続けられているということを学んだ。また、救済される側も、救済されるような存在になるよう、自らの行動を変えて行くことがあると理解した。司牧的権力は、群れの救済を目的とし、ただ善行をするために存在するように見えるが、良心的な人口を作り出すための人間の統治のあり方としても捉えることができるのではないかと思う。

本当に、日本の教育について振り返って考えてみると、まさに「羊をつくろう」としているのかもしれないのですよね。どのように羊を作ればいいのか、という議論に終始しがちである…が、まなキキは、タヌキやキツネ、否、まなキキブレンドにあやかってネコになろう、としていくことが必要なのかもしれないですね。人口を構成する、救済の対象たる”羊”ではなく、”ネコ”を目指しましょう!
→ネコ?という方は、ぜひ、まなキキブレンドのパッケージをご参照ください。(笑)
また、今回のまとめで出てきた「恩返し」的な気持ちにさせられてしまう、という議論は、実はフーコーが触れているわけではありません。少し私の読解が含まれてしまっているかもしれないので、ご注意ください。
しかし、すべての権力が「よいようになる」ように、統治されているはずではあるんですよね。別に「損なおう」としているわけではない。心からよくなるようにという思いで始められているはずのものが、安全装置という形をとった、ということを改めて考えていきます。今回はこうしたシステムが生まれてくる経緯を振り返っていきます。
第六講| 一九七八年二月十五日「司牧の分析」 他 /2021年11月23日
担当:Mせんせい
当日資料はこちら
当日リポート
本日もやはり、チャットを使って皆さんからも多くコメントをいただきながら議論が展開していきました。まず、今回のフーコーの講義は、ギリシアには、「司牧」がない?、という指摘(異論)に対する弁明?からスタートします。そして、本題となる、キリスト教と司牧のかかわりについて触れられていくのですが…。
まずは、「キリスト教と言えば隣人愛、平等愛のようなイメージがありましたが、司牧が群れに都合の悪い羊を追い出すというのはイメージとかけ離れたものだなと感じました」というコメントから議論が始まります。
実は、キリスト教は宗教改革にせよ、異端審問にせよ、十字軍にせよ、自分たちと信仰を共にしない対象に対しては容赦なかった。そのようなキリスト教的司牧が指すものとは…??という感じにもなりつつ、プラトン(ギリシア)の司牧観を受けて、改めてプラトンにもフォーカスして議論が進んでいきます。
プラトンは、「織物工のモデル」として、政治家とは、いろいろな職業の人たちがそれぞれの仕事をしたものをつなぎ止めるもの、「融和と友愛にもとづく共同体へと」人々をまとめる術を持つものとして指摘していました。
長らくの間、政治とは軍事的展開などを含む大きな話をするものだったのです。先の衆議院選挙でも各政党が「医療」や「福祉」、「教育」についてそれぞれの目標を掲げ、主張していましたが、かつての文脈における「政治」においては、医療も福祉も教育も、王にとっては些末なもので、語る対象ではなかった(政治が医療や福祉、教育を取り扱うのは、きわめて近代的な発想)。いわゆる「司牧」的な振る舞いをするのは、医師や教師など、「医療」や「教育」の場に立つひとたちであったかもしれないが、それは政治における「補助的な役割」にとどまるものでしかなかったわけです。
一方、キリスト教社会においては、群れと牧者の関係性がかなり重要なものとして捉えられていた、ということが確認されます。講読会のなかでは「司牧というと、群れを統率するイメージがありますが、一方で、言うことを聞かない暴れる群れがあるし、放牧というか、好き勝手に放し飼いにするやり方もあると思います。」という指摘がなされます。そして、司牧とはまさに”放牧”といえるようなものなのだ、ということが確認されました。
放牧――羊たちは、そこで自由に飛び跳ねて、好きなところで草をはむことが許されています。が、注意しなければならないのは、それが「牧草地においてのみの放牧」である、ということであったのかもしれません。どこへでも好きなところへ行ってもよい、ということではなく、あくまで「」つきの自由といえるような種のものであったのかもしれないのです。
ここで、キリスト教的な自由とは、ポリス的な自由と大きく異なっている、といえます。キリスト教的な自由とは、神を信仰するからこそ保障される自由、羊であるがゆえに守られる自由、というような種のものです。
実はこれは現在の私たちにおいても言えるものであったりします。例えば私たちは、国民であることで保障される「自由」があるのです。マイナンバー制度も、マイナンバーに加入し、いろいろと使いこなしていくことで、その自由度が増していく――そういった自由のあり方が、キリスト教的社会における司牧的権力の特徴として指摘されていたように思います。
司牧的権力が政治的権力と分かたれている、ということも、ヨーロッパにおける司牧制の特徴だと指摘をフーコーはしていました。例えば、「自分たちで決める」という、完全に政治的主体であろうとする発想こそが、ギリシア社会(ポリス)における「自由」の意味となっていました。ですが、今や、自分たちが政治的主体ではないほうが「自由」なのです。政治的主体というよりかは、経済的主体であることのほうが、「自由」を意味するようにもなっており、それこそが、キリスト教的な発想ともいえるようなものかもしれない、ということが指摘されました。
いわば、「自由」に対する、ギリシアとヨーロッパ(キリスト社会)での感覚の差、みたいなものがあり、ギリシア的な自由はむしろない方が「自由」である、というような「自由」の認識は、特異な考え方として見なすことができるのです。そしてこの発想がキリスト教由来である、という指摘は、おそらく否定しがたいものとして受け取れるのではないか、という説明がされました。(マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』など)
フーコーは、キリスト教社会における司牧的権力は少なくとも18世紀まで政治的権力とは異なるものとして保持された、と説明していましたが、18世紀以降、市民革命などがいくらか司牧的権力のありかたに影響を与えることになった、と理解することはできるようです。ただし、それは司牧的権力が司牧制という制度から形を変えて新しい権力の形へと姿を変えた、とも解釈することができるといった指摘もされました。ここには、これまでずっと考えてきた安全装置という権力メカニズムと司牧制の接続がみられる部分なのかもしれません!?
フーコーは、社会関係を躊躇しながら話すきらいがありますが、やがて「自己統治」や、「他者への配慮」といった議論へと展開させていくことになります。そもそも「政治」とは人に影響を与えることにほかなりませんが、その「政治」という議論を考えていくうえでも、いわゆる「政治」を成り立たせる前提となっているものを問い直すことを通じて、私たちが持っている「自由」とはどういうものなのか、今後も議論を深めていけたらと思います。
参加者の皆さんからのコメント
同じ「権力」ではあるが、政治的権力と司牧的権力は区別されてきた。フーコーによる、この二つは全く異なる特徴、タイプを持つものであり、司牧的権力はその特有の特徴を持ち続けたことは、とても興味深い。
司牧の下では自由のようであっても、「決められた牧場の中で」という条件が決められていて、本当の自由であるのかどうかは疑問である。これは今でも同じことが起きており、日本国民であるという条件が常にくっついている。政治的主体であると自由でなくなり、経済的な主体であると自由であるというのが印象的だった。

まとめの最後の段落のところは、実は「いや、どうだろう?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが…汗。そういう話が出た、ということで記録としてとどめておくことにしましょう…。
さて、そして前回大事だったのは、司牧的権力としてのありようが説明されたことと、そこから「自由」というものについて考えさせられた、ということですよね。自由は自由でも「大変な自由」もあるし、「安全な自由」、「やさしい自由」もある。いろいろありますが、もしかしたら今回の議論から考えると、いわゆるギリシア的な自由とは果たすのが難しい「大変な自由」に相当するといえるのかもしれません。一方、キリスト教における「自由」はやさしいのかもしれませんが、それは本当に「自由」と言えるのだろうか、という疑問も残ります。
おそらく、この「自由」というのはそのまま「権力」と置き換えても理解できるのではないかと思います。ギリシアにおける権力は、それを行使するのもなかなか大変さがあるが、キリスト教における権力は、努力をもたず、「信仰」がありさえすればよい、というようなものとして理解することができそうです。
いただいたコメントの二つ目などを見ていると、よいコメントでありながらも難しいなと思わされるところがあります。フーコーは政治的自由と経済的自由は両立しえない、とどうも考えていたように感じるのですが、みなさんはどうお思いでしょうか。もしもこれを「意志の自由」と「欲望の自由」と捉えるならば、フーコーのいうとおりだなと思うわけですが…、このあたりも継続して考えていきたいところです。
第七講| 一九七八年二月二十二日「良心の指導」 他 /2021年11月30日
担当:Nomさん
当日資料はこちら
当日リポート
今日のフーコーの講義もなんかすごいことを言ってる!、という感じで始まりましたが、宗教すべてを否定するわけではないにしろ、やはり第二回まなキキオンライン講読会(『科学哲学への招待』を読みました)でも学んだとおり、「信じること」と「考えること」は分けなければなりません。ですが、今回のフーコーの議論は、司牧的権力というものが、ふつうに生きている生活の中で発動しうる権力であることを指摘しており、それが衝撃的であったようにも思います。
司牧的権力を考えるうえで重要になってくるのが「全面的依存」というものがありました。これは、司牧的権力に固有なものとして説明された特徴でもあります。
自由に野原を飛び回り、草をはむ、そんないわゆる「自由」は、全面的依存があってこそ成立する、ともされていました。
ということで、「全面的依存」を説明する3つの特徴をひとつずつ確認していきました。
まず、「全面的依存」は、①個人的な関係によって成り立っている、という特徴を持ちます。
私たちの暮らしにおいては、家族などに代表されるような集団、グループといった単位で考えることも少なくないわけで、その意味でも、少し特異とみなせるのがこの特徴です。<あなたひとり>と牧者との個人的な関係が持たれるので、「なぜそうなるのか」といった理屈抜きに、どれだけ相手に身を委ね信じることができるか;依存できるか、ということが問われるようになります。
次に、②何かのために、目的があって服従するわけではない、ということ。
服従する目的がない、つまり、もはや服従することを目的に服従するようになるのです。「意志を持たないという意志を持つことだけが許され」て実施されるようなものが、「全面的依存」の特徴として2番目に挙げられた説明でした。
最後に、③秘密、真理はあるがかくされている、という特徴が説明されていました。
隠されている真理を持っているのは牧者だけで、だからこそ牧者は指導することができます。ギリシアにおける教育は、個人を育てることを目的とするものでしたが、司牧的権力における教育は「そうありつづけること――よい羊であること;人にやさしく、博愛に満ち、姦淫せず、勤勉に働きつづけるようなよい人間」を目指し、そのために隠された「真理」が用いられます。
この「全面的依存」の話は、私たちが義務教育で学ぶ「道徳」の授業の実践においても通じるところが少なからずあるのかもしれない、という指摘もされていました。
「正解」が用意されている道徳教材を前に、道徳の授業は、「よい子」をつくる努力がされているわけです。そこで子どもたちは、先生が期待する「よいこと」を想像し、忖度して回答していくようなところがあります。背景にある、そもそもの「?」には敢えて触れずに「良い子」として生きていくことを目指す、それを是とする実践が、「道徳」の授業の中にも指摘できるのかもしれません。それを踏まえると、司牧的権力における「自由」もいよいよあやしいものに思えてくるようにも感じられます。
その後、まどか☆マギカにも「功徳と罪過の精妙なエコノミー」のような話があったなあ、というコメントがあり、この「功徳と罪過のエコノミー」とはそもそも何か、という議論に展開していきました。
そもそもエコノミーとは何だったか。経済、何かものの”やりとり”や”取引”を指していますが、フーコーの議論ではおそらく二つのことが指摘されているようだ、という確認がされました(と、同時に今回の講義では、ちょっと整理された区別が重複していたり、論理的に詰め切れていないところがあるような気もする、という指摘もありましたが…)。
まずひとつが羊たちという群れに牧者は対峙するものの、牧者とのやり取りにおいては個別的に各羊たちが扱われ、功徳と罪過がやりとりされている(羊たちの罪を牧者が贖ったり、牧者が羊たち一匹一匹それぞれに対して責任がある、と考える)ということ。
そして、よい牧者には困りものの羊たちを、悪い牧者にはよい羊たちの組み合わせになるようにするなど、その効力が最大限に得られたかのようにみえる形に(需要と供給の一致がごとく、功徳と功罪の一致を目指す)調整すること――”精妙なエコノミー(やりとり)”がされる、ということが説明されていました。
功徳と罪過の精妙なエコノミーとは、依存関係を生むような「やりとり」のことでもあります。このことは「馬券を買う」という例になぞらえて説明がされました。競馬など賭博においては、儲けて大当たりする人もいれば、負けて大損する人もいます。でも、誰が勝とうが負けようが、主催側にとってはお構いなしで、変わらずに利益を上げることができるのです。
人々(羊たち)の欲望を安全に管理するための一例としての「馬券を買う」という行為があり、みんなが熱心に賭けに投じるほど、そもそも「こんな賭けをする意味って?」という前提を問うことすらなくなる――そして依存関係に陥っていくのです。我に返ることももはやありません。
当日の議論では、十分に話をしつくせなかったかもしれませんが、今回のフーコーの講義の中では209-210頁のあたりで牧者の持つ逆説(愚かな羊を排除することを許す)についても明白に指摘しており、そのあたりも踏まえながら、今後の議論も進めていけるとよいかもしれません。
司牧的権力において、羊たち同士の交流はなく…つまり、横のつながりは持たれずに、常に牧者との関係;縦のつながりにおいて説明されていきます。今回の功徳と罪過のエコノミーや全面的依存、真理についての言及もまた、安全装置を説明する要素にもなっていきそうです。
全13回の講読会も折り返し地点についたところで、今後の展開もますます楽しみに読んでいきたいところです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします!
参加者の皆さんからのコメント
Covid-19によって子どもたちの間には学びに格差が生まれてしまった。その差は形ばかりの教育となり、学びの空洞化につながっている。自粛下での青春を強いられる子どもたちにとって、現状行っていることの意味が説明できないという問題もある。そして、Learning Crisisは特に努力しなければならない障害を持つ子どもの気力を奪っている。
全体的に内容が難しく、講読についていくのが大変でした。良い買い物ができた!という時は良くない販売者で、失敗した!という買い物をした時は、良い販売者がいた、という例えがわかりやすかったです。
全面的依存の話は様々なところに通じる。功徳と罪過は「エコノミー」としてうまく組み合わさるように調整される。「功徳と罪過の精妙なエコノミー」は依存関係に陥らせるようなやりとりのことでもある。「エコノミー」の関係がずっと続くので、良心の指導もずっと続くのだろう。
今回は特に難しかったと感じました。論点がずれているかもしれませんが、力が集団の中で分有されていると、各勢力同士で争う混乱状態になると学んだことがあります。そのため、権力を牧者に集中させるためには、羊が牧者に全面的依存した「良い人」で、権力を持たない必要があるのだなと考えました。

「功徳と罪過のエコノミー」のところは難しいですが、大事なところですよね。「良い子と悪い子の市場経済」という形で理解すると少し分かりやすくなるかもしれません。「良い子」がいるとは、つまり「悪い子」がいて成立するんです。比較対象があって初めて「よい」「悪い」が生まれます。裁判の判決も似たところがあるかもしれません。これまでの判例など参照するべきデータや資料に基づいて、決断が下される…そこで「よい」「悪い」の評価をされる個人は、それぞれ喜んだり、辛かったりしますが、でも両者を含む社会にとっては、「よい子」「悪い子」間で相殺された結果だけを得るので、利益しかない。牧羊犬で追いかけながら、「よい羊」を作ろうとする、そのことの意味を考えさせられますね。
「よい子」、「わるい子」の例でいうと、おそらく、落ち着きなく机に座ってじっとしていられないような子は「わるい子」で、羊ではなく「ネコ」とされてしまう。よい買い物の例でいえば、安くいい品物を購入する場合は、逆にそれが販売者側の身を切ったような結果であって、生産者や販売者は涙を流しているかもしれない。利益と損失は循環しているが、トータルでは変わらない、そういう有様を「功徳と罪過のエコノミー」は説明しているといえるかもしれませんね。
また、賢い消費者や良い子でいるためには、比較対象となるような存在が不可欠になることも忘れてはいけません。相手ありきで成り立っている、という点で、「依存」が発生するということを指摘できるでしょう。
みんなジャイアンのように生きたい、という欲望を抱いていますが、その力を調整することがどうしても必要なのです。先日まで読んできた『社会は防衛しなければならない』は、まさに権力のあり方や分立の変遷をみてきました。今回の議論の中で指摘されている「安全装置」という権力のあり方は、今もなお、社会の骨格を形成している可能性があります。そこに迫って考えていきたいですね。
第八講| 一九七八年三月一日「『操行』概念」 他 /2021年12月7日
担当:H松さん
当日資料はこちら
当日リポート
まなキキで現在、現在すすめられている「まなキキ・ブレンド」の開発…。沖縄の就労施設・ワーカーズ・ホームさんにご協力をいただき、まなキキ用にブレンドしていただいたコーヒー(勉強のおともにどうぞ。ミルクをたっぷり入れて飲むカフェ・オレにしてもおいしい)を、クラウド・ファンディングで進め、伴ってこれまた新たに進められているプロジェクト、まなキキ・フォスター・プラン(障害や事情があって学びにくさを抱える子どもたちを大学生が家庭教師として教え、それを地域社会が支えていく)が大きく動き出しそう…という気配が漂う中での開催となりました。(まなキキ・コーヒーのクラウド・ファンディングは12月27日スタートの予定です。またぜひご案内させてください)
さて、とはいってもフーコーも、今日はとても難解な、クセのあるところだったかもしれません。
フーコーは、前回の講義で司牧的権力の特徴を議論し、例えば、その一つの特徴として、功徳と功罪のエコノミーについても説明をしてきました。今回の講義録の冒頭にでてきた「魂のオイコノミア」もまさに「良心のエコノミー」とも言い表せられるようなもの。これを「魂の操行」として予測される反論を整理しながら、操行について、司牧的権力のありようを対比的に説明しようとしている回であった、といえるかもしれません。
それも、司牧的権力がどのように統治性・統治技術へと形を変えていったのか、という議論を展開させていくためであり、その意味では助走のプロセス、あるいは伏線の部分としても読めるところであったのかもしれません。司牧的権力が統治性へと変遷していく過程を「司牧の危機」とも「爆発」とも言いながら、読み進めていきました。
フーコーは、司牧的権力が牧者と群れとが個人的なつながりを持っていることで成立する、という点や完全なる服従がキーになる、と説明してきていましたが、今日はそうした司牧的権力が揺らぐようなあり方――反操行――とでもいえるようなものを列挙(修徳主義、共同体、神秘主義、聖書、終末論的信仰)していくような構成となっていました。ですが、それでもなお、司牧的権力はそうした、「反操行」をも自らの手の内にあるものとして扱っており、司牧的権力から逃れることはできないのだ、とそうしたことを指摘していた、と説明をしていただきました。
反操行が取り上げてきたテーマとは、すべて、「明らかにキリスト教にとって、一般的に言って外的(まったく外的)なものなどではない(P264, L3)」と、フーコーは説明しています。いずれも「教会自体によってたえず取り上げられ(P264, L5)」てきたもので、「それらの戦術的要素が周縁的なしかたではあれキリスト教の一般的地平の一部をなしているかぎりにおいて、そのようなことがなされる(P264, L11)」とも述べています。
つまり、どれだけ、司牧的権力を成り立たせなくさせるようなもの/成り立たせなくさせたもののように思われても、これらの議論は本当の意味で司牧的権力を成り立たせなくさせるような力は持たない――むしろ、キリスト教においてよくある議論の一つでしかなくなってしまうようなもの、として説明されていたように思います。(そして、次週の講義へとつながっていく)
実際にフーコーは「反操行」は政治的制度の上でも起こっているとして、軍、秘密結社、医学を例に説明していました。ですが、いずれにおいても、「反操行」のように思われた動きも、結果的に、形を変えて操行にまた立ち返っていってしまうような経緯をたどっているとも指摘しているようだったのです。
今回の議論は前回からちょっと急に趣を変えて始まったところもあり、なかなか読み取るのが難しく感じたところもあったかもしれません。ですが、議論はこの後に続いていく、ということで、どんなふうに議論が展開されていくのか、楽しみに読み進めていきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
今回のテーマが難しかったというのは大きな要因だったと思いますが、「それ」や「あれ」等の指示語がが説明の中で少し多かったように思います。私の理解力の問題もあり、丁寧に説明して頂いたのにも関わらずうまく説明の趣旨を捉えることが出来なかったことが悲しかったです。
今回の購読会はとにかく難しく感じました。正直、反操行の例は司牧性を立証するために用いられたということくらいしか分かりませんでした。今までに増して、他の回との関連性が強いということで、来週の購読会に注目したいと思います。まなキキブレンドも楽しみにしております。
以前にも参加させていただいたのですが、今回のお話の方が難しかったと感じました。…うまくまとめることができず、すみません。個人的に、高校時代に世界史が好きでよく勉強をしたので、歴史的な流れにもこのような社会的な考え方が働いて物事が起こっているという事が分かり、時代背景だけでなく、やはりそこに存在する人々の物事のとらえ方や倫理観が大きく歴史に関係するのだと感じました。
操行と反操行の転換が起こりそうな時というのは、とくに注意を払って社会を見極めなければいけないと感じました。
今回の講読会で、操行と反操行について、H松さんの説明と、最後の先生の説明の中で、戦争の例で説明していただいた箇所が非常に分かりやすく、理解することができました。戦争は本来、意思のある人が兵士として参加するものであったはずのものであり、戦争自体は反操行的なものであるはずなのに、戦争が倫理となることで、兵士であることが操行になるという変換は社会の動きとして非常に興味深いと感じました。
司牧的権力が栄えていた時代も、現在も反操行は存在していた。その具体例に修徳主義、共同体等がある。他にも神秘主義や終末論的信仰が存在していたのにも関わらず、それら反操行の試みが成功しないということから、司牧的権力が如何に強固な存在だったかがわかる。また、戦争や秘密結社など今まで反操行と勘違いしていたものが操行そのものであると学んだ。
操行と反操行は複雑に絡み合っているということ。社会的に反操行と認識される行為であっても、その主体者にとっては操行を体現していることになる。物事を善悪で二分することができないように、同じものを対象としていても、立場によって捉え方は異なってくる。誰もが操行を体現した結果、誰かにとっても反操行が生まれてしまうという仮説を立てると、例え批判の対象となっても、この世から反操行を排除することはできないだろう。
今回の内容の中で、兵士の例が登場しましたが、この現象は現代にも繋がる部分があるように思います。兵士であることを運命や職業として誇りに感じていた層が、状況の変化と共に「戦時下の倫理」として共通認識が形成された時、その事実をどのように受け止めていたのかが気にかかりました。
COVID-19では、「感染しないこと」が1つの倫理となりました。人々が健康であることに越したことはないですが、本来は自己実現の1つとして目指されていた「健康」がいつしか義務として重くのしかかってきました。心身を整え、健やかに生きることを理想として日々活動していた人々にとって、目指すべき状態は変わらなくとも、「絶対にミス(感染症にかかること)してならない」という条件が加えられると、どう感じるのだろうかと思いを馳せると、テキストの中で提示されていた例がもう一段階深く受け止められるように感じました。

エコノミーという言葉、なかなか難しいですよね。フーコーはこの言葉を経営学的な意味でも、生態学的な意味でも使っているような印象があります。利を求めて運営され、特に目的はもたないもの。何か「よいこと」を求めて立ち回っているようなもの――「良心のエコノミー」に」は、よいことをしている、ということに意味があるんです。守っているという行為に意味を持っていて、いわゆる「チート能力がある」とでもいうのでしょうか。そこでは、なぜ「よくあること」が必要なのかは問われないんですよね。重要なのは、「よいことをしている」ようにみせること。それは、政治においても同じような状況にあるかもしれませんね…もはや結果責任を問われることがない、という。
ちなみに前回の議論では、統治術という安全装置から逃れるための「反操行」の試みをいろいろ指摘していましたが、その中でその反操行といえるようなものは極めてマイナーなものか、あるいは結局よく在る空間を支えているようなものに過ぎなかった、ということであったと思います。でも、よくも悪くも、このCOVID-19感染拡大は、安全装置というものを暴く機会の一つにもなっていたように思うのです。だからこそ、反操行の可能性も広がったとも考えられるのではないでしょうか。
操行という言葉は、いわば、「安全装置に誘導されるとおりに生きるようなこと」。反操行を実践するためには、本質的に操行の意味を捉えなくてはならないのです。そうでないと、反操行と思いながら、操行そのものを体現してしまうことになる(猫の被り物をした羊状態)。
一方で、操行はあり・なしの二元論で割り切れるような種類のものです。操行があるかないか、は、マーケットの例に例えると消費行動をとるか、ぼーっとするなど経済行動をとらない、という形で区別できます。でも、「反操行」とは単に無操行な状態を指すわけではないのです。操行に陥らないように、反操行であり続けられるように敢えて努める姿勢のことを指す――だから、「反操行」の呼称?をフーコーも議論していたのだと思います。
また、フーコーが言っていた軍事とは、いわゆる徴兵制・総動員体制を指していますが、ここでは「軍人・兵士であること」は問われることなく、「よき市民」であるため、「よき市民であること」を示すために実施されようとしています。それは現在の米国の状態にも通じるところがもしかしたらあるかもしれません。市民権を得るために兵役を志願する、という状態があるわけですから。
また、今日において「健康であること」を倫理とするような、健康のエコノミーたる状況は本当に起こっている(起ころうとしている)といえるかもしれませんね。極限の状態の中で、何を選択していくことになるのか――健康のエコノミーの下で、何を守るのか(経済?私たちひとりひとりの生?)…医療費や介護費の”無駄な”出費を抑えようとする傾向がますます強まる中で、私たちにはそれを注視していくことが求められているといえそうです。
第九講| 一九七八年三月八日「司牧制から政治的統治へ」 他 /2021年12月14日
担当:K原先輩
当日資料はこちら
当日リポート
小平市は雪?みぞれ?もちらついたという、寒い一日となりましたが、フーコーの議論はますます熱を帯び、難しいながらにも、なんだか楽しくも興奮する講読会となりました。フーコーの講義録は読みながら、どのようなロジックで議論されているのかという論理の枠組みも勉強になるような気がします。(英訳版も併せて読む、という精読の仕方も紹介していただきました)
特に冒頭では、「知解可能性」ってどういうことなのか?といった疑問も出されていました(294-295頁あたり)が…。「自然の諸原則」と「国家理性」が分かたれたということを、どのように説明するか――フーコーは歴史的経緯を踏まえながら細やかな分析を経て説明するのが一般に求められるが、ここでは現在見渡すことのできる多様なプロセスや関係性を対比させたりすることを通じて議論していくよ、ということを指摘していたようです。
さて、それにしてもやはり、今回の講義の重要な論点の一つとして、「自然の諸原則」と「国家理性」が分かたれたという点を挙げることもできるようです。
フーコーは、これまでずっと「司牧的権力」について語ってきましたが、最終的に取り扱うのはどうやら「司牧的権力」ではありません。289頁の注釈にもあるとおり、16世紀ごろ、「司牧の大危機」を経て、司牧的権力は失われてしまうためです。
その背景には宗教革命や市民革命などの存在があったわけですが、神の存在は否定されて、司牧的権力として、神不在のまま統治術が残ることになった、と考えられるようなのです。
そこで必要になったのが「自然の諸原則」と「国家理性」の分別、といえるのかなあということでした。
神がまだ存在している時点では、神によって統治されることは、ある程度の説得力を持っていました。ある種、神さまによる統治――(王様は神が自然を創造するかのように国を統治する、など。あるいは天皇による統治、など。善し悪しはともかく、なぜ、その人たち(神や王)に人が統治されるのか、という理屈ははっきりしている)は、自然な形でなされるのです。
ですが、前回までの講義でも議論されてきたとおり、ある時期(16世紀ごろ)になると、「反司牧」や「反操行」の動きが高まり、神様による「自然の諸原則」としての統治は否定されるようになるわけです(科学革命などの展開との関連も指摘がされていました)。
ある種、「神様」にとって都合のよいように”群れ”が統治されてきた体制をそのまま、神が不在のまま引き継ごうとした…でも、そこでは、「誰が」人を統治することができるのか、その合理性や妥当性が議論される必要が生じるかもしれないのです(それを頑張って議論して、体制として整えようとしてきたのが「政治家」だった、とも個人的には読んでいました)。
神不在の中、何者かの人間が統治をする、ということの正当性を説明する;その分別を「国家理性」という概念が果たそうとした、ということが確認されたのかなあと思います。
今回の講読会の中では、神不在の統治術は、しだいに、「なぜ〇〇が統治をするのか」という意味も問われなくなっていくことも示唆されていたように思います。
大事なのは「誰が」統治しているか、ではなく、どれだけうまくいっている――エコノミーがうまく機能しているか、になる……まさに、安全装置として転換していく通過点を、みなさんと一緒に目撃?している、ともいえるのかもしれません。
(実際に、今回の講読会の最初の頃に書いたようなことを、改めて書いているような印象もあります)。
次回のフーコーの講義では、その「国家理性」の統治というものについて、具体的に議論がされていく、という予告されていました。
なかなか難易度も高いままフーコーの議論も盛り上がっていますが、頑張って食らいついて、クライマックスをみなさんと一緒に見届けていきたいと思います。
ただ、寒くなってきていますので、くれぐれもみなさん体調管理にはお気をつけて!
参加者の皆さんからのコメント
三角読みを講読会で初めて知りました。大学院で学ぶ内容とのことでしたがこの場で知ることが出来て良かったです。
また、いつも講読会の三分の二が経過した時点まで情報の整理に必死で混乱していますが、最期の先生もまとめでいつもそれまでの情報に合点がいき、講読会が終わるころには「おもしろかった」と毎回思えています。有難うございました。
政治家は一種の宗派であり、職業としての政治家ではないというのが印象的で、政治家とは何なのだろうと考えさせられました。また、よくわからないなと感じたときに、邦訳、英訳と比較し一つ一つの単語に惑わされないということが勉強になりました。
主権者が新しいモデルを自分で探し出さなければいけないのが統治術という言葉が今の政治にかけているものを気づかせる大切な一文なのではないかと思いました。
「国家理性」が成り立っているのは、統治している者が「うまくできているかどうか」に掛かっている。現代でいうと総理大臣がそれにあたり、確かに我々は支持率や世論で統治者を評価し続けている。「自然主義」もかつての「自然性」とは異なり、理性のみが主軸となっている。
最近「18歳以下に10万円給付」について、当初政府は半分クーポンにするという方針を出していましたが、自治体や国民からの批判を受けて全額現金でも良いと方向転換しました。しかし、このシフトに対しても「もっと早く」などと批判が集まっています。この現象は、良くなることそのものが目的となっているわけでなく、過程を問われるようになった証左なのか、そもそも国民が岸田文雄に統治されていることに納得できていないということが明らかになっているのか、どちらなのだろうと疑問に感じました。今後も統治するものと国民の間に何か摩擦が起きたときにフーコーの議論を思い出しそうです。

司牧的権力と国家理性の話をずっとフーコーはしてきたわけですが、この二つには「似ているところ」もあれば、「似ていないところ」もありました。神様が打倒されたあと、神様に代わる主権が登場するのか、と思いきや、ほぼやり方はそのままで引き継がれたのです。そう考えるともしかしたら、分かりやすくなるかもしれませんね。そして、この似ているところと似ていないところを「国家理性」や「内政」などの概念を通じてフーコーは概観していくことになります。
さて、私たちの現在における政治のあり方は、もしかしたら、次なる「統治」のあり方へ変遷していくような過渡期にあるのかもしれません。考えてみれば、現在の統治も決して「自然」とは言い難いものです。なぜなら、みんなが統治者とされていながら、その「みんな」は被統治者でもあるからです。今回の議論に出てくるような「演劇性」などの話とも重なってきますが、「ちゃんとやってる感」を出すためのドラマトゥルギーのようなものが大事になってくるのですよね。
「国民の声をよく聞いて」というフレーズも、本当に国民の話を聴くつもりがあるか、は疑わしいところがありますよね。現実問題として、なかなか話を聴くようなつもりはなさそうですよね。「国民の声」は生の声ではなく、支持率という「人口」的な数値を以て聞かれているのかもしれませんね。
第十講| 一九七八年三月十五日「国家理性の定義」 他 /2021年12月21日
担当:Nom
当日資料はこちら
当日リポート
よく考えたら今回が年内最後の講読会となりました。ここまで長かったようであっという間でした。この文章を読むのも考えてみれば、年明けになるのですね。少し、間があくので、きっと記憶が朧気になっているかと思うのですが、今回の講読会はとても面白い議論が展開していました。
今回は、Nomさんの指摘してくださった「真理」にまつわる質問から議論は始まりました。この「真理」というのは、フーコーが国家理性の特徴として挙げている3つの特徴のうちの一つだったわけですが、実はこの3点セット、繰り返し何度も指摘されている3つでもあるのです。(→①救済、②服従、③真理) 司牧的権力の説明のところでも、この3点について触れられながら議論が展開していましたが、ここからもまた同じようにこの3点で説明することがあると思います。ぜひ、覚えておいていただけたら、とのことでした。
さて、まず、この「真理」について注目してみると、司牧的権力と国家理性において「似ているところ」と「似ていないところ」があったことが分かります。
司牧的権力においては、羊たちは自らの犯した「罪」を告白し、牧者はそれを証人としても受け止めて、「真理」は双方向的に取り交わされ、共有されていくことになります。
一方で、国家理性では、「真理」は統治にとって必要なものとして、いわば数的に把握されていきます。しかも、データはどのように構成されているのか――プロセスや生み出される経緯は明かされず、秘密のまま、主権者の知として扱われます。まったく開示されないわけでも、共有されないわけでもないのですが、共有されるのは、統治の正当性を説明する・統治の正当性を補強する真理が共有されることになるのです。
”羊たち”は、司牧的権力においては「告白する」という意識を自ら以て秘密を明かし、真理を共有することになりますが、国家理性において、”公衆”は、自らの秘密を提示するといった意識はまったくもたれていません。
おそらく、国家理性が秘密を保持し、国家の正当性を示すデータだけを「真理」として提示するようになった背景には、世界帝国を築こうとするようなフェーズが終焉し、複数の国家が均衡を保ちながら国際関係が維持できるようにするために「国家機密」化した、ということが一ついえるかもしれません。ですが、国家理性が秘密にする対象は、外国だけではなく、その国家内の「公衆」という「私たち」でもあるようなのです。
そして、国家理性の特徴として「救済」というキーワードが出ていましたが、「クーデタ」を例として説明されていました。クーデタとは、”緊急事態”の国家を守るために(法律を無視して)国民を殺す/行動の制約をするという事態を指します。
一見、「クーデタ」と「革命」は混同されがちですが何が違うのでしょうか。「革命」は国家を壊すことを目指しますが、「クーデタ」は国家という体制を守ろうとすることであったりします(例えば、2.26や5.15など)。国家を守ろうとする、とはつまり、「国家を保存する」ということに重きを置くものであって、いかに国家を延命しうるかに力が注がれるわけです。なので、戒厳令などがときに敷かれたりすることになる…。
いずれも暴力を帯びる、という点で混同してしまいがちな「革命」と「クーデタ」ですが、もしかしたら革命には波及性がある、という特徴も挙げられるかもしれない、とも指摘されました(アラブの春ことカラーレボリューションしかり、香港のデモしかり)
国家を救済し、国家を保存するという意味で、国家理性の特徴が以上のように確認されたのでした。
こうして、国家というものを「守る」枠組みが生まれていったといえるでしょう。これまでは、国は滅び、衰退し、王朝は交代を繰り返しながら歴史が蓄積されてきていました。国は滅びて、人々が残っていたわけです。ですが、この国家理性の成立を境に、国家は存在しつづける代わりに人が死ぬ(制約される)ようになります。国家理性は、国家を生き残らせるための理性なのです。
国家理性の3つの特徴の最後が「服従」です。服従しないとはつまり、反乱や謀反を起こす、ということになるのですが、国家理性は反乱や謀反を大きな問題としては捉えません。これまでの反乱や謀反は、主権の正当性を問うようなものとして行われ、王朝の後退を招くようなものであったといえるのですが、国家理性においては、おなかをすかせていて不満がある羊――反乱や謀反を起こすような存在――に対してその不満を解消するような調整をすることで「かいならす」;経済的に対処するような統治術が展開されます。
こうして、「正当性」を問うような議論はもはやされることはなく、政治と経済が連動しながら統治されるようなありようがもたらされたのだ、ということが確認されたように思います。
ここでの「真理」とは統計学のようなものを指していましたが、COVID-19感染拡大などを経験した私たちにとって、今回の議論は、かなり現実味を帯びたものとして迫ってくるものがあったように思います。secrutiy-安全について考えさせられ、economyー富の分配の問題とも否応なしに直面し、data science―データサイエンスが求められるような昨今です。
「命を守る」という言葉を口実に、実は国家理性が何を守ろうとしてきたのか、そのからくりが少しずつ見えてきているともいえるのかもしれません。ここからの展開もどんどん、ぐんぐん、広がり深まっていくとのことで目が離せませんね。
ということで、来年もどうぞよろしくお願いいたします!
参加者の皆さんからのコメント

残念ながらみなさんからのコメントはありませんでしたが…
革命とクーデタ、実は厳密には分けられないところもあるかもしれません。クーデタも、「革命的」な言い訳から、「革命的」な理念が掲げられてされたりもするものなので。でも、革命とクーデタのそれぞれが、何が目的で果たされるものなのか、ということを踏まえ、議論することで見えてくるものがあるのではないか、というのがフーコーの指摘であったのかもしれません。
分かりやすいのは、革命には、「世界革命」とか「IT革命」、「美容革命」などといったように、接頭語的なものをつけて成立する言葉だということです。つまり、〇〇に対して革新的なことをする、みたいなニュアンスが革命には持たれており、それはすなわち「中身の一新」であったり、「劇的な変化」を意味するものだと捉えられるわけです。
一方、クーデタには接頭語はつきがたいです。国家や組織にしか不随しないためです。クーデタの目的は、統治者や統治のシステムを変える、ということにあって、国家そのものをどうこうしようとはしないもののなのです。その国家であったり組織の「形式」は守り抜こうとします。
その意味では、ロシア革命を果たして「革命」と言えるのか?ということも議論できるように思います。結局、フーコーは、こうした議論を通じて、理想や理念などといった中身についての議論がされなくなり、形、形式の延命のみが議論されることになっているのではないか、ということも指摘しているように思います。「なぜ、統治されるのか」「何のために統治するのか」という問いは成立しなくなり、「どう統治するか」が問われ、統治される側も、統治される意味が問われなくなり「うまく統治される」ということを重視するようになる、ともいえそうです。羊は、自分たちがそもそも統治される意味なんて知る由もないのです。
第十一講| 一九七八年三月二十二日「新たな統治術」 他 /2022年1月11日
担当:大学生M
当日資料はこちら
当日リポート
2022年の第一回目の講読会となりましたが、今回も盛り上がりながら議論していくことができたように思います。特に、やっぱりクラウゼヴィッツが指摘したような「戦争とは他の手段で継続される政治である」といった、平和を保つうえで戦争は必要な道具だ、という指摘は、ドキッとしてしまった、というコメントもちらほら聞かれながら議論がスタートしました。
特に、国家間の競合に関連して、「外交」の意味や目的などに関する「?」から話題が広がっていましたが、そもそもなぜ「競合」するようになったのか?を確認してみました。
「競合」のきっかけとなったのは、帝国(スペインなども例に挙げられていましたが)の滅亡をうけて、”国”が滅びないことが志向されるようになったか、ということがまずいえるのではないかと確認がされます。かつて、神聖ローマ帝国にせよ、カトリック教会にせよ、自らの徳性を世界に知らしめたい、メンツをたてたい、みたいな形で、勢力を広げていました。ですが、このような”国”のあり方は、国の存亡をまったく保証するものではありませんでした。歴史で学ぶ国々が滅亡をいずれも経験してきたとおり、国というものは滅亡することが大前提だったわけです。
それに対して、自らが滅びないような空間として、いくつもの国が競合しあうようなあり方が目指されるようになった――それが国家間の競合が生まれた背景にあるといえそうです。
国家理性というものに基づいて、国家間の競合が果たされるとき、大事な役割を負うのが「戦争」でした。ここでの戦争は中世の戦争とは異なるもので、相手の命運を断とうとしたり、屈服させようとするものではありません。少しでも有利な生存を獲得できるか、くらいの意味で「戦争」が行われていた、というのです。競合関係を保つためには、目に見える形でお互いの「力」が提示される必要があります。それゆえ、常備軍は生まれたわけです(前回の講読会・『社会は防衛しなければならない』でも「ディスプレイ」の話が出てきました)
一国が独占的に支配するのではなく、そこに参加している各々が争い合うことで均衡が保たれ、「平和」がもたらされる――競合関係が保たれることで守られる「平和」?とはイメージがなかなか湧きにくいかもしれませんが、株式市場などを例に考えてみると分かりやすいかも、という説明もありました。
例えば独占禁止法などがあるとおり、市場が独占されるのではなく、いろいろな人たちが市場で争い合うことが、市場の健全性を守るうえで不可欠とされます。いわば、ここでの「平和」とは、市場・マーケットの存続に一番重きが置かれたものだと考えられるのです。(つまり、国家間の競合関係も「国家」にとって平和;国家の存続が保証される術なのだともいえるかもしれません)
もはや「なんのために競うか」が問われなくなり、バランス・均衡を保つことだけが重要になります。争うことの意味が問われないようになる、というのは、現代の大学入試などの例からも言える部分があるかもしれませんし、今後のコロナウイルス感染症についても見られるようになるのかもしれません。
***
講読会終了後、少し残ったメンバーで議論されたのは、「自己肯定」(368頁あたりに出てくる)についてでした。この「自己肯定」とはどういう意味なのだろう?といった疑問から生まれた議論だったのですが、普遍性を帯びた「帝国」というものに対して、各国それぞれが競合していけるようになる前提として、それぞれが国として存在するための”自己肯定”だったのではないか、という話に展開しました。そして、そこには、やはり「愛国心」も絡むのだろうか?というコメントも出てきます。
「愛国心」とは、日本人が日本への愛国心を持っていてもいいし、アメリカ人はアメリカへの愛国心を持っていてもいい、といったような、異なる国家の国民同士が愛国心を抱くことは許容される(むしろ歓迎されたり、相手をリスペクトするきっかけにもなる?)ようなものです。このような形で「自己肯定」が達せられるようになったことが、ものすごい進展だったのかもしれないね、と盛り上がりました。
自己肯定がすなわち他者否定だったようなフェーズから、それぞれの自己肯定が共存し得るようなあり方に移った――その変化を捉えるのに、「愛国心」というキーワードは重要なポイントになりそうです。
国家間の競合を通じて均衡を保つこと――それが主に軍備を通じて果たされた、ということを今回は確認してきましたが、次回は、人間と人間の関係、”ちょっとだけましに生きていくこと”を可能にするものとして「内政」に議論が移っていくようです。いよいよ展開が楽しみですが、引き続き楽しく読んでいきましょう。
参加者の皆さんからのコメント
講演会タイトルや本の内容から難しそうだと思っていましたが、解説が分かりやすくて良かったです。
国家維持のための競合について理解することができました。そこから、争う事自体に意味はなく、国家や市場のための争いがあることを学びました。そして、争いの形骸化が起こっている現状について考えることができました。またコロナ禍の現代にも当てはめることができると気づきました。
「戦争の無い平和な世界をつくろう」というフレーズがあるが、この「平和」とフーコーが指す「平和」は全く違うと学んだ。前者の「平和」が夢物語で馬鹿馬鹿しい、なんてことは決してない。ひとりの人間として生活する中、国家存続を意識する人がどれほどいるだろうか、「命」と「国家」を天秤にかけて「国家」を選ぶ人は果たしているのか、そう考えると空虚であろうが正義や自由や戦争の無い平和を人(民衆?)が求めることは必然だと感じる。しかし今回こうしてフーコーの指す「平和」を学んだ後では、目的が曖昧な競争を繰り返す人生をどれだけ一生懸命に送ろうとも、我々は国家という巨大な存在が存続し続けるための使い捨ての歯車でしかないのだと思った。
国家に所属する人間は、1度手にした戦争という手段を手放せないのでしょうか。それに変わるバランスを保つための手段があればいいと心から思いました。

考えてみると「愛国心」という概念は、フーコーがこの議論をした当時には、はっきりは生まれていなかったものなのかもしれないですね。どちらかというと、今ではこの「愛国心」をこそがディスプレイされて争い合われているもののようにも感じます。考えてみれば、他国があってこそ、自国への愛情が生まれるんですものね。ここでの均衡を図ろうとすることがいかにギリギリで危ういものなのか、ということは私たちも実感をもって経験してきているとおりですね。
「平和」というものについても考えさせられましたね。古代、エディアカラ期などとして区分されるような時代に生きた生物たちには、目や口がなかったそうです。そしてその生物たちは互いを捕食することはなかった――もしかしたら平和な時代を生きていたようです。じゃあ、目や口を捨てるのか?といったらそうもいかないわけで…本当に難しいところです。
前回は外に向けられたディスプレイを見てきましたが、今回はそれが内に向けられたときのことに着目していきます。
第十二講| 一九七八年三月二十九日「テクノロジーと内政」 他 /2022年1月18日
担当:ぱんこ
当日資料はこちら
当日リポート
フーコーのこれまでの議論がみっちり詰まったような今回の講義録。まずは、「内政」が何を示しているのかが説明されていた部分の確認から議論を始めていきました。
特に「内政の保守長官・改革長官」って何だろう?と感じてしまう部分があったと思いますが、英訳に立ち返ると分かりやすいよ、という話から始まります。
この「内政の保守長官・改革長官」は英訳バージョンだと” Commissioner (Conservateur) and general reformer of police” とされています。”reformer of police”という表記に注目すると、この役職が、ポリス(内政)のリフォームを司った、ということが分かります。講義録の中でも、17世紀に入って以降、ポリスに新たに加わった意味が解説されていましたが、まさにギリシアのポリスを近代的な意味でのポリスにリフォーム;改革する役割、とみなせるでしょう。「保守・改革」と訳されている部分も、いわば、「内政をもう一度担い、つくるもの」と捉えることもできそうです。
以上を踏まえたうえで、「内政」というものに着目していくと、新たに生まれ変わった「内政」が何を引き受けるのか、ということの説明も見えてきやすくなるかもしれません。
説明されていたものは下記の通り、それぞれ英訳も載せています。
1.人間たちの数 number of men
2.生活必需品としての食糧 the necessities of life
3.健康 health
4.人間たちの活動 the activity of this population
5.流通 circulation of goods, of the products of men’s activity
この意味で改めて捉え直していいただくと少し分かりやすく内容把握できるかもしれません。
最後の「流通」が「circulation」と表現されていたことからも象徴的ですが、内政を通じて「循環」が行われるということ――再生産がされて、国力になっていく…というところが、内政が果たすべきとされる役割:「国家の増強」に相当するものとして理解することができるかもしれません。
「ただ生きるというよりも、少しばかりましに生きること≒存在と安楽」が指す言葉についても確認されましたが、英語版では、being(存在)とwell-being(安楽)と表現されていたようです。
「ちょっとだけまし」に、「豊か」に生きるとはいっても、ひとりひとりが多様な存在であるのだから、それぞれの個人がどのような状況を「ちょっとだけまし」や「豊か」と捉えるのかは、それぞれに異なるはずなのです。でもそれを分かりやすく解釈するために、最終的に”国力の増強”を以て、「ちょっとだけまし」を捉え直そうとしたのが、「内政」だったといえます。
(それを測るために「統計」という技術が展開していった、ということも紹介されていました)
「内政」が「市民の忠誠・謙譲を見張らなければならない」(397頁)もので「道徳的機能」を備えたものであったとも説明がされていました。
それは、つまり、内政の目指すことが、教育などを通じて「人間たち」を生かし、その「諸個人の生」を経由して「ちょっとだけまし」な”安楽”や”至福”を実現するということにあった、という点とも関係しているようです。
最終的に「国力増強」に通じるような、「公的有用性」を生み出す「真の臣民」を再生産していくということ――これが、内政の目指すものです。”国家に有用”つまり、社会にとって有用になるようなことが「美徳」とされ、社会にとって有用にはならないものは「悪徳」とするような、そういう矯正を司るものという意味で、「内政」は「道徳的機能」を持っていたと考えられたようです。
今回のフーコーのテキストの中に出てくる「社会性」という言葉も、結局、社会にとってどれだけ有用か、という点において判断されるようなものであったといえるのかもしれません。
議論は、内政が目指した「社会性を備えた/社会にとって有用な人間」の再生産というテーマについて、今回のCOVID-19の状況を照らし合わせて考えていくことに至ります。
私たちは、<well-being>な状態を目指して、「生かされて」いるのかもしれないわけですが、新型コロナウイルス感染拡大前は、ここでの「well」は明確に、「市場に貢献する」という意味合いで捉えることができてきました。ですが、ポスト・コロナ下の社会において、また、新しい生活様式が求められる社会において、市場が制限されたり抑制されてしまう事態が訪れています。ここに来て、私たちは「何を以てwell-being」とみなすのか、という解を見出しがたくなっているともいえるのです。
「よりよく生きて」国家に貢献する、というときの「よりよい生」に、もしかしたらオルタナティブを見出すことが求められているかもしれない今、もしかしたら、「羊」ではなく「ネコ」だか「クマ」だか「タヌキ」だかとして――「反操行」を以て生きるチャンスがあるのかもしれません。
「反操行」として生きていくために、一つヒントになるかもしれないと指摘があったのは、391頁にも挙げられていたような「統計学」に関するもの。今でいうところのデータサイエンスに関するものです。
そもそも統計は、対象を比較するためにとられるものです。比較するために「人口」という概念が生まれ、「統計」という技術も生まれました。こうした比較可能なツールを備えたことで、私たち人間も対象化されて捉えられるようになったのです。
今日はやりのDX(データトランスフォーメーション)も、比較可能性を前提にしていますが、もしかしたらここで、”良い生のためのものではないDX”、”比較可能性をかなえないDX”を思い描くことができたら、安全装置や「内政」に対するカウンターになりうるのかも分かりません。
「有用性」を前提に語られることの問題性や、そうした問題にどう向き合うか、という観点について問題提起がされたところで、今回の議論を終えることとなりました。
来週はとうとう最終回。みなさんと議論しつくして、しっかりと考えることができたらと思います。

前回議論された「being」と「well-being」。
「being」は”存在”という意味でしたが、結局「well」は”有用”という意味になるのですよね。
「安楽」に通じるような”有用な”存在――。ここでは何にとっての有用性、何にとって役に立つ、ということなのかが問題になりますよね。
そういう意味で2022年は、この”有用性”が試されているともいえるのかもしれません。この2年間で、何が有用であったのかということを改めて位置付け直すような時間が持てるとよいのかもしれません。
あと、「反操行」という言葉。今回(最終講)のテクストを読んでいると、単純に「カウンターショット」とはみなせないところもあるかもしれません。ちょっと注意して読んでいけるとよいかもしれません。
ところで、「愛国心」についての議論も面白かったですよね。「愛国心」こそ「国の役に立つ」という意味で、有用性と切り離すことができないものです。でも、このCOVID-19感染拡大下、忘れてはならないのは、特にオミクロン株がどうやって日本で流行が始まったか、という問題です。…沖縄県から、だったんですよね。つまり私たちは自分たちで国境を管理できていない、ということでもあるのです。もっと、実はこのあたりも丁寧に考えてみる必要があるように思いますね。現代の国家理性が何を守ろうとしているのか…という問題です。ご指摘にもあるとおり、基本的人権や自由を尊重することがとても大切にされていますが、それは、そこで保証する自由が「国家への貢献」につながるから、ともいえます。場合によっては人の命よりも自由が重んじられることすらある。このことは今日の内容にも関わってきますね。
「有用性」の議論は、身近な人にとって有用であろうとすることも容易く、公的な有用性に回収されてしまう、という問題を確かに孕んでいますね。「強さ」もキーワードになるように思われますが、「弱くていい」と思えることも、もしかしたらヒントに繋がるのかもしれません。
参加者の皆さんからのコメント
レジュメが非常にわかりやすかったです。
前回の復習の時に話されていた「愛国心」について関心を持った。今年行われる北京オリンピックが愛国心のぶつかり合いという話を聞いてなるほどと感じた。愛国心の定義は時代・国によって大きく異なるので、各々どのような特徴があるのか自分でも調べて見ようと思う。
人々の幸福と国力が繋がるということでしたが、特に、基本的人権の尊重や安全を確保する事が国家の義務として認知されている現代では、通用しない?と考えました。そして、コロナ禍において、国力と幸福の繋がりや社会規範が覆される可能性があることを学びました。
人間はより良く生きるために教育と職業訓練通じて幸福を感じることになるが、これこそが内政の目指すことであり国力を強くしているのだと学んだ。また、COVID-19の状況では何を有用とし、何を良いとするのかがわかりづらくなっているため新たな構想が求められていると学んだ。
covid-19の状況下と多様な人間がいる社会から、自らの役に立てる場所を見つけ出し、有用性を発揮することの難しさを感じました。
「有用性」に囚われずに生きる、ということは、例えば、「自己満足」して生きることや、あるがままな自分や他者を受け容れるということでもあるように感じますが、それでも、人は「他者から認められたい」といった承認欲求からは逃れられない部分を持っているようにも感じます。
実際に「人があるべき姿」を暗黙的に皆が共有していて、そのありように自らを寄せようとしていることは否めません。日常に潜み、ときにストレスの要因にもなりうるような、でも生きていくのに欠かせない「他者からの承認や評価」が「公的有用性」と非連続とは言い難い部分があるように感じます。
自分が生きていていい理由、生きる意味や価値を、その本人自身が見いだせればいいですが、そう開き直るには一定程度以上の「強さ」が必要だと感じます。「有用性」に囚われずに生きること、あるいは「有用性」に代わるような”肯定”をどこかに見出すことは可能なのだろうか?と疑問に思いました。
第十三講| 一九七八年四月五日「生 – 権力の誕生」 他 /2022年1月25日
担当:大学生M
当日資料はこちら
当日リポート
笑っても泣いても今日が最終講。それくらい感慨深い思いを抱いてしまうほど長く、でも充実した講読会でした(手前みそながら…)
今日は、特に、フーコーの講義の最後で国家理性に対する「反操行」が意味するところを議論するところから話していきました。「反操行」とは、つまり何だったのか――実は英語では「counter-conducts」と表記されています。いわば、反操行とは、反統制とも理解することができるでしょうか。
フーコーはこの最後の講義で、戦争とかで殺しあったりするのではなく、皆が共存、矯正していく一つの様式として「経済」が重要となったということについて触れ、経済がどのように意味を持つようになったのか、重商主義から重農主義へと変遷していくプロセスを通じて説明をしています。
重商主義時代、国家増強を目指す具体的な方法が、従順で豊富な働き手によって生み出される食糧を媒体とした国家間貿易による利益獲得でした。いわば、そこでは人間たちは「使い捨ての労働力」のような扱いをされていたわけです。もはや「最低限で生きていればいい;being」の状態であったわけですが、それではない「well-being」な生き方が目指されるようになります。
そこで登場したのが重農主義です。ここで統治の在り方が大きくかわり、人間がよりよく生きることのできるような環境へ”調整”や”管理”をしていくこと――よりよく生かす権力;生権力が誕生することになります。
重商主義時代、そこでは自由(ジャイアン的自由)は規制の対象となりました。恒常的クーデタとして、国民に対しては「統制;規律」介入を行っていたのです。
それに対する「counter-conducts」の結果が、新しい統治の在り方に繋がります。よりよいものを追求していくことを是とする経済、そして人口に対して「統制」するのではなく自律性を重視する「自由」;自律的調整が実践されていくのです。
「自由」は、国家の”well”につながるようなものが「自由」として歓迎されることになります。いわば、新しい統治の在り方は、自由の枠組みを規定し、逆にジャイアン的な自由なるものは警察などにより取り締まりの対象とするのです。外枠だけを”管理”して、人口だけが安定的に増えていきます。そして、この新たな統治体制によって国家は永続的に”安全”が保たれ、それがゆえに「自由」も保障されていくのです。
ですが、大事なのは、ここで「誰の」命や自由が守られるのか、ということは全く問われていない、ということです。
以上のような内容のふり返りを踏まえて、その後、第二部でより深い議論に展開していきました。
(当日は、19時半以降、延長戦と称して第二部が予告なしで展開されました)
特に中心となったのは、「市民社会」がなんか急に出てきた感じがする、という違和感についてでした。
実は、今回たびたび登場した「内政」とは英語では「police」と表記されています。
私たちが「市民社会」と聞いて素朴に連想するのは、近現代の産物としての市民社会ですが、そしてもちろんそのような意味もおそらく含意されてはいるのでしょうが、もしかしたら、ギリシア由来のポリスにおける「市民社会」、「市民」という意味合いもあったのではないか、と話されました。
日本語で読むと「内政」と「市民社会」で突然湧いて出た、みたいな印象をどうしても持ってしまいがちですが、「police」からの「civil society」や「citizen」には連続性があったかもしれません。かつてポリスにおいて、人々は自由に意見し、一人ひとり尊重されたりする共同体としての原型があったかもしれないのです。国家に統治されるよりも以前に、市民社会的なものの原型がすでに存在していた――と。
ところが、「規律・訓練」という形をとる生権力は、こうした「市民」的なものは規制の対象となったり、重視されないものでした。
それが、「反操行」の末に、市民社会として新たに国家に対置され、国家を統治するメカニズムの一つになっていくのです。つまり、新しい統治の体制;安全メカニズムにおいて、「市民社会」とは、いわば「自由にものを言ったり、意見を言うことのできる空間、その枠組み」と捉えることができるかもしれません。何を語ってもよい――中身はもはや問われない形で「市民社会」というカタチが保証される――もしかしたら、安全メカニズムは形骸化した民主主義を前提に機能するような統治の体制、といえるのかもしれません。というか、フーコーはそこまで含めた意味で「counter-conduct」としての安全メカニズムを講義の最後に提示したのではないか、と話されました。
考えてみれば、いわゆる市民社会の総意として反映されていると私たちが思い「込んで」いる”世論”とは、世論調査によって成形されているものです。いわば、人口を言論として形にしたようなものであります。市民社会として提示される世論は、そのままマジョリティを誘導し、そしてそのマジョリティ;人口を統計的に把握する、ということでしかないのかもしれないのです。
COVID-19の流行で多く求められた倫理や道徳は、実は市民社会によって醸造されたものであったともいえるかもしれません。「よき市民たれ」という理想の”共感”を求める市民社会は、もはや安全装置の擁護者的な立ち位置にあるともいえ、市民社会がマイノリティを生み出している可能性も考えられるべきかもしれないのです。
もちろん、今回の議論は経済や市民社会のネガティブな部分を特に取り上げているという点について確認しておくことが重要です。ただ、素朴に「よきもの」として受け流してしまうと、思いもかけず安全メカニズムにおける「羊」になってしまうかもしれない、という点を確認しつつ、来る新たな?市民社会像のようなものの検討を考えていけたらいいね、と話されていたりしました。
実は、そのほかにもいろいろと興味深いトピックスが語られたのですが…と同時に、次回の講読会開催への願望も語られていました。
…ということで、ぜひまた次回のまなキキ・オンライン講読会でも再び皆さんと議論ができることを楽しみにしております。また、どこかでお目にかかりましょう。
参加者の皆さんからのコメント
今回初めて受講させていただきました。前回の講義の復習では、well-beingな状態を目指して「よりよく生きる」という内容を考えることができました。コロナ禍の状況を私たちがどのように捉え、前向きな姿勢を取る必要性があるのかについて考えることができました。本日の内容では、国家のなかに存在する自由について考えさせられる内容であったと思います。一定の枠組みの中に存在する自由を私たちは秩序を維持しながらも獲得することができるようにと変容していったことについて学習することができました。初めて講読会に参加し、とても難しい議論内容ではありましたが、大変勉強になりました。ありがとうございました。
管理内の自由・人口を増やすための自由というところで、同性婚が認められないことも関係あるのかなと考えました。 ジェンダー平等が叫ばれる中、同性婚への取り組みが遅いと感じています。コロナによって社会が変革する可能性もあると思いますが、ジェンダー平等の過程で、人口の重要性が変化するのかなとも考えました。