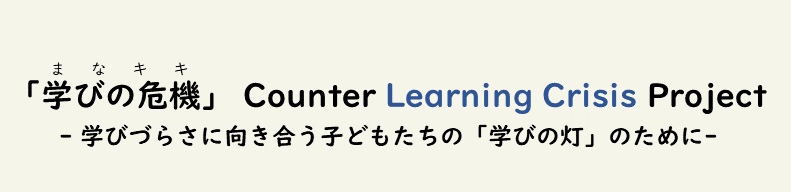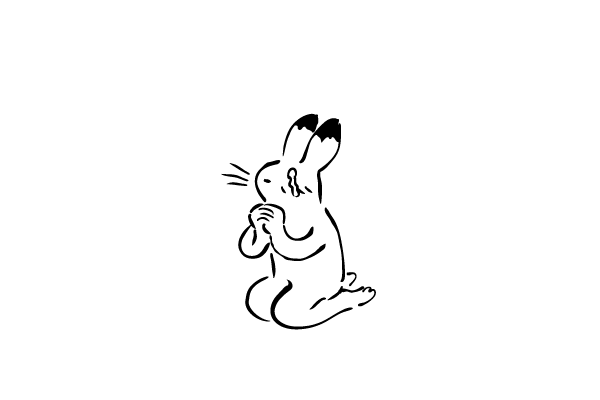▶ を押すと文が増えます
- 講読会について
- 第一講| 一九八〇年一月九日「真理の現出化」 他 /2022年10月11日
- 第二講| 一九八〇年一月十六日「統治と真理の諸関係」 他/2022年10月18日
- 第三講| 一九八〇年一月二十三日「真理陳述の手続き」 他 /2022年10月25日
- 第四講| 一九八〇年一月三〇日「真理の二つの体制」 他 /2022年11月15日
- 第五講| 一九七八年二月六日「真理の体制の帰結」 他 /2022年11月22日
- 第六講| 一九八〇年二月十三日「主体性の歴史」 他 /2022年11月29日
- 第七講| 一九八〇年二月二十日「主体性と真理の関係」 他 /2022年12月6日
- 第八講| 一九八〇年二月二十七日「法の体系と救いの体系」 他 /2022年12月13日
- 第九講| 一九八〇年三月五日「自己と事由の開示」 他 /2022年12月20日
- 第十講| 一九八〇年三月十二日「自己の探究と良心の検討」 他 /2023年1月10日
- 第十一講| 一九八〇年三月十九日「指導・従属の諸特徴」 他 /2023年1月17日
- 第十二講| 一九八〇年三月二十六日「生者たちの統治」 他 /2023年1月24日

「Fact」と”Fact”が、「真理」と“真理”が激しくぶつかり合い、社会が粉々に分断されていくこの世界において、学問に、科学に、思想に、何ができるのか。Post COVID-19の荒廃した時代の中で、ミシェル・フーコーの〈真理・自己・権力〉の議論を手がかりに、「生きるもの」としての統治のあり方を再考します。
※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
(どなたでもご参加いただけます!)
講読会フライヤーPDFはこちら
講読会について
講読書籍
ミシェル・フーコー講義集成 < 9>「生者たちの統治」
(コレージュ・ド・フランス講義1979-80)
ミシェル・フーコー著 廣瀬 浩司訳 筑摩書房(2015年)
講読期間
2022年10月11日(火)~2023年1月24日(火) 全12回
開催時間
18:00-19:30ごろ(入退室自由)
参加方法
ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。
- ①一般参加会員
その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。
当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員
継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。
講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
※ 参加登録は一度のみで完了いたします。
※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。
お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加
特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。
一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。
ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。
お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!
第一講| 一九八〇年一月九日「真理の現出化」 他 /2022年10月11日
当日資料はこちら
当日リポート
ようやく始まりました、まなキキ・オンライン講読会の第6弾ということで、「みんなでユルく読むフーコー」(通称、ゆるフー)のパート3です。
柴田先生から、なぜこの本なのか、ということもご案内いただきましたが、岸田首相の所信表明演説で「マスク着用」の話題が上がるほどに、このCOVID-19時代は、マスク着用にせよ、ワクチン接種にせよ、その是非を問う際に、人々が「正しい」と捉えるものがあまりにもバラバラで、私たちはさまざまな分断に直面しているともいえるのかもしれません。
フーコーは、こうして私たちがバラバラになってしまう理由、みたいなことも、おそらく触れてくれている社会学者でもあり、思想家でもあるはずです。そんなわけで、今回もフーコーを読んでいこう、ということになりました。
ちなみに、取り扱っている文献は、ミシェル・フーコーの講義録、ということになっています。いわゆるopen universityとでも表現されるような、フランスの最も叡智が集結したコレージュ・ド・フランスでの講義の様子が収録されています。誰に対しても開かれていて、且つ毎年新しい知見を提供することがオブリゲーションとして求められている講義です。
今回も、この講義録を読み解いていきます。
ということで、今回の内容は『生者たちの統治』とタイトルがつけられた1979年から1980年にかけての授業の第一回目の講義の内容でした。
ローマ皇帝セプティミウス・セウェルスとオイディプス王(古代ギリシアの悲劇作家ソフォクレスによる悲劇・フロイトの言うエディプス・コンプレックスの元ネタとなった物語)を対置させて紹介しながら、「真理の現出化」(アレテュルジー)について考えていこうとするものでした。
そもそも「事実」と「真実」って違うのだろうか?何が違うのか?という疑問が、議論の中でも挙げられていました。一般的に、「事実」としてのfactに対して、「正しい」という価値判断を含んだものとして「真実」truthが位置付けられることもあるようですが、おそらく、何を「事実」と思うか、事実認定を試みる過程で、そもそも「真実」の意味を満たしてしまうのではないか、という指摘も柴田先生からされていました。つまり、「事実」とは、「真実」のことも同時に意味するようなものだ、と。
国定教科書などで取り上げられているものは、(どんなに議論がされていても)それが「事実」とされた結果でもあるわけです。一概に、「うーん」と納得できない人もいらっしゃるかもしれませんが、それが「事実認定」の難しさをまさに物語っているといえるのではないでしょうか。
ただ、今回のフーコーの講義の中で、間違いなく「真実」factとして認められるものは、セプティミウス・セウェルスの宮殿に描かれた星空でした。いわゆるホロスコープです。この皇帝が産まれた日の夜空の星々の位置に偽りはない。その星々において、「自分が王である」とする―ーそこに真理の現出がありました。
今日は議論の中で、プーチンがウクライナ4州を併合した際の祝賀集会の様子の動画も一緒に確認をしました。その中でプーチンは「我々の中に真実があり、だからこそ、勝利する」といった発言をしていました。プーチンを前に大勢のロシア国民が拍手と喝采で迎えるその事実を以て―ーある種そうした”儀式”を通じて、プーチンにとっての(ロシアにとっての?)真理が現出されていたといえるでしょう。
こうした「真理の現出」ともいえるような過程はさまざまな形で現れてきていたともフーコーは指摘していました。例えば、その中で、フーコーは、ある知識を持っているか、持っていないかという知識の不公平感があり、そこにから権力が生まれてきている、という指摘をかつてしていました。ですが、おそらくそれだけでは説明できないことがある、と気が付いたからこそ今年の主題になったのではないか、今回「知-権力」概念から「真理」の概念を考えていかなくてはならないとなったのではないか、という解説もされていました。
知識がどれだけあるか、ということで統治は果たされない、ということ―ー
それは、ドラえもんの出木杉君は統治者として描かれていないことからもうかがえるのかもしれません。一方でジャイアンはもしかしたら統治者として描かれているのかもしれない。プーチンが統治者となるのは、その言っていることが「正しく」、それに同意する人たちがいるからです。
私たちが、「事実」を求めようとすればするほど、「真理」からは逃れられなくなってしまうのかもしれません。ただ、「科学」がそこでできることは、反証可能性を常に意識すること、なのかもしれない。仮説の域は脱しないにはせよ、ほぼほぼ事実と認めてもいいだろう、という蓋然性の高い事実に基づいて、ひとつひとつ積み重ねながら検討を重ねていくということ。私たちが「事実」を求めることが、つまり「真理」/「真実」にとらわれてしまう、ということとほぼ同義であることを意識しつづけるということ。
……こうした実践が実際にどのように体現できるのか、ということをも、これからの講読会の中で、皆さんと一緒に考えていくことができたら、と思います。
次回は、オイディプス王に関すること。あらすじを理解してから参加していただくことをオススメします!
参加者の皆さんからのコメント
無学なので『セプティミウス・セウェルス???』の話は聖書の中の話ですか?
コリントという言葉から聖書の話かと思いました。プーチンに洗脳されていれば真理だからと言われているので、民衆に支持されるのは当たり前ではないでしょうか?マスクの話は自分で考えられるから、正しいか正しくないのかは判断できます。プーチンの話とは別次元のように思います。哲学的な話でinterestingでした。
聞きなれない言葉や知らないことが多く、とても新鮮な講義であったが難しかった。大学院では、このレベルの話が理解できないとついていけないのだと学んだ。情報が溢れすぎている現代では、先ずは知識を身に付け、ロシアのように間違った道に進んで行かないように、何が真か偽かを見極める洞察力をつけることが大切だと考える。
セプティミウス・セウェルスは権力の行使を正当化するために、真理の表明として真実である天空の星空を利用した。オイディプスの例は真理に翻弄される話であるが、何を真実と認定するかは難しい。事実は様々な形で成立しうるから、それを証明しようとするとそこに権力が宿ることにもなる。
何を正しいと言うか思うかは人によって様々である。それこそ事実と真実の違いは何か?という質問に対しても答えは人それぞれ違うのがそのことを示している。事実があると考えてその事実を求めることが真理論になり、事実と真実は一体的であるとも言える。
真理を現出させる儀式と権力行使の関係は単なる功利性にはおさまらない。統治があるところには必ず「真理の現出」があり、その「真理の現出」は経済合理性を目指す意味での真理とは次元の違うところで行われてきたのではないか。「fact」は様々な形で存在し得るが、あるfactをfactであると証明しようとする=真理の現出を目指す、ということでそこに権力が宿る。

「ゆるフー」なのか「ユルフー」なのか…も議論が残りそうですが。
また、ジャイアンは統治者じゃない、っていうかドラえもんに統治者は出てこなかったよね、とも思いつつ…
反証可能性については、触れておきたいと思います。フーコーの議論の中で出てくるものではなく、実はカール・ポパーがいう「反証可能性」の議論を使いながら、フーコーを理解していくうえでの補助線として活用出来たらという狙いもあります。
ところで、洗脳の仕組みについて考えてみると、よくその手段として使われる「プロパガンダ」も、別にだます仕組みとして用いられているわけではないことに気が付きます。プロパガンダは、ひたすら「正しさ」「美しさ」を演出することで、それによって統治をしようとするものです。「正しい方がベストだ」という主張することで力を得ようとしているのがまさに、現在の国家元首たちにももしかしたら該当するところですが、科学はそうは考えません。「自分が間違っていると疑ってかかる」姿勢に立つのです。
何が真?偽?という問いは、真に対する偽が存在していることを前提にしていますが、本当に「真」以外はみな「偽」なのでしょうか。実は、私たちが直面しているものは、「真」と「真」の対立なのです。これを「ファクト」と「アルト・ファクト」などと表現したりしますね。「真」と「真」が対立し、より正しかったほう―ー説得力があったほうが権力を持つ、という構造になっています。
実は私たちも、何かしらの「ファクト」に基づいて生きています。その中で、自分が言っていることが間違っている可能性を疑うことは、あらゆる反対や反論を受け付けて、その過程によって確かさを高めようとする試みでもあるのです。これが科学が持つ反証可能性の発想です。
第二講| 一九八〇年一月十六日「統治と真理の諸関係」 他/2022年10月18日
当日資料はこちら
当日リポート
今日は、『オイディプス王』という物語にどっぷり浸りながら、フーコーが言わんとしたかったことを探っていくような回となりました。
『オイディプス王』の主人公、オイディプスは、「父親を殺し、母親と交わる」という不吉な予言を受けて、なんとかその予言から逃れようと抗いながらも、成就してしまう、というような悲劇として描かれています。というか、その不吉な予言「父親を殺し、母親と交わる」が成就してしまった、という「真理」が明かされていく過程が描かれている、ともいえるような作品であったかもしれません。
(アリストテレスの悲劇の本質的要素には、「状況の転換」と新たな事実が暴かれて起こる「認知」がある、としていましたが、まさに「真理の道のりや働きがおのずから登場人物の運命の逆転をもたらす」(p27)ような作品となっていました。
実は、神様の予言という形で、「真理」は最初から出オチ状態なわけですが、「本当か?」というようなコロス(コーラスの語源になっている、作品の進行役的な存在、とも説明がありました)のツッコミ?を受けて??、オイディプスやイオカステ(母であり妻でもある;つまり予言は成就してしまっている)、そして文字通りのキーパーソンたる召使や奴隷が、証言をしていくことを通じて、神様が予言した「真理」と同じ「真理」に、別ルートで到達する様が描かれていたのが、『オイディプス王』の物語でありました。
『オイディプス王』の物語では、既に、神様や予言者、占術師による「宗教的・儀礼的アレテュルジー」が真理を現出しているのに、そうではない手続きを通じて、真理を現出させようとする働きが示されていたことが描かれていました。
逆に言えば、真理の現出は、宗教的・儀礼的アレテュルジーがなくても、達せられうる、ということが、もしかしたら注目すべきポイントなのではないか、と講読会の議論も展開していきます。
このもう一つの真理の現出を担うのが「奴隷たち」の存在です。そして彼らが果たした真理の現出は、「奴隷のアレテュルジー」と称されていました。
奴隷のアレテュルジーが達せられるには3つの条件があるということも紹介されていました。
1.言われたことにのみ答える、「尋問」という形式をとること。
好き勝手に、言いたいことを話すのではなく、望まれたことについて回答する、というもの。
2.記憶されたものについて語ること。
フーコーの講義録では「追憶と記憶の掟」(p44)と紹介されていました。
3.まさにその場にいたこと、彼ら自身の目で見、彼ら自身の手で行動したということ。
のち、アウラという言葉で説明されるようなもの、とのことでした。
この形態が私たちに連想させるのは、まさに「裁判」という方式です。
つまり、裁判の形式をとれば、真理に到達することができる、そういうテクノロジーとして、『オイディプス王』にでてくる奴隷のアレテュルジーを捉えることができるのかもしれません。
裁判において繰り広げられるのは、原告と被告のそれぞれが持つ「真理」を戦わせる、真と真のゲーム;真理のゲームです。
その場に「神秘的なもの」は不要であり、かつ「真理」は各々に内在するということにもなります。
フーコーが『オイディプス王』を挙げながら議論したかったのは、この、真理の手続きのルールであり、かつ、この真理の現出は、「奴隷―ー真理に対する奴隷」にこそ、達成しうるもの、ということだったのかもしれない、とも解説をしていただきました。(実際、裁判においても、全員が真理の奴隷となる。)
ここから、「真理」というものが、神様などから、あるいは天井の星空のような形で、外部からもたらされるものではなく、私自身やあるいはあなた自身から出て来うるものだ、ということに注目していくことになりそうです。
これまでのフーコーでも「羊」が登場してきましたが、今回のフーコーにも「羊」が登場してくることになりそうです。じゃあ、タヌキや猫もまた出てくるのかな?という期待もしつつ、引き続き読み進めていきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
今回の講読会で読んだような本にはたくさんのカタカナ用語(アレテュルジーやコロスなど)などがあるためまずは、言葉についての知識を身に付けることが重要だと感じた。また、普段の生活では絶対にこんな難しい本を読んでみようと言う気にはなれないため、フーコーの思想に関われる機会を得られたことが率直に嬉しい。
第一回の購読会に参加できなかったこと、またこのような難しい本を読んだことは初めてだったので、正直理解には追いつきませんでした。ですが、奴隷のアレテュルジー?が現代の裁判と同じ形式であると知った時、何か心の中がすっきりとした感覚がありました。貴重な体験ありがとうございました。
講読会のメンバーの方達?が、今回読む本について「私の考えはこうだ。」「私はこう思う。」など、一人一人が深い知識を持ちそれを表明することで、議論がより深いところになり面白くなっている様子を見て、一つのことに詳しくなるとそれについて語ることができるためより進んだ学びを得ることができると言うことを学んだ。皆さんが議論する様子を見て真の学びの様子を伺っている気分であった。
『オイディプス王』の話を理解していないためか、前回も含め、あまりよく分らなかったが、今日の柴田先生のお話で、やっとモヤモヤしていたものがすっきりとして納得した。人間は神や預言者なしで真実に到達できる方法として、裁判という形式をとっているということが分かった。回を重ねるごとに興味が湧いてくるようだ。
神の言葉は一方方向であるため、それを受け取る人が必要である。真理の現出には神や預言者の言葉だけでは到達できない。もう一つのルートとして、奴隷に尋問するように、問いかけに答えること、記憶されていること、その現場にいたことを証明する手続を経て真実に到達することができる。
オイディプス王の物語をもとに、真理がどのように現出するのかについて考えた。真理が現出するためのプロセスとして、神の語りが必要であるパターンがある。しかし、それとは別に奴隷が尋問形式で語ること、記憶された過去の事実であること、現場にいたという事実があれば神の預言なしで真理の現出が可能であるということがわかった。
現代では、神の預言ではなく人間の証言が真理を現出するという考えが一般的だと思うが、オイディプス王の物語の中では神による真理の現出が主流なものとされており、奴隷のみでの真理の現出が神に依存しない新たなプロセスとされていることを学んだ。また、奴隷による真理を現出するための条件が現在の裁判に似たかたちだということも学んだ。
オイディプス王の物語では、登場人物によって、事実の見方や捉え方が異なっており、それが各々の真理の違いになっていました。その物語では、登場人物がそれぞれの真理に従って行動しており、それが悲劇的な展開に繋がっていました。この物語は、世の中の縮図であると自分は考えました。神の意見や宣言は、同じであるのに人によって真理が異なっていました。
前回のフィードバックで、「この世界は真と偽で出来ているのではなく、真と真で出来ている」という話があり、正義の反対はまた別の正義であるという言葉がまさにぴったりだと感じた。プーチンは自分の考えを本当に正しいと感じていて、その信念を貫いているように感じる。どちらの考えがより正しいか、ではなく、論理としてどちらがより強いか、なのではないかと思わされた。今回は、真に到達するルートについて考えた。私利私欲のためではなく、あくまでも尋問という形式をとること、それをきちんと記憶されているということ、そして、現場にいたという条件が揃って初めて証言として成り立つ。だからこそ、奴隷的であると考えられる。奴隷がその役割を担うということはすごく意外であった。裁判の形式が埋め込まれていて、その形式が最も合理的であるということに気付かされた。それに加えて、「奴隷の方が到達できる」という先生の言葉にハッとさせられた。
真理の現出の部分で奴隷という単語が出てきた時、王に支配されているような存在を思い浮かべていました。物語の中ではその意味での奴隷でもあるのかもしれませんが、「記憶というかたちでしか真理を語れない」とあるように神以外の人間を表すものに近いのかなと考えていたので、柴田先生の真理に対する奴隷という話しを聞き、奴隷と真理の現出の部分が理解しやすくなりました。

Mせんせいに、「本当にタヌキとかキツネとか、でてきたんですか」と聞いたら、過去の記憶を頼りに、かつご自身の目で見たということで、証言してくれていましたね。まさに、「奴隷のアレテュルジー」がなされていたともいえます。
奴隷のアレテュルジーが裁判の形式を持つ、という話をしてきましたが、このような形での真理の現出は決して歴史的に普遍なものではなかったということは興味深いことですよね。裁判における証人が奴隷である必要があるというのは、その証言が私利私欲に基づくものであってはならない、ということの裏返しともいえるかもしれません。ただ、そうした奴隷のアレテュルジーの中に権力や統治の仕組みが入ってくる、そういう可能性がこれから論じていけるのかもしれません。
講読会への参加そのものの感想についてもお寄せくださりありがとうございます。マインド・マッピングって流行っていたりしますが、ぜひフーコーの頭の中をマッピングして理解しよう、という意識を持って講読に臨めると、また別の次元から理解が深められるかもしれません。
フーコーが取り組もうとしていることは、「真理の現出(アレテュルジー)」であって、どのような真理であるかを問うのではなく、その真理がどのようにプレゼンテーションされるのか(理解され、つまびらかにされ、明らかにされるのか)ということだったといえるでしょう。その方法の一つが神様や予言者によるもので、二つ目が奴隷、証人によるもの。この後者に注目し、そのような真理の現出と権力の発動に注目していこうとしているわけですね。
第三講| 一九八〇年一月二十三日「真理陳述の手続き」 他 /2022年10月25日
当日資料はこちら
当日リポート
ニュースでは、ロシアとウクライナの紛争を伝え、中国の党大会の模様なども報道されています。そこにあるものは、「偽」ではなく、やはり「真」。「ロシアが勝っている」とか「ロシアが苦戦している」とか、そうした「真」と「真」がぶつかり合っている、まさに真理のゲームとも理解できるような状況が報じられています。また、中国党大会での胡錦涛前総書記の途中退席。これも、何かしらの「真実」を現出したものであったのかもしれず、思惑と思惑がぶつかり合う、ある種の権力の存在を意識させられてしまうような出来事でした。
だんだんと、真理を語る資格を持つ主体―ー奴隷?証人?…今まさにここにいる「個人」へとフォーカスが移っていく気配を感じながら、今日の話題に入っていきました。
特に今回は、結局オイディプスは、なぜ罰を受けなくてはならなかったのだろう??という疑問から議論がスタートしていきます。オイディプスは決して性格がよいわけではなかったかもしれませんが、しっかりテーバイという都市に対して貢献もしていたのです。
例えば、スフィンクスの謎を解くことでテーバイの街を救ったという事実。コロスもオイディプスを称賛していたのは、そういった事実があったからでした。それでも、オイディプスが罰せられてしまったのはなぜか、という問いを考えていきました。
フーコーは、オイディプスがスフィンクスの謎を解いたりする行為のことは、グノーメーと整理していました(p76)。このグノーメーは、意見、思考法、見解、判断などとも説明されていましたが、講読会の中では、うまく知識を生かしたり、もうけたりするようなこと;役立っていること―ーと説明されていました。
実はフーコーもかつて、権力や統治について論じるとき、こうした功利的な側面を強調してきた経緯がありました。(「効率的に統治するために有益な知識を構成したり形成したり集約したりする」(p25))今回の講読会の第一講目の内容でも、フーコー自身が語っていたとおりでもあります。
ですが、どうやら統治において、それ(グノーメー)だけではダメだ、ということをフーコーは指摘したいようなのです。これまでフーコー自身がしてきた指摘を刷新するような新たな指摘を試みようとしているとみなせる統治に関する議論の新展開なわけです(わくわくっ)。
このフーコーの統治に関する指摘に基けば、オイディプスが罰せられなければならなかった理由;グノーメーとはまた別のものをオイディプスが達せられなかった(持ち得なかった)が故、と理解できるのです。
統治において大切なもう一つの条件とは何か:フーコーはそれをテクネー・テクネースとして説明していきます。テクネー・テクネース(究極の術、人間たちを統治する術→良心の指導、魂を指導する術, p58)です。これは、真理の現出を通じて統治する正当性:正しさを示し続けること、として講読会のなかでは説明がされていました。
統治が行われる際、そこではもうけていたり、うまく機能していたりしているだけではだめなのです。うまく機能していると同時に、そこで行われている統治が「正しい」こと―ー歴史的な意味においても、社会的な意味においても正当であることが示され続けていなければならない…ということをフーコーは『オイディプス王』を通じて指摘していたのではないか、と議論されました。(神意という「掟」に書かれたとおりに何かが実践されている状況下ではおそらく「統治」は発動していない、ということも確認されました)
『オイディプス王』において、私たちは最初からオイディプスが「正当性」を持ちえず、オイディプスが王としての「正しい」という真理を現出できずに終わる「悲劇」を知っていました。まさに、テクネー・テクネースを持ち得なかったから、オイディプスは、私利私欲から振る舞っていたと批判されたりして罰せられたんだなあと理解できるわけですが、現実世界における統治の世界では、誰も「真理」を知りえません。それでも、統治の場面では、各々が「真実」と信じるものを現出させていく、まさに真理のゲームが繰り広げられているといえるのかもしれません。
ここからは、テクネー・テクネースで真理の現出に貢献していた奴隷や証人といった一人の個人について考えていくことで、「アウラ」=私という視点、真理を語る資格を持つ「個人」としての私に、議論を進めていくことになりそうです。
ギリシア神話から、少し離れて次の話題へと展開していく…ということで次回の講読会開催まで少し日があきますが、読み進めていくのが楽しみですね。どうぞよろしくお願いいたします。
参加者の皆さんからのコメント
私は今日初めて参加したので、話の内容に全然ついていけなかったです。カタカナの用語がたくさん出てきて理解が難しかったのですが、「権力を振るうには正しさが必要」という意見にはとても納得がいきました。また自分の正しさを証明しようとしすぎるが故に、独裁的な政治になってしまうこともあるのかなと思いました。また今度参加しようと思いました。
真理を真理と思わせることが権力を維持する上で必要だけど、それが私利私欲に見えると権力を失いかねないというジレンマがあり、統治することの難しさ、危うさを感じました。知というものを、誰がどのようにコントロールするか、も重要な点だろうと思いました。民主制についての言及もありましたが、知がコントロールされている以上、無知な人は発言権を持てず、民主制など実現できないのではないか(まさにロシアや中国のような)と考えさせられました。
第二のアレテュルジーとは自分から出発するものである。また自分が正しいことを証明するためのものがテクネー・テクネースであり、真実に基づいて勝つことが必要である。今までは権力は私たちをうまく動かして儲かるように活かせばよかったけど、フーコーはそれだけではいけないと否定し、「正しい」ということも重要だと主張した。
権力とは正しくないといけないということを学びました。権力を振るうのは私利私欲はだめで、自分が正しいということを証明するためのものであり、かつ利益も出さなければいけないという難しいものだと改めて分かりました。またこれを求めていった結果、自国の正しさを証明し合う戦争が起こるということも分かりました。
オイディプスはなぜ権力を失ってしまったのかということについて考えさせられた。権力には、きちんと役立っていることと、真偽を発見し続けて真実に基づいていなければならないという二つの側面がある。私は、うまく統治できていればそれでいいと思っていたが、そうではないということを学び、その上で現在のロシアや共産党の状態を見ると、非常に腑に落ちるところがある。
権力には「役立っていること」と「真理を解明し発見し続けること」の2つの技があり、片方が欠けてしまうと統治者ではいられなくなることがわかった。オイディプス王はポリスに対して悪いことはしていないが、真実に叛いたために権力の座から引きずり下ろされてしまい、権力の使い方が私利私欲に見えてしまったことが問題点であった。それゆえ、統治は真理に基づいていなければならなく、統治の正当性を論証しなければならないと言うことができる。今回の話を聞いて、真理は権力に深く関わっているということを始めて知った。

「真理」というものが、神様とかそういう誰か他者から与えられるものなのではないかもしれず、証人としての「個人」がいて、それを通じて「真理」が構成されているのだ、ということが明かされていたように思いますが、とてもおもしろいところですよね。
先日、米中会談や米国議会の中間選挙もありましたが、いずれも「私利私欲」とは無縁だということを主張しますし、政敵の批判も相手の「私利私欲」の存在を指摘するようなところが多いですよね。でもフーコーが言う「真理」とは、私利私欲とは切り離されたような「奴隷」のような存在による証言が重要な意味を持っていたわけです。
ちなみに、トランプはビジネスマンとして、あるいは腕のいいトレーダー、商売上手な存在として評価を受けている側面があるようですが、その彼がこだわるのは「fact」だったりするんですよね。権力とは有用性だけでなく、「正しさ」が重要というのは、そのようなところにも象徴的に現れているように思います。
第四講| 一九八〇年一月三〇日「真理の二つの体制」 他 /2022年11月15日
当日資料はこちら
当日リポート
2週間の時間が空いてしまいまして、久しぶりの講読会となりました。その間に世界も劇的に変化していて、また次回までの一週間にもいろいろなことがあるのかもしれません。
そのいろいろな「何か」の中に含まれるかどうか、は分かりませんが、まなキキのイベントも開催されます。よろしければ、ぜひご参加ください。笑。
今回の講読会で、まず確認されたのは、フーコーは「イデオロギー」による分析はやらない(p86)、って言っているけど、じゃあフーコーがやろうとしているという議論はどういうものなの?というあたりからでした。
「イデオロギー」による分析とは、もしかしたら多くの、普通の研究が取り上げがちな方法ともいえるのかもしれません。それは例えば、「狂人とは〇〇である」とか「狂人になる原因は〇〇なので、△△によって狂人化を防ぐ」などのように、”狂気/狂人がある”ことを前提にされるような議論であり、問いです。
でも、フーコーがしようとしているのは、「なぜ、この社会は狂気を必要としたのか」ということなのです。フーコーにとっては、狂気そのものがあっても、なくてもどちらでも構わないかもしれないのです。ただ、「狂気」と呼ばれるようなものが議論されなくては・取り沙汰されなくてはならなくなった、その”そもそも”の事態を問おうとしている、ともいえるのかもしれません。
そうしたアプローチを採ろうとするからこそ、権力から自由になって議論ができるし、「権力」を正しく取り扱うことができる、と考えたと解説がされました。
ここでいう、「狂気」はもちろん「権力」や「福祉」、「障害」などの言葉に置き換えて、考えていくこともできるかもしれません。というか、フーコーはそういう試みを続けてきた、ともいえます。所与のものとしてそれぞれを取り扱うのではなく、こうした概念がなぜ、必要とされてきたのか、というようなことを問う、ということ、ともいえるのかもしれません。
ちなみに一見、こうした議論をすると、アナーキズムを推奨しているようにみえるかもしれないけど、そうではないよ(でもアナーキズムを全否定しているわけでもないよ)ということもフーコーは指摘していました。(p89)権力がないほうがいいとか、そういうことを言っているのではないのです。「権力」そのものに対する評価をするのではなく(評価をしてしまうと、権力の存在を前提とせざるを得ない)、「権力の自明性を疑う態度(p89)」に基づいて議論していくと説明しています。
フーコーは、「イデオロギー分析」に陥ることなく、権力の行使において真理の現出が不可欠であること、その真理の現出には、奴隷的な証人としての「個人」のかかわりが不可欠であるということ。それが万人を救出するような構造になっているのだ、ということを説明していこうと思う、と宣言しています。
そしてそれを考えていくうえでの題材とするのが、キリスト教の真理の体制でした。
キリスト教における真理の体制には二つあり、一つが「信仰の体制」であり、もう一つが「告白の体制」としています。
前者の「信仰の体制」とは、いわゆるオイディプス王での神託や預言に相当するような、神様のいうところを信じる、というようなこととして捉えられるかもしれません。
今回、注目していくのは、後者の「告白の体制」のほうです。告白では、(1)真理の現出の遂行者はその本人であって、その本人が他者に強いられるわけでもなく、自ら自立的に実施するもので、(2)その告白を客観的にも認める証人としても両立しえ、(3)自分について語る、という再帰性の特徴を持つものです。
キリスト教において、この「信仰の体制」と「告白の体制」が真理の裏側にあるものとして説明されていたわけです。
「信仰の体制」と「告白の体制」は緊張関係にあるが、お互いに深く根本的な関係を持っているとされています。実際にプロテスタンティズムの特徴なども、この両者の結びつきを以て説明することができてしまうとフーコーはしています(p98)。
フィロンの例を挙げつつ説明されていたのは、「告白の体制」においては「正しい行いをする」とか「神様に祈る」ということが救いの要件になるのではなく、「自分自身を内面化して告白していく」ということが救済の要件であり、それがキリスト教という真理を現出するものだ、ということだったのだと思います。実は、この発想は、ギリシアにおける太陽神信仰とも連なるものがあり、西洋社会における「統治」を理解するうえでも伏線となりうるような、通底する発想として捉えられるだろう、とも確認されました。つまり、フーコーが今回取り上げた「告白」という「真理の業」が、もしかしたらヨーロッパの民主主義ヨーロッパの個人主義などの根源的な部分にも相当するのかもしれない、ということです。
ここからより、真理の体制についての理解を深めていくよう、議論を読み進めていけたら、と思います。真理の体制=イデオロギー、すなわち、真理の体制とは社会体制を示すようなもの、として読んでしまいたくなるかもしれませんが、真理の体制がもっと細かいことを指している可能性がある、と意識しながら読んで行けるとよいかも、とのことでもありました。
難しい!と思われるところもあるかもしれませんが、みんなと一緒に、ぜひ「ゆる」っと議論していきましょう。引き続きよろしくお願いいたします。
参加者の皆さんからのコメント
個人は、権力関係における主体であり、真理を現出する際の行為者、証人あるいは対象にもなる。キリスト教における真理の体制には、信仰の体制と告白の体制の二つがある。告白の体制として、裁きの対象となった場合には、自らの行いを自主的に、客観性をもって認めることによってゆるされるという考えが西洋社会に広まっている。
フーコーの考える無政府主義とは、政府のある社会を否定するのではなく、絶対的だと思われている政府の存在を一度抜きにして考えてみようというものだった。それは無政府主義に限らず、どのような論題においても適用されるものである。前提を疑うことが、議論の余地を広げ、真理に近づくことを可能にする。
権力の存在が前提とされて議論がされがちだが、そもそも権力があるべきなのかを問うべきだとフーコーは述べているのではないかという話を聞き、大学院生の方々との議論を聞き、フーコーの主張について考えさせられた。
イデオロギーではなく、根源を問うべきだというフーコーの考え方は、権力に限らず福祉や教育など様々な話題に応用できるということを学んだ。福祉の問題について考える際、福祉があることが前提として議論をしてしまいがちだが、そもそも福祉はあるべきなのかという根源を問う考え方をしてみることも必要だと学んだ。

社会に埋め込まれているエンジンのようなものとして、「告白」という真理の業があったというふうに、まずは理解することができるのかもしれませんね。また、まとめについて一点だけ修正させてください。前回確かに、ヨーロッパの民主主義にも通底していくようなものかも、とは話をしていたかもしれませんが、フーコーはそこまでは言及していなかったかもしれません。「ヨーロッパの個人主義」くらいまでを言及していたと、理解しておくのがおそらく妥当でしょう。
考えてみると、自分のことを大騒ぎして取り沙汰するような文化や思考、個人を確立させて物事を議論するというのは、ヨーロッパの特殊性ともいえるようなことなのかもしれないのです。いわば《主体の析出》が実践されていて、それが次第に民主主義や至上主義のベースになっていったとはいえるのかなあと思います。『鎌倉殿の13人』などをみていても、「北条家を守るため」、「源氏の復興」など、あくまで家の話しかされず、個人のことは語られていないのも面白いですよね。
今の私たちにとっては、「主体」があることがあまりにも当たり前になっていて、敢えて議論されることが少ないのですが、近代ヨーロッパから個人という発想が出てきているといえるのかもしれないですよね。また、政治や権力があることを前提に議論するのではなく、それがあってもなくてもよいという立場で議論すること。「あるべき」「ないべき」というイデオロギーの地平に立たず、それが議論される意味を知ろうとすることがフーコーが試みたものなのですね。
第五講| 一九七八年二月六日「真理の体制の帰結」 他 /2022年11月22日
当日資料はこちら
当日リポート
先週の土曜日には千駄ヶ谷祭というイベントにまなキキは初参加し、そこには「えーあい先生」や「漢字ちゃん」という存在も出演していました。これらの人物?は、キャラクターにすぎない存在なのか、それとも実在した人物?なのか、という謎も少し取り沙汰されながら、今回の議論は始まっていたともいえるのかもしれません。えーあい先生だとか、漢字ちゃんだとか、こういう問題を取り扱う際に必ず出てくる「守らなければならないこと」/「義務」とはどういうものなのでしょうか?
フーコーは、「真理の体制」をいわば真理の義務、真理が強いる「守らないといけないもの」について説明していました。これは政治論とも科学論ともきりはなされるべきものだともしていたようです。
例えば何かを強いることは、政治論につながっていきます。真理であるかどうかを問わず、義務は発動し得るのです。ジャイアンの言うことが「正しい」と思っていなくても、ジャイアンに従うことはあり得て、その義務に従属するか否かは、真理の体制とは関係なく行われます。政治論の範疇として説明することができるものなのだ、といいます。
一方で科学論は、「何を真とするか」を問うていきます。何が真理とみなせるのか、という議論はいわゆる知識論や科学論に該当するものですが、いわば狭量な一つの見方にすぎないことをフーコーは指摘します。結局、ここで「真なるもの」が同定されても、すなわち義務が発動することにはならないのです。
でも、真だと守らなければならないものが発動する=真理の体制と言えるようなものが、唯一存在しているとフーコーは指摘します。
誰もが、えーあい先生や漢字ちゃんは、「実在しないだろう~」と思っていたとしても、えーあい先生やら漢字ちゃんを標榜する、その当人―ー個人や主体は、絶対にその真理を守らなければならないのです。自らがその真理の対象となった場合に、「自分自身の存在を真理として現出させる義務」が働くということをフーコーは指摘していたようです(p116)。
そして、これをキリスト教の「告白の体制」という真理の業が練り上げ、昇華させ、洗練させ、そしてspreadさせていった、ということが説明されました。
いわば、「主体」というものの存在が、真理の現出において重要な役割を担っていることが指摘されていったともいえるでしょう。それは、政治論とも科学論とも切り離されて論じられるような種類のものです。「私自身」が思っていること、自分が知っていることを開示していくことが、ある時点において求められ、制度化されていったともいえるのかもしれません。
自分にとっての真実に向き合っていく過程とは、その当人である自分を切り刻むような、いわば辛くなるようなプロセスともいえるのかもしれない、とも講読会では共有されていました。安易にイデオロギーに則ってしまったほうが楽な議論なのかもしれない。けれども、そうではなく、自分自身が、取り沙汰される「権力」や「科学」に対して何を思い、考え、知っていると捉えていこうとするようなことが、フーコーのいうところの「知への意志」にも繋がっていくような試みなのかもしれません。
キリスト教が、「告白の体制」を通じて練り上げていった思考様式が、こうした「知への意志」すなわち、個人主義的な発想の萌芽に深く関与していたのではないか?というフーコーの主張について、引き続きの講読会を通じて、ぜひフォローしていきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
真理の体制の難しさを痛感した。フーコーは真理が何かを強いることが真理の体制になり、真理の体制というと、政治論か化学論の二つの議論に勘違いされがちだと言った。真理だから守らなければならないということが、何かを強いる義務論・権力論・政治論、つまりは何でもいいから強いられているという議論や、何を真とするかということを議論する化学論と我々は誤解しがちである。それらと真理体制論は別であるという主張をしたかったのだということを知り、真理の体制について学ぶことができた。
真理の義務が真理の体制になる。真理は政治論か科学論に誤解されやすい。何を真とするかとそれを守るかは関係ないが、真理の現出化において自らがその対象となった場合にそれに対する真理があるときは義務として自分に課される。
主体は真理の体制がなくても、真なるものに常に正直で、守らなければならないという点で特別な存在である。しかし、主体が真に従わなければつまり、自分を他人と異なる存在として認識できていないということである。それはフーコーによれば狂気であり、現代でもアイデンティティの喪失として問題になる。
真理は強制力を持っているため、真理の体制をとる必要がないと考える人がいるが、それは間違いである。真理が真を示しているということと、それが真だから従わなければならないということは区別しなければならず、真であるということ自体に強制力を起こすのは主体に対してのみである。
非常に難しかったので、正しく理解できているかわからないが、真理だから義務的にやらなければいけないことなのだというわけではなく、たいていの場合真理は義務的に行うこととは切り離して考えることができる。しかし、自分が真理の主体である場合には真理を必ず守らなければいけないということを学んだ。
本人だけは真であると信じ続けなければならないというのが、ロシアのプーチン大統領が自分の考えを心の底から信じ抜いて主張していることと繋がり、腑に落ちる部分があった。権力者でありながらも、最も真であるということを強く信じることを強いられているのは当の本人であるということがとても興味深いと感じる。

ある意味当たり前のようなことなのですが、こうした形で「真実」が取り沙汰されるのをみると、本当に独特で、歴史的に特別に生まれてきているんだ、ということが分かりますね。漢字ちゃんとしーさんのやりとり(詳しくは「みんなで学ぼう漢字ちゃん」をご覧ください…)にしても、とてもふざけているような内容にも思えるのですが、やっている本人たちはいたって真面目です。でも、そうしないと、ある種「真実」というものは伝わらなかったりするんですよね。みずからがみずからの何を真とするかということを向き合うことが求められることを、フーコーは「真理の体制」としたんですね。
「真理だから」と守る必要もなく、間違っていても押し通そうとする政治の世界と、何が真なのか問うて、どこからが真と想定しうるのか考える科学の世界が一点に交わるところを、フーコーは注目したわけですが、そこに「主体」が出てくるきっかけがあったんですね。「アイデンティティ」という言葉も、まさに露骨に「主体」を現していますよね。今となってはポジティブな意味も持つような言葉ですが、エリック・エリクソンは「アイデンティティ」という言葉を「アイデンティティ・クライシス」という文脈で使っていたわけです。ポジティブな意味がこうして付与されてきた経緯をみると、近代という時代は、主体を重視するところがあるのかも、と思えます。フーコーに関してはこうした「主体」のありかた、regime of truth・真理の体制をひとりひとりが持っていることを良いとも悪いとも言っていませんが、最近は真理の体制の暴走みたいな状況が現出しているようにも思えます。それが、プーチンやトランプなどにもみられるところにも感じられたりしますが、みなさんはいかがでしょうか。
第六講| 一九八〇年二月十三日「主体性の歴史」 他 /2022年11月29日
当日資料はこちら
当日リポート
今日は、H松さんの愉快な整理…「とっとと洗礼」と「ギリギリ洗礼」にも助けられ、説得力のある議論に「ううむ」と思わされた方も多かったのではないでしょうか。
フーコーの議論の中で出てきた二つの真理の体制、「信仰の体制」と「告白の体制」がど区別できるのかを中心に確認されていきました。
まず、「とっとと洗礼」と「ギリギリ洗礼」とはいったい何のことだったのでしょうか。
そもそも宗教というものは、困っている人たちが救いを求める経緯を通じて生まれていたもので、いずれにせよ、最終的には救済が訪れることがお約束になっています。そもそも救済のない宗教にすがる人はいないのです。
ただし、何を以て救済の対象とするべきなのか、といったような問題に、どの宗教も課題を抱え、独自の解決策を見いだそうとしてきました。そして、キリスト教については結構特殊な解決法を提案したようだ、ということが今回の講読会で確認されたといえるでしょう。
かねてより、キリスト教は、救済は「洗礼」によってなされると説明してきました。
救われるために、洗礼を受ける、という判断に至ります。
ですが、…となると、救ってもらえるならなるべく早めに受けておこう、という「とっとと洗礼」を選択する人たちが一定数出てきます。
一方で、洗礼を早々受けて、その後の生き方に制約が出てしまうと面白くないから、さんざん堕落の道をとことん楽しんでから、最後に洗礼を受ければいっか!という「ギリギリ洗礼」を選択する人たちも出てきてしまう、という問題に直面してしまうことにもなるのです。
この問題を解決したのが、テルトゥリアヌスによって生み出された「原罪」という発想でした。万能である神が作った人間に欠陥はありません。ただし、生まれてから悪魔に騙され、たぶらかされてしまった経験を皆持っているのです。(アダムとイヴの智慧の実に象徴的ですね)
洗礼を受ければ救われると思いたいところですが、いわば”前科持ち”の私たちは、洗礼を受けても、また悪魔に騙されたりたぶらかされてしまうかもしれないわけです。そのような、私たち自身の心の中に棲まう悪魔に打ち克ち続けないことには、本当の意味での救済は訪れないよ、ということをテルトゥリアヌスは唱えた、と考えられるわけです。
いわば、そこには、「神への畏れ」以上に、自分自身――悪魔に誘惑されてしまうかもしれない己自身に対する畏れが発現していくことになります。そして、悪魔との闘いに負けてしまわないように、鍛錬し、悔い改めつづけることが必要(:修練)とされたのです。
つまり、「原罪」という発想を手に入れたことで、キリスト教は、神様に与えられるコンテンツとしての真理をただ「教えられ」、知識として身に着けることだ気ではだめで、自分にとって開示される自らの真理についてを一生懸命開示し続ける、ずっと自分自身に正直であり続けなくてはならない「魂の真理」といった発想をつかった真理の体制を生み出したのです。
このずっと悔い改め続ける、という発想が、やがてプロテスタンティズムの発想とも繋がっていくということは、プロテスタンティズムが「努力して報われる」という発想をベースにして発展したことを考えてみても、その連続性については納得することができるのではないでしょうか。
我々が、どのような存在であるのか真理を現出していく、ということは、まさに訓練のたまものであり、かつ試練の構造にあって初めて成り立つものなのです。また、試練を現出し続けることが求められるような存在として「奴隷」という表現も対応していることが確認できるでしょう。
こうした真理の体制を以て、《信仰の極》にあるような真理に対する知識だけではなく、自分にとっての正直さ…《魂の真理》が求められ、それに基づいて「主体」が確立していったといえるのだ、と指摘されていたように思います。
フーコー自身はそこまでは言及していないとは断りもありましたが、こうした転換がいわば、人間の精神を神から離陸させていくことになった、ということも確認されていました。神にとっての真理について迫っていくというよりも、《魂の真理》においては、自分自身に対してとことん正直であることが求められることになります。それは最後の審判に至るまでの、生きている間の長い間、神というよりかは自分自身の判断基準を真理と見なすことが許されるということでもあるのです。
講読会の中では、《魂の真理》という発想がいわゆるサイエンスのきっかけの一つにもなっていたのかも、という話がされていましたが、今日では、誰しもが自分にとっての「正しさ」みたいなものを主張してやまない状況ともみなせます。ある種、”ミニプーチン”や”ミニトランプ”的な振る舞いをしてしまいかねないような状況ともいえます。だからこそ、「真理の体制」や「主体」というものがどのように発現していったのか、丁寧にフーコーの議論を読み解いていくことは、とてもタイムリーで非常に重要なことのような予感がします。ちょうど「ゆるフー」も折り返し地点となりましたが、引き続き楽しく読み進めていきましょう。
参加者の皆さんからのコメント
真理への到達として、自分が完全に純粋であるなどと決して確信してはならず、救われるだろうと確信してもならないということを学んだ。本質をみるには、客観的な視点から物事を理解をする必要があり、助けを待つだけでなく主体的に行動することで、真理へ到達できることを学んだ。
真理の歴史や客観性の関係や構造の視点、志向性の構造の視点からではない心理の歴史を素描すること、その輪郭を描くことに繋がるため、テルトゥリアヌスは洗礼や業が魂の清めと真理への到達の関係をどのように定めているかを探求してみたかった。そして彼は清めと真理の関係の組成にいくつかの変化をもたらした。

先週末、とある学会が勤務先が主催校となって実施されていたんですけれど、準備の至らなさを「とっとと謝罪」の作戦でいくか、「ギリギリ謝罪」で攻めるか、相当迷った結果、どちらもやって、そして結局許されない、というとんだ目に遭いました…。が、キリスト教は、洗礼が救済にいたる、というお約束を持つことが大事だったんですね~じゃないと商売あがったりですものね~
ただ、やっぱりそれでは問題があったわけで、「神の絶対性」と「キリスト教の絶対性」を主張するために、原罪という概念が提唱されていたわけです。神様の創造物として欠陥があったのではなくて、人が勝手に堕落してしまった、なので個人の責任においてなんとかしなくてはならない、という論理を採用した、ということですね。
そこには宗教としての落とし穴もあって、真理性が個人の責任においてなされるもの、ということにもなった。今日の議論でも出てきますが、主体性という語が「subject」と訳されるところにもある種象徴されているような気もします。
それまでは何が真理かは、神様が基準になっていたわけですが、それ以外の正しさを大々的に取り上げたというのが、キリスト教の斬新なところだったんですよね。神の下での悔い改めが内面に振り返ること(本人の意志)を見つめていくことに――reflectionを生むことに至るんですよね。
第七講| 一九八〇年二月二十日「主体性と真理の関係」 他 /2022年12月6日
当日資料はこちら
当日リポート
前回から引き続き、洗礼=救済の関係が単純なものにならないような工夫としての「真理の体制」がどう築かれていったのか、どういう仕組みなのか、を改めて見直すような内容だったからこそ、前回の内容にどのようなプラスアルファが加わったということなんだろう??という確認から始まったような回でした。
報告では、「悪魔祓い」というワードに引っ張られ、人の魂に居座る悪魔をどのように追い払うか、その戦いが延々と続くイメージを「試練」なのかぁ、と捉えてしまっていましたが、最後の闘いとしての洗礼を終えた後に訪れる「真理の試練」で闘うのは、悪魔なのではなく、私たち自身=内なる他者なのだ、ということが確認されました。
フーコーは、真理の試練が果たす意味を、「真理を求めるお前、お前は自分の内に死の修練を確かにするようなことを知らなければならない。お前が生命を知るのはその後だ」(p179)と述べています。
また、「私たち自身を監視し、真理そのものをみずからの内に引き入れ、私たちを見、監視し、裁き、導いている者つまり牧師[=導き手]に対して、私たちの存在の真理を供さなければならないのです」(p181)というときも、内なる他者として自分自身を対象として捉え、その対象を吟味する過程として、真理の試練が説明されていることが確認されました。
主体――英語ではsubjectと表現されますが、subjectには「従う」という意味が含まれます。自分の内なる他者に死の修練を強いること――その自分自身に従う、というところで、subjectーー主体は生まれるのです。自分に従って、自分を統治することになります。
洗礼の準備期間は、いわば神の代理人である神父や司祭に、その統治の役割を担ってもらうということでもあるのだろう、という説明もありました。ですが、洗礼を終えた後は、自らを自らで問いただし、尋問していくこと――修練が求められるようになるのだ、というのです。
いわば、博士号を得るまでも、研究のいろはを指導教官に指導されながら、研究者志望者は研究の手法を学びます。ですが、博士号を取得したら、自分自身で自分の研究をorganizeしていくことが求められるわけです。それと似たようなものとしても捉えられるだろう、という説明もありました。
フーコーは、「この回心の問題、つまり同一性の断絶の問題においてこそ、主体性と真理の関係の問題が取り結ばれたのだと私は考えます」(p182)とも述べています。
アイデンティティとは「自己同一性」とも訳され、自己理解が同一性というキーワードと関連しているのかなと思ってしまいがちですが、「自分で自分自身を対象として自分自身を精査し続けていく」、完全に自己を「内なる他者」として切り離す、断絶があってこそ、初めてsubjectとしての主体が生まれるのだ、とフーコーは指摘していたと考えられるのです。
いわゆる、self-governance:自律としても捉えられるようなものが、フーコーがいう死の修練であり、主体の始まりであったということなのでした。
自分を自分自身から切り離し、分離することで、自分自身を客観的にまなざすことができるわけです。
ただ、「死の」修練というだけあって、その自己への統治は、生ぬるいものとしてはどうやら捉えられなさそうです。近代的な主体がどうやってできたのか、ということを振り返ると、強力な自己否定、自己批判の繰り返しから成立していたのではないか、ということが、フーコーの議論から発展して展開されました。
また、実は近代→現代にいたる過程で、「強力な自己否定、自己批判」はやがて「強力な自己肯定」に変わった可能性も指摘されました。「あるがままの自分」を認めようとするような傾向は、現代と近代の断絶を生んでいるのではないか。そして、協力に自分を肯定することが、強力な他者不信を煽り、ミニ・プーチン的存在を生んでいるのではないか…といった議論にも至りました。
現代における「強力な自己肯定」は、おそらくフーコーのいう真理の体制を突き詰めた結果とはいえず、どこかで何かしらの断層があったのではないか、という指摘もされました。
強力な自己否定、自己批判は、自らのありようが正しかったかどうか、自分が間違えている可能性を問い続けるような、反証可能性とほぼ同義的なものとしても確認されます。こうした意識の持ち方は決して普遍的なものではなく、キリスト教が真理の体制として大胆に取り入れた手法が、このような形で実を結び、結果として思わぬ形で発展・展開を見せたものとして理解することができるかもしれません。
強力な自己否定、自己批判を行う死の修練においては、もしかしたら、他者に寛容であった可能性も議論されました。一方、強力な自己肯定とかなり対比的に捉えることもできそうです。
こうした真理の体制――死の修練が、どのように定着していったのか。他者として自分を理解していくことにも、訓練が必要なはずです。このあたりを次回以降、また深めていくことになるようです。
自分自身、自分と本当の意味で向き合えているのか、その覚悟が持てているのか、非常に悩ましい今日この頃ですが、皆さんと引き続き考えていきたいところです。
参加者の皆さんからのコメント
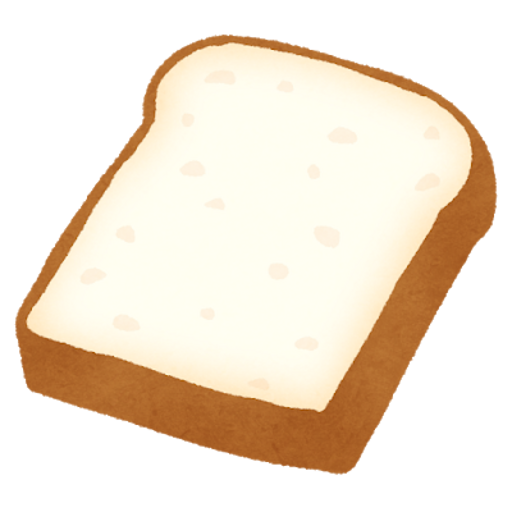
なんと、感想はありませんでした。Mせんせいが落ち込んでいました!!!悲劇!

コメント0の回、とうとうきてしまいましたね~。が、まあ、気を取り直して。
フーコーが死の修練で説明しているのは、自分を自分から切り離してみることでした。これって今となってはもしかしたら当たり前に思われるかもしれませんが、フーコーがこの講義をした1970年代においてはまだ「主体」への意識はほとんどされていなかったような時代でもあったようなのですね。私たちが今慣れ親しんでいる人間観、個人観というものは、フーコーの議論を境に定着していった可能性もあるようです。
例えば、マイノリティへのリスペクトといった、今となっては当然の態度も、もしかしたらポスト・フーコーの時代に少しずつ築かれていったようなところもあるのかもしれません。その好例として「発達障害」などが挙げられそうです。かつては(まったく評価できることではありませんが)「恥」と捉えられがちだったかもしれないところが、「一目置かれる一つの要素」としての意味合いも含めて捉えられるようになったかもしれない。
ただ、フーコーのいう「主体」が「強力な自己否定・自己批判」的なものだったものが、「自己肯定」に変わっていった背景には、もしかしたら、自分に対して嘘をつかず、自己批判的であるような態度は、シニカルでネガティブなものともいえ、あまりよいものとして捉えられないからこそ、ポジティブでコネクトなありようが求められ、変化していったという考え方もできるのかもしれません。いずれも「真理の体制」で、自分にとっての真理を大事にする主体なのか、真理を探究して止まない主体なのか、そういう真理に対する態度の違いが現れているとも捉えることができるかもしれないですね。
第八講| 一九八〇年二月二十七日「法の体系と救いの体系」 他 /2022年12月13日
当日資料はこちら
当日リポート
本当にめっきり寒くなり、12月らしい気候になりましたが、いかにも「師走」。みんながあわただしく年末に向けてワチャワチャ??するようにもなりました。そんなわけで、今日も、裏では「ギャー」みたいな悲鳴が聞こえてきそうな雰囲気???で始まったのかもしれない今日でしたが、今日は、キリスト教が「再堕落」の問題をどう捉えることにしたのか、を確認していく回であったといえるのかもしれません。
前回の内容で、「洗礼」が、自分自身に対してとことん正直であること;「魂の真理」を求め、そのために、自らを相対化して捉えることができるよう、自らを「自己」から切り離していくような「試練」の存在を確認していきました。
が、今日は、「洗礼」を受けた後のこと、が問題となっていました。
「洗礼」を受けるとき、真理のほうへ魂が向かっていくことを「メタノイア」(回心)と表現していましたが、その真理に向き合っていく過程(洗礼準備期間など)で、自分が洗礼を受けるに値する人間かどうか、などいろいろな人に証言してもらいながら、真理と主体の一致/結合:すなわち「洗礼」が果たされるのだ、と私たちは読み進めてきたと思います。
「試練」は、まさに、自分がキリストの教えに対して正しく在れているのだろうか?ということを常に問い続けることが重視されてきたわけです。
「真理を知る私」が「堕落しそうな私」をみるような関係――「みる自分」と「みられる自分」があったのです。
もしも、洗礼を受けた人が、本当に「試練」を続け、「真理を知る私」が「堕落しそうな私」を諫め、完璧であり続けられたならよいのですが、現実には、実は、そんなことはなかなか難しい。
「真理を知っている私」でありながら、「堕落してしまう私」がいる、という問題にキリスト教は直面することになるのです。「知っている」はずなので、「知らなかったから間違えてしまった」という言い訳は通用しません。「知識」とは、知ってしまった後で、知らなかった状態には戻ることができない、不可逆的な特徴を持つものなのです。
――では、なぜ、真理を知っているのに、間違えて/堕落してしまうのか。
――実は、真理を習得したとはいえない状況だったのではないか??
という疑問にキリスト教は回答しなくてはならなくなった。グノーシス派などは、それぞれ極端な形でこの問題に応答しようとします。
…例えば、もう絶対間違えないように/堕落しないように生きるという選択を採ろうとする人たちもいました。ですが、そもそも「法律」で善悪が定められているように、人間は間違えるということが経験則的に明らかになっているのです。やはり間違えない人間などいない。また、一方で、最初から全部デタラメだったってことなのでは?と快楽主義にふけるような選択をする人たちもいました。
そういう困った状態の中で、追い詰められていたからこそ?、キリスト教は画期的な解決策を得ることになった、という話も確認されていきます。
――キリスト教は、そんな「間違えてしまう人間」であろうとも、そのような人間のまま、救済してしまおう!という結論に至るのです。
「法律」がある行為をするか・しないか、で正義や不正義、善悪を判断するものである一方で、キリスト教のこのアイデアは、キリスト教徒として「悔い改めつづけなくてはならない」と、自身がどういう人間であるか照らし続けるようなことが実践されているかどうか、が、救済の対象となるか否かの判断として重要な意味を持つ、というような発想であった、ともいえます。
なんてむちゃくちゃな!とも思えますが、「信じる者は救われる」というその言葉が、ものすごい求心力を持って世界宗教になるきっかけを得た、という事実を理解するには非常な説得力があるとも思えます。罪を犯すこともありえるかもしれない「人間」という存在のまま、救済の対象とする、ということは、他の宗教と比較してみたときに特色的なものと見なせるかもしれません。
「再・堕落」の問題を考えていくうえで、キリスト教は、「真理を知っている自分」が「間違えてしまうかもしれない自分」「実際に間違ってしまった自分」をその後もずっと見続けていく――メタノイアの恒常化を以て解決しようとしたといえるのかもしれません。
つまり、「悔い改めつづけること」を受け入れるような人、正しいことを知っていながらも、自らが誤りうる主体である、という認識を持ち、自らを戒め続けられるような主体は、現実に堕落していたとしても救済の対象としよう、ということが「真理の体制」として築かれていったのです。
ここでは、もはや「何が真理なのか」ということは言及されません。そうではなくて、「真理にどうこだわるか」ということが重要になってくる、とも説明がありました。
これは、迫害され続けたキリスト教だからこそ、編み出し得たような発想であったのかもしれない、という確認もされましたが、世界中の人のこころを鷲掴みすることとなるキリスト教という宗教が、常に信者に「魂の統治」を求め続けた、という事実は、確かにものすごい革命的なことだったのかも…と改めて圧倒されます。
この後もフーコーの議論に、圧倒されていくことになるのでしょうか。残りの回もワクワクしながら、読みすすめていきましょう。
参加者の皆さんからのコメント
善悪の判断を行為に向けるのか、属性に向けるのかという話に関して、同じ行為でも、それを行う人によって行為の意味が変わるという見方が当たり前ではないということを学んだ。それは今までの行為の積み重ねでもあるが、相手が自分をどのように見ているかの判断にゆだねるものでもあり、ある意味自分ではどうしようもなく、残酷な見方だという印象を抱いた。
この章では、一度救われた人々であっても再び堕落しうるのか、ということが争点となっていた。真理を知る者が間違えることはないという主張もあったが、その思考では、法と救いの関係を考えることを必要とし、人が再び間違いを犯す可能性があることも意味している。キリスト教はこの問題を、主体と真理との距離という観点で明らかにしようとしたのだろう。

ただたんに、キリスト教徒であるかどうか、が救済の対象となる、というわけではないことに注意です。どちらかというと、「人間が人間のまますくわれる」ということがキリスト教の特殊性だったのかもしれないですね。このあたりは、修正されて赤字になっています。
また、今回の発想は、客体としての自己を維持し続けることを要請するものでもあるのです。いわば「自己の分裂」とでもいえるようなものなのかもしれないのです。どんなキャラクターも、自ら真理を語る、ということはなくて、いろいろとうそをついたりしている可能性がある。そのキャラクターが真に「真理」を語っているということが分かるのは、そのキャラクターが「客体」として描かれているときのみなのです。だからこそ、「語る自分」と「語られる自分」を一緒にしてしまわないようにする、という分離を通じて「主体」というものを考えようとする契機をもたらしたキリスト教の発想が興味深いとフーコーは指摘しているのかもしれないですね。
第九講| 一九八〇年三月五日「自己と事由の開示」 他 /2022年12月20日
当日資料はこちら
当日リポート
今日は少しこじんまりとした形でスタートした講読会。なんだかんだで年内最後の講読会となりましたが、なかなか理解が難しい内容にもなっていました。
フーコーは結局のところ、洗礼をした後の「再・堕落」してしまった後の問題をどう対処することになったのか、という議論をしていきます。そして、今回のパートは、キリスト教が見出した「真理の体制」というものがどのように構成されているのか、その内容の整理と歴史的な経緯を丁寧に迫った部分であったと理解することができるのかもしれません。
講読会の中では、真理の体制として位置付けられた第二の洗礼、もとい、第二の悔い改めを以下の三つによって整理できるのではないかと解説されていました。
***
まず、一つ目がエクスポシティオー・カーススあるいは、コンフェッシオーと表現されていた「事由の開示」にあたるものです。これは、誰が悔い改めを行うのか、外的に、その存在を客体的に吟味するような、分析的で記述的なプロセスです。悔い改めたいという、一度キリスト教を棄てた人であったり、罪を犯したりする人が、悔い改めに相当するのかなどを判断するために行われるものですが、この判断は、その本人にはできないことなのです。あくまで「悔い改めようとしている主体」は客体として扱われる、ということがここで確認されていました。
そして、二つ目がエクソモロゲーシス。「真理の業」ともされていたものでした。
実は、「悔い改め」はなんだかんだ何回もしていいものではないようなものでした。二度目の悔い改めの機会は与えられるが、それが絶対に最後であるということ。何を以て「悔い改め」が済んだと判断されるのかは非常に難しく、議論を呼んでいたような問題でした。それゆえ、このエクソモロゲーシスは、やがて「悔い改めの恒常化」を示すものになったと説明されていました。
もしかしたら生涯にわたって悔い改め続けるかもしれない、そういう期間や行為の様態そのものを指したと理解することができるかもしれません。
最後の要素は、エクソモロゲーシスを進化・発展させたようなもの:プープリカーティオ・スィーです。「自分を公の前にさらさなければならない」というもので、悔い改めに固有な劇的な次元を持つものとしても説明がされていました。
いわばここでは、何が罪であるかとかそういうことよりも、「自分が罪人である」ということを現出化させることが目指されたのです。
フーコーは、キリスト教が「真理の体制」というものを長い時間をかけて築いていったとしていましたが、以上のような三つの要素を組み合わせた形で、その真理の体制がもたらされた、ともしているようでした。
結局のところ、その本人が「悔い改める」ことを、本人以外の誰にも(もしかしたら神様にしか)知りえないという中で、結局自分自身が、この「悔い改め」に向き合うほかない、という事実に直面していくことになるのです。自分自身が悔い改める「主体」となっていくということは、自分を徹底的に客観化して、客体化していくことが求められる、ということでもあります。
フーコーは、このことを「死」という表現を以て説明していました。「罪人の状態としての死と罪において死のうと欲することとしての死という二重の意味」(244頁)とありますが、現世で生きることを「死の道」と捉え、新たな再生に向けて死ぬことを欲するとき――死ぬくらい徹底して自分自身を強力な自己否定を以て”悔い改めよう”とすることが、第二の悔い改めにおいて求められるようになった、ということでもあります。(死に物狂いで幽体離脱して、のほほんとして生きる自分自身を精査する、といったようなイメージ?と講読会後、確認がされたりもしました)
死ぬくらい徹底的に強力な自己否定を行う、とはつまり、自分から距離をとって、客観視する、というような、(フーコーはこのようには表現していませんが)「見る自分」と「見られる自分」に分離させて自らを捉えるような”主体”のありようを、結果として生み出したといえます。そして、それが西洋文明を強く特徴づけるものになっていったともフーコーは指摘していたのかもしれません。
この自分が罪人であるということを認めることで、罪人という状態からの離脱になる、という謙譲のパラドクスが、フーコーの講義でも最後に予告的に触れられていたことが気になりますが、今回みていた「強力な自己否定」というあり方が、これまで議論してきたような反証可能性などに通底していくことも確認されていたかと思います。
もしかしたら、現代においては持たれにくい態度になりつつあるのかも分かりませんが、丁寧に引き続き読み解きながら考えていきたいと思います。
そして、次回は、2023年に明けてから、1/10の再開となります!
どうぞよろしくお願いいたします!みなさま、よい年末年始をお迎えください。
参加者の皆さんからのコメント
主体の分離(見る自分と見られる自分)の区別だけではなく、「真理を知っている自分」と「再堕落している自分」を主体が元々持っていることを認める。これこそが真理の体制である。分離する主体を作って、ある意味真理を守っている。例えば、悪とされる行為をして反省するけど、真理を知っている自分はいて、心境は保たれるなどだ。
現在の人間は確かに行為ではなく属性で判断していると感じた。この体制が構築された過程を見ることで世の中を見る目が少し変わったように感じる。誤りうる主体をいれることで、「正しいことを知っているけど間違った行為を行ってしまうことの説明」をすることに成功した。人間の再堕落という大きな問題を上手く説明できていると感じた。

この時代、プーチンにせよ、トランプにせよ、ブラジル前大統領にせよ、そして私たちも、常に「真理」を求めているわけですが、この時代にフーコーが、こうして真理をめぐる議論をしていることは改めてすごいことだなあと考えさせられますね。真理とは、自分が自分である根拠のようなものだし、自分が自分であるために作り出す作業そのもの、自分のことを決定していくために必要なことなんですよね。
フーコーは、この「真理」に到達するために、「死」という表現を使って、その”試練”の重さのようなものを指摘していたように思うんです。真理に到達するには、魂の試練が必要。でも、あまりにももしかしたら、現代は真理に到達するためのその過程をショートカットしすぎているのかもしれません。
この正月、私も実はお餅が美味しくて、ちょっと食べ過ぎてしまったんですが、そんな重たくなりがちな自分をきちんと見極め、自分をコントロールしていかないとだめだなあ…なんて。
第十講| 一九八〇年三月十二日「自己の探究と良心の検討」 他 /2023年1月10日
当日資料はこちら
当日リポート
2023年第一回の講読会も始まりました!今日の内容は、そんな新年第一回目にふさわしいような、今回講読しているこの本の、核となるような、「爆発!」みたいな部分だ、ということで講読会もスタートしました…が、実は、次回分も含めて俯瞰すると、この「爆発」具合がよくわかる、という作りにもなっていた回でした。
ちょっとややこしいですが、今回議論に挙げられていた「良心の指導」の議論は、古代ギリシアの例を引いて説明されていましたが、まさにそれこそが、キリスト教における「良心の指導」の根っこに相当するようなもので、この「良心の指導」が持つ特徴が、ドラマチックに展開されていったような回だったのです。
さて、この「良心の指導」とは、一体どのようなものなのでしょうか?
そもそも、「真理」を目指しつづける実践として「洗礼」や「悔い改め」がある、とこれまで議論されてきましたが、その両者の特色として見出される「過ちの言語化」と「自己の探究」の結合を進めたものが「指導」という実践であった、ということで、今回の議論の核となったのが「良心の指導」となたのでした。
そして、今回の爆発物の正体たる「良心の指導」とは、古代ギリシアの、特にストア派が確立してきた一つの方法論としての「良心の指導」のことを指すようです。講読会の中では、この「良心の指導」が、まさに以下の三つの要点によって整理することができる、と解説されていました。
「指導」とは、強制で行われるものではなく、指導者の意志と被指導者の意志が、自由意志の下で共存するような実践だと説明されています。これはつまり、どういうことなのか。
一つ目に、被指導者が指導者に対して「全面的に私は委ねる」、「あなたのいうことに従う」としたとしても、最終的な決定や決断までは指導者に決して委ねられることがなく、私(被指導者)の意志によって決定される、ということがありました。
まさに、「わたしは他人の意志を、私自身の意志の原理として参照する。だが、この他者の意志を欲するのは私自身であるべきだ」(262頁)としているとおりです。
そして、2つ目。その決定が誰に望まれているか、というと、完全に私(被指導者)自身の自由意志のもとで自発的・内発的に希望されたものである、ということです。「制裁も強制もなく、被指導者は常に指導されることを欲し、そのかぎりにおいて、指導は機能し、展開する」(263頁)ものであって、被指導者が「もう指導されることを欲しないのもいつでも自由」(263頁)なわけです。
最後に、これがあくまで自分、被指導者自身についてのことを対象とするものである、ということです。いつでも、ここで取り沙汰されるのは、自らの魂のことであって、誰かのためのものではないのです。「外的目的ではなく、自己の自己への関係として理解された内的目的」(264頁)…つまり、自分についてのことが対象とされる、という特徴を持つものでもありました。
この3つの要点をまとめると、「良心の指導」とはすなわち、すべて自分のことについて述べたものであって、「自分に自分が従うこと」を意味しているともいえます。
「良心の指導」とは、「自分に自分が従う」ための手続きをテクニカルに整理した、いわば”技法”なのだ、ということが講読会の中でも確認されました。
同じ古代ギリシアにおいても、ピタゴラス派など、「よい」か「わるい」かに分別していくような形で「良心の指導」を試みるものもありました。
が、ストア派は、「良心の指導」を”手続き”とみなします。そして、「世界全体に適合した振る舞い」を可能にするもの、合理的原理そのものとみなすのです。さらに、この良心の検討――合理的原理/合理的振る舞いが、主体を「自立」に導くカギとなる、としているようなのです。
・「合理的原理は普遍的であり、合理的振る舞いとは世界全体との関係において私を自立させてくれる」(280頁)、
・「もし私が自分の理性に則って自己を管理して、実際に自立したものになったとしたら、私は自分の行動を、世界を支配する一般的で普遍的な理性の原理に適合させることができるだろう」(280頁)
とフーコーは述べています。
次週の内容に少し関わってきますが、フーコーはこのストア派に見いだした「良心の検討」こそが、キリスト教にかつて「哲学的性格の技法」として見出され、育まれていった”技法”――真理の体制(の根っこ?)なのだと論じていこうとしているようです。
私たちが「真理」を大事にしていることはいつの時代においても同じです。ですが、その「真理」にいかに到達しえるのか、それを技法として明かしているこの議論は、なんだかすさまじいインパクトがありました。
ただ、「技法」として明かされているとはいえ、この技法を修得していくのは、非常な努力を要するようにも思われます。この過程をバイパスしようとしたり、真理それ自体を擬制化しようとするような向きも、この現代においてみられるのではないか、という指摘もされていました。プーチンが、もしかしたら役者たちを募って軍隊を演じさせ、その「擬制の真理」によって、ロシアの正当性を主張しようとしているのだとしたら、まさに、その「真理」を安易に手に入れようとしたことそのことが、現在のこの悲惨な事態を招くことになったといえるのではないか、といった指摘もされていました。
わが身を振り返りつつ、フーコーの次週以降の議論もますます楽しみですね!
今年もどうぞよろしくお願いします!
参加者の皆さんからのコメント
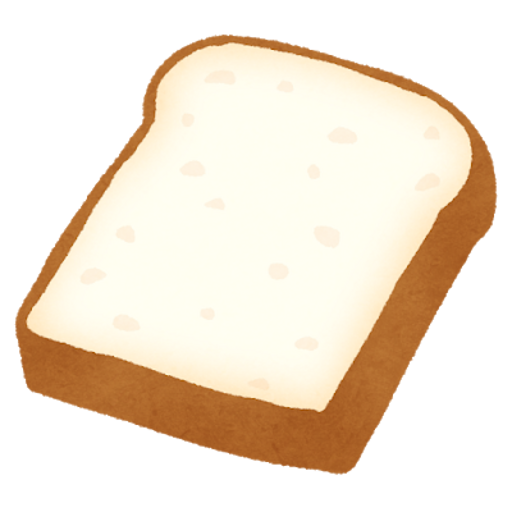
しくしく…

残念でしたねぇ。。。
さて、振り返りの、「『良心の指導』とは、『自分に自分が従う』ための手続きをテクニカルに整理した、いわば”技法”」というところは、フーコーはそこまで指摘していなかったかもしれません。自分についていっているのは確かだが、「自分に」したがう、というところまで言っているかどうかは、待ったをかけたほうがよいかもしれません。
それにしても、「良心」というのは、従来、他人のことを思ったり考えたり、いわばsympathyという道徳や倫理として捉えられがちな側面が大きかったかもしれません。でも、今回の古代の指導に基づくと、その人がどう思うか、自分について、自分がどうするか、自己満足しているかどうか、という相当にselfishなものであった可能性も伺えますね。
もしかしたら、良心の両面性…ヒューマニズム的であるようにみえる一方で、独善的にも捉えられることがあるような…そのからくりを説明していたようnところだったのかもしれません。
第十一講| 一九八〇年三月十九日「指導・従属の諸特徴」 他 /2023年1月17日
当日資料はこちら
当日リポート
なかなか難しいところもありましたが、前回まで述べられていた「古代の指導」をそのまま引き継いだ形で、「キリスト教における指導」が実践され、その特色についてが触れられていた章でした。
そもそも、この「キリスト教における指導」が実践されるようになったのは、4世紀ごろ。ちょうど、修道制を取り入れる過程で、古代の哲学的生活が導入されたのだ、という話でした。
今回、結構ターニングポイントになった時期として挙げられる4世紀って、何が起こっていたんだっけ?と振り返ってみると、実は、ちょうどローマ帝国の国教としてキリスト教が位置付けられた時代…(313年:ミラノ勅令にてキリスト教の公認。380年:テオドシウス帝によるキリスト教の国教化、381年:コンスタンティノープル公会議にてアタナシウス派の三位一体説を完成させ、キリスト教の正当として確定…)。
キリスト教が広く伝播していた時期と重なっています。
このタイミングというのが、フーコーの語るところによれば、非完徳による救済宗教という難問を解決した時期でもありました。
それまで、「完徳」…いわば鉄人になれるはず!とも思ってきていたし、頑張ってなろう!としていた時期が続いていたのです。でも、堕落してしまうという現実があった。それでも(堕落してしまったとしても)、キリスト教は、救済の対象にしますよ!という画期的な宗教であったわけですが、それを支えたもののひとつが、<悔い改め>であり、もう一つが<修道制>だったのです。
悔い改めが、いわば堕落している人を救済するものであったとするならば、修道制は、完徳を目指す人がなぜ報われないのかを説明するような、「完徳」しないという状態を目指し続けることを説明する装置として機能した、と講読会の中では説明されていました。
修道制を成り立たせる大前提として説明されたのが「本質的従順さ」です。
この従順さとは、
①全世界は命令でできている
②自らは完全に受け身であり続ける
③自分自身は、あらゆるものから劣っている
と捉えるところから成り立っています。
キリスト教の指導は、そうした「従順さ」があって成立するもので、それなしには成り立たないものでした。
だからこそ、古代の指導がもたらし得た効果を逆転させてしまえたのだ、とフーコーは説明しています。
古代の指導は、一時的なもので、かつ師の能力を前提とし、あくまで目的を叶えるための道具として活用されてきました。だからこそ、そこでなされる良心の指導は、主体を「自立」に導くカギとなり、合理的原理/合理的振る舞いを以て、世界に合わせていくことができたのです。
キリスト共の指導も、基本的には古代の指導が用いた技法をそのまま取り入れています。ただし違うのは、主体が「従順」であるということです。その本人の意志で、従属することを望むのです。それによって、自己は強制的に世界の奴隷になるのです。世界が自己にとっての主人になっていきます。
これが、司牧的権力などといった言葉で説明されたものに相当していく、という話も講読会中でされていましたし、生権力のからくりそのものでもある、ということも振り返りの中で語られていました。
積極的に従順であることは、世界が望むことを、自らも望むものとして振る舞っていくことにもつながります。フーコーは、「指導の手続きや技法は、それを変質させたり、その効果を逆転させたりしてしまうような指導の一般的な装置ないしはテクノロジーに組み込まれることになった(314頁)」としているのは、おそらく、このようなことだったのかなあと思います。
ただし、キリスト教の指導が、いわば徹底的な自己否定・自己卑下のような態度を貫いていったことは、その後のヨーロッパにおける自己や主体の確立に欠かすことができないものであったのかもしれない、という指摘もされていました。古代の指導で実践されたようなものが核となったことは確かですが、でもそれだけでは、批判的精神を醸成していくには不足していた。キリスト教の指導の実践そのものが、自己批判的な態度や精神の持つ意味、そこから生まれるものの価値を見いだすヒントにもなっていたのかもしれません。
また最後に、フーコー議論を発展させて、柴田先生の論点として紹介されていたこともありました。古代の指導が、自分自身の主人になることを通じて世界の主人になることを叶えてきたものであったとしたら、キリスト教の指導は、きわめて似た形をとってはいるものの、「世界が主人になることを認める」ものでした。でも、実は、自分自身もその世界の一部を構成する存在であるのです。すなわち、自分自身が主人になることも論理的には可能なのです。
徹底的に世界に従属することを通じて、誰もが他人の主人になりえてしまう、それぞれが世界の主人にもなりえてしまう、ということが持つ意味を考えると、少しぞっとしてしまう、という話で、今回の講読会は締めくくられていました。
思いがけない形で、議論が展開してきましたが、残すは来週の一回。どこにどう着地していくのか、ぜひ楽しみに読み進め、講読会を終えることができたら、と思います。
参加者の皆さんからのコメント
共住修道院に入ろうとする者が通過しなければならない3つの契機が、非常に印象的で、私にはできないなと思いながらみていました・・・。楽しく購読会に参加できて良かったです!
最初はキリスト教思想の説明があり、救済するためのシステムの具体例が述べられている。それが悔い改めと修道制の二つの制度について解説された。古代の哲学的⽣活や古代の教育、キリスト教、非キリスト教の指導の対比について解説された。最後にカッシリアヌスがあげる、従順さについての特徴が挙げられ、それがストア派などの古代の思想とは対極にある。
今回が初めての参加で話が難しいと感じる部分もあったが今回学んだことは、キリスト教の指導と非キリスト教の指導の違いである。前者の従順さは、⼀つの状態であり、普遍性がある。他人がいて命令を発する以前に従順さの状態にあり、それが指導の目的でもあるという従順さと指導の循環と説明された。後者は従順さとは限定的で指導者と被指導者には差異があり、自分自身が至高の指導者になるための段階であるという違いである。
キリスト教の指導は主体が「従順」であるという点で古代の指導と異なる。古代の指導が、自分が自分自身の主人になることを通じて世界の主人になることを叶えてきたものだとすると、キリスト教の指導は世界が主人になることを認めることであった。これは、その世界の一部を構成する自分自身も他人の主人になることが論理的に可能であるということでもある。
キリスト教は、完全ではない人も救済の対象としている宗教だが、それを支えたものが悔い改めと修道制であるということ、修道制を成り立たせる大前提として「本質的従順さ」があり、キリスト教の指導は「従順さ」なしには成り立たないものであったということなどを、今回の講読会を通して学ぶことができた。

改めてみてみると、ギリシア・ローマにおける発想も、キリスト教における発想も、ヨーロッパ的思想の土台になっているのですね。その後起こっていくヨーロッパにおける主体や市民革命を支える裏付けになっている、ということはきっと確かなのでしょう。
キリスト教の特殊性っていうのはやっぱり、ぼろぼろの人間も救うという、「非完徳の救済宗教」という点です。「洗礼」さえすれば、救済の対象になる、というロジックは、その後、「とっとと洗礼」や「ギリギリ洗礼」という言葉が出てきていましたが、宗教として認めがたいような事態も生まれます。これを解決するのが、「悔い改め」だったわけです。
悔い改めっていうのは、言ってみれば、自身の中に「悪魔」的な存在があることを自覚し、それを一生懸命悔い改めることでした。そこで自分を相対化して捉えるような、「見る」自分と「見られる」自分が産みだされた、といえるでしょう。
一方、悔い改めさえすればいい、というと、完徳のための努力は不要のようにも思えてきてしまいます。そうではなく、良い人間として生きるということを示す場として修道院が産みだされたと考えられるでしょう。
「よい人間」であるために、ギリシア・ローマでは、自らを世界に合理的にあわせていく努力をしていくことになります。合理的に自分を判断し、監査するのですね。
一方で、キリスト教的発想においては、自らを世界に従わせ、自らを世界の奴隷にしていきます。だから「従順」というキーワードがでてくるのです。統治される主体、「奴隷」としての存在として、導かれ、指導される存在として生きようとするのです。そこでは「権力」が発動します。
ここでいう権力は、いかにも「自分がよく生きよう」「自分の意志で生きよう」としているようにみえるものそのものが、国家や社会に統治されたり従わせられていることの結果となっている、「生権力」のことをさします。
このキリスト教的発想における「自らが世界の奴隷である」という考え方は、ちゃんと世界の奴隷になっていればいるほど、他者に対しても世界の奴隷であるべきと考えることになる、という特徴があるように思われます。自らが忠実な奴隷だからこそ、奴隷にならない存在を肯定できないのです。それはプーチンやトランプや、私たち自身においてももしかしたら見られるようなことなのかもしれません。自分を世界に合理的にあわせようとするのではなく、自分を世界の奴隷になろうとすること…それは、「正しさ」の奴隷になっている、ということでもあるのです。「正しさ」の奴隷になるとき、間違えている人間は正されなくてはならなくなります。キリスト教の布教の強力な力になったのは、こうした正しさの強制、真実の奴隷になることで果たされる、「真理体制」ともいえるようなメカニズムによるものだったといえるのかもしれません。
第十二講| 一九八〇年三月二十六日「生者たちの統治」 他 /2023年1月24日
当日資料はこちら
当日リポート
近年まれにみる大寒波の予報のなか、遭難してしまうかもしれない極寒??の中で開催された最終回。議論を通じて少し暖かくなれたのだろうか?という感じも持ちつつ、振り返っていきたいと思います。
今回の内容は、古代における「良心の検討」とキリスト教における「良心の検討」を徹底比較していく、というような回だったかもしれません。この両方が「真理」を求める技法だったわけですが、かくも極端に異なるのか、というくらい違いがあったことも印象に残ったのではないでしょうか。
一方における真理の探究では、内容についての真理を、一生懸命語ることを通じて、検証しようとする――裁判や監査の言葉で説明されていました――ものでしたが、
もう一方は、考えることはやめて(自分で考えても、その考えは信用ならないものだから)、告白することに没頭すべき――告白の形式を通じて、正しくあろうとしているかを示すこと;真理陳述をすればよい、という発想をするものでした。
意外と、私たちが自分について考えるというとき、どちらの真理のレジーム(真理の体制)に依っているか、判断をするのは意外と難しいということはあるのかもしれません。
ただ、フーコーの立場は恐らく明確で、キリスト教的な真理の奴隷になるな、ということだったはず、ということが講読会の中では確認されました。いわば、フーコーは、フーコーが「真理」をどう語るんだろうという期待を持った聴衆たちに対して、「自分の真理は自分でちゃんと考えて語れ」ということを、一番に伝えたかったのではないか、「他人や世界に自分を語らせるな。語る形式に甘んじるな」ということを主張したかったのかもしれないのです。
実際のところ、キリスト教的な発想に基づく自己に対する捉え方は、徹底的に否定的なものになっています。まったく自分という存在について肯定的な色を示しません。ただ、それは考えようによっては、カール・ポパーがいうような反証主義(自分の正しさを否定する形で「真理」を探究していく)の発想にも繋がっていくような可能性として読解していくことができるものかもしれないこと。
デカルトが指摘したような「私が(悪魔に)欺かれるためには、私があるという真理があるはずだ」という指摘は逆に、自己肯定の土台となっていった可能性もあるかもしれないことも確認されました。
いずれにしても、私たちが今回のこの本の講読を通じて考えさせられることは、真理の奴隷になるのではなく、真理について、その内容をみずからの中で裁判し続けるような姿勢を持つことの意味を再考することなのかもしれません。
自立を促す古代の良心の検討がしていたのは、世界に自分を合わせる努力でした。この実践のためには、相応の知識を獲得するための努力が求められるのです。もしかしたら、新型コロナウイルス感染症拡大が招いた「学びの危機」は、この「世界に自分を合わせるため/自立のため」の努力を、納得して学ぶきっかけが損なわれたり、奪われてしまった、ということに尽きるのかもしれません。
成績や評価のために、私たちは「真理」を求めるはずでは、学ぶはずではなかったはず。私たち自身が日々の生活の中で実践する自己との向き合い方を、考えさせられるようなそんなエンディングだったのかもしれません。
今回の講読会はここで終えますが、次回の講読会もはやくも開催予定。
来年度の5月ごろを目安に第7弾を開催していけたら、と考えています。真理を追究していくための、現代における方法論をウヴェ・フリック著の『質的研究入門--〈人間の科学〉のための方法論』(春秋社)という文献を通じて迫っていきたいと考えています。もしよかったら、ぜひ皆様、お気軽にご参加ください!
それでは、ご参加くださった皆様、閲覧を楽しんでくださった皆様、お疲れさまでした!
また、どこかで議論しましょう。
参加者の皆さんからのコメント