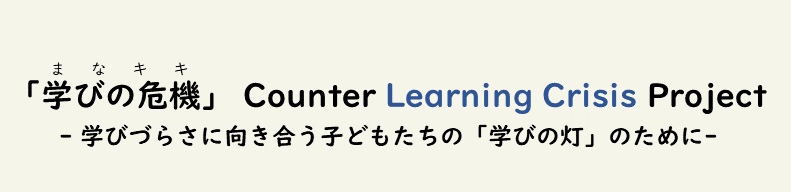▶ を押すと文が増えます
声の文化―どうやって伝え・残されてきたの?
平家物語にしても、アイヌの物語にしても、イーリアスやオデュッセイアにしても壮大な物語です。
この壮大な内容を文字を読みあげるのはなく、朗々と謡うことができたのだろう?ということについて、オングさんは、「声の文化」に独特の特徴が背景にある、と指摘しています。
■ 強いリズムがあり均衡がとれている型にしたがっている
■ 反復や対句が用いられている
■ 頭韻や母音韻をふんでいる
■ [あだ名のような]形容詞を冠したり、その他のきまり文句的な表現を用いている
■ 紋切り型のテーマ(集会、食事、決闘、英雄の助太刀、など)ごとに、きまった話しかたがある
などなど
W-J・オング著『声の文化と文字の文化』p.78
※ 改行・太字はM先生による

声の文化にもとづく思考は、それが長くつづくときには、定型詩でない場合でも、非常にリズミカルになる傾向がある、とオングさんは言っています。リズムは生理学的にみても、何かを思い出すのを助けるのだとか。(78-79)
‥‥実際、歌やリズム感を利用して覚えたりすることってありますね。
オングさんの説明によると、
声の文化に生きる人たちにとって、物語を伝え聞き、謳っていく過程には、いわゆる文字通りの「暗記」は存在しないようなのです。
吟遊詩人は、何か月も何年も、お手本となるほかの吟遊詩人の歌に耳を傾けることで学ぶといいます。
かれがもっているテーマと決まり文句のたくわえのなかにその話を漬けておくための時間、その話と「一緒になるget with」ための時間が、かれには必要なのである。
彼が話を思い出し、語りなおすというとき、かれは、べつの歌い手が歌ったようなしかたで韻律表現を、読み書きができる人が言うようなどんな意味でも「記憶」したのではない。他の歌い手がどんなふうに歌ったかというようなことは、新しい歌い手が、自分のやりかたで語ろうと話を練り上げているときには、とうのむかしにかれの念頭から消えているのである(Lord 1960, pp20-9)。
W-J・オング著『声の文化と文字の文化』p.130
※ 改行・太字はM先生による

文字で学ぶ・記憶することができないからこそ、それを血肉とするような…大事なポイントやエッセンスをじっくりと消化して自分のものになるからこそ、自分なりの形で、吟遊詩人は謡うことができた、ともいえそうです。そういう学び方・記憶の仕方って、文字を介した学びや記憶でどれくらい再現できるのだろう?と感じてしまいます…。
そして、「一緒になる」という説明が、声の文化ならではの特色なのかしら?と気になりますね。
文字の文化 ―何が変わったの?
一方で、「書くこと」は、どのようなものだとオングさんは言っているのでしょうか。
一人の話し手が聴衆に話しかけているとき、聴衆は、ふつう、かれらのあいだで、また、話し手とのあいだにおいても、一体となっている。
ところが、もし話し手が、手渡した資料を読むようにと聴衆に求め、聴衆の一人ひとりが自分だけの読書の世界に入ると、聴衆の一体性はくずれ、ふたたび口頭での話しがはじまるまではその一体性はもどらない。
書くことと印刷とは[人びとをたがいから]分離する。読者を表わすことばには、「聴衆audicence」に対応するような集合名詞や集合的な概念がない。
W-J・オング著『声の文化と文字の文化』p.157
※ 改行・太字はM先生による
「声の文化」で、情報が伝えられるとき、そこには必ず「聞き手」の存在があったのですね。
一方で「文字の文化」では、情報を受け止める相手が必ずしも目の前にいるとは限らない。
そのことはつまり、文字を書く時、私たちは、読み手の存在をもう意識できなくなってしまうのです。
誰かと話をしているとき、現実の生きた人間によって、現実の生きた他人、あるいは、他の人々に向けて言葉は発せられています。
そして、ある特定のとき、ある特定の現実の場面で発せらてもいるのです。

そうした場面は、つねに、たんなる「ことば」以上の、はるかに多くのことがらが含まれています。
話されることばは、つねに、ある全体的な状況…例えば、その人のコンディションや、性格、どういう状況で話をしているのか、身振りや手ぶりなど、相手のリアクションなどなど…の影響を受けます。
交わされている情報は、「ことば」で表わされているもの以上のものを含んでいるのです。

一方で、文字になるとき、「ことば」以外のもの(その特定の場面の状況やその人の様子、相手の反応など)から孤立します。

身ぶりも、顔の表情も、声の抑揚もなく、現実の聞き手ももたずに、その話しが、すべての可能な読者に対してすべての可能な状況においてもつだろうすべての可能な意味を、書き手は、用心深く予見しなければならない。
しかも、どのような生活上のコンテクストの助けも借りずに、それだけですべてが明瞭になるようにことばをはたらかせなければならないのである。こうしたこまかな気遣いが必要だということが、書くことを、ふつうそうであるように、苦痛に満ちた仕事にしている。
W-J・オング著『声の文化と文字の文化』pp.216
※ 改行・太字はM先生による
だから、オングさんは「文字を使って書く」という行為は難しい、と言っているのです。
そして、「書くことは技術でもある」としています。

音の中で発展してきた精緻に入り組んだ構造や指示体系は、
その特殊な複雑さそのままに視覚的に記録されうるようになり、
さらに視覚的に記録されることによって、それよりはるかに精緻な構造や指示体系を算出できるようになったのです。(p178)

それまでは、リズムや韻、独特の言い回し方によって、「声の文化」の中でもさまざまな知識や知恵が構成されてきました。
それが、文字という形に残ることになったことで、もっと複雑な構造に発展させて、それを記録することができるようになった。
身体に染み込ませていたような重要な事柄を「外部化」したともいえるでしょうか‥‥。
「~しなくちゃ」と頭の中で考えていることを、メモとして文字で書きだしたら、文字で書きだしたことに安心して忘れてしまう、ということもありますよね。なんだかそれとも関連してきそう。(そして、メモを失くしたら、もはやどうしようもなくなる…)
…こうした変化は、思考の仕方を変えることにもつながったとオングさんはいいます。
正確に反復できる視覚情報があらたに生まれ、そのことによって生じた帰結の一つが近代科学である。
正確な観察 [それ自体] は、近代科学とともに始まったわけではない。はるか昔から、たとえば、猟師や多種の職人が生き残るためには、正確な観察が常に欠かせなかった。
近代科学をそれ以前のものから区別するのは、正確な観察をことばによる正確な表現と結び付けたということ、つまり、注意深く観察された複合的な事物や過程を、正確なことばで記述したということである。
W-J・オング著『声の文化と文字の文化』pp.261
※ 改行・太字はM先生による