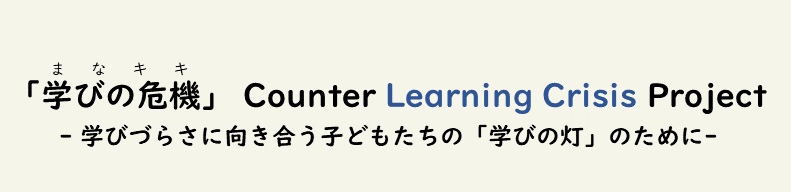▶ を押すと文が増えます

COVID-19 Crisisからの再起をはかる時代、求められるのは「モノをツクる」ことに真摯に向き合い考える営みなのではないか…。
再び「働き」出す私たちに必読の金字塔を、みんなで集まって「生産」的に読み解きます。素人歓迎!
※ 大学研究会の主催ですが、お申込み者は、自由に一回からご参加いただけます。お気軽にご参加ください。
(どなたでもご参加いただけます!)
講読会フライヤーPDFはこちら
講読会について
講読書籍
『クラフツマンーー作ることは考えることである』, リチャード・セネット 著 高橋勇夫 訳 筑摩書房(2016年)
講読期間
2022年5月24日(火)~2022年8月9日(火) 全12回
開催時間
18:00-19:30ごろ(入退室自由)
参加方法
ご参加方法には、①一般参加会員、②継続参加会員、③傍聴参加の三種類があります。
- ①一般参加会員
その都度ごと参加の申し込みを行って参加いただくものです。
当日の講読に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
ご参加予定の講読会の一週間前までにこちらのGoogle Formよりお申し込みください。 - ②継続参加会員
継続的に講読会にご参加いただくということで登録される会員です。
講読会に必要な資料を事前にお送りさせていただきます。
※ 参加登録は一度のみで完了いたします。
※ また、継続参加会員が毎回必ず参加が必要というわけではありませんので、ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。
お申込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ! - ③傍聴参加
特に講読用の資料を希望せず、ZOOMでの傍聴のみを希望される参加のスタイルです。
一回のみのご参加でもお気軽にお申込みいただけます。
ご登録いただいた方宛てに、開催前にZOOMのURLをお送りいたします。
お申し込みはこちらのGoogle Formよりどうぞ!
第一講| 序論 自分自身の製作者としての人間 /2022年5月24日
当日資料はこちら
当日リポート
今日はまなキキ・オンライン講読会の記念すべく、第5弾!ということで、これまで開催してきた講読会についても簡単にご紹介させていただきながら、ゆるゆると始まりました。(ちらしの資料はきちんと訂正版に差し替えさせていただきましたよ!)
参加してくださる皆さんと一緒に、講読を深めて理解や関心を深めていきたいと思います。初回の今回は、皆さんからもとても積極的にご発言をいただいて、本当に盛り上がった会となりました。
そもそも、今回の講読対象となった『クラフツマン』は副題に「作ることは考えることである」とあります。
今、私たちが直面している社会は、実態はどうあれ、「ポスト・コロナ」の社会へとシフトしていこうとしているところでもあります。新しい社会の形をつくっていこうとしている――まさにそんなタイミングの今、この本を読んでいくことで、何が必要になるのか考えていけたら…という思いも改めて確認させていただけた初回となりました。
著者のリチャード・セネットはリースマンやエリクソンなど著名な研究者の影響も受けながら、当時アメリカに滞在していたハンナ・アレントの影響も強く受けていたといいます。その意味で、ドイツの批判理論を強く引き継いでいるとも理解された人物である、とも説明がありました。
今回は序章を見ていきましたが、『クラフツマン』の主題ともなっていくテーマについて――ハンナ・アレントが提示した問題に対して、「いや、そうではない捉え方もできるのではないか」というセネットの主張が端的に述べられていたところでもありました。
ロシアとウクライナの間に起こっている戦争を目撃している私たちにとって、ハンナ・アレントの問題提起は他人事扱いできないようなものだったように思います。
アレントは、「凡庸なる悪」として、オッペンハイマーやアイヒマンなど、ある種、”仕事に没頭して働く”ことの問題性を指摘していました。「よい仕事」をしようとするとその仕事に没頭してしまうものだから、その仕事がなす「意味」や「理由」を問えなくなってしまうのではないか、意味を考えようとする理性が奪われてしまうのではないか…と指摘していたのです。
これは、ある意味でマルクスに由来するといわれる唯物論批判だったともみなせるのかもしれません。「物がどう生まれるのか」を考え、物を中心に考えていく;人間の活動や産業式など産業の在り方【下部構造】が、精神やその在り方を決める倫理、宗教、法、哲学、文化【上部構造】を規定する、と捉えたマルクスに対して、意味や価値、理想を持つことの必要性や価値を主張しようとしたのかもしれません。こうした姿勢は、当日の議論の中でも挙げられていたような「ヒューマニズム」の価値を主張したものとしても捉えられるのかもしれません。
実は、セネットはそのアレントの「労働」観に対して、「否」を唱えます。
アレントは、オッペンハイマーやアイヒマンの働きぶりを認めたうえで、だからこそ、「仕事に忠実に」「没頭して」働くことの問題性を指摘しましたが、
セネットは、そもそもオッペンハイマーやアイヒマンは決して「良い仕事」をしたとは見なせないのではないか、と主張していくのです。「良い仕事」というものは、「仕事に忠実に」「没頭して」働くからこそ、その意味や価値をしっかりと理解もして果たされているのだ、と。
当日、「障害者就労」の例も話題に上がっていました。
H松さんの研究対象にもなっているところなので、ぜひ、またH松さんの話も楽しみにしていただけるとよいのではないかと思いますが、障害者就労の現場で、働く人たちが、よい仕事をしていくことができるよう、さまざまな工夫がされていたりします。
言葉を換えれば、障害者就労の場で”合理的配慮”を行うことは必須です。そこに労力を割くことに価値や意味を見出せないと思う人ももしかしたらいるかもしれません。実際に、障害者就労の場で働く人たちも「なぜそこまでして働くのか」、その働く意味を問い直すことがある、というのです。
「なぜ、働くのか」「自分がする仕事にはどのような意味を持つのか」など向き合わさせられる機会があるからこそ、そこでの仕事は、きっとセネットが主張したかったような「労働」にも通じるところが出てくるのではないか、そういう指摘もあがっていました。
他にも、たくさんの議論が出ていた中、時間があっという間に経過してしまい、話しきれないこともありましたが、その中の一つが「テクノロジー」に関する話題。柴田先生が、アレントにはなかったユニークな議論として指摘していたところでした。私たちのこの講読会もZOOMで開催されていますが、その意味や価値を問い直していくうえでも、今後の議論の展開と、皆さんとのディスカッションがとても楽しみです。
さて、まだまだ講読会は始まったばかりです。どうぞよろしくお願いいたします!
参加者の皆さんからのコメント
当日のフロアから
自分のやっている仕事に誇りを持ち、正しいと思いながら没頭するということは良いことだと思われますが、それがどういうことに何につながるのか(つながる可能性があるのか)を考えないと、悲惨な出来事に繋がってしまうということがよくわかりました。ただ、未知なものにつながる可能性を予想するのはほぼ不可能に近いのかなとも思いました。
エピグラフなのか著者のモットーなのかわからないのですが、謝辞の前のページにある、「travail, opium unique(労働、唯一のアヘン)」という言葉が何を意味しているのか気になりました。
仕事がたくさんあり、仕事に没頭せざるを得ない、考える時間もない場合もあろうかと思います。アレントは没頭する本人、そうさせている環境、どちらを批判しているのか疑問を抱きました。
作ることに没頭することを批判し、考えることの重要性が強調されている感じだと思いますが、それに対してどう感じられていますか?先ほど障害者就労に言及されていたので気になりました。

「働く」ということをこれほどまでに肯定的にも、否定的にも捉えることってなかなかなかったかもしれませんよね。どちらかというと、私たちは「勤勉であることは素晴らしい」といった思いこみや前提意識を持ってしまいがちです。そんな中、アレントやセネットは、そうした発想の欠点に切り込み(アレント)、再評価していこうとさらに議論を深めた(セネット)といえるかもしれません。
「働いていること」「働くことの意味」を問い直しながら、「働く」実践を見直していくことが、まさに《アヘンに毒されず考えようとする》ことともいえるのかもしれません。
この講読会は、「仕事として」受けている人はいないわけで、「望んで」集まり、議論していく関係性にあってこそ、初めてできる議論もあるはずです。そこから、ぜひいろいろと考えていきたいですね。
感想票から――
今回初めてまなキキの講読会に参加しましたが、過去の講読会のテーマ紹介を聞いて、とても面白そうだなと感じました。リチャード・セネットという人物は今回の講読会で初めて知りました。彼の言うクラフツマンがどのような特徴なのか、興味深かったです。まなキキのメンバーのみなさんと柴田先生の軽快なやりとりがとても面白くて、楽しく聞くことができました。
レジュメが分かりやすくまとめられていたが、詳しい内容について理解することはむずかしかった。
ハンナ・アレントが指摘したように、与えられた仕事をどのようにしたら効率的に出来るかについて考えることに没頭し、それに対して忠実に行うことが、オッペンハイマーのような悲惨な事態を生み出す可能性があるということが分かった。
著者であるセネット自身はアレントを批判しているけれど、アレントの見解にも納得できる部分はあった。それは、「WHY(なぜ?)」にこだわるという部分である。確かに、作ることそのものが目的となっている場合、作り手はそれがどんなに悪影響のあるものでも作り続ける。しかし、「なぜそれを作るのか」という目的に焦点を当てると、作ることをやめるという判断も可能になると感じた。
ものの大きさが変わったとしても、そのものが持つ意味や価値、影響力について形成の過程の中で考えることに変わりはないように感じた。本文の中では社会全体に影響をもたらすような「大きな」ものの形成について取り上げているが、ものの形成には趣味のような個人の範囲のものまで含まれるように思う。どのような大きさであれ、ものが形成された先には、そのものを受け取る人間(作成者自身を含む)がおり、ものに対する何かしらの評価がなされるはずである。「ちゃんと」もの作りに向き合う人であれば、予想される評価から改善点を見出し、作成中のものにさらに磨きをかけるのではないだろうか。私は今回の講読会でものの大きさはなんであれ、作成の過程に思考するという行動が含まれないというのは実態と乖離した意見であるように感じた。
セネットがアレントの二区分を統合していたことから少し発展させて論じることができると思い、以下記述してみました。
アレントの区分は、「労働する動物」―「工作人」であるが、これは本能/自然―精神/文化という二項対立とパラレルであると思う。つまり、「労働する動物」は文化レベルでの本能性であり、「工作人」は文化レベルでの本能性を抑圧する、また一つ上の精神性(文化)であると読み替えられる。セネットがこれを統合するところから論証を始めるのは非常に理にかなっているように思う。なぜなら、自然と文化の二項を分立させては語れないからだ。
自然にある特殊な形を与えて(制御して)成り立つものが文化である。つまり、文化は自然を前提にしている。ここでアレントの議論に戻ると、彼女が「工作人」を「労働する動物」から切り離したひとつ上の次元にある者として語るのは間違いである。前者の概念は後者を前提としているからだ。セネットのように、「文化レベルでの本能に対して、いかにまた一つメタの文化で抗っていくのか」を連続して思考することは、弁証法を用いた新しい解決策を提示する可能性であるように思う。
先を読むのが楽しみです。よろしくお願いいたします。
柴田先生はオッペンハイマーやアイヒマンを「よい」労働者ではないとおっしゃっていましたが、彼らの置かれた環境においては「よい」労働者であったのだと思います。自分の置かれた環境における「よい」に従うことの是非もまた議論になるとは思いますが、それはひとまず脇へ置かせていただき、後世に生きる私たちが、相対的に判断される「よい」という価値観を用いて、彼らの行動の是非を判断することは、彼らのような行動の意味やそれが生まれる背景、仕事の仕方についての議論を両断してしまい、本質を見落とすことにつながりかねないのではないかと考えました。
今回が初参加で、非常に先生方のお話や皆さんの意見・感想が面白いものばかりでした。またM先生のレジュメがとてもまとまっていてわかりやすかったです。その一方で次回の購読会で私がレジュメを作らせていただくのですが、現在苦戦しているので的を得ない内容になってしまわないか不安です。が精一杯やらせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

おそらく、セネットもアレントも「どういったものをつくるか」ということではなく、「どうやって作ろうとしたのか――といったメソッド論を問おうとしたといえそうです。まさにこれから、みなさんと一緒にそのあたりを読み解いていけたら、と思います。
また、「よい仕事」というよりも、もしかしたら「勤勉な」とか、あるいは「適正化された」「愚直な」仕事という表現をしてもよかったかもしれません。そもそも「よい仕事」とみなされるものにどのような問題性があるのか、その本質を見極めていきたいですし、実はこれまで講読会で読んできた文献も、同じ道筋にあったことのようにも感じます。ぜひ、本質に迫れる議論をしていきたいですね。
第二講| 悩めるクラフツマン/2022年5月31日
当日資料はこちら
当日リポート
序章が比較的コンパクトだったのに、第一章はぐんとページ数が増えました。ですが、Iさんに丁寧に要点をまとめていただき、その内容に基づいて議論が始まりました。
特に、「分かりにくかったところ」として指摘がされていたのは、「暗黙知と明示知」のところでした。これは、言語化されないような、本能的に、自然な振る舞いとして行動されるような技能と、マニュアル的に明示されるようである技能の二種類があるとも理解することができますが、クラフツマンシップは「(暗黙知と明示知という)対立する価値観を体現している」とされているのです(99頁)。
それは一体どういうことなのだろう?ということがクエスチョンとして提示されたのでした。
原文を見てみると、必ずしもどうやら副題にあるような「暗黙知VS明示知」といった対立する概念としてセネットは議論はしていないようです。そもそも、明示知とは、explicit な知・awarenessとして記述されています。暗黙知が(practicedの結果として)ほぼ本能レベルで行われるようになった技能だとしたら、明示知とは、意識されながら取り組まれるような知、明らかにされているからこそ、対照可能・測定可能な知として理解することができそうです。
97頁にあるように「高度な技術の段階では、暗黙知と自覚的認識の間に絶え間ない相互作用が起きている。その際、暗黙知は錨として、明示的認識は批評と矯正として、それぞれの役割果たして」おり、それぞれが役割を果たしていくことで技能の質が形成されていくとセネットは指摘しています。つまり、クラフツマンシップは、このような意味で、暗黙知と明示知の両方を必要とし、組み合わされて実践されていくことで成立するものと説明されていたといえるでしょう。
ただ、例として挙げられていたのは、NHS(英国の国民保険)は、より明示的な知に重きを置く方向に舵を切り、効率的に多くの人を救う(あるいは税金を合理的に活用)改革に進んだ、ということでした。エビデンス的には申し分なく医療の役割を果たしている、という結果を前に、現場で働くクラフツマン(効率的に患者さんをみるのではなく、おばあちゃんを気遣うような一言が大切だと思うようなかかわり方)はなかなか、明示知として展開される方法論に否定はできないことも指摘されています。
明示知的なアプローチが、「官僚的な監視から時間を稼ぎ出すために、書類上の虚構を創り出」す医師たちを生んでしまうように、問題を孕んでいること、最善の策ではないことが共有されていながら、暗黙知的なアプローチが軽んじられてしまうような傾向に、今回の章のタイトルにもあるような「悩めるクラフツマン」のありようが現れていました。
暗黙知的なアプローチそのものが医療の場で果たす役割も、否定しようがないほど大きいはずなのに、です。
実は「悩めるクラフツマン」と、クラフツマンが発揮されることで果たされる可能性は他の側面からもうかがえます。
市場主義的な発想下では「競争」の原理が重要とされますが、よいものを作るのであれば集団的目的を持ち、その中で「協力」していくことが重要になりえるかもしれないこと。
技術を高めていこうとする中で、テクノロジーの発展が果たす役割はとても大きくて、否定のしようがありません。ですが、その万能にも見えるようなテクノロジーの仕事(例えばCAD)にも、行き届かないところがあって、そこには身体感覚に依拠し、練達したクラフツマンシップのようなものが重要な役割を持ちうるかもしれないということ――。
クラフツマンが、どういうところで育ち、いかに展開してきたのかをここから振り返っていくことを通じて、競争原理やテクノロジーの進展、そして明示知に重きが置かれ、それを否定しがたい状況に身を置く私たちが、どうしたらクラフツマンシップ的なものを大切にしていくことができるのか――ぜひ考えていきたいと思います。

前回のセネットの文章で主題となっていたのは、「暗黙知VS明示知」というよりも、「correctness・正しさ」と「practical・実践的」の対比なのでしょう。市場原理の下では、モチベーションを盛り立てるのは「競争」であるべき・あるはず、という「正しさ」がありますが、現実には、協力的に本当に良いものを作ろうとする試み;practiceの中にモチベーションが育っている。でも、それでは儲からなかったりして、マーケットに席巻されてしまう。
CADというテクノロジーも、きれいなものをたくさん生み出せる「正しい」ものとして建設現場で活用されていますが、実際には、設計時点では発言権がほぼ皆無である現場の人間が、実際の運用上の観点から調整されて成り立っている状況があるわけです。
クラフツマンシップは、いずれの「正しさ」からも排除されてしまう、そういう状況にある、ということを指摘していたとみなせそうです。
参加者の皆さんからのコメント
Iさんのレジュメが非常に分かりやすく、レジュメ作成の勉強になりました。機械の誤用に関する説明を聞いて、英語を学ぶときにAIやGoogle翻訳などの機能に英文をそのまま打ち込んで和訳したり、或いは和文を英文に直すプロセスを取ったりすることも機会の誤用と言えるのではないかと考えました。
「クラフツマン」は「物事に打ち込んでいる特別な⼈間の状況」を表している。私なりにその言葉を考えると,「クラフツマン」は,現場で仕事をして,対象と直接かかわり,行為を工夫し動かす人なのだと思った。『市場主義的な発想下では「競争」の原理が重要とされますが、よいものを作るのであれば集団的目的を持ち、その中で「協力」していくことが重要』とされる可能性が今後出てくる。今までの歴史からも分かるように,これからテクノロジーや競争原理が進展すると,クラフツマンの在り方も変わりうることが分かった。
機械的に仕事をしていくのか、人と人との交わりをしながら仕事をしていくのか、どちらに重きを置くにしてもクラフツマンはその間に立たされているということ。効率的に進めようと機械が導入されても、それでもクラフツマンは現場で、見えないところで、仕事をして大きな発言をする力もないく働いている。機械的に仕事をこなす看護師と、人間的な関わりを大切にしようとする看護師の例えが分かりやすかったです。
フォード式に関連した参加者の方が過去に大手のチェーン店で働かれていたときのエピソードを聞いて、クラフツマンであることの難しさはその人自身がどのように働き創造するかという問題もあるが、それ以上に周りの環境が人々にどのように労働させることを目的としているかということが大きく関わっているように感じた。序章を読んだときはクラフツマンであることが最も良いことであると思っていたが、効率や正しさに対してはクラフツマンでは太刀打ちできないこともあることから、いくらクラフツマンでありたいと思っていたとしてもそれを許さない環境があり、どの視点から見るかによってクラフツマンの評価も変わるということに気付かされた。
議論の中であるバーガーショップの話題や病院の看護師の話が出てきましたが、よく考えてみるとたしかに周りにクラフツマンなど存在しないことに気づきました。クラフツマンの特徴だけ見ると、仕事の在り方を考えさせられるようでとても素晴らしい仕事人のように思えましたが、現代社会にはもはや必要とされていないことを学びました。

Google翻訳などは、機械の誤用なのか、というあたりはおもしろい観点ですよね。今後、そうした研究会などもぜひ開催していきたい、という声もあるようなので、ぜひ議論していきたいですね。
また、クラフツマンはもう、この世界では求められていないんでしょうかね。クラフツマンシップが存在しない社会…「それでよいのか?」と問われたら、おそらく、著しく悪いはずです。私たちは、COVID-19感染拡大を経て、「ちゃんと仕事をしよう」もとい「ちゃんと学ぼう」としている人たちが非常に過酷な事態に直面していたことを見てきたと思います。
「今のままでいい」とは思えないような世界にいるとき、それでは、何に依拠して、何を参考にして、立て直しをはかっていけばいいのか。その縁にクラフツマンがなるのではないか、と思います。
第三講| 作業場(ワークショップ) /2022年6月7日
当日資料はこちら
当日リポート
ここまで、クラフツマンシップは、今の時代において成立しえないものなのではないか、とつい悲観的な思いになってしまっていたかもしれませんが、ここからの章は、クラフツマンがクラフツマンたるための要素が示されていくところとして読み進めていけるようです。今回はまず、その一つ目の要素として紹介されたところでした。
議論されていたのは「作業場」。中世ギルドにおける作業場は、親方がいて、職人がいて、徒弟がいました。よいものを作ろうという想いで集まり、その技を盗み、磨くような場として機能する作業場は、まさに製作するものの良質性を保つべく、きわめて権威的で、かつ自律的な場であったとされています。
ここでいう「自律性」とはいったいどういうことなのか――「表現に富んだやり方で、他の力を借りずに活動するように私たちを駆り立てる、内側からの衝動としての自律」(121頁)は、ある種、自由で自立しているもののように見え、「権威」とは真逆なもののように感じられます。本質的に対立するように思われるこの「権威」と「自律」が絶妙に両立されていた空間として「作業場」が存在し、それゆえに良い製品が生み出されていた、というのです。
「よいもの」を作るための技能は、権威的な構造の中でしか伝達され得ません。ですが、完全に権威化されているものの中でも、技術は伝達しえないのです。
これは、大学での研究室やゼミを似たように捉えることができるのではないか、という指摘にも繋がっていました。
大学で取り扱われているような「知識」も権威的な場にあってこそ初めて伝達され得るものです。未知の内容について、学ぶ側にある人は、その要/不要を判断することができません。本人が、「この授業のスタイルで私は学びたくありません」と言っても、それでは単位はつかない。その意味で、既に権威的な構造が大学には前提として存在しているのです。
でも、得られた知識から自由に発想し、研究を進めていくことについて、誰かに強制されたり指図を受けるものではあってはなりません。実は大学という場で、「自律性」は非常に重んじられているのです。大学という場所も、本来、「権威」と「自律」が共存している場でありえるのかもしれません。
もしかしたら民主主義の世界では無条件に尊ばれるものなのかもしれない「自律性」。でも、それだけではクラフツマンシップは成立せず、そこには、「権威」と「自律」が両立している必要があるということ…。大学での例を踏まえて考えると、クラフツマンシップにおいて「権威」と「自律」の両立が必要だ、というセネットの主張は、ある種の意外性を持ちながらも、説得力のあるものとして理解することができるかもしれません。
なお、ギルドの中での「権威」と「自律」は、「よいものを作るとき、社会や第三者に対して、おもねらない」というところにも特徴がありました。ある個人が独創性を発揮させるような形でものづくりに挑むとき――芸術とも表現できるような場面では、どうしても第三者の感性に評価を委ねざるを得ないという点で、「自律性」を保つには困難があります。
その芸術家が所属する社会空間に評価を託さなくてはならない=社会空間に依存・忖度せざるを得ないためです。その時代・その空間におもねいた作品を生み出さねばならない、という点で、「独創性」と「自律性」を両立させることは非常に困難であったのです。
同様の理由で市場原理の中での製品づくりも、社会からの評価にある種依存せねばならない――「自律性」を欠かざるを得ないものとして理解することができるのです。
「良質なもの」を生み出す実際の技・知に「権威」が宿り、その「権威」の下で技術や知が継承されていくということ。そして、その引き継がれた技術を忠実に繰り返していくことで「自律性」も具えた集団的努力が発展していく――その営みに与することができたなら…と思いながらも、個人的には、COVID-19感染拡大で変容した「学び」の環境では、”親方”からの知恵を習得していく、”膝を突き合せた”共にある場の構築に、相応の工夫や努力が求められているようにも思います。
クラフツマンの講読を通じて、クラフツマンシップを成り立たせる秘密を探り、私たちが学び、生きていく環境をどう築いていくことができるのか、考えられたらと思います。
参加者の皆さんからのコメント
今回初めてまなキキ講読会に参加しました。正直、すごく理解するのが難しかったです。クラフツマンの作業場ということで中世は特にキリスト教の影響が強く感じられました。師弟関係はすべて親方によって決まるので、弟子は親方選びが重要だと思いました。今の社会ではほとんど消えている師弟関係ですが、伝統的な工芸品などを作るうえでは重要で消えてはならないものだと感じました。
今日の講読会に参加して、クラフツマンとして生きていく上で、自律性と権威への従属のバランスをうまく取っていくことが難しそうだなと感じた。先生たちのお話にもありましたが、例えば授業評価アンケートでウケのいい授業を展開したとしても、それが学問的には歓迎されることなのかと考えると微妙な調整が必要であるように思う。周囲から求められる、所謂明示的認識に合わせつつも、自分の持つ暗黙知をどう活用し、そして発信していくか、という部分はクラフツマンの難しさでもあり、面白さでもあるのではないかと考えた。
クラフトマンは自律と権威の境界線にいるという点がとても興味深かったです。たびたび例として取り上げられているロシアの状況下に置き換えてみても、軍隊の中に、あるいは最も権力をもつまとめ役の中に、クラフトマン的思考を持つ人がいれば、全く現在とは状況が異なるはずだと思います。どのようにアプローチすればクラフトマン的思考が現在の自由競争社会に柔軟に取り入れられるか、しっかり考えなければならないと考えました。
権威的な中では自由は生まれないのではないかと思っていたので、第二章を読んだ際にもなんとなく腑に落ちない感覚があったのですが、大学の例を聞いて納得しました。大学では学生は権威的に教わり、その中で自由な発想のもと論文などを書いていくと思いますが、社会に出ると社会で思われる良い人像みたいなものに自信を当てはめようとしてしまうので、現代社会の中で自分が社会の中でクラフツマンであり続けるためにはどうしたら良いのだろうか、ということを考えながらこの本を読み進めていけたらと思います。
技術や工業の発展の段階として、作業場やギルドの存在は必要不可欠であったと考える。一方で、自分たちが行っている仕事そのものではなく、その仕事が組織される方法に準じなければならないことは、自律への障害となりる。この様にクラフツマンシップには功罪が存在する。ストラディバリウスを例にすると、暗黙知により積み上げられた技術はあるものの、次世代(後継者)への伝達の難しさや容易な教育方法論が見つからないという課題が挙げられる。クラフツマンシップにより積み上げられた技術や経験を基に、「創造的」に働き独創性を発揮することのバランスのとり方の難しさを感じた。
芸術的に天才として新しい発想のもと社会に媚び諂うのと、クラフツマン的に作業場で社会にあるものに自律性を加えてモノを作ることと、この違いが難しく感じた。どちらも社会的な評価を得られるという点は同じなのか。それとも自由市場社会では前者がより評価されるということなのか。例えば、音大卒N響バイオリニストはクラフツマンで、独学で音楽をし成り上がった元バンドマン俳優の星野源はアーティスト(またはクリエーター)だとすると、この違いは何か?やっぱり前者の方が素敵なのだろうか?加えて、ギルドの始まりや親方は天才と言われたりしなかったのか?次に、仮に「天才」「才能」「独創的」を否定するのであれば、この論はギルドに生きられないような(社会性がないような)人間の逃避場所や孤独な生き方を完全に否定しているようで、少し危険なのではないかと感じた。孤独な人間もクラフツマンも肯定される社会を考えるべきではないか?でも、中世と現代はそもそも違うから、以上のような議論は不毛なのだろうか?この辺りが非常に気になった。
『クラフツマン』の第二章を読み、議論を行なった。セネットは権威と自律という二つの側面について考察しており、その中で中世のギルドやルネサンス期の芸術家といった例を用いていた。クラフトと芸術は明らかに異なっており、その違いをセネットは行為の主体、時間的な差異、そして自律の3点に求めていた。
当初は「クラフト」という大きい枠組みの中に「芸術」が含まれているのだと考えていたが、特に自律の面において、クラフトはそれが持つ独創性をコミュニティ内の他者に認めてもらうことで自律が生まれるが、芸術は独創性を認める他者の存在はクラフトに比べると小さなものであるため、クラフトと芸術は別物なのだと学んだ。

「自律」という言葉は、ほぼ「自由」という言葉に置き換えて捉えてもいいと思うのですが、セネットは、実は「自由」に振る舞うことは、それほどcreativeなものにはならないと捉えているように思います。何もないところから、ただ「自由」であるだけでは、創造的にはなれないのですね。一方で、権威的すぎであってもいけない。命令のままに動いて、歯車のように動くことでは、クラフツマンシップは成立しないわけです。封建主義的な徒弟制はこの時代においては、とても時代錯誤的に思われるかもしれませんが、これが両立してよいものが生み出される、という話でした。
現代の「授業評価アンケート」なども、結局のところ、本当に授業の評価ができているかはあやしいです。私がアメリカでたまたま鑑賞していた映画の中で軍隊の兵士である登場人物が突然命令に背いて発砲しだすシーンがあったのですが、そのシーンをみて、軍歴のある人は「あれはプロじゃねえ。本当のプロは上官の命令に背かないんだ」と教えてもらったことがあります。兵士もクラフツマンっぽく見えるところがありますが、軍隊においては、パーツとして捉えられている側面が強く、ほぼフォードシステムに近いようなものなんですね。
独創性、天才という観点も非常に面白い議論ですよね。どちらかというと、星野源のほうがクラフツマンっぽくも感じられますが…私の知人のデザイナーは、「センスがよくてすごい」のではなく、年がら年中デザインのことだけ考えて、ものすごくデザインを見ていることで、デザイナーとしての自分が成立していると話してくれたことがあります。私自身もライターですが、最初からライターだったわけではありません。ものすごくたくさんのものを読んで、自分なりの文体や書き方を修得していったんです。権威的なところからベースを得ているともいえるでしょう。そういう意味では、クラフツマンと芸術家は、少し対立するものとして説明されていたところもあったかもしれませんが、ほぼ重なるものとして理解されていたと思います。ただ芸術のほうがおもねるところも実際にはあるのかもしれませんし、N響のバイオリニストのほうが自由なのかもしれないところはあります。メジャーデビューすることで、売れ線を狙う/狙わざるを得ないアーティストもいるわけですものね。この独創性・天才も大変おもしろいテーマになりそうです。
第四講| 機械 /2022年6月14日
当日資料はこちら
当日リポート
クラフツマンがクラフツマンたるための3要素の今日は2つ目が紹介されている章、として読み進めていきました。タイトルは「機械」。人間の模倣であるレプリカントと、人間の拡張であるロボットの二種類を「機械」に据えるとしたら、後者のロボットは、人間には達成しえない人間の能力以上のことをもたらします。そのことが、例えば笛吹人形たるレプリカントがほのぼのとした癒しをもたらした反面、同じ技術を転用した織機は、リヨンの織工たちを迫害した例が紹介されていました。
現代にもどこか通じるようなテーマにも感じられる中、議論は進められました。著者は、「啓蒙主義」の概念を示し、人間が機械の能力には及ばない「不完全性」を自覚し、敢えてその事実を織り込みながら機械を用いることで、革新性が生まれるのではないか、という趣旨のことを提起していたようです。これはどういうことなのでしょうか。
例えば、ガラスの窓を作るのに、人が作っていた当時は大変な手間がかかっていました。その分コストもバカ高かったわけですが、その出来は必ずしもよいものではなく、問題も多いものでした。圧延機と呼ばれる機械が導入されると、人間にはとても作れないような滑らかできれいな機能性も高いガラスを大量に生産することが可能になったわけです。
それはそれで素晴らしいことなのですが、実は私たちはそこに物足りなさを感じることも、また事実なのです。気泡が入っていたり、歪みがあるようなガラスに魅力が感じることもある。絵付けの器なども、機械的につくられたものよりも、ひとつひとつ表情が違う器の中から、自分が選び取る器だからこそ、愛情が持てるというようなことは、よくある話だと思います。人間――クラフツマンは、機械が作るものを「模倣」するのではなく、その機械が生み出す完璧性と折り合いながら、人の手を加えることで新たな価値を生み出す――「革新」性を付与することができるのかもしれません。
私たち人間は、機械と比べてしまえば不完全で完璧なものは作ることができません。ですが、「不完全」であるが故に、「模倣」を超えた「革新」を通じて、新たな意味や価値を生み出すことができるのです。
そこで鍵となるのが、「啓蒙主義」的な姿勢です。
冒頭の「啓蒙主義」が示したことは、「理性の力ですべてコントロールすることができる」という発想に立ち、理性を備えようとする働きや運動のことを示すのではなく、己の限界の自覚を通じて節制的であることに重きを置くような姿勢として理解することができるのかもしれません。
自分の限界を知って居るからこそ、完璧なものである機械に対して、どのように”不完全”である自分の手を入れていくことができるのか、を考えるということ。――そこには、相当のトレーニングや相当の自覚が求められるのかもしれません。また、だからこそ、「実験的精神」が求められ、「有益な失敗」もこうした前提のもともたらされうるのかもしれません。
自分が「完全ではない」、「完璧ではない」という自覚を持ちながら、何か物事に取り組んだり、介入しようとする姿勢は、自分が正しくない可能性を担保して語る――反証主義的な――節制的な態度といえ、それこそ、理性があって成立し得るものなのかもしれません。この、節制的な態度、自分は完ぺきではない、と自覚して臨む態度は、機械には持ちようがないものです。この鍛えられた姿勢や態度こそ、クラフツマンがクラフツマンたる二つ目の要素と見なすことができるものなのかもしれません。
完全・完璧であることを疑わない機械に対して、私たちは、もっと慎み深く、あらゆる可能性を熟慮しながら次の一手を考えることのできる存在なのかもしれない、ということ。昔、ちびまる子ちゃんというアニメーションの主題歌で「エジソンはえらい人」と謳われていましたが、そのエジソンは「1%のひらめきと99%の努力」という言葉を残していたよなあと思い出されたりもしていました。「天才」と呼ばれるような人も、啓蒙主義的な態度のもとで、「実験的精神」と「有益な失敗」を経て、革新的な発明を生み出していたのかもしれません(モーツァルトの例も引かれていましたね)。「才能のなさ」を切なく、悔しく思うこともありますが、だからこそできることもあるのかも、と七転び八起きの精神で、引き続き読み進めていきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
「人は社会に受け入れられないとやっぱり生きていけないんだなあ」という,ぱんこさんのこめんとにハッとさせられた。クラフツマンはなんのためにクリエイティブなものを作っているのか考える必要があると思った。自分のためなのか,社会のためなのか,結局社会に還元できない生産は意味がないのだろうか。
私は最近短歌作りを嗜んでいるのですが、短歌を「うまく」詠むためにはlearn by doingにどうしてもなってしまいます。短歌におけるここでの「やること」というのは、私は歌集を読むことや他者の詠んだ短歌に触れる中で、どのような特徴があるのか、どのような点に惹かれるのか、己の中で分析し、自分の制作に落とし込んでいくことを指すと考えました。その上で、講読会の中でも話題に上がっていましたが、分析し特徴を落とし込む中ではみ出した部分が己の個性や詠みたいものであり、「はみ出してはいけない」と完璧を求める中でそれは生まれないのだと思い、元気をもらえたような気持ちになりました。全ての「もの作り」に対し、完璧じゃなくて良いのだという姿勢を打ち出すことは、後世の製作者を生み出す面でも重要であるように感じます。
モノの使用者について考え、実際にモノを制作し、使用者に納めるという一連の流れ全てを「ものづくり」とすると、機械は二段階目であるモノの現実的な制作の種類を提案し、実行することはできたとしても、そこに新たに考えを付随することはできない。考えを膨らませ、考えに裏打ちされたモノの制作ができるのは我々人間であると学んだ。
人々は多様性や個性、機械が作ることのできない唯一無二のものを欲します。機械に求めるのは人間の不完全性なのです。この不完全性を発揮するには、機械を否定することなく、不完全であるという自覚をもって、機械の現場に入り込むことが必要です。あえて人間の手を加えて新たなものを作り出すことがイノベーションであるをと思います。

エジソンの発言には実は諸説があるようで、「1%のひらめきがなければ、99%の努力は無駄になる」という解釈もあるのだとか…。そう考えると、まったく逆の意味になってしまいますが、いずれにしても含蓄のある発言ですよね…。ですが、こうした革新は長期戦の戦略を通じて生まれていくはず。くじけずに頑張りましょうね。
「社会のため」、あるいは「有用性」の議論についてですが、セネットはその議論を注意深く取り扱っていて、議論を避けているような印象があります。それゆえ、丁寧に読み込んでいくことに意義がありそうです。
実は前回の節には、おそらく二つの意味合いが持たれていたといえるようにも思います。まず一つは、「人間の不完全性さ」に関する議論。そしてもう一つは、「結局つくるのは人間である」ということなのではないでしょうか。機械だけですべてが作られているわけではないのですね。すべて人間の行為なのです。「人間の拡張」という表現も、人間が前提として置かれていることからも、人間があってこその機械というセネットのスタンスが伺われます。セネットはテクノロジー万能主義の議論はしていないのですね。ただし、現在はセネットが議論していた当時よりも、メタバースなどをはじめとして、より機械に人間が溶け込んでいるような時代でもあるように思います。だからこそ、人間の不完全性を肯定的に引き受けていくことが重要になるのかもしれません。機械として目指されるのは「効率性」や「注目度」、いわば”イイネ”の数だったりするのかもしれませんが、そうした尺度からは評価しえない、人によっては「欠陥」とみなされるようなもの――万人受けはしない不良品こそが持つ意味や価値を対置させて考えていくことが意味を持つのではないか、と思ったりもするのです。
第五講| 物質への意識 /2022年6月21日
当日資料はこちら
当日リポート
1章の最終節となった今回。柴田先生のリトアニアでの経験も語られた回でした。リトアニアの首都・ヴィリニュスの聖ペテロ&パウロ教会に訪れた際に圧倒された、漆喰(スタッコ)の超絶技巧の彫刻についてお話くださっていました。当時の人間(クラフツマン)の生への渇望ともいえるような…怨念とも言ってもいいような…ものすごい気迫が衝撃的で、その後(悪?)夢にも出てくるようなインパクトがあった、というお話でした。――そこには、おおよそ「人工」とは言い難い、過酷な自然に対してささげられた祈りといったような、まさに「自然」を象徴するものがあったように思う、というお話だったと思います。
考えてみると、「煉瓦」という人工的に作られたモノは、もしかしたら石よりも、木よりも、自然になじみ・溶け込んでいるようにも見えるかもしれない、という指摘もされました。一方で、景観を損ねないという名の下に茶色くデザインされた標識や信号、コンビニエンスストアは、自然の中にあって、結果としてその人工性を際立たせているようにも見える、とも指摘されていました。
いわば、「自然性」を狙って”デザイン”されたとき、その目的は、”デザイン”どおりには達しえないものなのではないか、ということ。今回の節で指摘されてきたような、「煉瓦」の例は、クラフツマンが「煉瓦」というものに向き合い、その土の特性を丁寧に生かし、その煉瓦を焼成する窯の特性を把握し、その成分に配慮し、煉瓦をひとつひとつ積み上げるうえで必要な細やかな調整と修正を(ある種、命がけで)徹底したその結実(――そして、そこにクラフツマンたるローマ時代の奴隷は、その「しるしpresence」を残した)として、完成されていたということ。そして、その「煉瓦」たる本質――物質を眼差すことで、その「煉瓦」が人工的に作られたものでありながら、もっとも自然に調和したモノとして、完成されていたのではないか、という指摘をセネットはしていたのかもしれません。
そもそも、この節で論じられようとしていたのは、古代ギリシアから課題とされてきた「文化が自然界の変容の循環にいかに抵抗するか」(220頁)ということでした。セネットによれば、プラトンは、イデアは持続していくという観点で、朽ち行くモノに対して上位にあると捉えていた、とし、それが行為と観察を分離させるきっかけにも、西洋文明の源泉にもなった、としています。
つまりセネットは、この節を通じて、クラフツマンが、この自然界におけるエントロピー;やがて朽ちていく「崩壊」に対して、どのように向き合ったのかを議論していくことを主題としていたのです。
クラフツマンの正しい意識の領域として示されたモノに対する意識、すなわち「物質への意識」がどのように覚醒されるのか、について3つの観点から指摘がされてきていましたが、いずれも、時間をかけて、じっくり、そのモノたる対象に向き合う実践がされていることが説明されていたように思います。そのモノにとっての一番最適なありようが実現できるよう、クラフツマンは手を加えていた、ともいうことができるかもしれません。
今日の私たちの社会では、何かが生み出される工程において、しばしば「考えたり、デザインをする」ことが上位におかれ、「つくる」ことそのものは低くみられてしまいがちです(そして、それは決して今に始まったことではなかった)。セネットは、モノに手で触れて何かしようとする取り組み――その本質を見極め、それがよりよくなるよう手を加えていく、ということこそが、そのモノをより豊かに発展させていく可能性をもちうることを主張していたのかもしれないのです。
議論の中で、ある自然の中でつくられた展示作品が、「自然」を感じさせるどころか「人工性」を際立たせているよね、と紹介されていたりもしました。自然をどう取り扱い、どのように作品化させるかは、それぞれの作り手に託されるもので、評価もさまざまにあってよいものと考えますが、今回の議論に照らして考えると、その作品は、「クラフト」とはいえず、その作り手も「クラフツマン」とはいえないのでしょう。
決して「よしあし」を議論するものではないにせよ、セネットは、青写真的に描かれる”デザイン”よりも、忠実にモノと対峙する時間をかけた実践にこそ、容易く「崩壊」することのない、”文化”といえるようなものが築かれていくヒントがみられるのではないか、といったことを指摘したかったのではないか、と思いました。(と言っている時点で、生み出されるものに対する価値判断が入ってしまっているようにも思えてしまうのですが……)
ここまでで、クラフツマンがクラフツマンたる要素を見てきましたが、ここからは、より具体的な技法にも目を向けていくことになるようです。次回からはいよいよ第二章。引き続きよろしくお願いいたします。
参加者の皆さんからのコメント
陶工たちは物質(煉瓦)を擬人化させるとあり、生命を持たないものに人間的性質を与えるというのは面白い考えだなと思った。職人ではない私たちにとってはただの煉瓦であっても、彼らにとっては新しい価値をもたらし活かす考えを持っていることがわかった。
人工的に作っている物の方が自然に溶け込んでいることもあるというのが面白いと思った。
デザイン的思考で作り出すものは偽物チックになってしまい、ただレンガを積んでいるようなものの方が自然で人間味がある、というのは私たちはどうしてもまずは頭で考えてしまいがちだが、頭で意識せずに実際に手で作ったものの方がいいものになる。この考えは何となく理解できるため、自由な発想でものを作ることが1番自然なのだとわかった。
京都のローソンのお話が出ていましたが、私はあの例を中学の社会科の教科書で始めて見ました。その際に「景観を壊さない」配慮というように出てきた気がします。現場の人間(がクラフツマンだとは限りませんが)はあのようなコンビニをどのように作ったのだろうと気になりました。「これって本当に景観を守っているんだろうか?」と思っていたかもしれない、とも思いました。

フーコーもそうでしたが、セネットも表立って「これがいい」みたいな話はしない論者ですよね。一方これまでの講読会で読んできたイリイチははっきり「いい」「わるい」を指摘していましたが…。ただ、セネットは「クラフトのよさ」を指摘していることは確かだと思います。同時に、クラフト、クラフツマンという存在が軽んじられてきた、ということも指摘しています。プラトンがいうような「理論」に対しても、現実社会における「デザイン」や「アート」に対しても劣ったものとして軽んじられている、ということに問題を提起し、クラフトには重要なものがあるのではないか、ということを主張しているようです。クラフトは言ってみれば「地に足がついている」もので、実物、目の前にある、そのモノに対して何を作っていこうとしているのか、ものすごく考えて営まれるものだ、という指摘をしています。そのような意味では価値判断が入ってしまっている、という理解をしてしまってもいいのかなあとも思ったりもします。
また、クラフツマンは、「自然の制約」の中で手をかけている、ということが鍵になるのかもしれません。頭の中で考えることはある種、自由な発想が許されていて、現実に依存しないところがありますが、クラフツマンは自然の在り方に抵抗をしませんし、そもそもそこに「自由」が効くとは捉えないようなところがあるようです。煉瓦の色も、土の性質など、その対象・モノの自然を正直に受け止める過程で現れてくるものだった、と指摘されていました。制約の中で、そのものの良さのようなものが発揮されているのです。
本当に山の中へいくと、コンビニというようなものは存在しません。人工的なものである「山小屋」は確かに建っていますが、決して自然の景観を壊すようなものではないのです。「自然の景観を損なわないように」といったことを考えるまでもなく、ただ、その自然の中に溶け込んでいるありよう、というものを、景観に配慮したコンビニと照らし合わせて考えてみると、セネットの指摘に納得できるような気もします。
第六講| 手 /2022年6月28日
当日資料はこちら
当日リポート
講読会に対する冒涜!みたいなスタイルでの報告となってしまった前回…(講読開始時間前までに帰宅できず、車内からの報告となりました…)。個人的にも不本意な展開で、深く反省もしているところなのですが(時間管理の勉強の必要性…:時間の計算についてはこちら)、音もよくなく、映像もおかしい、(報告も分かりにくい…涙)ということで、大変失礼いたしました…。
前回のふり返りの中でも確認されたとおり、セネットは、この著作を通じて、「(理論からも・デザインやアートからも)劣ったもの」と軽んじられてしまいがちなクラフツマンの価値や意義を提起しようとする試みをしているようです。今回の章以降はその具体的なありようを注目していく、ということで、2部の初回となった今回は「手」に着目した回となりました。
たくさんの「手」にまつわる技術が指摘されていましたが、セネットは「客観的基準」があるからこそ、失敗を繰り返したうえで「移行対象」たる”真実”を目指す、実践=練習=習慣・practiceが可能になるというようなことを主張していたように思います。
ただ、この「客観的基準」はすべてのものに備わっているのだろうか?相対的になってしまうものもあり得るのではないか、というような疑問から、今回の議論が始まっていたように思います。何が、クラフツマンたる人たちの「客観的基準」になり得るのだろうか、といった疑問です。
特に、今回は「手が高度に訓練される3種類のクラフツマン」に着目するということで、音楽家、料理人、ガラス吹きが注目されていましたが、ここではなぜ、「画家」や「ダンサー」などは例に上がってこなかったのでしょうか。もしかしたら、そこにポイントがあるのかもしれない、と議論が展開していきます。
音楽家や料理人、ガラス吹きにはあって、画家やダンサーにはないもの…?
音楽家や料理人、ガラス吹きなどには、おそらく「よい」とみなされるような”本物”――truth / correctness が明示的にあるという指摘がされました。音楽家にとっての「正しい音」は分かりやすいかもしれません。料理については、「ミルクのかかったコンフレーク」は◎だけど、「オレンジジュースのかかったコーンフレーク」は×といった、多くの人にとって共有される”基準”のようなものが確かに存在している、といえるのです。
「正しい音程」だったり「おいしさ」といった”真のもの”に、クラフツマンは常に拘束されていて、所与の条件から、この基準に適うようにうまく対応していくことが求められる、ということ。そのpracticeの過程に、「力加減」に関する議論や「反復」やリズムといったポイントが見いだせるともいえるのかもしれません。
一方で頭で考えることは、現実のモノのありようや状態に拘束されることなく、自由です。”本物”に拘束されないがゆえに、ぐちゃぐちゃになってしまうようなこともあり得るのです。モノに合わせて加工していくこと――すなわちモノに依存して、手を介していくことで、良いものは作り出されている、という指摘であったのかもしれません。(この話を通じて折り紙を連想した、というコメントもいただいたりしていました)
一方で、注意欠陥障害の子どもたちに対しても、取り組む内容について、「それ自身のための内的リズムを創造することによって」(304頁)集中力を持続させることができるのではないか、といったセネットの指摘については、「本当にそうなのかなあ」といった指摘もされていました。
自分が何をしようとしているのか/どういう状況に身を置いているのか、理解のないままに、集中力を持続させることなどできるのだろうか?といった声もあがったところで、今回の議論は時間切れとなりました。
そもそも、報告者にとっても、もしかしたら参加してくださったみなさまにとっても、とても集中力を欠くような形態での回となってしまったことが、皮肉そのものでしたが、個人的には、「客観的指標」が存在するとは、志向すべき対象がある、ということそのものだと感じました。
そうした”移行対象”があってこそ、試行錯誤は可能になると感じます。何をしているのか、何をしようとしているのか、分からない状態で集中しろと言われたところで、集中のしようがないのは当然としか言いようがないようにも思います。スズキ・メソードでも、まずは「正しい音」を定着させることが大前提とされていたとおり(275頁)、身体のpracticeは、客観的指標が示されたうえで成立するものと指摘されていたようにも思います。
以上のような議論がされていた章であったからこそ、”真”/”明示的な本物”がないモノについて、クラフツマンの議論はどう成立するのか、相変わらず疑問に思いましたし、注意欠陥障害のある子どもたちへのアプローチについて、「内容を伴った取り組みが集中力を育てる」という議論に「否」を唱えるセネットの指摘に「??」が浮かぶ結末となったのだと感じました。
「??」もありつつ、引き続き皆様と議論をしていけますと幸いです。また、次章以降でも、どのようにこの後の議論をセネットが展開していくのか、も楽しみです。
参加者の皆さんからのコメント
身体が感覚的データを得る前に予測し行動するといった動作の専門的名称を抱握といい、例えば指揮者は音に一瞬先んじて指示の手ぶりを行う。高度に技術化した手によって価値が増進するのではないかとセネットは述べている。あるテーマの内容をまだ深くは理解していない見習いたちにとっては、「集中」することが第一に必要である。
「手」の操作を通じて人間が技術を獲得していく過程についてクラフツマンでされている説明をまとめた。そしてセネットの主張について、技術獲得における試行錯誤の到達点、「真実」を示す基準は普遍的に存在するのか。感覚的、相対的なものではないかといった議論がなされた。最後は内容を理解せず試行錯誤を行うことなどへの疑問が残る形となった。
音楽家、料理人、ガラス吹きに共通するのは、よいとされる本物が明示的にある・客観的指標があるというところで、それが画家やダンサーとの違いであると分かった。また、客観的指標がないものについて、クラフツマンの議論はどう成立するのかということや、注意欠陥障害のある子供たちへのアプローチについてのセネットの指摘については、疑問があることに気づいた。
なぜ画家やダンサーは例として挙げられていないが、音楽家や料理人、ガラス吹きは例として挙げられているのかというと、音楽や料理には、正しい音・おいしい料理というように、正解や本物が明示的にあるが、画家やダンサーには明示的な正解がないという違いがあるという議論が、とても印象に残りました。
最初に、手をカップ状にできるのは人間だけだという事実を知って驚いた。人間の手は様々な場面で活躍していて、音楽などの芸術も生み出すことのできる素晴らしいものである。私はセネットの考える、身体を動かして対象を良くしていくという考えに賛成だ。実際に手や足などを動かして得られる経験は大きな刺激になると考えるからだ。

二部に切り替わって、セネットが指摘しようとしていたのは、モノとイメージの関係性についてですよね。私たちは、イメージを形(モノ)にしていこうとするので、つい、イメージがモノに先行すると捉えてしまいがちです。でも、セネットは、イメージを先行させるばかりでは、「よい仕事」はできないと考えたんです。
具体的にモノを作っていくとき、そこには何らかの拘束や制約があるわけです。使えるもの、本当に「よいもの」をつくるためには、実際にあるモノと向き合っていくことが不可欠となる。そこで、頭と実際のモノをつないでいくプロセスが必要になる――ようやく登場してくるのが「手」です。『most likely to suceed』というアメリカのHigh Tech Highという高校で実施しているproject based learningの授業を題材としたドキュメンタリー映画があるのですが、その中で登場するシーンからも、前回の内容を彷彿させるようなシーンがありました。壮大な歯車でできたしかけを作ろうと意気込む少年が出てくるんですけど、CADなど使いこなしながら、わき上がってくるたくさんのアイデアをあれもこれも叶えたい!と挑戦するんです。でも、実際にモノをつくろうとすると、なかなかうまくいかなくて、本来完成すべき締め切の日を大幅に過ぎて、ようやく長期休暇に入って完成させていました。それはそれは素晴らしい力作です。これも、頭の中だけで考えているだけではできない、完成しないようなことがあって、モノと対峙することなしに、「よいもの」は作ることができない、という、ある種の現実の現れだったのだと思います。
”creativity”という言葉はよく取り扱われる単語ですけど、現実から拘束されているからこそ、多様なものが生まれるといえるのかもしれませんね。そのためのデヴァイスの一つとしての「手」を挙げて、それが人類特有なもの、とセネットは指摘していたのかもしれません。
ちなみに余談ですが、自然人類学?などの分野では、実は親指と他の指が対向しているということよりも、「爪」の存在のほうが、サルとヒトを分ける要素になっていたのではないか、という指摘があるそうです。本来動物にとって爪は武器にもなるようなものですが、ヒトは実は爪をのばすことができない(巻いてしまったり、割れてしまったり、折れてしまったり)。武器になりえない爪をもつ生き物という意味では、ある種「奇形」や「障害」の一種としてもみなせ得るものかもしれないわけですが、爪をのばせなかったからこそ、モノをやさしく、精確につかむことができるようになったのかもしれず、道具を取り扱えるようになることに繋がったのかもしれません。
第七講| 表現力の豊かな指示 /2022年7月5日
当日資料はこちら
当日リポート
今回は、思わずお腹が空いてしまいそうな内容…というよりかは、どちらかというとK原先輩のミネラルバランスやドアチャイムが心配になるような形で始まった講読会となりました。足が攣ったりすることもなく、セネットの本文にツッコミを入れながらのK原先輩の愉快な報告(詳しくはレジュメをご参照ください)を受けて、結局のところ、大事なキーワードになっているようである、「指示対象の喪失 dead denotation」とは、何が「dead」だったのかしら?という議論になりました。
この「指示対象の喪失」を考えていくために引き合いに出されていたのは4人の料理人で、1人の悪例とともに、3人の例が紹介されていました。悪例においては、「指示対象が喪失」しているが、3人の例は「指示対象の喪失」を乗り越えようとしている、とセネットは説明していたのです。悪例と3人の例で何が違っていたのか――。
柴田先生は、dead denotationと聞いて連想するのは、ウクライナとロシアの戦争で、ロシアがロケットランチャーを乱れ打ちしながら進軍している様子だ、とのことでした。おそらく、軍隊では分厚いマニュアルが与えられているのだろうが、結局何を指示をされているのか要領がつかめず、それゆえ、前線で、兎に角、やみくもに攻撃をせざるを得ない、という状況に置かれているのではないか…と。
本文にも出ていた例では、取扱説明書もありました。取扱説明書も分厚く言葉を重ねて説明をしている最たる例といえるかもしれませんが、利用者は読まなかったり、読んでもほとんどよくわからないままだったりすることも少なくありません。
悪例として引き合いに出されていたリチャード・オルニーのレシピも、おそらく一番詳細に料理の手順を説明していたものだったのでしょう。でも、そのレシピは、正しくレシピを見てその料理を初めて作ってみよう!と考える人にとって、決して分かりやすい(失敗をしない)ようなものではなかった。
こうしたものをdead denotationとセネットは呼んでいました。ある種、詳細な説明をしているつもりなのに、その説明が無効化してしまっているような状態――を指していたのかもしれません。
一方で説明が無効化/死ぬことなく、生かされていた3人のレシピにはどのような工夫がされていたのか、というと、ジュリア・チャイルドのレシピには「①共感的例証 sympathetic illustration」があり、エリザベス・デイヴィッドのレシピには「②背景説明 Scene Narrative」がありました。最後のベンショー婦人のレシピは、「③比喩 Metaphors」を用いた工夫として紹介されていました。これらは、「説明」が伝わりやすくなるような工夫、ともいえるものなのかもしれません。
初めてその料理をする人の立場に立って、その勘所のようなもの――心情を例証しようとするものであるのが①共感的例証といえますが、自身の体験をなぞり直しながら、実施する側の立場に思いを寄せて説明するやり方といえるのかもしれません。
また、その料理の歴史的・文化的背景を説明するということは、料理の詳しい作り方はなかなか知りえないにしても、その料理の理解を深めることができる、という点では、dead denotationを克服していると捉えることができそうです。→②
③比喩は、直接説明をするわけではなく、あるモノで例えてしまう――それは、プラトンでいうイデア、イメージから、より具体的なモノや例に置き換えて説明をすることで、より説得力を持たせ、より具体的に大事なポイントを料理初心者に伝えることを叶えている、と今回の議論の中では共有されました。
ところで、今回の内容は、タイトルが『表現力の豊かな指示』とありましたが、原題は”Expressive Instructions”。instructionsは、「指示」という訳し方でいいのかなあ、という疑問も出されていました。
denotationに対してのdirectionという語も紹介されていましたが、知っていることを「知っている」つもりにならないで言語化させていくこと――これまでもギルドなどで、用いられている技は、なかなか言語化することが難しいという話がされていました。ディドロの『百科全書』のところでも、うまく説明できないから、ディドロも実際に体験してみて、才能のなさに直面してがっかり…という話もありました――の難しさ考えさせられ、また実際にそんな体験したことあるなあ、と思い出させられるような章でもありました。
そうした、「技」をどう伝えていくか、という意味では、親方目線だと確かに「指示」になるのかもしれませんが、どうやって「伝えて」いけばいいか、「説明」するといいか、という意味で捉えると、instructionの訳し方は「指示」以外の他のバリエーションも考えられるのかもしれません。
皆さんもどう思われたか、次回冒頭で、シェアできたりするのかしら?と期待しつつ、報告を終えたいと思います。暑い日が続いたり、台風が迫ったりと、忙しなく汗もかきがちな今日この頃ですが、きちんと水分・ミネラルを補給して、バテずに頑張っていきましょう。
参加者の皆さんからのコメント
取扱説明書のように詳細に説明していても、読み手にうまく伝わらないことがあるというのは、とても共感しました。たとえ説明が曖昧であっても、比喩を用いるなど、具体的に説明するよう工夫したほうが、相手に伝わりやすいというのは、自分も経験したことがあると感じました。
レシピとは簡潔かつ明確であることが多いと思います。一見、誰が書いても同じようなものになりそうですが、人によってあまりにも違いすぎていて、言葉の使い方ついて比べるのに一番ピッタリなのではと思いました。また、ベンショー夫人のレシピを通して、的確な比喩の利便性を学びました。
私も多くの人の意見と同じでベンショー夫人のレシピをすごく気に入ったのですが、このレシピはモデルの滝沢カレンさんが料理の説明をするときの言葉選びと似ています。私は実際にカレンさんの調味料の分量が書いてないレシピを見て料理をしたことがあるけれど、案外うまくいったので比喩は上手く使うととても有効だと思います。
ジュリア・チャイルドの、レシピが時に曖昧で時に詳細であることは初心者のためであるということはどういうことを言っているのか疑問に思った。
今回の講演では文字・印刷物に書かれている説明書を例に取り上げ、文字により物事を説明をすることにおいて重要なこととは何であるかという事を説明をしていた。4人の料理人のレシピを1人1人順番に取り上げてそれぞれの事例に対してレシピを教えるに至った経緯やその内容を分析したり様々な視点で捉えて説明をしていた。
教える側が言葉つまり印刷物であったり対面でリアルタイムで教えていても優劣はなく表現力豊かな説明書を創ることが情報の伝達において重要である事を知りました。4人のレシピを具体例に取り、「語るな、見せろ」というのは言葉で命令して語るようにするのではなくそのシーンを相手に示すことが出来るように語れという意味を表しているという事が理解できました。
参加した購読会で学んだことは、自分が本文のなかで着目したことについて具体的な事例に当てはめながら考えを深めていくことでわかることについてだ。また、英語の文章を日本語でどう訳されているかを見て、その表現方法について自分ではどう考えるかという見方について、言語が違うからこその視点で興味深いと感じた。

一言で、単純に言うとしたら、言葉を尽くして説明しようとすればするほど、うまくいかない、ということってありますよね、ということだったりするのかなあと思います。ズバッと核心を突くという方法で、説明できることがあるんじゃないか、という提案を、料理の説明の仕方という例を挙げて説明していたのかもしれません。実際、料理を言葉で説明するのは難しいですよね。
そんなとき、的確に説明する方法は、「モノ」に依存しているのかもしれません。実際にあるもの・みえるもの、という「モノ」に例えることが、頭で考えて説明するものよりも分かりやすいのかもしれない。
でもまあ正直、今回セネットが挙げていた例は、食欲をそそるような感じではなかったですよね、などと言いつつ…。「語るな、見せろ」という言葉からも、「みるように語る」こと、モノに託すことの分かりやすさを説明していたように思いますし、言葉を使うとどうしてもズレてしまうことがあることを考えると、敢えてメタファー・比喩を使うことで通じやすくなることもあるのかなあと感じた章でもありましたね。
第八講| 道具を目覚めさせる /2022年7月12日
当日資料はこちら
当日リポート
当日は、Iさんがillustrationを駆使したパワーアップ版のレジュメをご準備くださり、その報告から始まりましたが、道具を通じた直感的飛躍に関する議論が中心的なトピックスになっていたかなと思います。まず話題にあがっていたのは、三段論法(「人間はすべて死ぬ/ソクラテスは人間である/したがってソクラテスは死ぬ」)に直感的飛躍は抗う、とはどういうことだろう、という疑問です。
実はまなキキ・オンライン講読会の第3弾では『科学哲学への招待』を読んでいたのですが、おそらくその第6講(第七章・科学の方法)の中でも同様の議論がされていたように思う、という指摘もされていました。三段論法は第一原理を大前提とする発想である限り、新しい知見を生み出さないようなものです。『科学哲学への招待』の該当の章では、新しい仮説を発見していく方法としてアブダクション(後件肯定)などが例に挙げられていましたが、今回のセネットの議論では、直感的飛躍がその例としてしめされていたといえるのかもしれません。
直感的飛躍として、今日は、割りばしの例が挙げられていました。たとえば筋ジストロフィー症の方がPCのキーボードを打つとき、キーボードの端のほうにあるキーのタイプするのに困難があるとき、食べ物を食べるための道具ではなく、キーボードを打つ・入力するための道具として割りばしを活用する例があった、という事例(詳細は『情弱の社会学』にて)です。
また、まなキキ・ブレンドを作ってくださっているワーカーズ・ホームさんでも、製品のシーラー作業(梱包作業)をまっすぐ綺麗に行うためのルーラー的な道具として割りばしを活用するという事例が挙げられていました。
これは、セネットが説明する直感的飛躍の起こり方の4段階ともある程度照らし合わせて捉えることができる、ということも確認されました。
セネットは直感的飛躍の第一段階として①再フォーマット化を挙げます。これは、道具の用途を創意工夫で変えてしまう、と捉えられるでしょう。”キーボードを入力するための道具”や”袋を抑えておくための道具”に、”食べ物を食べるための道具”という割りばしの用途から再フォーマット化されるのです。
次の段階にあるのが、②隣接化でした。食事という領域から、PC作業/タイピング作業や梱包作業といった別の領域に移動してしまうようなこと、といえるでしょう。
さらにその後、③驚き、④重力/重荷と続きます。④の重荷はどちらかというと道具が直感的飛躍をするとはいっても奇妙奇天烈な使われ方がするわけではなく、ある種、「地に足をつけて」、現実性を持って扱われるというふうに捉えることができるだろう、と議論されました。
ただ、「?」が残ったのは、③「驚き」の部分。この道具の直感的飛躍を体験した本人は、別に「驚いて」はいないのではないんじゃないかなあ、という指摘が出ていました。例えば、「ひらめき」程度の、「あ、こうしたらいいや」という思いはあったかもしれませんが、おそらくその道具を使っている当人たちは、「しめしめ、うまくいった」と納得しながら道具を使っていることのほうが多く、「驚いて」いるのは、道具の使い方に一定のアイデアしか持たない周りの人間のほうなのではないか、という指摘です。
今回の章では、道具には限界もあって個性もあるということを受け止めながらも、だからこそ、道具が思ってもいなかったような利用法が持たれうるというその可能性を見直すことができたのかもしれません。
ただし、セネットが挙げている要件が、本当にすべてを満たすものになっているのかは疑問が残るという指摘もされていました。また、タイトルは「道具を目覚めさせる Arousing Tools」となっていますが、道具が目覚めるというよりも道具の使い手である私たちのほうが目覚めるのではないのか?といった指摘もあがり、依然として翻訳の難しさも話題に挙がっていたような回でした。
丁寧にセネットの議論を読み解いていけるように努力もしていきつつ、引き続きみなさんとも議論を重ねていけたら、と思います。
参加者の皆さんからのコメント
今回の部分は、特に後半が理解に苦しむ場面もあったのですが、議論の中での割りばしの例や、もんじゃ屋さんの例などを通して理解することができました。道具そのものの用途の枠を超えた使用には、人間の想像力が欠かせないのだと実感できました。セネット著作のような難しい書物であっても、先生方の議論を聴くことで理解でき、自分の生活を改めて振り返ることもできるので、今後も講読会には積極的に参加したいなと思いました。
教材のPDFをメールで送って頂いて読んでみましたが、難しくてよく理解することができませんでした。そのため、Iさんの資料と説明にとても助けられました。また、資料に図を載せて下さっていたので、マイナスドライバーと聞いた時に頭で想像しながら説明を聞くことができました。前回の授業には参加していませんでしたが、「語るより見せろ」とはこのことだなと実感しました。また、H松さんがチャットで送って下さったガストのロボットを私も見たことがあります。その時は、「今は料理をロボットが運んできてくれるようになって画期的だな」と技術の進歩を目の前にして驚いていました。しかし、料理を配膳するという動きだけで、特に何もクリエイティビティは生み出してはいないと本日の授業で気付かされました。最後に、柴田先生がいつも授業で扇子を持たれている理由を知ることができたことを通して、私が考えていた「暑いから扇ぐ」といった扇子の使い方とは全く別の使い方をされていたので、驚いたのと同時に想像力を刺激されたように感じました。このことも創造的飛躍につながるのかなと思いました。「隣接化」も割りばしの例を通して、具体的に理解することができたように、セネットが提示している直感的飛躍を行う際に関する4つの要素を見た時は抽象的でよくわからないという印象を持ってしまいましたが、自分の身近な出来事で置き換えて想像してみると、「確かに生活していて経験したことがある」という感覚になり、非常にわかりやすかったです。
私たちは道具を何か目的とセットで「〜をするためのもの」と普段から捉えていますが、ディスカッションであった割り箸のように、違った使い方を見つけられたりすることや、クイックルワイパーで掃除をするだけでなく何か狭いところにあるものを取るのに使うように無意識に違う用途にしたりなど、道具の使い方の多様性の可能性ついて学びました。この点、私は私たち大人より子どもたちの方が「最善の使い方」や「多様な使い方」を見つけるのが得意なのではないかと思いました。
「修理をする」ということが道具の構造や機能を理解する上で大きな意味を持っていることに驚きました。直感的飛躍を行う際の4つの要素のうち、「重力」がどのようなことを指し示しているのかが分かりにくかったです。
道具には個性も特徴もあって、使うだけではクリエイティビティは生まれないことを学びました。また、道具には限界があるためここに人間の力が必要なのであって、その道具にしっかり向き合うことで直感的飛躍が可能なのだと理解できました。しかし、AIが進み便利な世の中になった現在では、道具を創造性をもちながら扱うことは減ったのではないかと考えます。現代においても私たちは道具によって目覚め、AIが何を考えているのかを直感することが必要なのではないかと思いました。
今回この講演会に初めて参加させていただきました。初めてで緊張もしていたのですが、すごい温かい雰囲気で楽しかったです。1つの章、30分程度という短い時間の中であれだけの意見や議論ができるというのが面白いなと思いました。今回の講義のタイトルが「道具を目覚めさせる(Arousing Tools)」となっており、道具が目覚めるというよりも道具の使い手である私たちのほうが目覚めるのではないのか?という議題が上がっていましたが、私自身はArousing
Toolsだけを聞くと確かに、私たち自身が目覚めるという認識の方がしっくりくる気がしますが、講義内容やたくさんのお話を聞く中で私は、本来はある何らかの用途のために作られた道具でも、私たちの向き合い方1つで他にもいくつかの用途に使用でき、その道具の可能性を使い手である人間が広げうるという意味では、タイトルにある通り、道具を目覚めさせるという訳も良いのではないかと思いました。また、参加させていただきたいです、ありがとうございました。

前回のふり返りで少し論理の話が出てきていましたね。アブダクションとは、宇宙人に拉致される、という意味もどうやらあるようですが…。
まず、みなさんも論理の勉強でおそらく学んできたであろうものには、「演繹法」と「帰納法」があったと思います。「演繹法」は、「人間はみんな死ぬ」という大前提のもとロジカルに議論を進めていくようなものですが、実はこの大前提、なぜ「正しい」といえるのかは実は難しいですよね。経験的に分かってきているようなところでもあります。身近なところで、死なない人が今までいなかった、という理解の下、大前提たる第一原則は支えられています。ここでの「経験的な事実」を「帰納法」的アプローチとして見なせます。帰納法は、「原因」と「結果」のうちの「結果」にアプローチして、複数の「結果」から導き出される共通点からわかる根拠をもとに結論を導きだしていくものです。「帰納法」と「演繹法」、どちらも万能ではありませんが、現在の科学はこの二つを組み合わせるような「仮説演繹法」という思考スタイルをとることが一般的になっています。帰納法的に、既に知っている事実に基づいて仮説を立て、その仮説から演繹法的に論理を積み重ねて論証していく、というようなアプローチですね。
今回出てきたアブダクションは、濡れた地面をみて、「雨が降ったんだ」という理解をする論理の矛盾を指すものです。地面が濡れているという結果からは、本当の原因は分からないわけです。もしかしたら誰かが泣いた涙のあとかもしれないし、誰かのよだれの後かも分からない。ですが、クラフツマンたる存在は、対象と向き合い、まさに経験を積み重ねてきたわけで、そうした経験に基づいたうえでの論理の逆転の発想ともいえるような…直感的飛躍の持つ意義、みたいなことをセネットは指摘しようとしていたのではないかと思います。
また、コメントを伺っていても、道具の使用に「遊戯的な」態度が伺えるような、まなキキ・オンライン講読会の第一弾で取り上げたイヴァン・イリイチの「コンヴィヴィアル」と重ねて理解できるように感じられました。
「重力」についての議論は難しいですが、例えば私が使う「扇子」というものも、実はその使い方は、扇子の形にどうしても依存してしまうんですよね。どんなに「こんなふうに使ってみたい」と思い描いてみても、現実の形態に拘束されて、道具の使い方は拘束されてしまう。「重力」に関する議論は、ある種こうした道具の形やありように一定程度方向付けられることこそが、自然で、説得力を持ち得て、生産的なものになりうることなんだ、という指摘や理解として捉えることができるかもしれません。
第九講| 抵抗と曖昧 /2022年7月19日
当日資料はこちら
当日リポート
かくかくしかじかで、Mせんせい的には、前回の報告のリベンジ?的な展開となりましたが、今回の内容の議論が特に盛り上がったのは、ぱんこさんの帰省先で見て驚いた、という「こども園」の写真をみたことだったかもしれません。
幼稚園から、子ども園に改装?されたその建物は、「スタバっぽい」、しゅっとした現代的な建物で、とても子どもたちがワイワイ・きゃっきゃっと泥まみれになって?遊んでいるような場所(中の人のイメージ)からはかけ離れたものでした。
震災後、東北で復興の名の下に建てられていった役所や公民館、幼稚園にも、同じような印象を持ったなあと柴田先生。なぜか、どれも「まるい」デザインだったとのこと。なぜこんなにまるいのだろう?と思っていたが、ある時、鳥瞰的に街を見下ろしたとき、それはとてもきれいでコンパクトなデザインになっているのだ、ということに気づいたのだそうです。ブループリントの段階では、「まる」を多用したデザインは、そうした「シンプルな美しさ」を意図したものだったようだ、、と。
でも実のところ、直線で行けば近いところも、「まるい」ので、遠回りになってしまうし、「まるい」ので入口がどちらか、表がどちらで裏がどちらか分かりにくかったり、「しかく」い建物だったら、ある程度想定しやすい階段やエレベータの場所も、わざわざ覚えなくてはならなくなってしまったり、従来の区役所のイメージと「まるい」建物がかけ離れすぎているがゆえに、区役所がどれだか分からなくなってしまうなどの弊害があったのだとか。
一方で、私たちが暮らす街は、「分かりにくさ」もあるわけです。なぜ、道路がくねくねしてしまいがちなのか、ということを考えてみると、「敢えて」くねくねデザインさせたのではなく、道路を作った人たちが、なるべく低コストな方法を、自然の「抵抗」にうまく折り合って対応していく中で見出したがゆえのもので、結果として「くねくね」した姿をとるに至ったものともいえるわけです。
現場の状況――すなわち、今回でいうところの「抵抗」に向き合って、そこで対応していくことが、私たちを賢くもし、生産的にもしていく、というようなことをセネットも指摘していたのかもしれません。
「抵抗」の場として、境界線と境界領域についてがとりあげられていました。「国境」はborder、境界領域としても捉えられるものですが、そのことはかつて、市場が国境で開かれたということからもうかがい知ることができます。
ゴールデン・カムイという、アイヌの少女が日露戦争帰還兵とともに、金塊を探しに北海道を旅するマンガがありまして、先日完結してしまいましたが、そこでも樺太が魅力的に描かれていた、という例もだされていました。アイヌとロシアと、その領土のはじっこにある樺太という地域が、文化の中心として栄え、市場などを通じて異なる背景を持つ人々の交流があった様子が分かります。
creativity――もしかしたら「生産性」と訳したほうが妥当かもしれないという話もありましたが――が生まれるのは、ある種、境界領域と呼ばれるような「抵抗」の場でしか、そういう場だからこそ、生み出されるのだ、ということも確認されたように思います。
さまざまな背景を持つ人たちがぶつかり合う、という意味での「抵抗」の場として、捉えることができると思いますが、そこでは、互いが峻別できるような形で区別されているのではなく、混ざりあいながら、少しずつ程度や濃度を互いに違えながら共存し、お互いに影響を与えあっているのかもしれません。そうした「境界領域」と呼びうるような場にこそ、生産性や新たな展開が生み出され得る、とセネットは指摘したかったのかもしれません。
また、セネットは「私たちは境界領域よりも境界線を築く方が得意」(p388)とも指摘していました。一方で、私たちが、境界領域と境界との折り合いの付け方をより豊かに学んでいくことは可能だという文章も残して第2部は締めくくられていました。ここからいよいよ最後のパートに取り掛かっていくことになりますが、楽しみに読み進めていきたいと思います。
参加者の皆さんからのコメント
抵抗には種類があって、何かが人々を妨げる抵抗と、自ら作り出す抵抗がある。この抵抗に対して、人々はフラストレーションを感じてしまう。しかし、問題を再フォーマット化したり、これに耐えたり、抵抗と一体化したりすることによって、フラストレーションとの共存が可能となる。抵抗を理解することで、物事を成し遂げることができる。
今回の講読会で話した内容で最も印象残っているのは「抵抗は発見されることもあるし、作られることもある。」という話だ。フェミニズム運動はどの種類の「抵抗」であるか。個人の考えだが、「発見されること」と思う。まだ、曖昧さに関する内容は難しいと感じた。
抵抗という言葉が興味深かったです。抵抗と聞くと悪いイメージしかなかったのですが、想像力を持って共存することで新たなアイデアが生まれたりゴールに近づいたりすることができるということを学びました。もちろんこの抵抗を理解するにあたってはフラストレーションがつきものになってしまいますが、忍耐や一体化などの様々なプロセスを踏むことでフラストレーションと共存することができます。これができる人間こそがクラフツマンだと学びました。
前回の講読会の振り返りや参加者からのコメント紹介と今回の講読会のテーマである「抵抗と曖昧」についての報告、幼稚園や市役所の建物が従来のものとはちがい丸く変化していることが今回のテーマの一つである曖昧さと関連しているのではないかという話や国境、新幹線といったものも話題に取り上げながら議論をした。
曖昧さというのははっきりせずモヤモヤするというイメージが強く、自分も含め誰もが嫌うものだと思っていたけれど、ファンアイクのわざと曖昧さを設計するというのがとても印象深く新たな視点を自分に取り入れることができた。また震災の復興で丸い街づくりがされたのは不便ではあるがそれが抵抗に繋がるという発想が面白かった。
新幹線ほどつまらないものはない、抵抗が少なすぎるといったお話にとても共感しました。
第十講| 品質にこだわる作業(クオリティ・ドリヴン)/2022年7月26日
当日資料はこちら
当日リポート
今回は諸事情により、いつも議論をかっこよくまとめてくださるMせんせいが不在でした。力不足ですが、いつも助けられてばかりのぱんこ、頑張って先週のまとめに挑戦します!
今回の議論では、質を求めることと労働の関係について盛り上がりました。
議論の中で挙がったコメントのように、本文でセネットが指摘する「強迫観念」は、わたしたちが仕事をする上での「こだわり」とも言い換えられます。そして、質を求める、まさに今回のタイトルである「品質を追求する」上で「こだわり」は欠かせない要素なのです。
しかし一方で、セネットはこのような言葉を書き記しています。「忠誠心の強い労働者は諦めずに頑張り続け、労働時間の延長を厭わず、また日上がるくらいならむしろ賃金カットすらも受け入れるだろう(p.451, l.8-9)」、というのです。発表者でもあったぱんこは、この部分がなんだかブラック企業の描写のように感じられ違和感を覚えました。これは果たして良い働き方なのだろうか、クラフツマンはこういう働き方でないと存在できないのか、と疑問に思ったのです。
そこで柴田先生から「交換不可能」というキーワードが飛び出します。
つまり、上記のような忠誠心のある労働では、労働者は労働そのものに“質”を求めていて、労働に対する給料や時間にはこだわっていないと考えることができます。要するに、クラフツマン的な働き方においては、そうした給料や時間に規定されることなくその労働によってのみ高めうる“質”の探求に注力が注がれるのです。しかもその労働は、時間やお金では代替できないがために、他の人が代わりに行うことのできない活動になっています。つまり労働する当人は交換不可能な存在になるわけです。
“質”にこだわれば長時間労働になってしまうかもしれませんし、時にはサクサク仕事が進んでいつもより短い時間で労働が終わるかもしれません。しかし、どちらの労働も完成するモノの品質にかんしては一切妥協していません。そこで大好きなタバコが飲めなくなっても、よい仕事をするためにはそれを成し遂げる職人はいるし、自分の健康のためというよりは、その”ものづくり”をつづけるためにこそ体を鍛える職人もいます。そこでは、自分が働いた時間分の対価を得ようとするような時限とは全く異なるフェーズで、「よい仕事」をしようとする探求がなされているといえます。
しかも 、こうした労働は長期的にもとても時間を必要とするので、クラフツマンは人生をかけてゆっくりとゆっくりと、その技術を大成させていくのです。
例えば、一流のアスリートの多くは、小学校入学前からその競技に取り組み、日々多くの時間を割いて練習を続け、やっと素晴らしい選手になることができるのです。まさに人生をかけてその競技に精通していきます。彼ら、彼女らこそまさにクラフツマン的な品質の追求をしているのかもしれません。
時間や時給に縛られずに労働するということ。時間やコストパフォーマンスが品質を決めるのではないということ。そして「天職」としてその労働に人生を捧げること……こうした、職人的な「品質の追求」をセネットは再評価しようとしているのでしょう。
これと対比して議論されたのが近代的な法体系に基づく労働のあり方です。1日8時間労働が当たり前の現代で上記のようなクラフツマンシップを発揮しようものなら、容易に法律違反となってしまいます。
そもそもなぜ1日8時間労働なのでしょうか。どうやら、8時間×3交代=24時間、つまり3交代制で工場を24時間稼働させるための仕組みから由来しているのだとか。なるほど、そうだとすれば現代標準的とされる9時―5時出社の意味も再考せざるをえません。
働くということを時間や時給に換算して考えることと、品質を保証した働き方を求めることは、別の問題であるということが見えてきました。カール・マルクス的に言えば時給は「搾取」の構造にあたり、 裁量労働制が良いのではという意見が出た頃、無事この購読会の時間をオーバーして(クラフツマン的ですね笑)この日の議論は終了しました。
キーボードで「てんしょく」と打つと「天職」ではなく「転職」と勝手に変換されてしまう現代において、セネットは、職人的なやり方で時間をかけて一つの仕事や技術を大成し、それに誇りを持つことの重要性という、強烈なメッセージを放っていたように思います。 いよいよ購読会も残すところ2回。より一層、質(内容)にこだわった購読会になるよう頑張っていこうと思います。
参加者の皆さんからのコメント
完璧主義という強迫観念では、人が社会化に通じて、それの管理を学習できる。そのテクニックの学習が必要である。また、本日の最後で仕事について議論が面白かった。現代の仕事の方式は産業革命の「製品」である。しかし、今の仕事は社会の発展に合わせて変化しなければならない。福祉の政策も、その変化に合わせて変化するべきである。
今回私が学んだことは、時間制労働が合理的とは限らないということである。時間制労働は、能力に頼らずとも平等に賃金獲得の機会が設けられることから、私は時間制の労働を合理的であると考えていた。しかし講読会を通じて、そもそも時間制労働の合理性は後付けであることや、クラフツマンシップは人の特性として備わっているという考え方を学んだことで、労働はそもそも何を目標に据えているものかを問う視点が得られたと感じる。
完璧主義や強迫観念などは言葉が強く、あまりいいイメージを持たないけれど完璧を求めることやこだわりを貫き通すことも一つの考え方・あり方として自分も納得や共感できることがあるし、一方で企業や施設への忠誠心が強く特に自分の考えやこだわりを持たないで仕事をするというのもありだと思うので自分の仕事に対する気持ちの持ちように勝手に善悪を決めるべきではないと思った。

今回、ブラック企業と重ね合わせてしまうところがあったかもしれませんが、「忠誠心のある労働」というときの忠誠心を払う対象は何なのでしょう?私たちが思い描きがちなのは、①企業への忠誠心だったり、②顧客への忠誠心だったりするのかもしれません。でも、セネットが今回指摘していたのは、③製品/質に対する忠誠心だったのだと思います。
実は、③製品/質に対する忠誠心を標榜しながら、①企業や②顧客への忠誠心に捻じ曲げられてしまうような、ロイヤリティが捻じ曲げられてしまうような可能性はあるのかもしれません。ですが、真にクラフツマンシップを発揮しようとするとき、質の探究に没頭していくことになるわけで、そこでは、企業の都合も顧客の反応も関係なくなってくるはずです。そういう意味で、クラフツマンのありようは、ブラック企業とは一線を画するものにもなるのだろう、と思います。
また、時間制労働が生まれてくる背景には、生産手段の有無が大きく関わってくるといえるでしょう。例えば、職人や自営農をやっている場合、製品やコメなど生産物の質へのこだわりを以てその仕事をすることができると思うのですが、その生産を行う手段を本人が持ち得ていない場合、どうしてもその製品や生産物へのこだわりだけでは仕事はできなくなってしまいます。生産手段を持たないとき、労働者として、自分の時間を売るほかなくなってしまうのです。
また、「完璧主義」というとよいイメージをあまり持てないということがあったかもしれませんが、ある種、「完璧主義」という態度は、その本人がどれだけ自分で納得できるかという問題である以上、コストが高すぎてブラック企業では成立しえないものなのかもしれません。品質について自分がどれだけ納得して、満足できるか、というこだわりは、結局自主性や主体性があってこそ初めて成立するもので、こうした姿勢がクラフツマンシップを構成する要素として指摘することができるのでしょうね。
第十一講| 能力 /2022年8月2日
当日資料はこちら
当日リポート
幼かった当時の不可解な記憶として、知能検査の経験が共有されるところから始まった今回の内容でしたが、みなさんにもそうした記憶はありますでしょうか。どれだけ効率的に表面的な問題を処理することができるか――そうした「能力」を問う検査では、私たちがずっと考え続けてきた「クラフツマンシップ」を構成するような能力は測りようがないし、測りえない、ということが非常な説得力を以て確認することができたような章でした。
「クラフツマンシップ」が育っていく過程として挙げられていたのが「遊び」ですが、私たちはどれほど、「遊戯的」に物事に取り組むことがでできているでしょうか。セネットは、ホイジンガの議論を引用しながら、近代の仕事が「絶望的に真面目」になっていることを指摘しています(p456)。もしかしたら、本当に私たちは、「絶望的に真面目」すぎるのかもしれません。
いいものが生み出されるとき、というのは、おそらく「遊び」的なプロセスの延長にあるのだ、という指摘を、セネットはずっとし続けてきていたのだと思います。そして、この「遊び続ける能力」は私たちに等しく与えられているはずだ、ということも指摘しています。
講読会では、「絶望的に真面目に」STEMに取り組んだところで、どうしてそこから創意工夫が生み出され得るのだろう(いわんや、されるわけがない)、といった指摘もされていました。
「能力」というものを、セネットは「閉鎖系」と「開放系」という用語でも説明していましたが(p467)、私たち一人ひとりが、セネットがいうところの「遊び」を通じて、物事と向き合い、問題を見つけ、その問題を解決するために思索し、さまざまな発想を通じて状況を打開していくことができるような存在なのだ、という指摘であったのだと思います。その意味で、その可能性を多様に拡げていきうる「開放系」の能力観を持ちうるはずですが、知能検査に象徴されるような能力観は、きわめて閉鎖的といわざるを得ません。なぜなら、能力としてあらかじめ規定した範囲内でしか、「能力」を検討していないからです(そもそも、ビネー式は徴兵政策における選抜テストとして生み出されたものであって、人間の能力を測るものではなかった、ということも確認されました)。
知能検査で得られた正規分布上に、人の持つ「能力」が収まりうるはずがなく、それで「能力」を測ることができると考えること自体がナンセンスだという指摘もされました。人が持つそれぞれの能力というものは、あまりにバラバラで、あまりに多様で、ある指標の上に収まるようなものではないはずなのです。能力の範囲を規定できると思ってしまえるのは、愚かな発想とも言ってしまえるかもしれません。正規分布が示すのは、強いて言えば、「真面目に物事を言われた通りに遂行する能力」という、能力の一部を反映したものに過ぎないわけです。
セネットは、482頁で「よい仕事をするための能力は、人類にまったく平等に分かち持たれている」と指摘していますが、つまり、「よい仕事」とは人の数と同じだけあって、それだけ「多様」に生産物は求められているはずだということでもあるのでしょう。
人が等しく分かち持っている、「良い仕事をするため」の能力を発揮するために、結局必要なのは、才能なのではなく、動機づけ=意欲・motivationなのだ、とも指摘してこの章は終わっています(p483)。そのモノに対して、ある種の「忠誠心」や「こだわり」を持って実践=練習=習慣・practiceを続けていけるような姿勢――遊び――は、まなキキでも大切にしてきたもの/大切にしていきたいものといえるでしょう。
talentやgiftedの話をするのではなく、あくまでmotivationを問う、というまなキキが大切にしてきた姿勢は、きっと私たちが「できない」ことを「できる」ようにしていくきっかけにも、「夢」をかなえることにも繋がっていくはずだ、という理解に基づいているのだとも思います。
遊戯的であるとは??と考え始めると、どうしてもぎこちなくなってしまいそうですが、とことん対象を楽しんで、のめり込んで、いいものづくり/たのしいことを考えたい、という欲望に純粋にありたいと思います。そんなこんなで次回はいよいよ最終回。不真面目に、クラフツマンを語りつくしていけたら、と思います。
参加者の皆さんからのコメント
クラフツマンシップが育っていく過程として「遊び」が挙げられていた。セネットは、近代の仕事が、「絶望的に真面目」になっていることを指摘している。ビネー式の知能検査はもともと徴兵政策における選抜テストとして作られたものであって、人間の能力をはかるものではなかった。人間の能力は多様であり、人の数だけ良い仕事はある。知能検査で測れるのは、人間の能力のほんの一部に過ぎない。
ビネー式は徴兵政策での選抜テストとして作られたものであり、人間の能力を測るものではなかったということは、今回初めて知りました。知能検査で測れるのは、人間の能力のほんの一部であって、「クラフツマンシップ」を構成するような能力は測りえないということや、人間の能力は非常に多様であり、知能検査の正規分布上に収まりうるものではないということに、共感しました。

まじめであることが悪いこと、ということではもちろんないのでしょうが、私たちはどうしてもシリアスに問題と向き合いすぎ、ともいえるのかもしれません。問題がシリアスなのはもちろんそうなのでしょうが、シリアスに貢献しなくては、シリアスに幸せにならなければ、と思ってしまいがちなところがあるのかもしれません。
ですが、名作が生み出されるとき、そこには必ず余白があるものなのではないでしょうか。最近の「インスタ映え」とか「イイネ」稼ぎの風潮からもうかがえるのは、楽しんでいるというよりかは、「楽しむことをシリアスにやらされている」ともいえそうな状況です。イイネの数や閲覧数などを規準に「楽しさ」が測られるかのように思ってしまうようなこと。これは本当に全員にとって不幸な状況です。
人の数だけ能力も多様であるということ、そうであるべきこととして捉えていくと、その背景にはおそらく社会の責任もあるのでしょう。
「能力」というときに、どうしても「人が何かに貢献する能力」として捉えられがちですが、本来は「何かが人に貢献する能力」として捉えられるべきなのかもしれません。今日では、知能検査にも代表されるように、ある種”国家に貢献する能力”を求めてばかりになりがちです。そうではなくて、社会が人に貢献する土壌を持っていくようにすることが重要になるのだろうと思います。
また、前回本当にお世話になっているアドバイザーでもあるM野先生からはクラフツマンとしての先生や教員についてご感想をいただいていましたが、まさに先生というのはクラフツマンとして捉えることができる例なのでしょう。時間をたくさんかければいい、とかそういう話ではもちろんありませんが、よりよい授業、よりよい学びを提供したいという思いから時間や労力をある種度外視して取り組んでいるような姿は、クラフツマンシップをうかがい知れるように思います。自らが生み出すものに対して責任を持っていくその在り方こそが、クラフツマンとして大事にされるべき資質として指摘できるのかもしれませんね。
第十二講| 哲学の作業場 /2022年8月9日
当日資料はこちら
当日リポート
あっという間、というべきか、なんというべきか、ようやく最終回を終えることになりましたが、今回はクラフツマンたるための大事な論点を改めて整理することができたような回にもなっていたのかもしれません。
COVID-19は相変わらず猛威を振るい、ウクライナとロシアの戦争も続き、台中関係も不安定になっている2022年のこの夏、有史以降、実戦で最後に核が使われた8月9日から77年が経った今日、最終回を迎えることができたことは、ある種、とても意味があることなのかもしれません。
セネットが、高らかに指摘した「よい仕事をするための能力は、人類にまったく平等に分かち持たれている」(482頁)を受けて、「身体それ自体の豊かさ」(491頁)を論じるとき、この”身体”は何を想定しているのだろう?という疑問から議論はすすんで行きました。
恐らくセネットはここでの身体をかなり広い意味として捉えており、さまざまな自然条件下でそれを受け止める「受容力」そのものとして理解することができるのかもしれない、と確認されました。セネットがいう「良い仕事をするための能力」とは、すなわち「遊びの普遍性であり、特定(局在化)し、疑問を持ち、打開する能力」のことであり、「これらの能力は、エリートにのみならず、広く人類にいきわたっているもの」なのです(493頁)。
この発想に至る背景にあるのが、啓蒙主義だ、という確認が(講読会終了後に)されていましたが、啓蒙主義とはそもそも、人間に対する信頼、人間の能力に対する信仰として捉えることができるものです。より良いものを、人の手を通じて生み出していくことができる、という人間存在に対する絶対的な信頼感があるからこそ、より良いものを作りだしていくための「試行錯誤」の余地が生まれるともいえるのかもしれません。いわば、「遊び」としても捉えられた「特定し、疑問を持ち、打開する能力」とは、「科学的に考える」といった姿勢や態度のことでもあるといえるでしょう。このような態度や姿勢は、エリートにのみ独占されるものではない、というのがセネットの指摘です。そして、多様な特性を持つ我々ひとりひとりがこのような態度で物事に向き合っていくから、新たな多様性に充ちたモノが生み出されていく。この「遊び」としても捉えられた態度や姿勢は、モノを生み出していくだけではなく、自然や社会、人間との関係性も築いていくのだ、とそういったことが指摘されていたのだと思います。
「特定し、疑問を持ち、打開する能力」≒科学的に考えること、とは、いわば自分たちがつくるものについてとことん考えようとすることでもあるのでしょう。アレントは「つくること」には思考や思索が伴わず、故に「凡庸なる悪」が生まれてしまうと指摘していましたが、セネットは、「考えながら作る」という態度こそ、クラフツマンが持つ特性でもあり、そのことをアレントの主張に対する反論として指摘していました。
「考えながら作る」とき、そこには、セルフツッコミをするかのような、「これでいいのかなあ」と考えたりする自分がつくるモノへの理解――”ちゃんとものを考える”プロセスがあります。
一方で、シリアス/真面目にモノを生産しつづけるとは、いわゆる<よりたくさん作る>、<効率的につくる>ようなありようとして理解できるかもしれません。「考えながら作る」姿勢とは、自分が納得するまでとことんモノとの対話に没頭するということであって、企業の論理とは相容れないという意味でも、”遊び”的な態度と理解できるのかもしれません。
自らの生産物を理解しようとする努力――それこそがクラフツマンたるために必要なものであって、そのプロセスを「させないようにしている」ことが、今日において見られる現象なのではないか、という指摘にもなっていました。(pp493-494)
ロシアのウクライナ侵攻にせよ、中国の台湾を取り囲む軍事演習にせよ、今やろうとしていることの意味をどれだけ理解・反省・実践しているといえるでしょうか。まさに、自治が成り立っていない象徴的な事例としても捉えることができるのかもしれません。
長崎に原爆が投下がされてから77年後の今日、今こうしてクラフツマンを読み終えようとしていることはとても意味があることなのかもしれません。「これからも核を使うことはない」という想定が、あまりにも脆く思える今日の世界を前に、強烈なカウンターになりうるのは、私たちが、ひとりひとり、クラフツマンとして物事を考えたり、クラフツマンたろうとすることなのかもしれません。
現実を前に、丁寧により良い社会や未来を作ろうとしたとき…いわば、物事を判断し、自らで決定していくような自治――self rule――を積み上げていけたときに、よい仕事/クラフトは生み出されていきます。おそらく、今日における現実を前に、クラフツマン的思考を積み重ねていく先に、核を用いるという選択肢は出てき得ないはずなのです。その事実が、核の脅威に対するカウンターとして確固たる意味を持ちうるのでしょう。
核の問題のみならず、さまざまな問題に対して、カウンターを張っていくために、私たちがしっかりとクラフツマン的に考えていくための場―作業場を持ち続けていきたいと思いますし、まさにそこには、”科学的に考える”≒学問の力が求められてくるのだと思います。学びの危機――Learning Crisis――に立ち向かっていくためのヒントもここに隠されているのだと思います。
自治――self rule――や自己統治という課題を得てクラフツマンを読み終えることができましたが、また今年の後半は、この問題をより掘り下げて考えていくことができるよう、ミシェル・フーコーの『生者たちの統治』を読み進められたらと考えています。
5月中旬から12回にわたって講読会にご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。
また、次回のまなキキ・オンライン講読会にも、もしよろしければぜひ奮ってご参加ください。
参加者の皆さんからのコメント
クラフツマンは、自分が作るものを理解しようとする努力・「考えながら作る」という態度を持っている。それ故、クラフツマンとして物事を考えていれば、原爆投下などは起こりえないはずである。一方、近代の民主主義では自らの生産物を理解させないようにしているように見られると指摘されていた。確かに私たちは生産性や効率性を重視したり、自らの生産物を理解しないまま、言われるがままにものを作ってしまいがちである。
クラフツマンシップの基盤には、事実だけではなく、経験の質を解明しようとするプラグマティズムの考えがある。人間が技術を発達させるためには、遊びの普遍性が必要である。これは、局所化して疑問を持ち、打開する能力のことで、エリートのみならず、広く人類に行き渡っている。そして、クラフツマンは仕事そのものを通じて、人間関係を築き上げていく。
何も考えず、真面目に物を作り続ければよいのではなく、立ち止まって自分の作った物や周りに対して疑問の目を持って見ることがクラフツマンにとって重要であることを学んだ。このことは、強弱はあるにしも人類であれば誰にでも与えられているもので、その都度、自分自身で理解し、反省して実践することが必要であるとわかった。
楽しく参加できて良かったです。ありがとうございました。
ロシアのウクライナ侵攻や、中国が台湾周辺で始めた軍事演習などの話題が購読会の中で出てきましたが、私たちひとりひとりがクラフツマン的に物事を考えていこうとする姿勢を持つことの大切さを感じました。今やろうとしていることの意味をきちんと理解・反省・実践していれば、現在も続いているそのような問題も起こらなかったかもしれない、また、現在私たちはあまりクラフツマン的に物事を考えられていないのかもしれないとも思いました。
12回に渡るまなキキ講読会を開催してくださり、ありがとうございました。毎度、丁寧にテキストを解説して頂けるので、難しいセネットの考え方を自分の中でかみ砕きながら理解していくことができたと思います。また、自分では手に取ることのない本を読むことができ、貴重な機会となりました。そして、本日の最終回に参加し、総括を聞くことができてよかったです。何も考えず、真っすぐに物作りに励むのではなく、逆に立ち止まって自分の作った物に対してツッコミを入れてみたり、周りに対して疑問を持ってみたりすることがクラフツマンにとって重要であると理解することができました。このことは、学問の力とも捉えることができ、前期の社会学の主なテーマであったLearning crisisの解決にもつながる内容であったと思いました。そして、最後に紹介されていた「生者たちの統治」という本も難しそうですが、授業で習ったミシェル・フーコーのことが書かれているので、読んでみたいと興味を持ちました。
能力やモチベーションを正規分布で表せると考えてしまうのは、私自身も違うのではないかと思いました。正規分布が示すのは、真面目に物事を言われた通りに遂行する能力という、能力の一部を反映したものに過ぎず、そこから少し外れただけで途端に障がい者扱いをされてしまっているという現状に対し、それこそ、人々の可能性、能力に限界を決めつけてしまっているのではないかというように思われました。
最後に柴田先生も仰っていましたが、現代の人々の多くが真面目すぎであり、もはや真面目でいることにとらわれてしまっていて、真面目に騙されているというのが自分の中でとても衝撃を受けました。私自身も周りからもずっと真面目だと言われ続け、真面目でいることが正しい、真面目にやればいつか報われる、安心だと今までずっと思い続けてきましたが、真面目な人は、本質的に真面目な人にしてやられてしまう、不真面目にやらなければ達成できないこともあり、不真面目さが質を見出す余裕や新しいものを見出すことができると知り。これからの生き方を見直す機会になりました。もちろん真面目なこと自体は何も悪くありませんが、真面目にとらわれすぎず、時には不真面目にやって、創意工夫をしていきたいと思います。