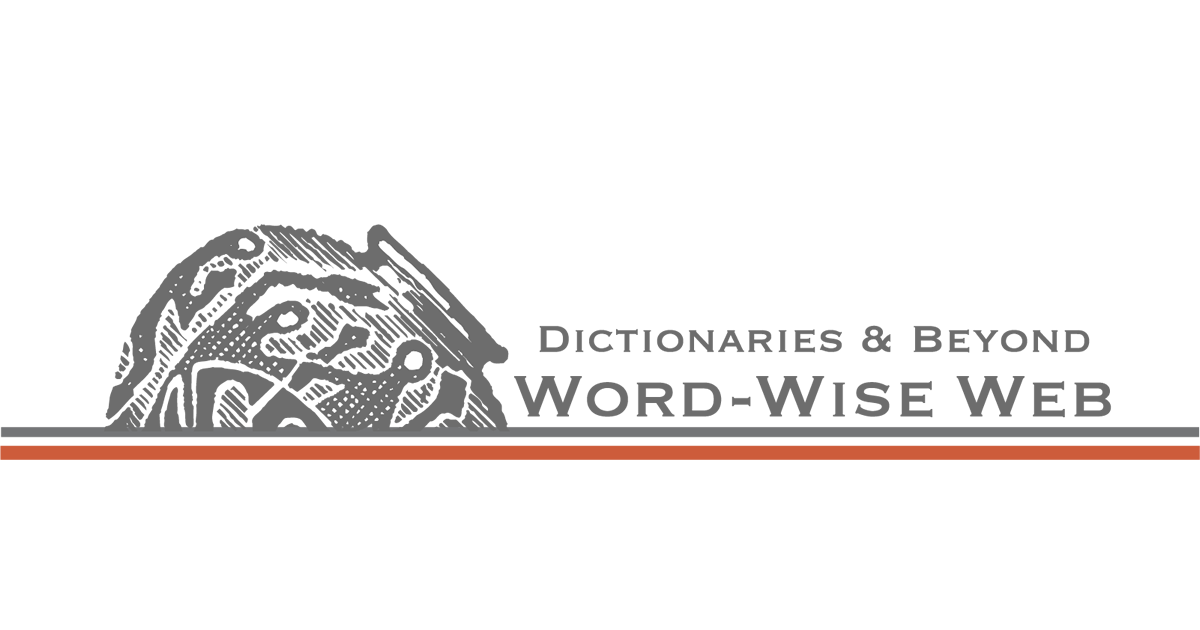▶ を押すと文が増えます
本日の紹介者

すみません。
「ああ。。。これは紹介したい…」という本がまた出没してしまい、やってまいりました…!
前回ご紹介した『クラバート』も、相変わらず、「やっぱ、いいよなぁ~」としみじみ思うのですが、どうやらマイナーなようで、kindleで手軽に読めたりもできないということもあって、みなさんにもなかなか手に取っていただきにくかったのか分かりません。
でも、本当にいい本なんですよ。
そんなわけで今回ご紹介するのは、もう少しさまざまな形で皆さんがアクセスできるような小説、比較的最近の作品をご紹介します。
舟を編む
著者:三浦しをん
出版社:光文社
出版年:2011年
ISBNコード:978-4334927769
概要
「大渡海」という辞書をつくる物語。
不器用で、周囲に「この人、大丈夫かな…?」と思わせてしまうような、いわゆる「変人」な主人公、馬締光也。
通称「まじめさん」は、辞書作りの適性ときたらピカイチ。
不器用ながらの恋愛もあったりしながら、辞書作りに勤しむ同僚とも愛情あふれるチームワークを築いていく姿がなんとも爽快な小説です。
本について
もともとは、女性ファッション雑誌(20代後半からアラサーOLを主なターゲットとする雑誌。ちなみにM先生は講読経験なし)に連載されていた小説。
その連載小説が、2011年に光文社から単行本として発行されました。
そして、2012年、本屋大賞を受賞。
その後、2013年に石井裕也監督、松田龍平主演で映画化。
2016年10月から12月までテレビアニメが放送されました。

冒頭でお伝えしたとおり、みなさんがさまざまな形でアクセスできる小説です。
本との出会い
実は、小説の存在自体は知っていました。
辞書を作るという内容の話だということも知っていました。
ただ、実際に読んでみよう、という機会は持ってこなかったのです、が、
「言葉でつなぐ、つながっていく⑤ なんでそんな漢字になる感じ?」という記事を書くにあたり、読んでみたところ、「これは!」と思うところが多々ありました。
※ 上記記事内でも、『舟を編む』についてご紹介しています。
なので、この本との出会いは、まなキキを読んでくださっている皆さんがくれた、といっても過言ではありません…。ありがとうございます。「倍返し」ならぬ「恩返し」的な記事、のつもりです。
この本が拡げた世界
私自身は最近、ずっと「漢字」や「ことば」にこだわって記事を書いてきたつもりです。
一生懸命、うまく伝えられるように、と頑張っているつもりではいますが、なかなか難しいなあと思うことも多々あります。
そんな私にとって、「辞書」をつくる、ということを目的としたドラマを描くこの小説の描写やテーマには大変励まされました。
その1 読み手を「きゅん」とさせる遊びごころ
文字で表現するスマートな洒落
例えば主人公は、「馬締」(馬の手綱を締める、の”馬”と”締める”で「馬締」)という苗字を持っています。
辞書作りの後任探しをしている荒木さんは、「辞書作りに適任そうな新人がいる」という言葉を聞いて、その新人の名前も聞かずに、新人が所属する営業部まで駆け込んできます。物語はそこから始まるのです。
「それっぽい人いないか?」と尋ねると、「たぶんあの人かな。まじめです。」と案内されるのです。
「そうかそうか、まじめなのか~。ますます適任だな。」と声をかけると、
本人も「はい、まじめです」と答える。「自称するっておかしくないか??」
…とそういうやりとりを経て、名刺を渡され、「なるほど、馬締で”まじめ”ね~」と合点できる一節があるわけです。
考えてみれば、同音異義語的にダジャレをつくるのとも少し似ているかもしれません。
このケースの場合は、苗字の「馬締」と”真面目”という意味の「まじめ」が混同されて、面白さが出てくる。
実際に音で聞いていても、楽しめそうな部分ですが、文字上でもこの「洒落」が演出されています。
それが、ひらがな表記と漢字表記の使い分けで表現されていたわけです。
しゃれ【洒落】
(名) ①気がきいていて粋な感じのすること。「―者」 ②同じ発音で二つの意味にとれることばを使った、言いまわし。だじゃれ。「―を飛ばす」 ③おしゃれ
がてん【合点】
(名)[―スル] 理解してなっとくすること。「―がいかない」「早―」「独り―」▷「がってん」の変化した形
さりげなく読者を「笑い」へとアシストする傍点
他にもあります。
主人公は、変人で、とにかく活字に浸りきった生活を送っています。
ぼろぼろの下宿に住んでいるのですが、もはや下宿人は自分ひとりであることをよいことに、自室以外の部屋にも自分の本を目いっぱいに所狭しと置いているわけです。
下宿の一階を、天井まで届く本棚でいっぱいにしているので、大家のおばあさんからは「地震があっても柱がたくさんあるから安心」と言われます。
…意味、わかるでしょうか?
原作では、この「地震があっても柱がたくさんあるから安心」の「柱」の部分に「傍点」がついています。
ふりがなの代わりに「点」が打たれているわけです。
意味は、「強調」といったところでしょうか。
なぜ、「柱」が強調されるのか。それは本当の意味での「柱」ではないからです。
主人公の馬締さんが積み上げた本の山が、まるで”柱”のような役割を果たしてくれてるかもしれないものね~という、大家さんの皮肉ともとれるような発言です。
ユーモアが感じられるところです。
ただ、もしかしたら、「柱」が「点」で強調されていなかったら、このギャグ要素はなかなか理解できなかったかもしれません。
「点」があるから、察しやすくなる、という効果がありそうです。
かつじ【活字】
(名) ①活版印刷に使う、なまりなどでできた文字の型。「一本一本―を組む」 ②印刷された文章。漫画などに対して、文字主体の小説などをいう。また、印刷物。「若者の―ばなれが進む」「―にする」
げしゅく【下宿】
(名)[―スル] 他人の家に部屋を借りて住むこと。また、その家。「―屋の娘」
ぼうてん【傍点】
(名)文字のわきに打つ点。強調したり注意をひいたりするためにつける。「――筆者(=引用文に傍点をつけたのは筆者)」
その2.「辞書」はどうつくられるのか。-ものづくりの真髄
やっぱり「辞書」って作るの、こんなに大変なの‥‥という驚きで圧倒される方も多いのではないでしょうか。
読めばわかるのですが、辞書とはひとりで作れるものではないのです。
※作中、何度か言及される実在する「大言海」は、大槻文彦がひとりで作ったのだそうです。(亡くなってからは後任の人がいたようです)
主人公は本を出版する出版社に勤める編集者です。
辞書の出版に関して編集者は大きな役割を持ちますが、彼らだけでは辞書は完成しません。
辞書の全体のグランドデザインを描く「監修者」という役割を持つ人がいます。
また、専門的な内容に対して原稿を書く、各方面の専門家の存在があります。
そして、辞書を印刷する紙をつくる人たち。(ただの紙ではだめなのです。ここもかなり強調して描かれていました)
装丁を担当する人たち…。
辞書作り、というだけで多くの職種が関わります。
行程にもさまざまな段階があるのです。
細かい行程については皆さんもぜひ調べていただきたいな、と思いますが、作品からひしひしと伝わってくるのは、辞書作りに取り組む一人ひとりの人の熱量の高さです。
私たちが、何とはなしに手に取る辞書、たかが辞書、ともいえるようなものが出来上がってくる背景には、確かな経験と知識に裏付けられた情熱があります。
筆力がなく、ふつーの感じになってしまいますが、「ものづくり」について深く考えさせられます。
辞書に限らず、私たちの日常を支えるあらゆる製品は、おそらくそうやって作られているのでしょう。
そうした「もの」に支えられて、そして私たちも何かの形で誰かを支えることにつながることを願いながら、経験を積んでいくのかもしれません。
どんなふうな仕事があって、どんなふうに働いていくことができるのか―
H松さんが以前特集されていた「エッセンシャルワーカーのお仕事を知ろう!」ももしかしたら参考になるところがあるかもしれません。
しんずい【神髄・真髄】
(名) ものごとのいちばん中心の奥深いところにある、たいせつなこと。本質。「学問の―をきわめる」「―を味わう」[類]精髄・奥義 ▷もと、精神と、骨髄の意味から。
かんしゅう【監修】
(名) 書物や映画などの編集を責任をもって監督すること。また、その人。「辞典の―者」
そうてい【装丁】
(名)[―スル] ①本の外装。箱・カバー・表紙などのくふうやデザイン。 ②本をとじて表紙をつけること。
その3.言葉は万能ではない。でも、つなぎとめてくれる。
そして、著者の考えなのか、もともと「言葉」とはそのようなものと捉えられていたのか、分かりませんが、言葉は、海になぞらえて説明されています。
「ひとは辞書という舟に乗り、暗い海面に浮かびあがる小さな光を集める。もっともふさわしい言葉で、正確に、思いをだれかに届けるために。もし辞書がなかったら、俺たちは茫漠とした大海原をまえにたたずむほかないだろう」
「海を渡るにふさわしい舟を編む」
松本先生が静かに言った。「その思いをこめて、荒木君とわたしとで名付けました。
辞書は、混とんとした気持ちを何とか「言葉」にして示そうとする私たちを助けてくれる道具なのだといいます。
「しりとりに勝ちたかったら、単語の末尾が『あ行』『か行』『さ行』で終わる言葉を言うのは避け、『や行』や『ら行』や『わ行』で終わる言葉をひねりだすことです。『怪獣』や『監査』ではなく、『鎌倉』や「カストリ』などを、どんどん相手にぶつけるといいでしょう。ただ、これがなかなか、咄嗟に思いつくのが難しい」
「松本先生でもですか」
岸辺が驚いて問うと、
「言葉の海は広く深い」
松本先生は楽しそうに笑った。「まだまだ修行が足らず、海女さんのように真珠を採ってくることができないのです」
10年以上の時間をかけて一冊の辞書は出来上がっていきます。
その辞書の監修役を務める松本先生という登場人物ですら、言葉の海から的確に「これぞ!」と思う言葉をすくいあげてくることの難しさがある、というのです。
なにかを生みだすためには、言葉がいる。岸辺はふと、はるか昔に地球上を覆っていたという、生命が誕生するまえの海を想像した。混沌とし、ただ蠢くばかりだった濃厚な液体を。ひとのなかにも、同じような海がある。そこに言葉という落雷があってはじめて、すべては生まれてくる。愛も、心も。言葉によって象られ、昏い海から浮かび上がってくる。
言葉に示されるから、私たちはともにいる人と、合意点を探ることができるのかもしれません。
例えばこの小説では「食事をしたときの感想」や「印刷会社の紙の質を確かめるときの感想」の語彙が豊かになってこそ、その絶妙なニュアンスを汲み取って工夫を凝らして、相手の求める食事や紙をつくることができるようになる、と語っています。
言葉ではなかなか伝わらない。通じあえないことに焦れて、だけど結局は、心を映した不器用な言葉を、勇気をもって差しだすほかない。相手が受け止めてくれるよう願って。
私たちは感じあったり、察しあったりすることももちろんできます。敢えて言葉にしないからこそ味わいが深くなることももちろんあると思います。
が、なんとか表現しようと苦心することにも意味があるのでしょう。
「国語」の辞書を編纂しようとしている、いわば言葉のプロフェッショナルを主人公とした小説の中で、こういう表現が出てくるのです。
誰もが、「誰かに何かを伝えたい」という気持ちを抱えながら、言葉としのぎを削っている、ともいえるかもしれないですね。
なんだか、妙に感動してしまいました。
ちなみに「舟を編む」というタイトルで「舟」という漢字なのは、すごく意味があることなのだと思います。
「船を編む」のではないのです。
実は、夏に書いた記事、フネで旅する漢字の海原(うなばら) シリーズ① いろいろなフネの中で、「舟」は、小型船のことを指して、いわゆる渡し船のような、ボートのような、カヌーのようなイメージのフネであること。
一方、「船」はもっと大型のフネのことを指す、ということを参照していました。
私たちはひとりひとり、舟に乗り込んで言葉の海に乗り出すのです。
私たち一人ひとりが、それぞれ言葉を選び、向き合い、生きていくのかもしれません。
誰かからの借り物ではなくて、私たち自身が混とんした海から丹念にすくいあげていく言葉とともにありたいな、と思います。
そういう意味では決して饒舌である必要はないのですよね。
ぼうばく【茫漠】
(形動) ①土地などが限りなく広いようす。「―たる風景」 ②つかみどころがなくてはっきりしないようす。「―とした説明でわからない」
こんとん【混沌・渾沌】
(形動) いろいろな力が入りまじってはたらき、区別ができない状態。また、状況がわからないようす。「前途が―としてきた」「―たる世界情勢」 ▷もと、宇宙ができたころ天地の区別もなくどろどろであったという意味から。
しのぎ(鎬)を削る
激しく争う。 ▷「鎬」は、刀の刀身と峰の中間の小高い部分。そこが激しくぶつかってけずられるほどきりあうという意味から。
教科との関連
言葉の意味を考えること
辞書とはそもそも何でしょうか?
私たちは見慣れない言葉に出会ったら、その言葉がさす意味を調べるために辞書を引きます。
辞書には、その言葉が意味することをとても端的に分かりやすく示しています。
少なくとも、そういうものであろうと、編集者の人達が苦心していることが小説を読むとよくわかります。
例えば、辞書の意味を辞書で引いて調べてみると、次のように書かれていました。
じしょ【辞書】
(名) ことばや文字を一定のきまりに従って並べ、その意味・用法・用字法・語源などをしるした書物。辞典。字引。「―を引く」▷ふつう、「字典」「事典」をふくめた広い意味で使われる。
小説の中では、ある有名な研究者が書いた言葉の意味を説明した内容を酷評して、校正を入れるシーンが出て来ます。
誰もが納得できる、その言葉の意味とは何なのでしょうか。
意外と私たちは、思い込みや自分の感覚的なもので対象を捉えようとしてしまうことがあります。
作中、「恋」や「恋愛」という言葉の定義についても言及されています。
みなさんは、「恋」や「恋愛」という言葉をどういうふうに定義しますか?
主人公たちも、この「恋」や「恋愛」という言葉の定義を巡って、自分の中に出来上がってしまっている「常識」を意識させられて、考えさせられていたりするのです。
それこそ、Googleに検索して出てくる答えで満足できるようなものではないですよね?
言葉の意味とは、私たち自身が経験したり感じたり、考えてきたことを受けてアップデートさせていくような種類のものだと思われるからです。
言葉の意味を考えること。自分の中の「常識」を疑うこと。
そういったことの持つ重要性も、この本が教えてくれているような気がします。
たんてき【端的】
(形動) ①ぴったりとあてはまるようす。「―にあらわす」「―に物語る」 ②てっとりばやいようす。てみじか。「―に言うと」
こうせい【校正】
(名) 印刷物の刷りもの(=校正刷り)と原稿を比べて、文字や図版の不備や誤りを正すこと。「赤えんぴつで―する」
ていぎ【定義】
(名)[―スル] ものごとやことばの意味・内容をはっきりと定めること。また、それをはっきりと述べたもの。「三角形の―」
おまけ
この本を読んで無性にいろいろな辞書を読み比べてみたくなりました。笑。
辞書づくりのプロセスを読んでみると、よくわかるのが、
①どの言葉を辞書に載せるか
②言葉の説明の仕方
が辞書によって、だいぶカラーが異なるということ。
どの言葉を辞書に載せる?
「死語」は省きながら、最新の表現をきちんと網羅する、ということでもあり、辞書作りにかかわる人達のアンテナの張り具合を見事に反映するもののように思われます。
小説の中では、「用例採集カード」なるものが登場します。
辞書作りに取り組む人達は、いかなる時も「用例採集カード」を手放さず、辞書に収録すべき言葉が飛び交ってはいないか慎重に耳をそばだてて生活しているというのです。
「版」という言葉をしっていますか?
はん【版】
①印刷するために、文字や絵をほったり、活字などを組んだりしたもの。②印刷して本をつくること。「―を重ねる」③戸籍簿
②の意味が該当していると思いますが、一度出版したあとで、新しい用語を含めたり、「死語」を削ったりして、「版を重ねていく」ということがあるのです。
小説の終盤、なんとか無事に「大渡海」は出版されるのですが、その出版記念パーティの席で、もうすでに次の改訂を見越して「用例採集カード」を片手に余念がない登場人物の姿が描かれています。

以下は、現在刊行されている国語辞書の中で、唯一の多巻本大型辞書である『日本国語大辞典 第二版』全13巻(小学館 2000年~2002年刊)について書かれたエッセイです。
しご【死語】
(名) 以前は使われていたが、現在は日常使われなくなった単語や言語。単語では、「労咳(=肺結核)など」。言語では、古代ラテン語・バビロニア語など。 [類]廃語
かいてい【改訂】
(名)[―スル] 書物などの内容を改めて、なおすこと。「―版の教科書」
よねん【余念】
(名) ほかの考え。よぶんな考え。雑念。「―がない」
言葉の説明の仕方
とても基本的なことなのですが私たちは人間ですから、ひとりひとり少しずつ物事の捉え方や説明の仕方は異なるのです。全く同じ表現で、ある言葉を説明する、ということはなかなかできません。
だからこそ、出版社やその辞書編纂に取り組む人達の個性が出てくるのだそうです。
ということを踏まえると、どんなふうに辞書を選んだらいいか迷ってしまいますよね。
そんな我々にピッタリ?の記事を見つけたので紹介して今回のブックレビューを終えたいと思います。
国語辞典の使い方など、国語辞典入門者のためのコラムです!

今回の私のレビューをアシストしてくれたのは、まさに国語辞書。
角川必携国語辞典(初版)です。
平成7年の辞書ですって‥‥。新調しようかなあ。